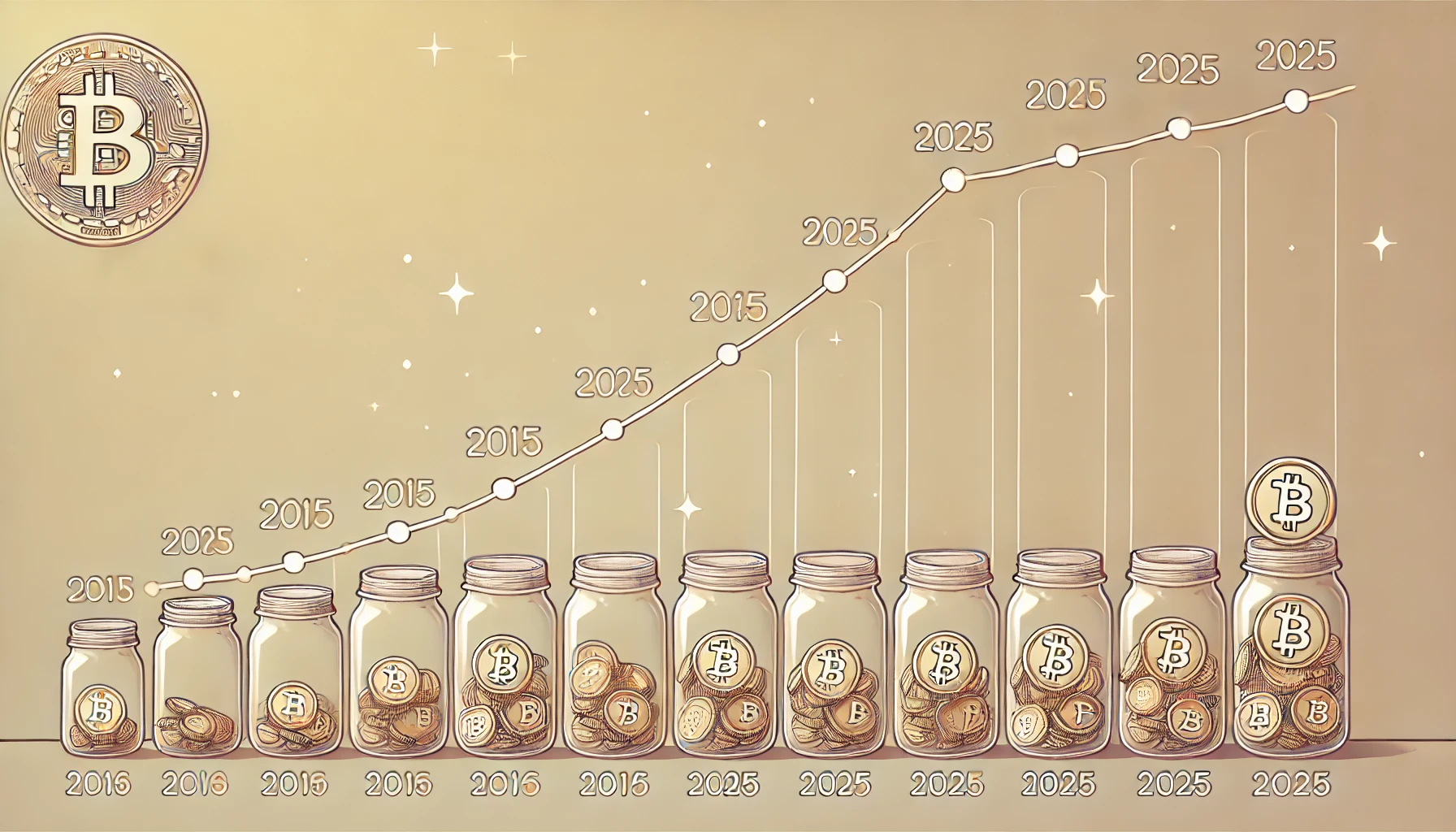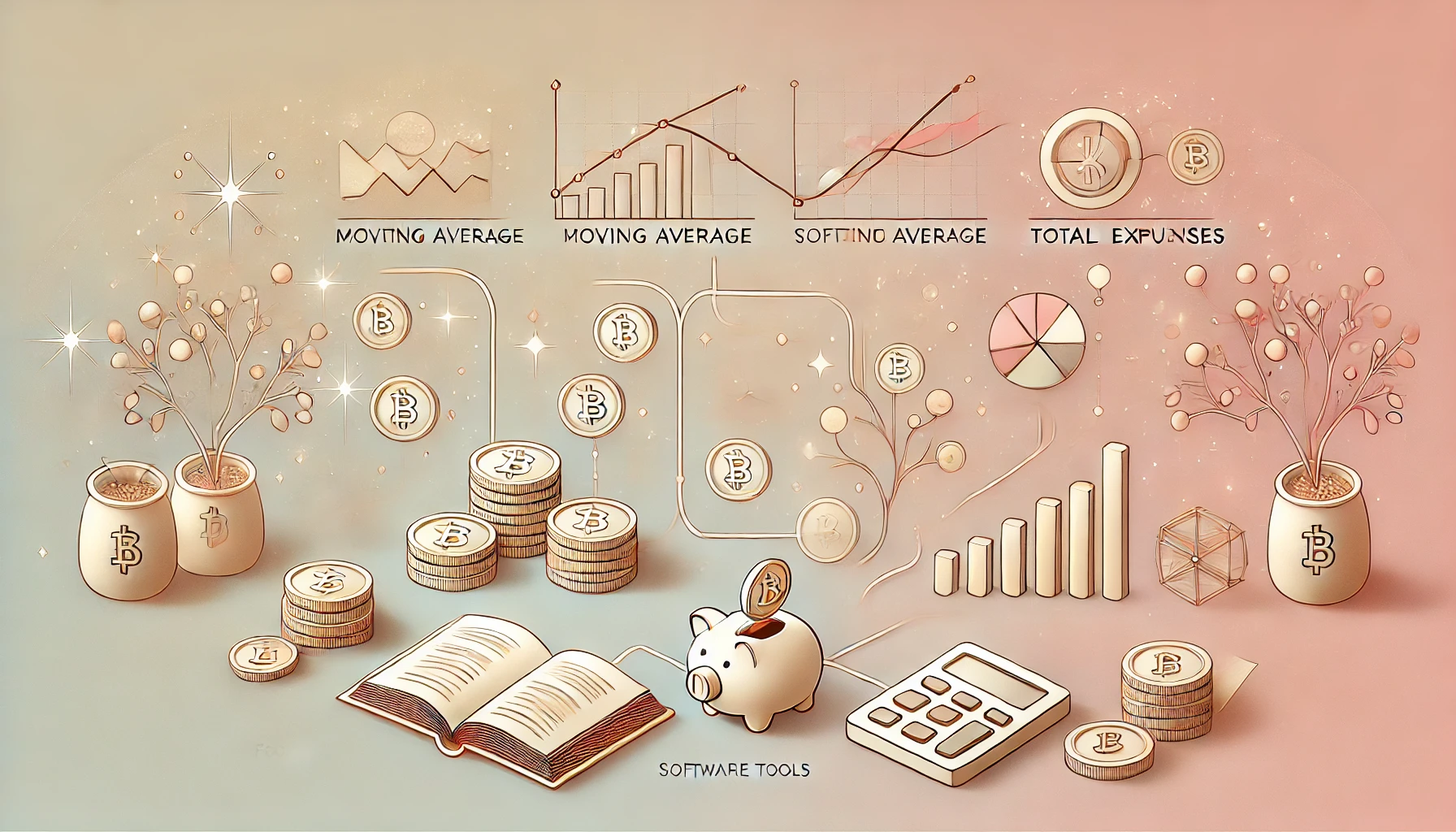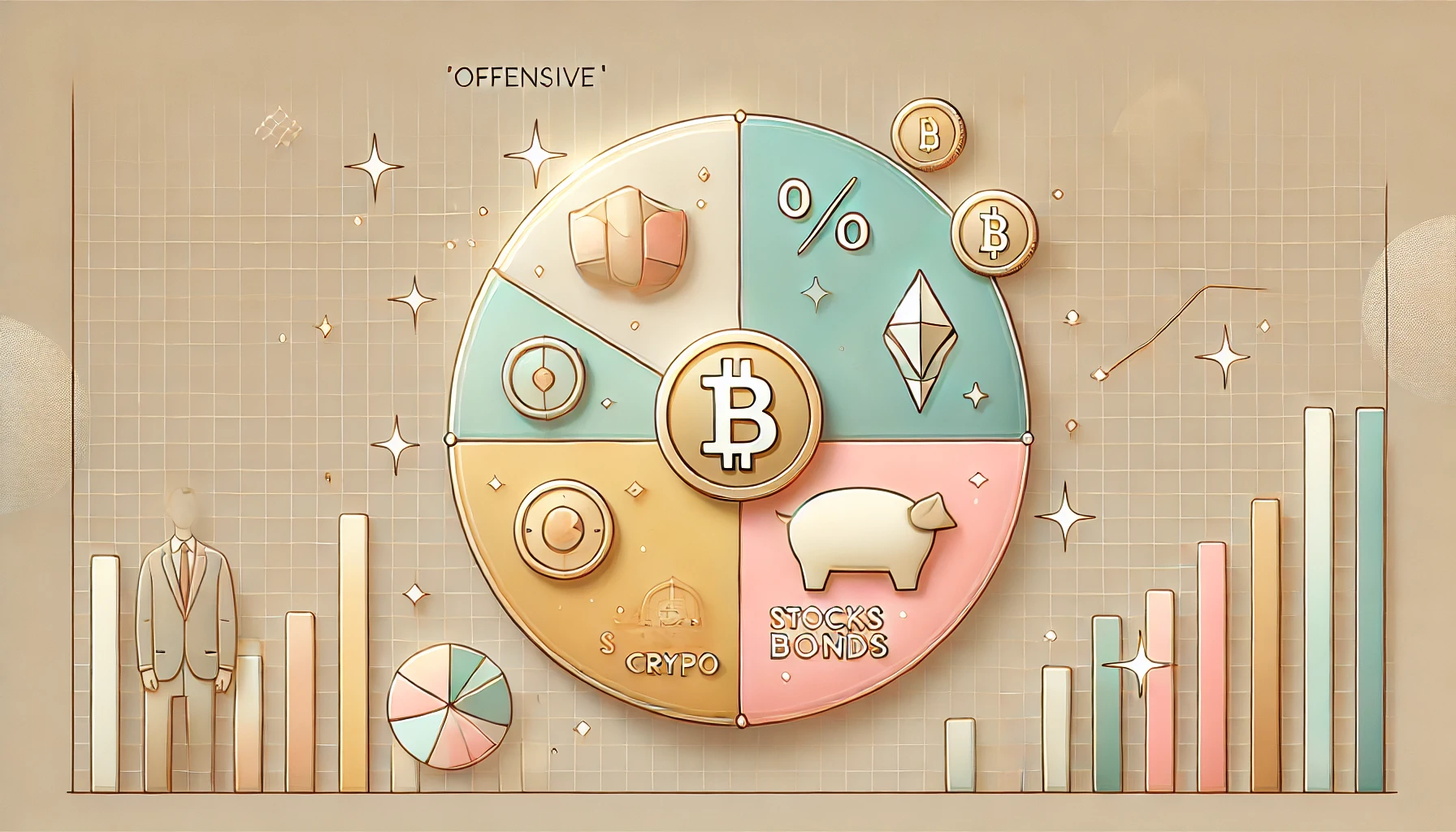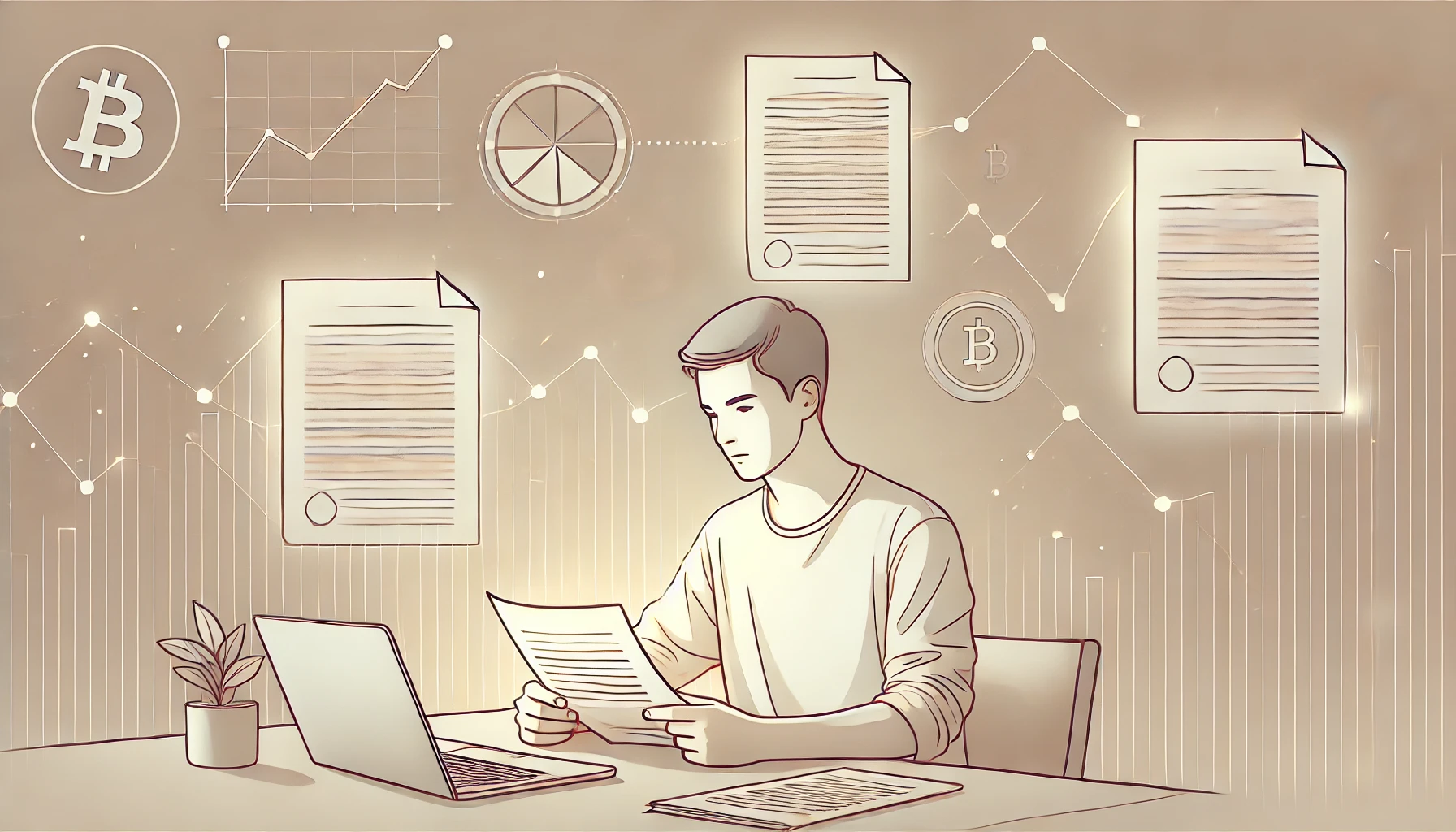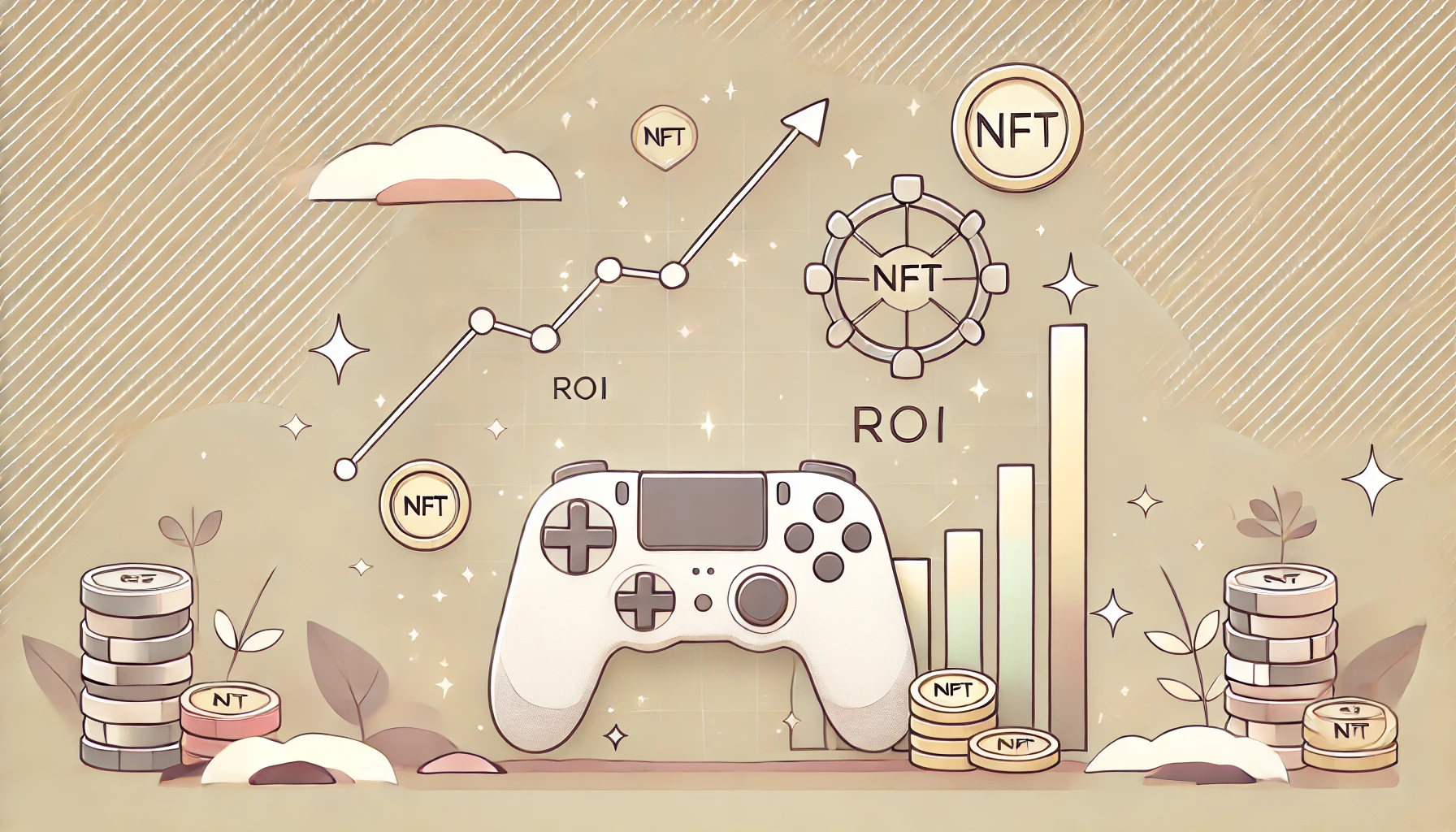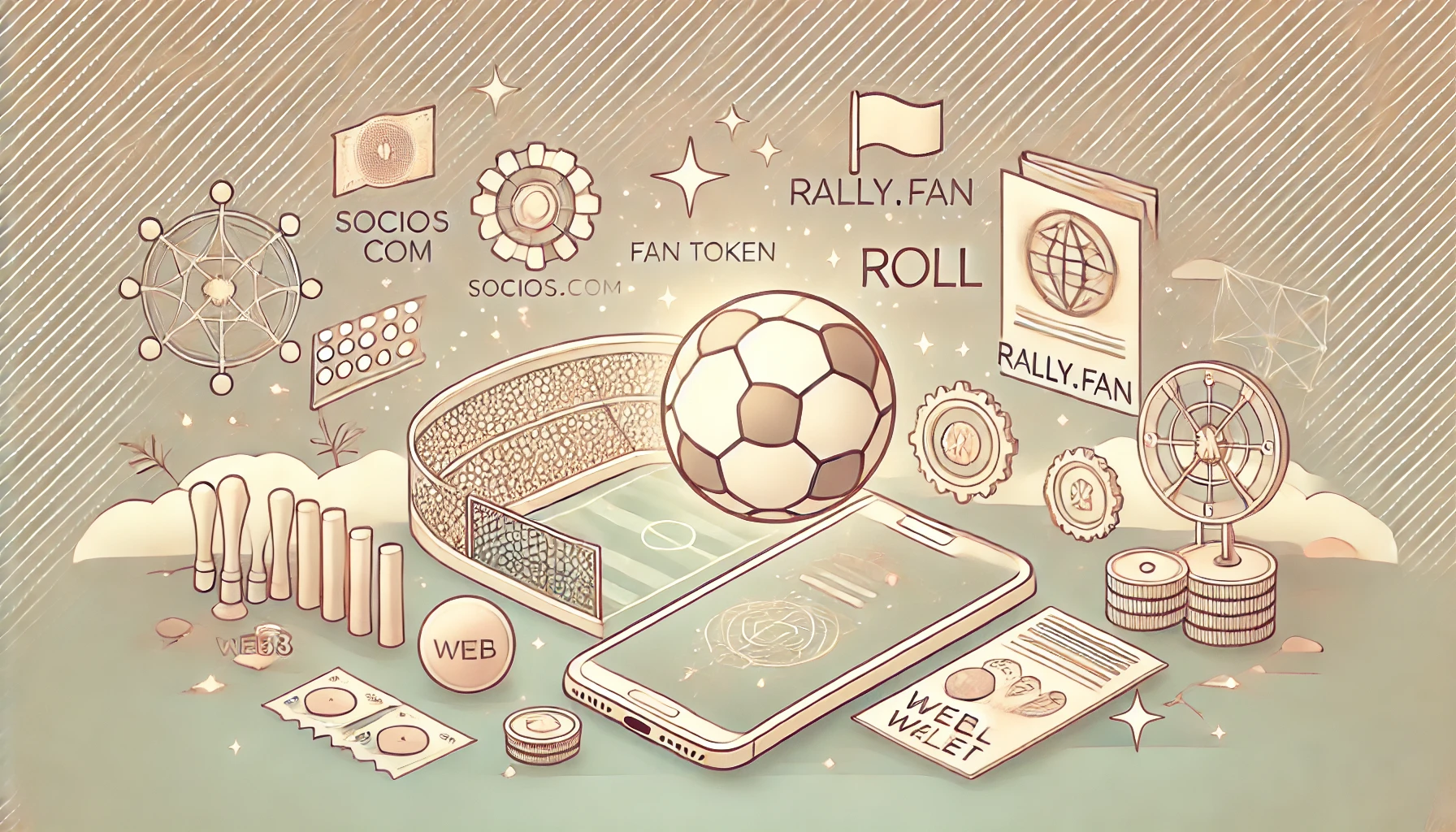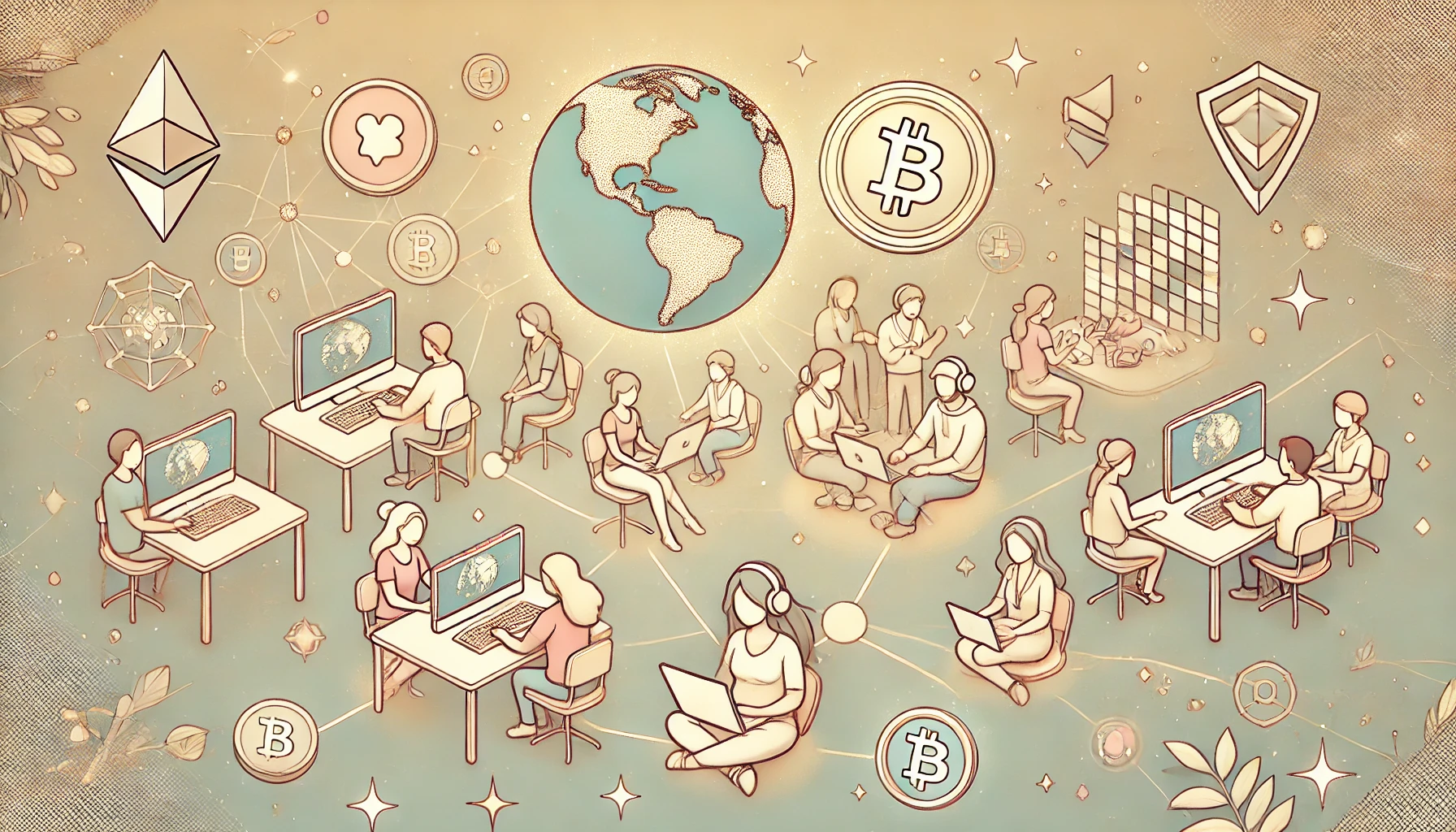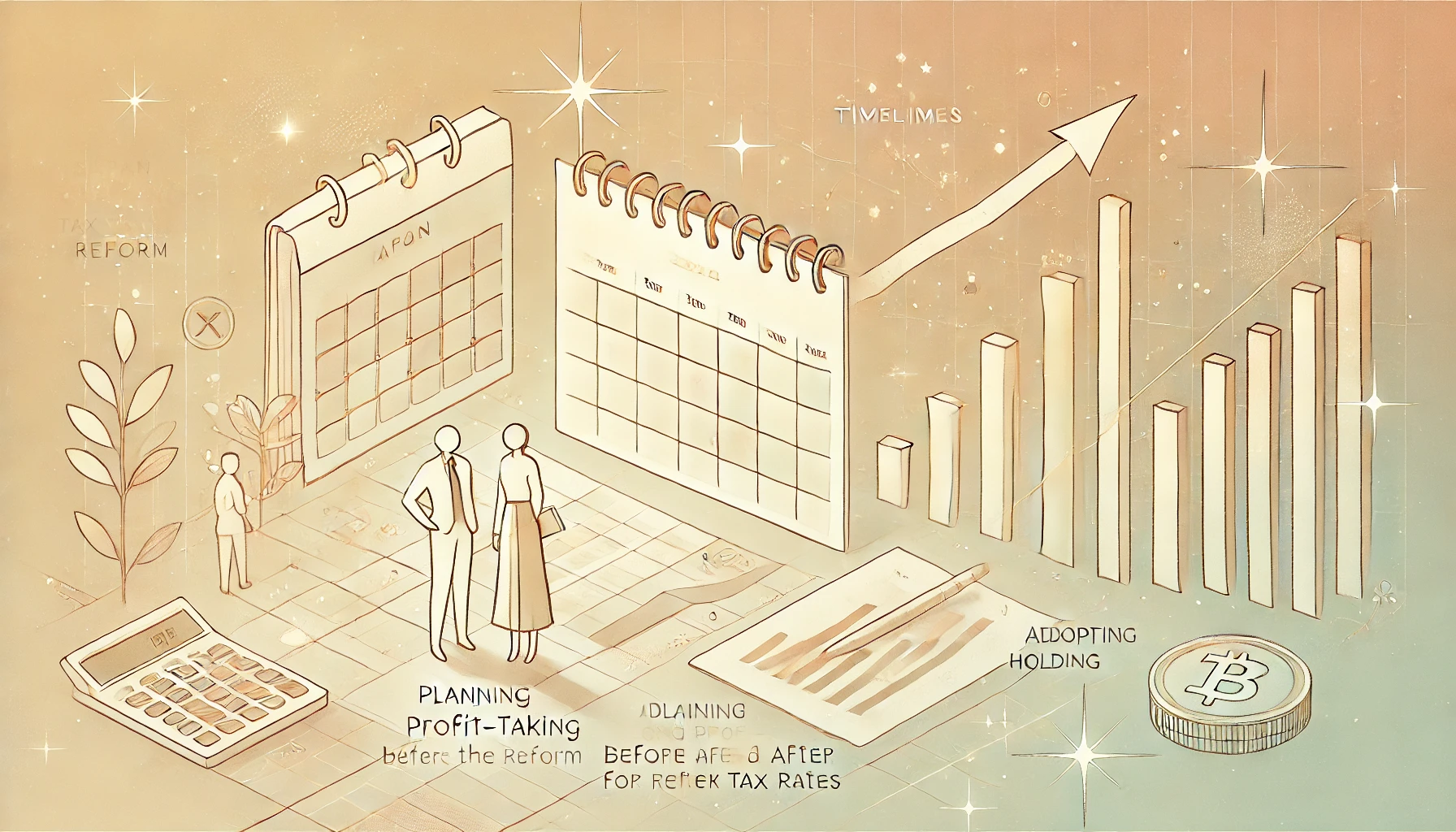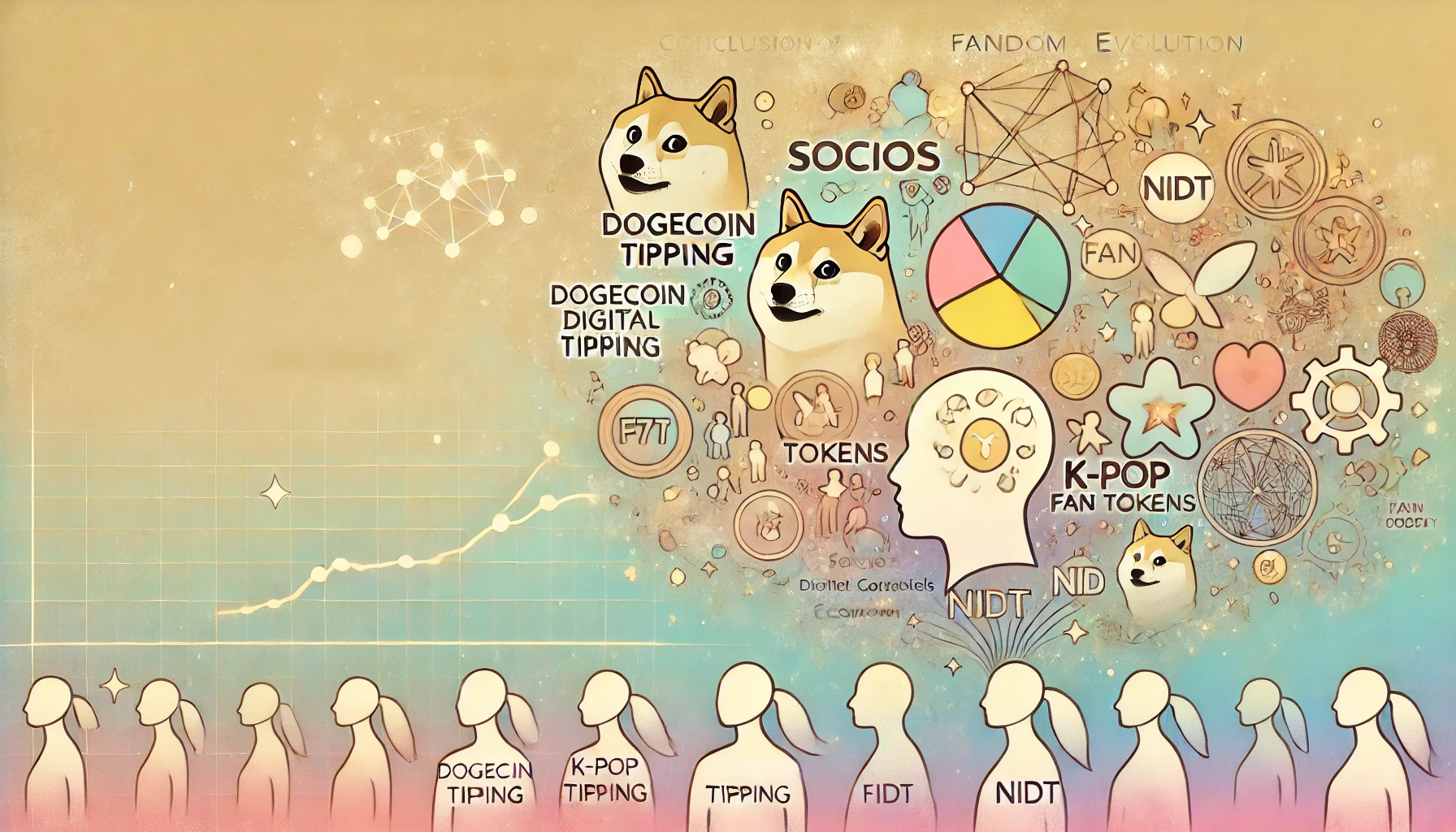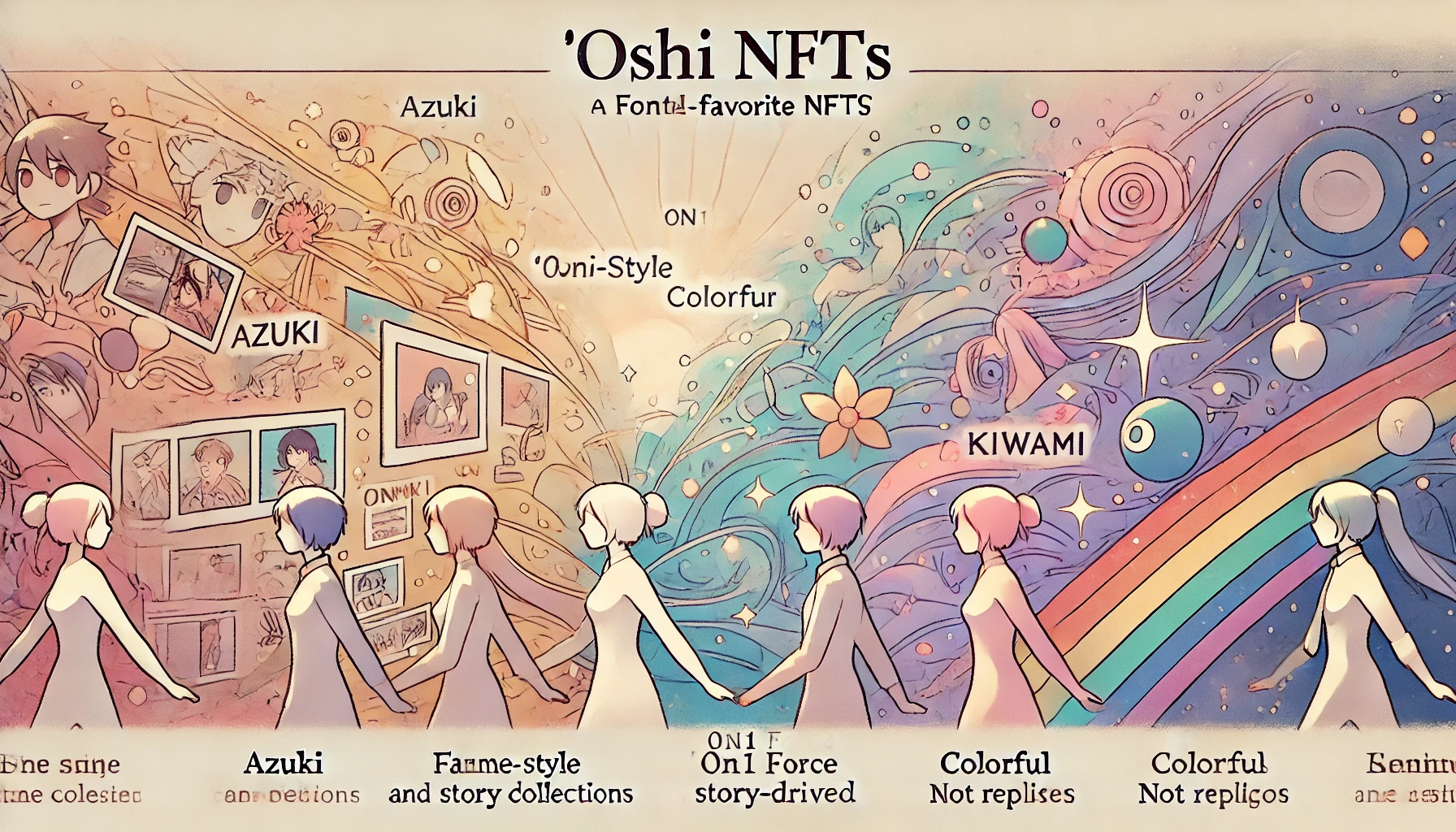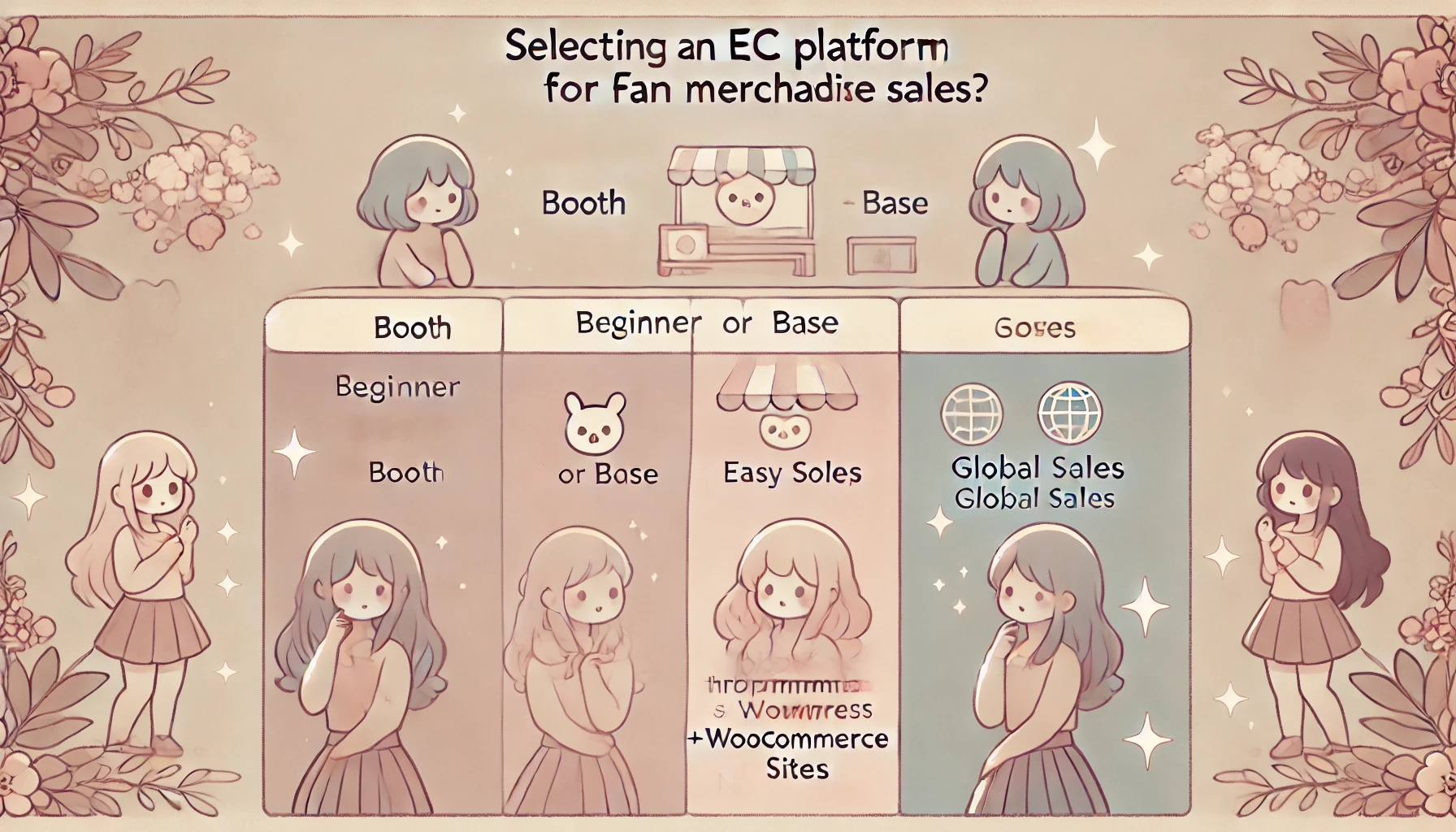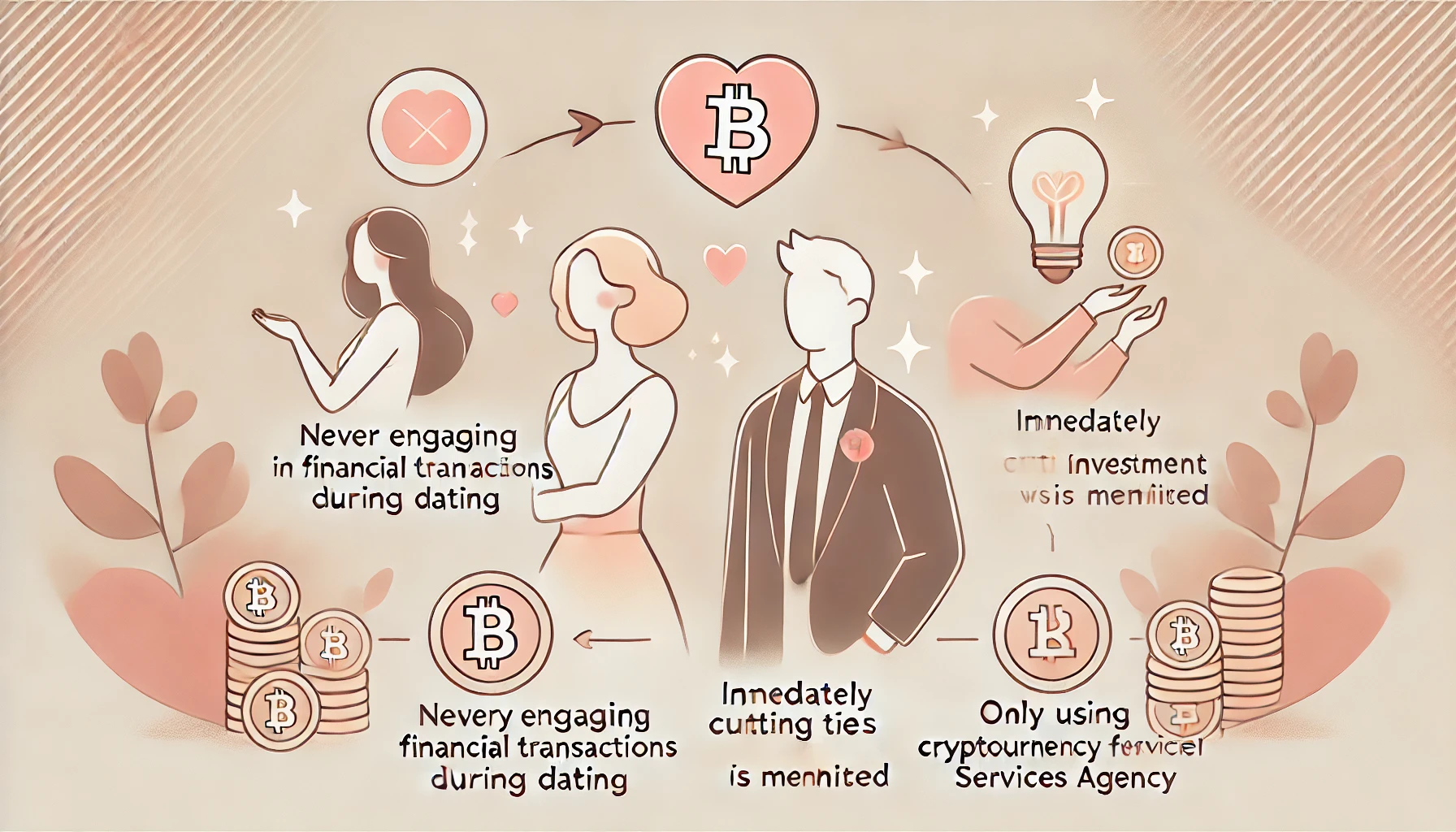仮想通貨は「家計の足し」になるのか?――多くの人が気になるこのテーマについて、実践者の声や税務の現実をもとに、リアルな副収入戦略を解説します。儲け話ではなく、知識・計画・リスク管理を前提とした現実的な選択肢を見ていきましょう。
仮想通貨は副業か?それとも資産運用か?

まず多くの人が疑問に思うのは「仮想通貨は副業にあたるのか?」という点です。
結論から言えば、会社員や公務員でも原則として仮想通貨投資は副業に該当せず、資産運用とみなされます。株式投資や不動産投資と同様に、本業への支障が少ないという点が理由です。
ただし注意すべきは、税務上は「雑所得」として扱われることです。これは給与や事業所得と合算される総合課税であり、特に20万円を超える利益が出れば確定申告が必要です。
会社にバレないための工夫
確定申告を行うと、住民税額が変動し会社に副収入が知られる可能性があります。このリスクを下げるには、住民税を「普通徴収」(自分で納付)に設定する方法が有効です。
仮想通貨で副収入を得る方法

仮想通貨には複数の収益手段があります。代表的な方法は次の通りです。
- 売買(トレード):価格差益を狙う取引
- ステーキング:通貨をロックして報酬を得る
- マイニング:計算資源を提供して報酬を得る
- DeFiレンディング:仮想通貨を貸し出して利息を得る
- NFT・P2Eゲーム:デジタルアートやゲーム内資産の売買
これらは収益性だけでなく、リスクや時間的拘束も大きく異なります。次の章から具体的に解説します。
売買(トレード)の収益性とリスク
最も一般的な方法は、安く買って高く売る「トレード」です。短期間で大きな利益が得られる可能性がある一方で、極端な価格変動(ボラティリティ)が最大のリスクです。
実践者の声として「一日で数十万円の利益を得た」という成功談がある一方、「モナコインの暴落でほぼ資産を失った」という失敗談もあります。感情に左右されない取引ルールの設定が不可欠です。
失敗を防ぐ具体策
- 損切りルールを事前に決める
- 短期の値動きに惑わされず、長期視点を持つ
- 詐欺的な「必ず儲かる案件」に注意
ステーキングで受動的収入を得る

ステーキングは、プルーフ・オブ・ステーク(PoS)型のブロックチェーンで通貨をロックし、報酬を得る方法です。手間がかからず受動的に収入を得られるため、人気の高い選択肢です。
しかし、注意すべきは「スラッシュ(没収)」や「ロックアップ期間」に伴う流動性リスクです。さらに、報酬受取時点の価格で課税されるため、納税資金の確保が不可欠です。
ステーキングで気をつけるべき点
- 報酬受領時の価格で課税される
- ロック期間中の急落リスク
- スラッシュ(罰則)による資産没収の可能性
マイニングによる収入の現実
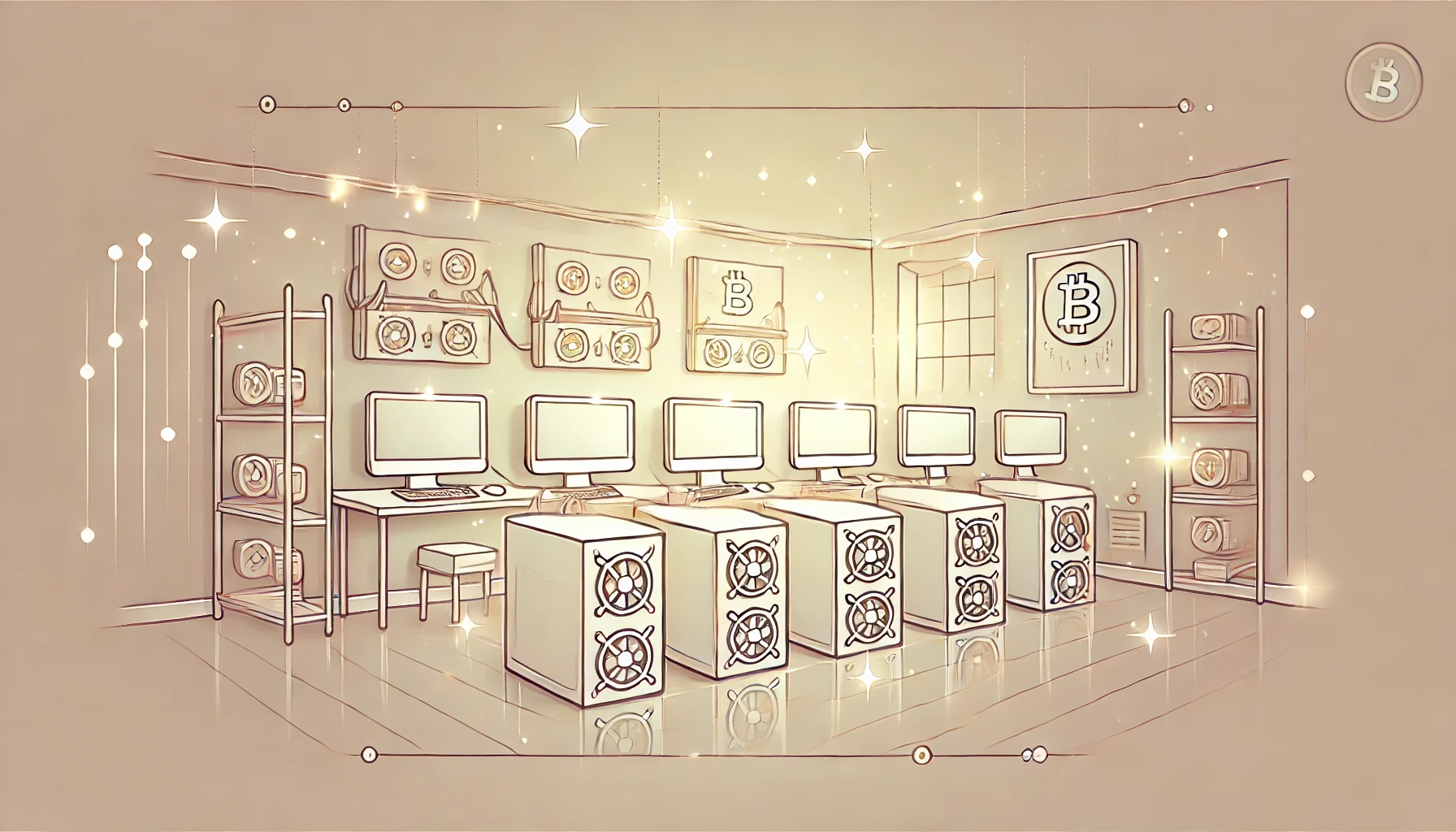
マイニングはコンピュータの計算力でブロック承認を行い、報酬として通貨を得る手法です。特にPoW型では高性能機材と多大な電力コストが必要です。
初期費用や運用コストの高さが最大の課題であり、さらに受け取った報酬は受領時点の価格で課税されます。市場暴落時に納税資金が足りず赤字になるケースも少なくありません。
マイニングでの節税・管理
必要経費として電気代・機材費・インターネット代が計上できます。ただし利益が20万円を超えれば確定申告が必要であり、厳密な記録管理が求められます。
DeFiレンディングで仮想通貨を貸す
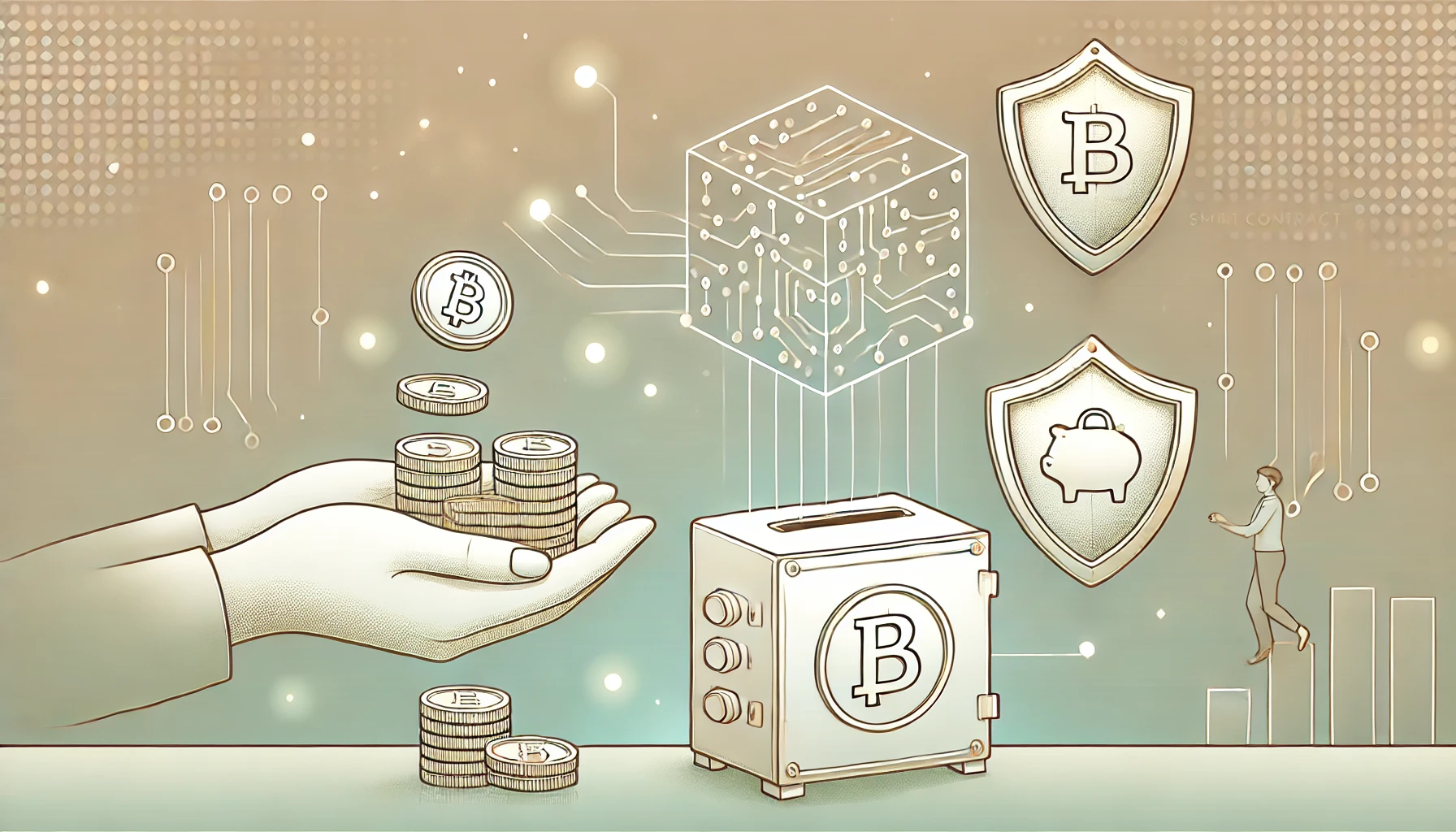
DeFi(分散型金融)では、仮想通貨をプラットフォームに預けて利息を得られます。銀行より高い利回りが期待できる一方、スマートコントラクトの脆弱性やハッキングリスクが大きな懸念点です。
DeFiレンディングのリスク管理
- 監査済みのプラットフォームを利用する
- 担保率や清算条件を理解する
- APYの変動や元本リスクを考慮する
NFTやPlay-to-Earnで稼ぐ
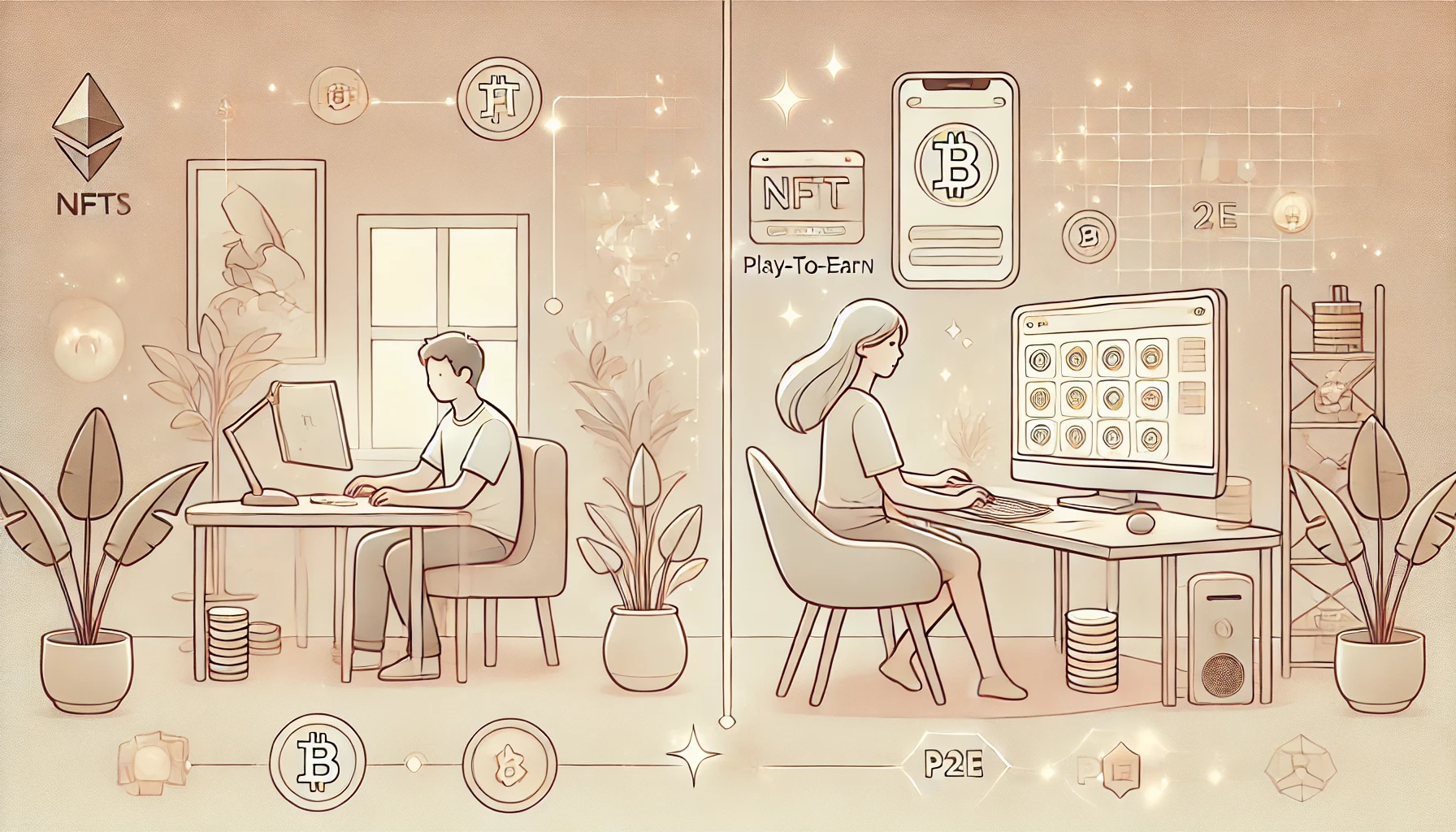
NFT(非代替性トークン)やP2Eゲームは、クリエイティブな活動やゲームプレイで収入を得る新しい方法です。デジタルアートの販売やゲーム内通貨の現金化が主な収益源です。
一方で、市場は未成熟で法整備も遅れており、詐欺・ハッキング被害のリスクが大きいことも忘れてはいけません。
稼ぎやすさと課題
- 初期費用が必要なゲームはリスクが高い
- 著作権や所有権の法的トラブルに注意
- SNSでの詐欺DMにも要警戒
仮想通貨利益の税務と確定申告

仮想通貨の利益は雑所得(総合課税)に分類され、最大55%の高税率が適用されることもあります。20万円超で確定申告が必要です。
また、住民税の変動で会社に副収入が知られる可能性があるため、普通徴収の選択が有効です。
扶養や会社員への影響
- 扶養内は33万円までなら申告不要
- 会社員は20万円超で確定申告必須
- 副収入がバレないための工夫が必要
経費計上による節税

仮想通貨取引にかかった費用は経費として計上可能です。手数料・PC費用・セミナー参加費などが該当します。
領収書の保管は必須であり、経費計上により課税所得を減らし実質的な手取り額を増やせます。
損益通算と損失繰越の限界
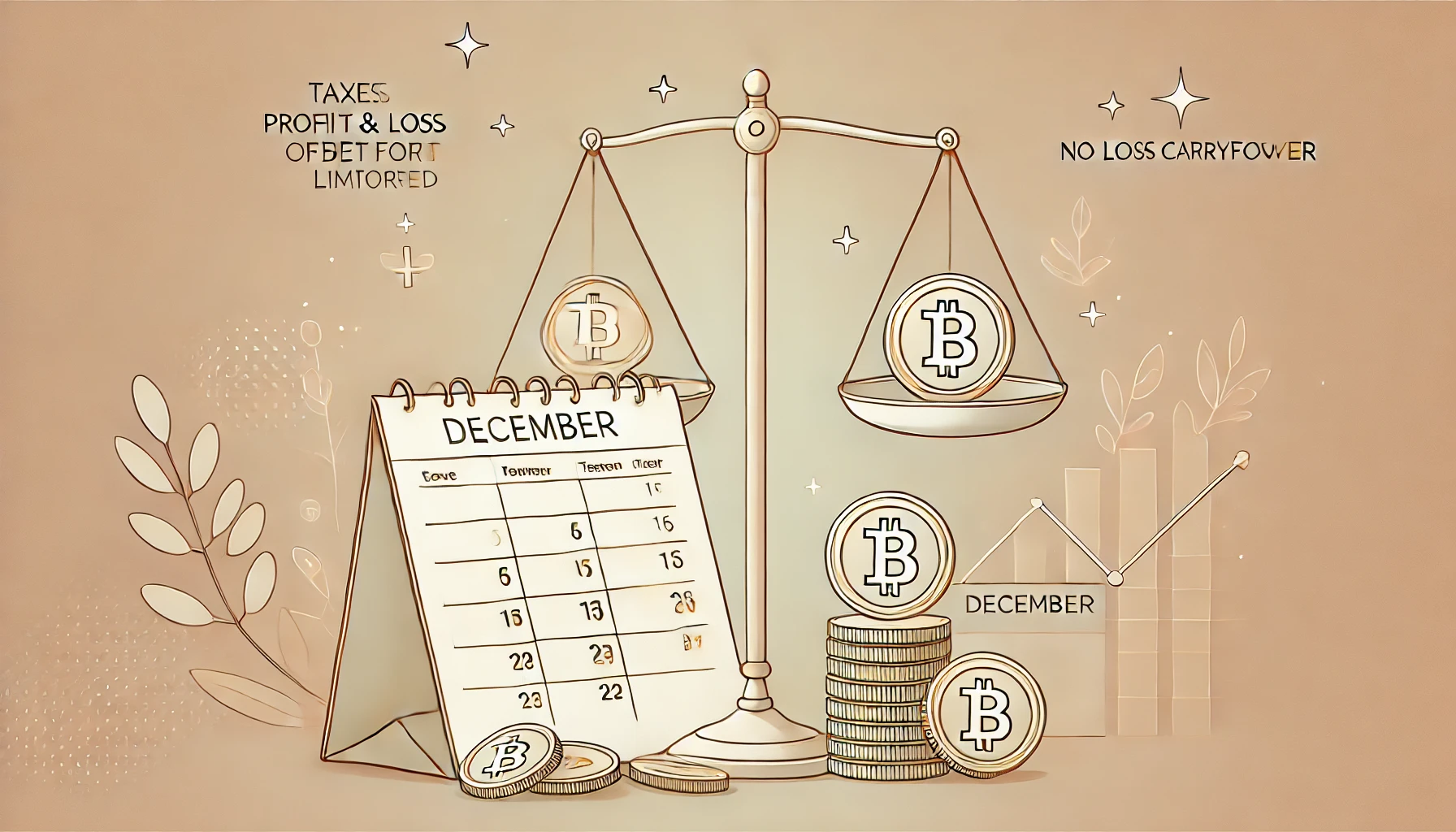
雑所得では損失の翌年繰越ができません。同一年内の仮想通貨間での損益通算は可能ですが、年度をまたいだ控除は認められません。
この制約は「税金だけ払い、手元に利益が残らない」という事態を引き起こす要因になります。
節税のための年末戦略
- 年末に含み損を確定して課税額を減らす
- 利益確定と納税資金確保をセットで行う
税務調査の現実とペナルティ

仮想通貨の税務調査は近年強化されています。無申告や過少申告には最大40%の重加算税が課されることもあります。
突然の税務調査通知や、銀行口座の入出金履歴チェックも行われるため、正確な申告が必須です。
追徴課税の種類
- 無申告加算税:10%〜15%
- 過少申告加算税
- 重加算税:最大40%
- 延滞税
税金計算ツールと専門家の活用
複数取引所を利用している場合、手作業での損益計算は非常に困難です。CryptactやGtaxなどの自動計算ツールが有効です。
また、仮想通貨に詳しい税理士に相談すれば、節税のアドバイスや税務調査への対応もサポートしてもらえます。
リスク管理と家計への活かし方
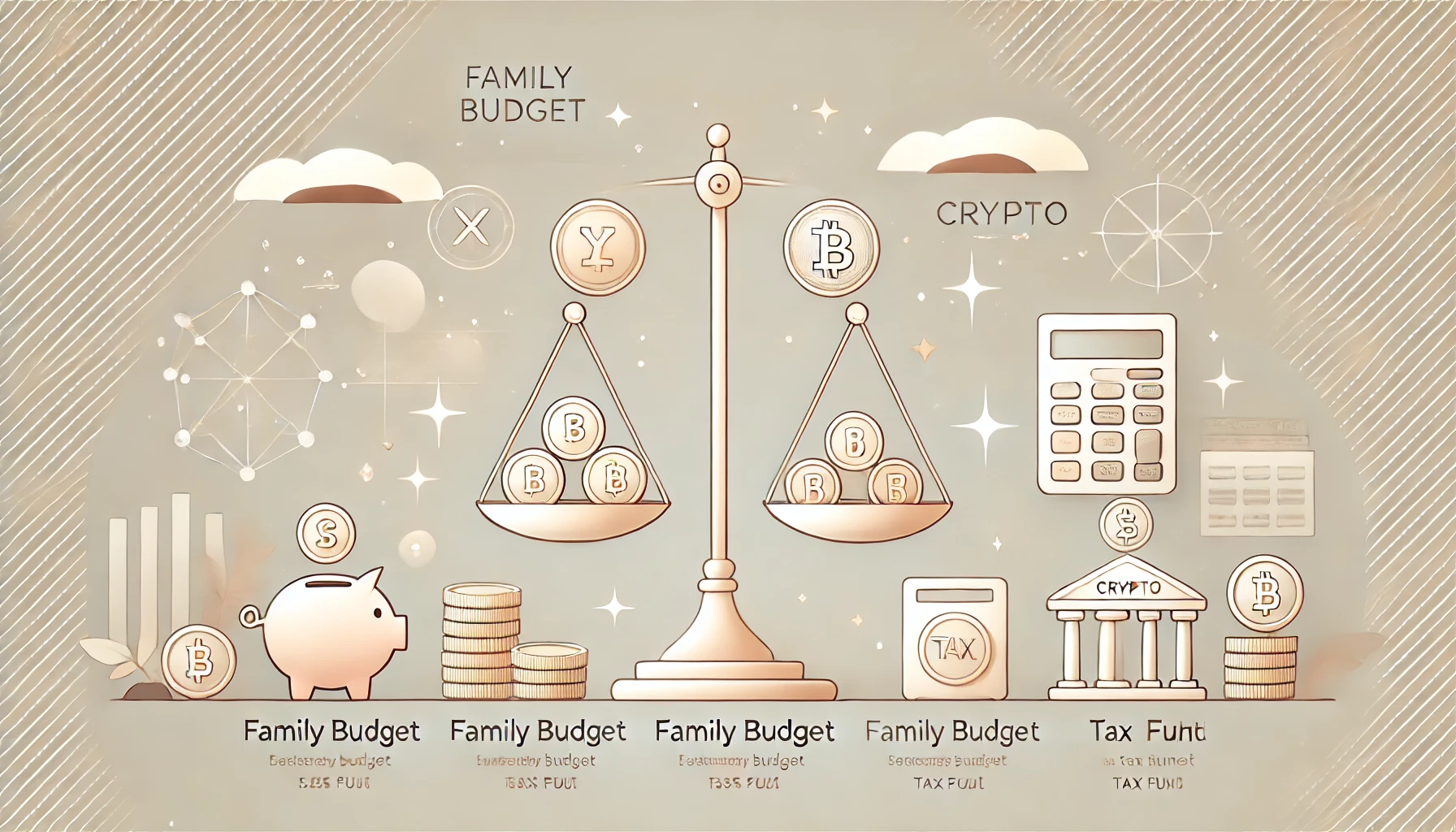
仮想通貨を「家計の足し」にするためには、余剰資金での投資・分散投資・損切りルールの設定が欠かせません。
特に、納税資金を仮想通貨のまま放置せず、換金して確保しておくことが重要です。
金融リテラシーを高める
仮想通貨の保有は経済への関心を高め、自然と金融リテラシーが向上します。信頼できる情報源を選び、詐欺や感情的取引から身を守ることが成功の鍵です。
仮想通貨は家計の足しになるのか?

仮想通貨は確かに副収入となり得ますが、それは「知識」「計画」「リスク管理」が揃ったときのみです。無計画な取引や無申告では、家計の足しどころか負担になりかねません。
正しい知識と準備で、仮想通貨を賢く活用し、家計改善に役立てましょう。
本記事では、仮想通貨を家計に活かすための現実的な手法を紹介しました。
大切なのは「いかに稼ぐか」だけでなく、「いかに守り、いかに納税するか」。
長期的な家計の安定のために、今日から計画を立てて行動してみてください。