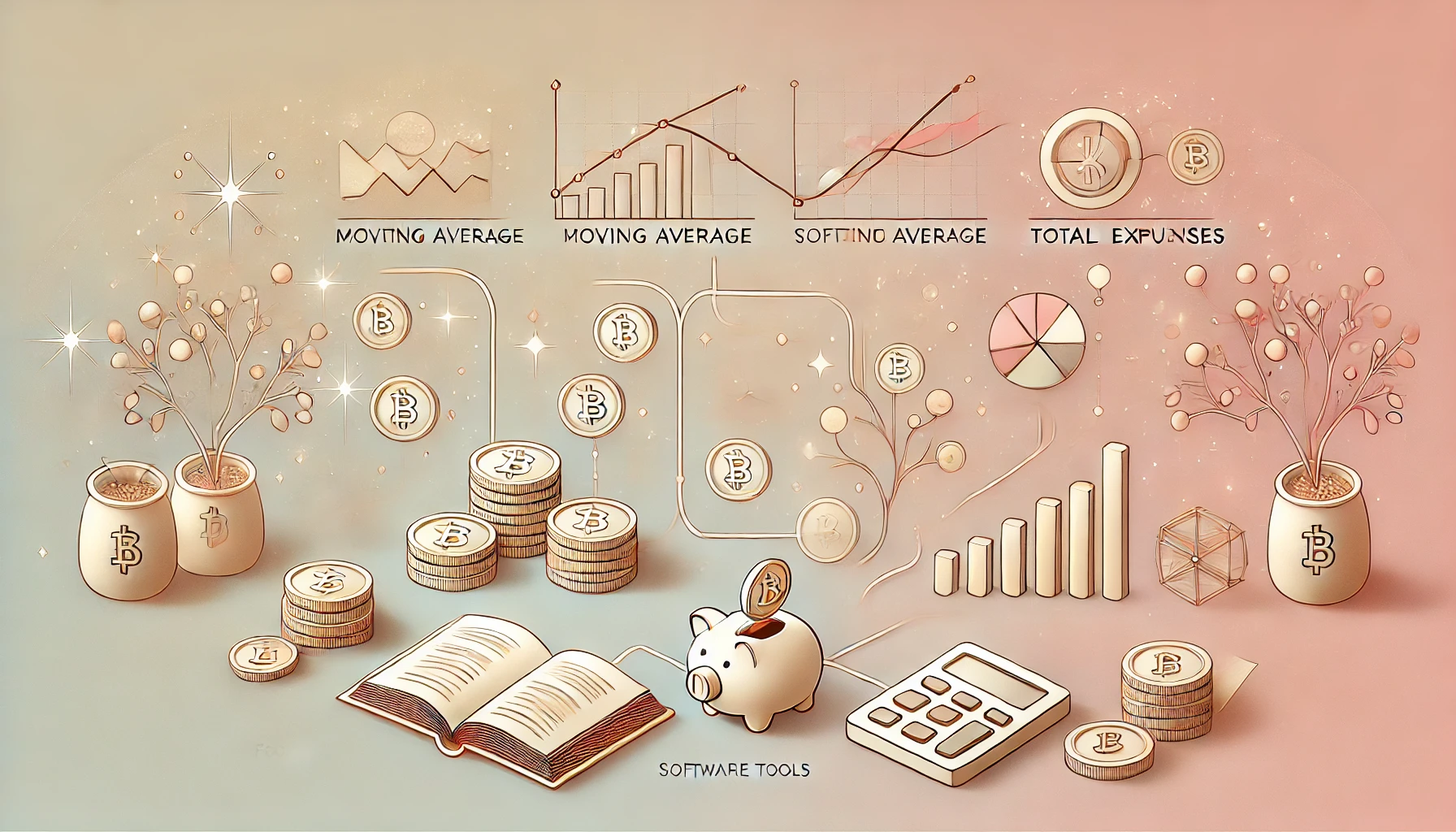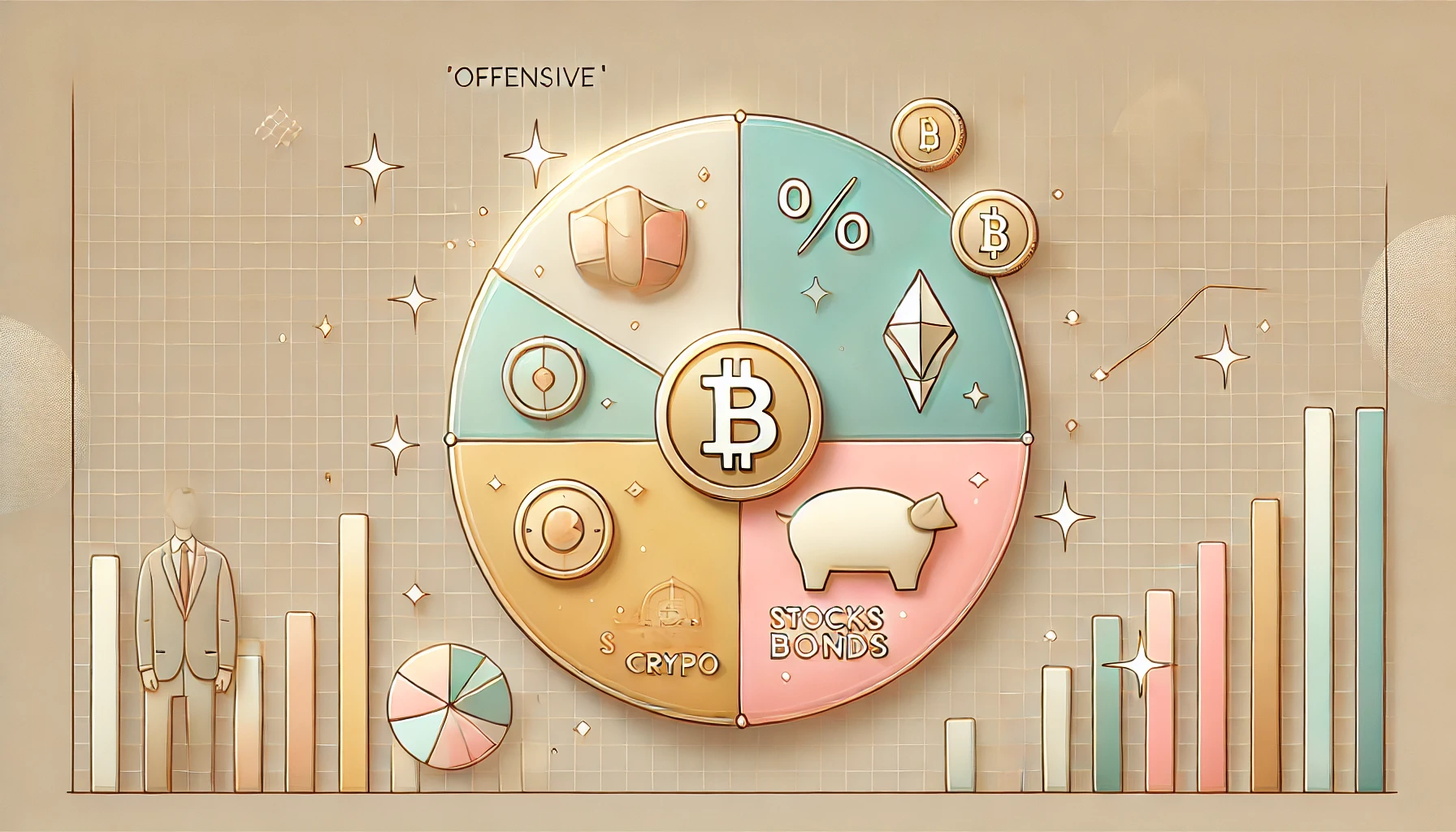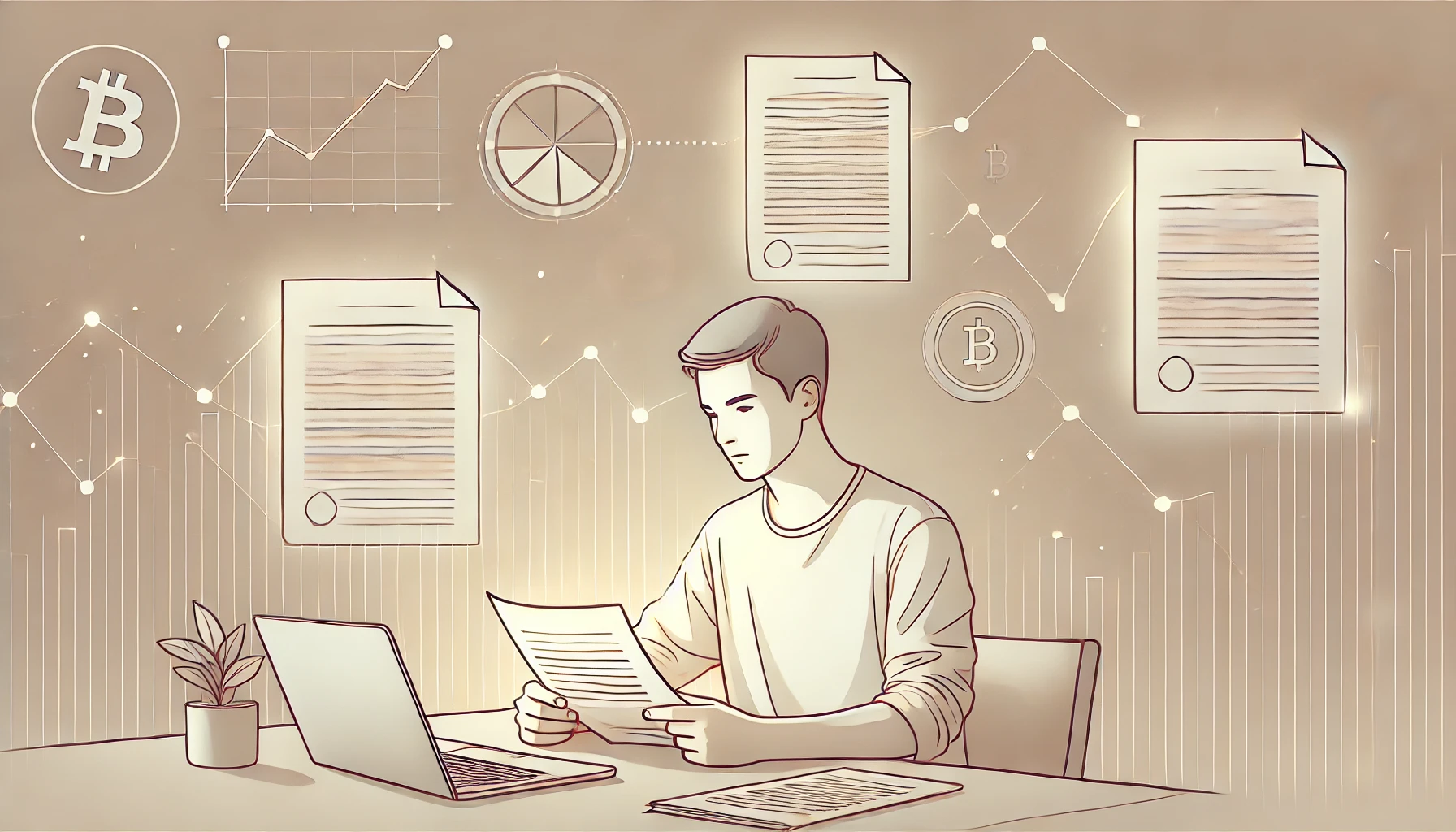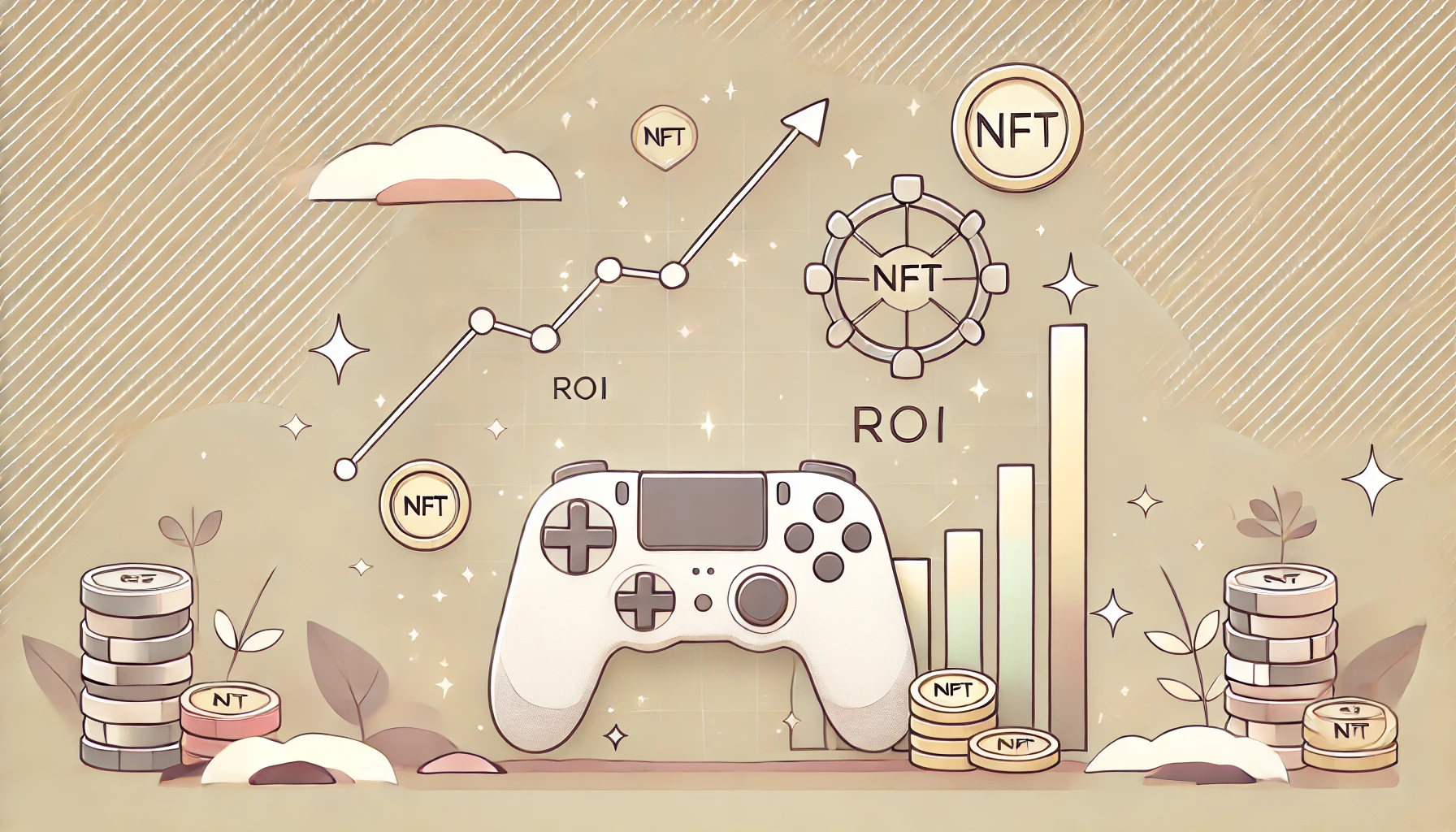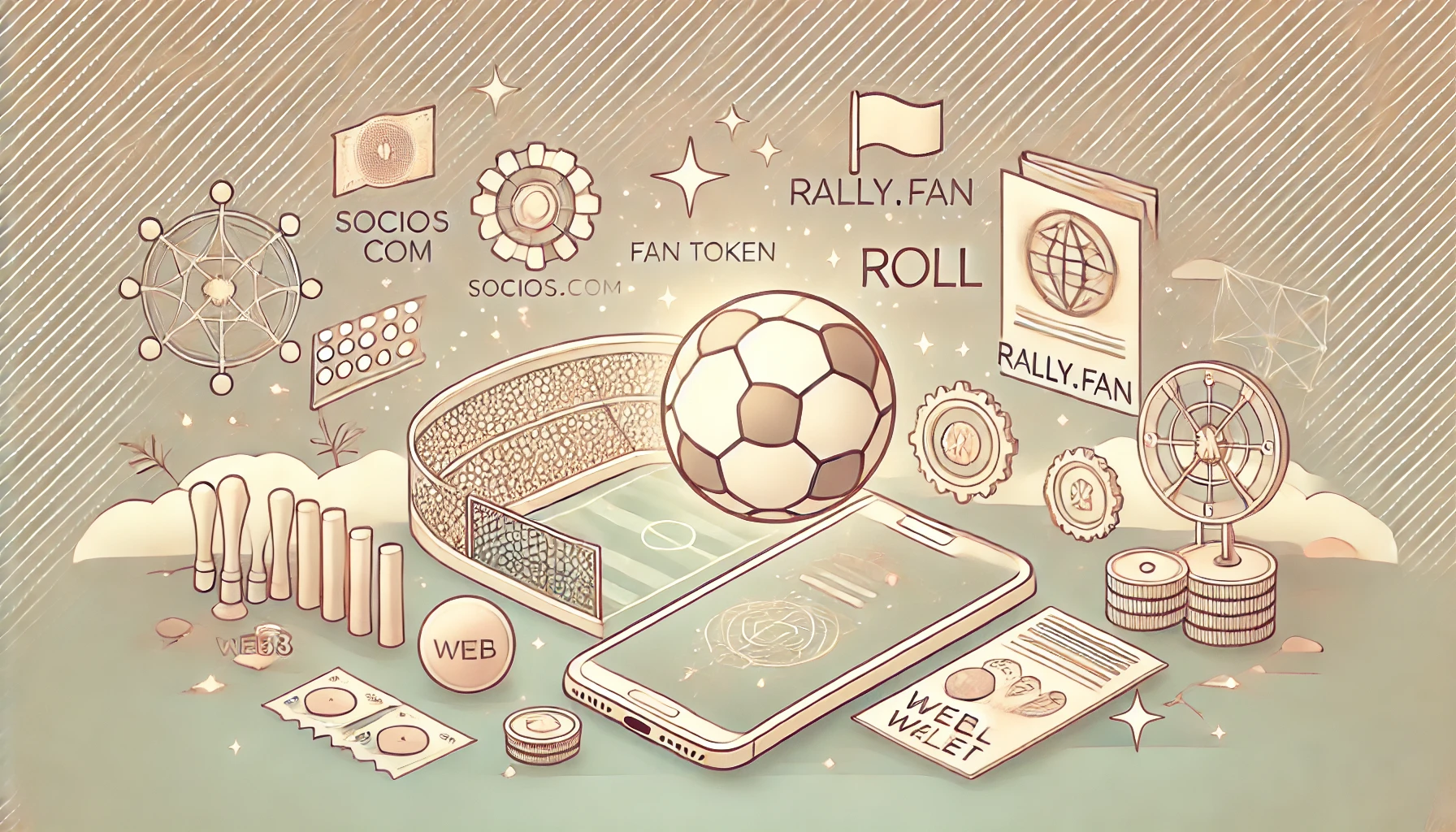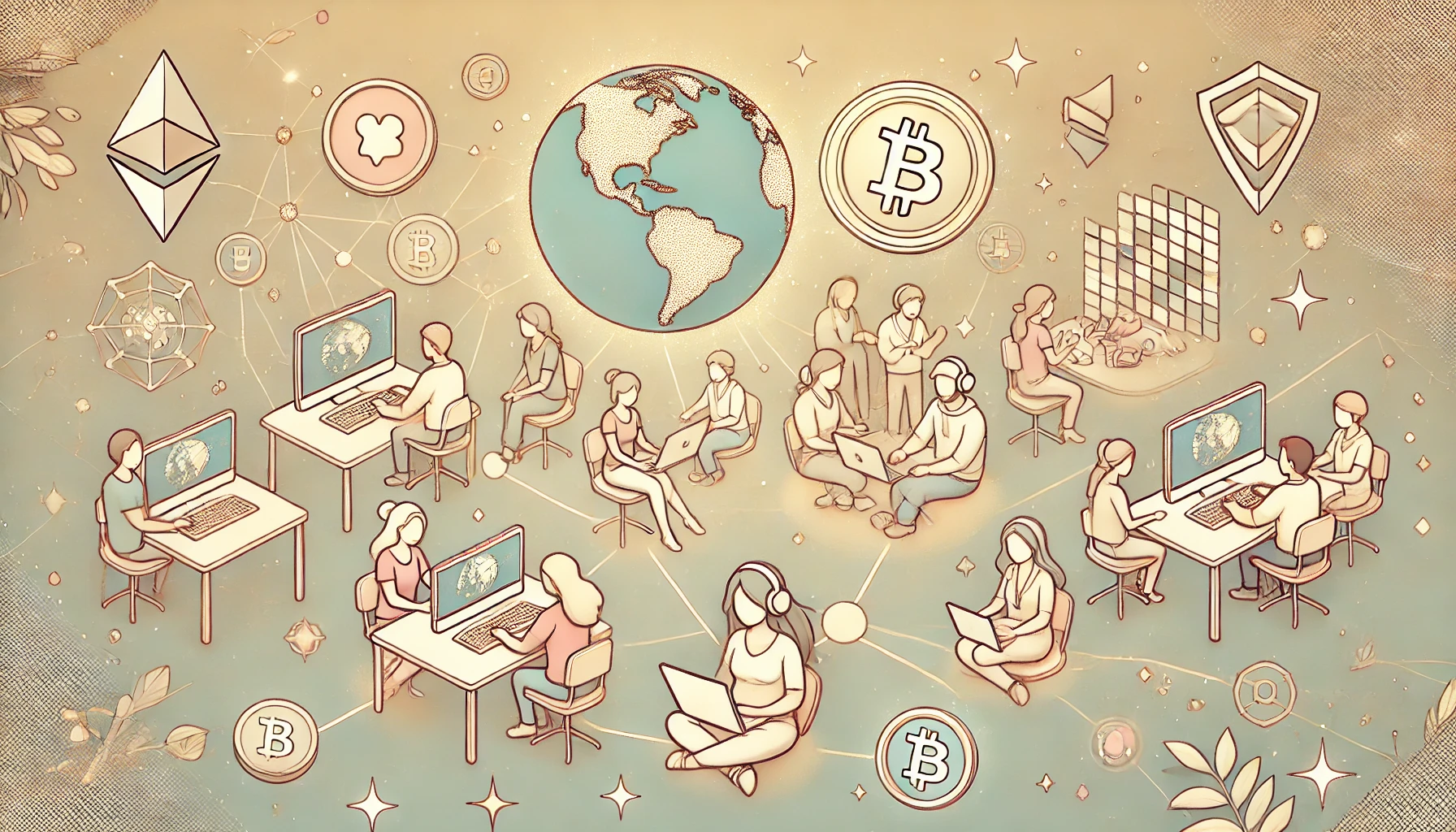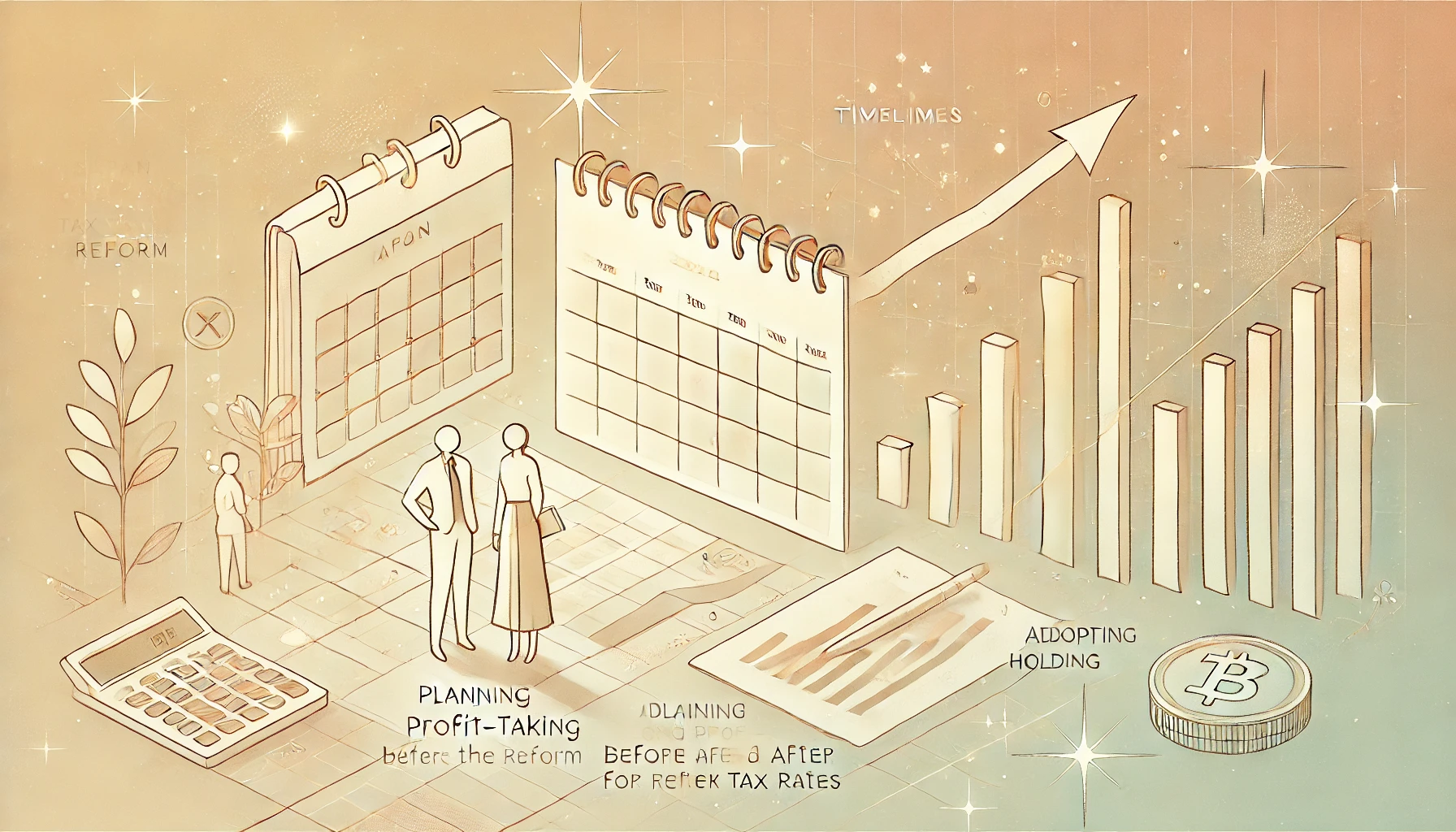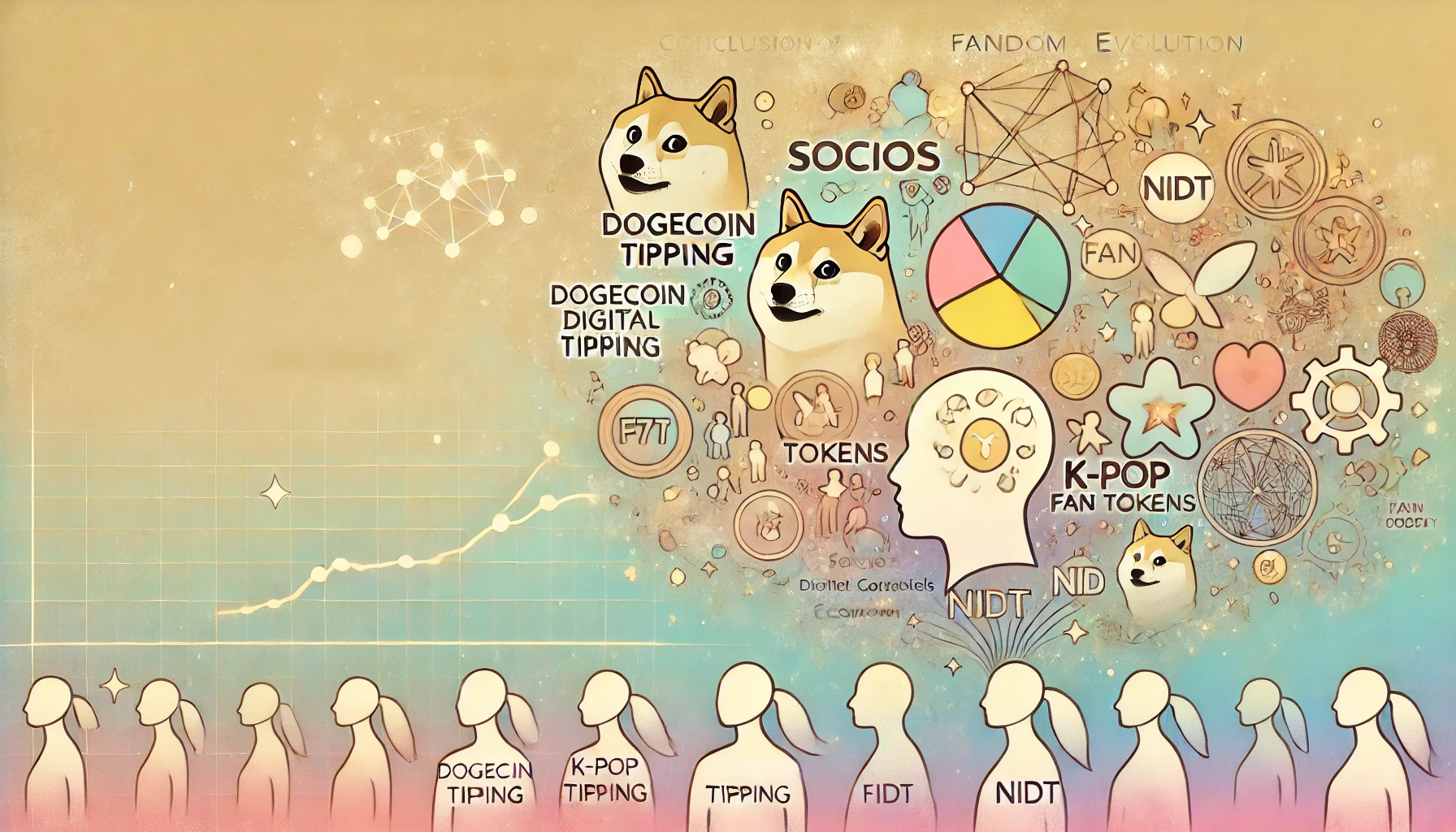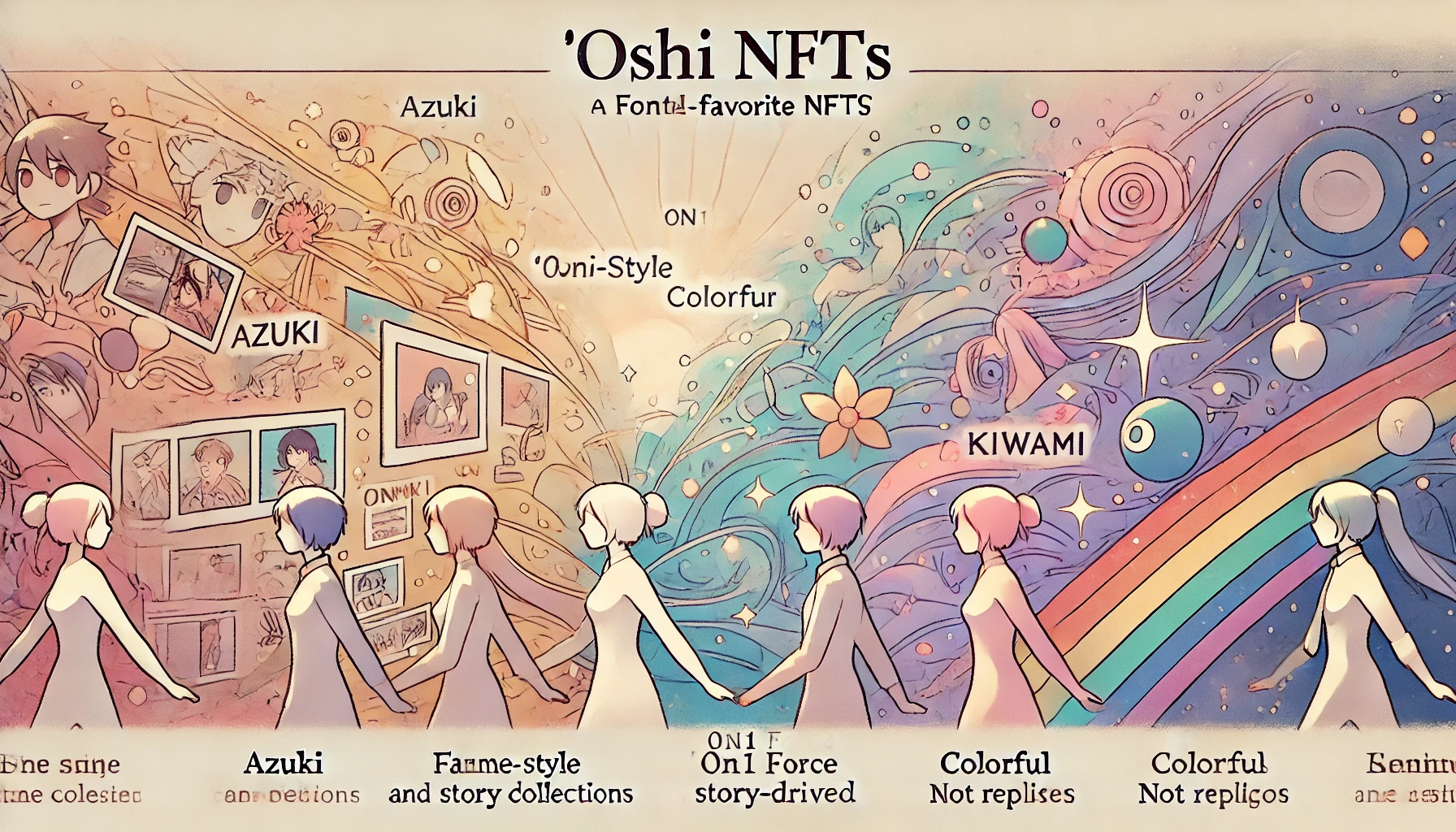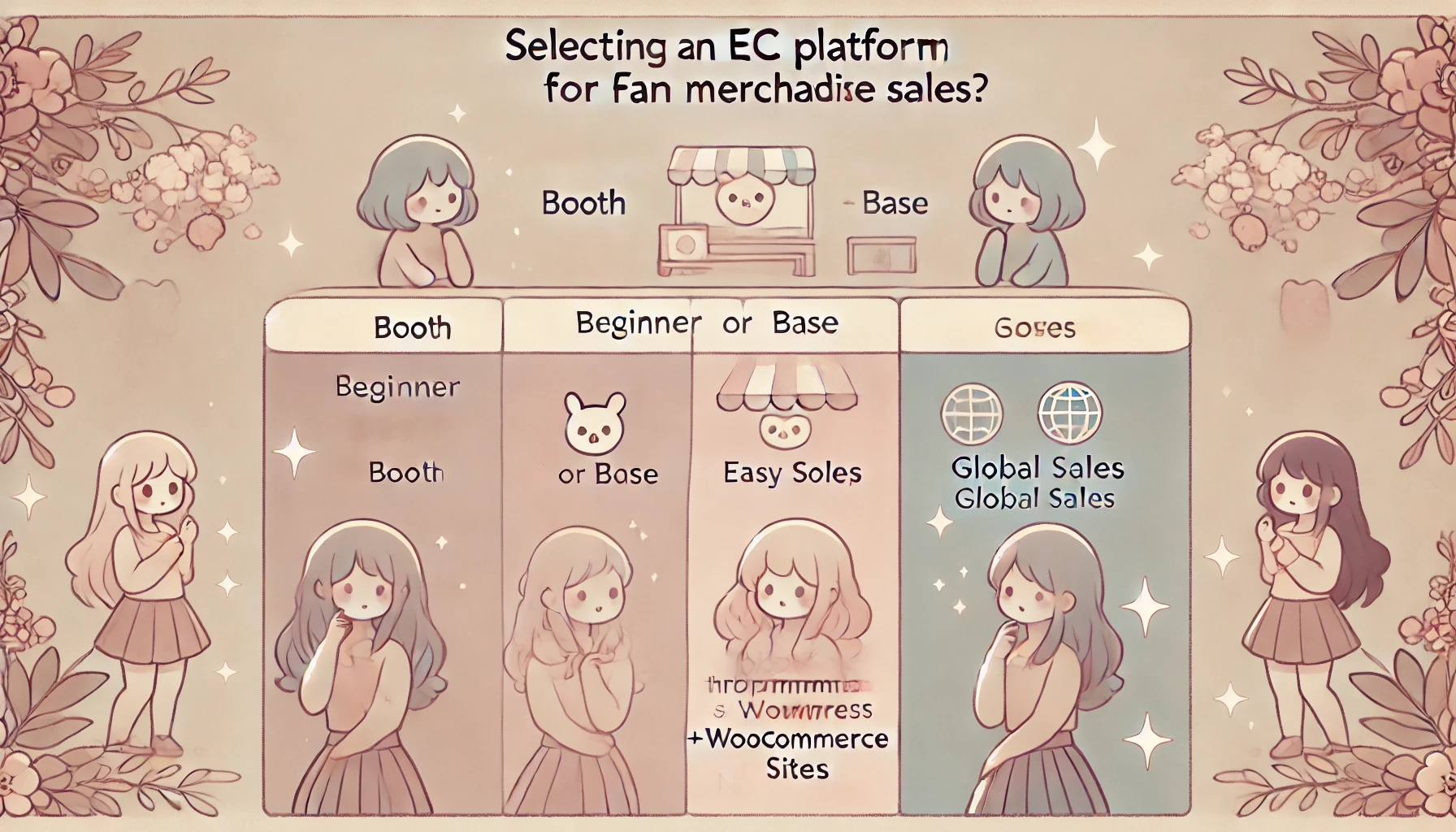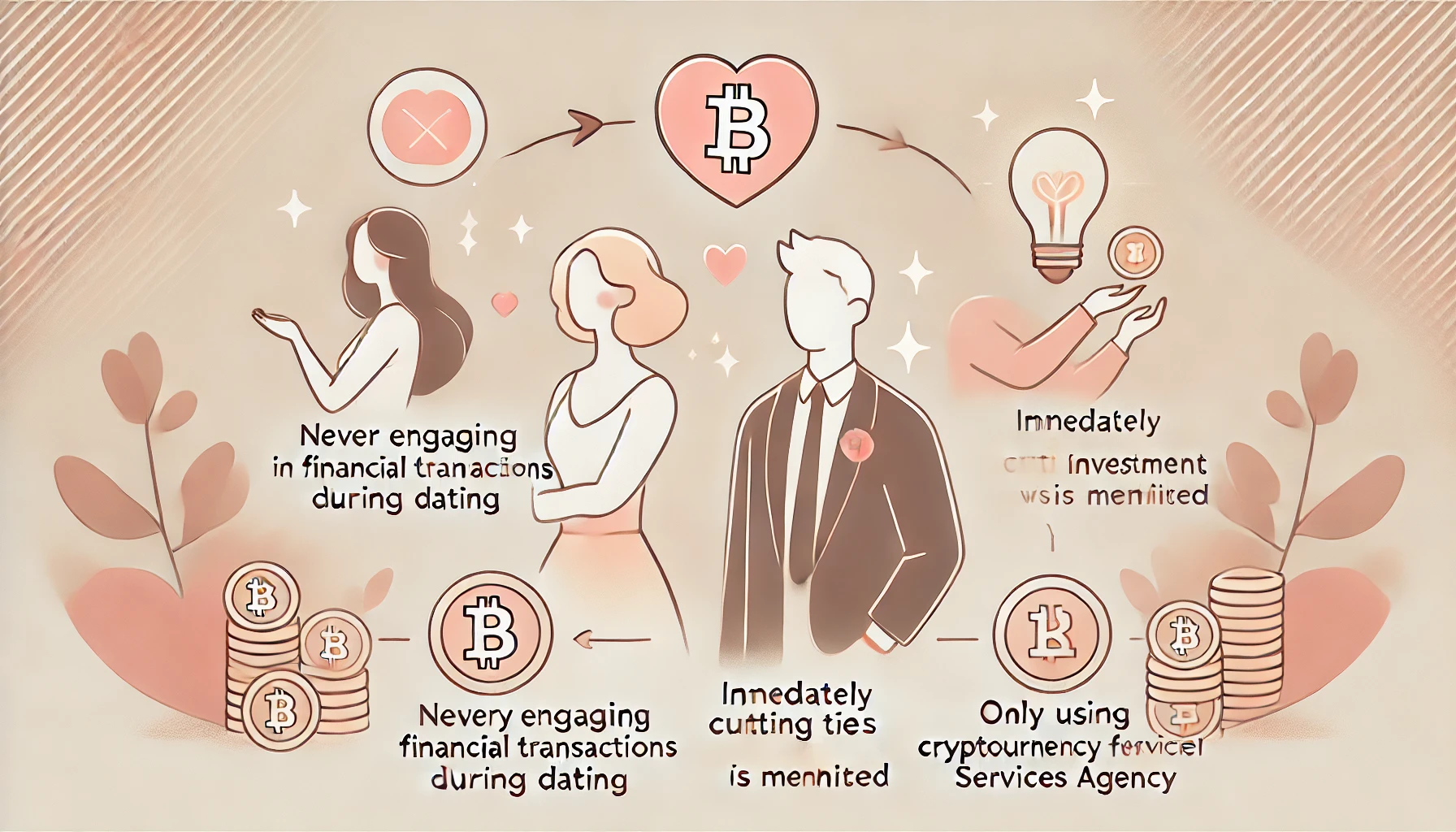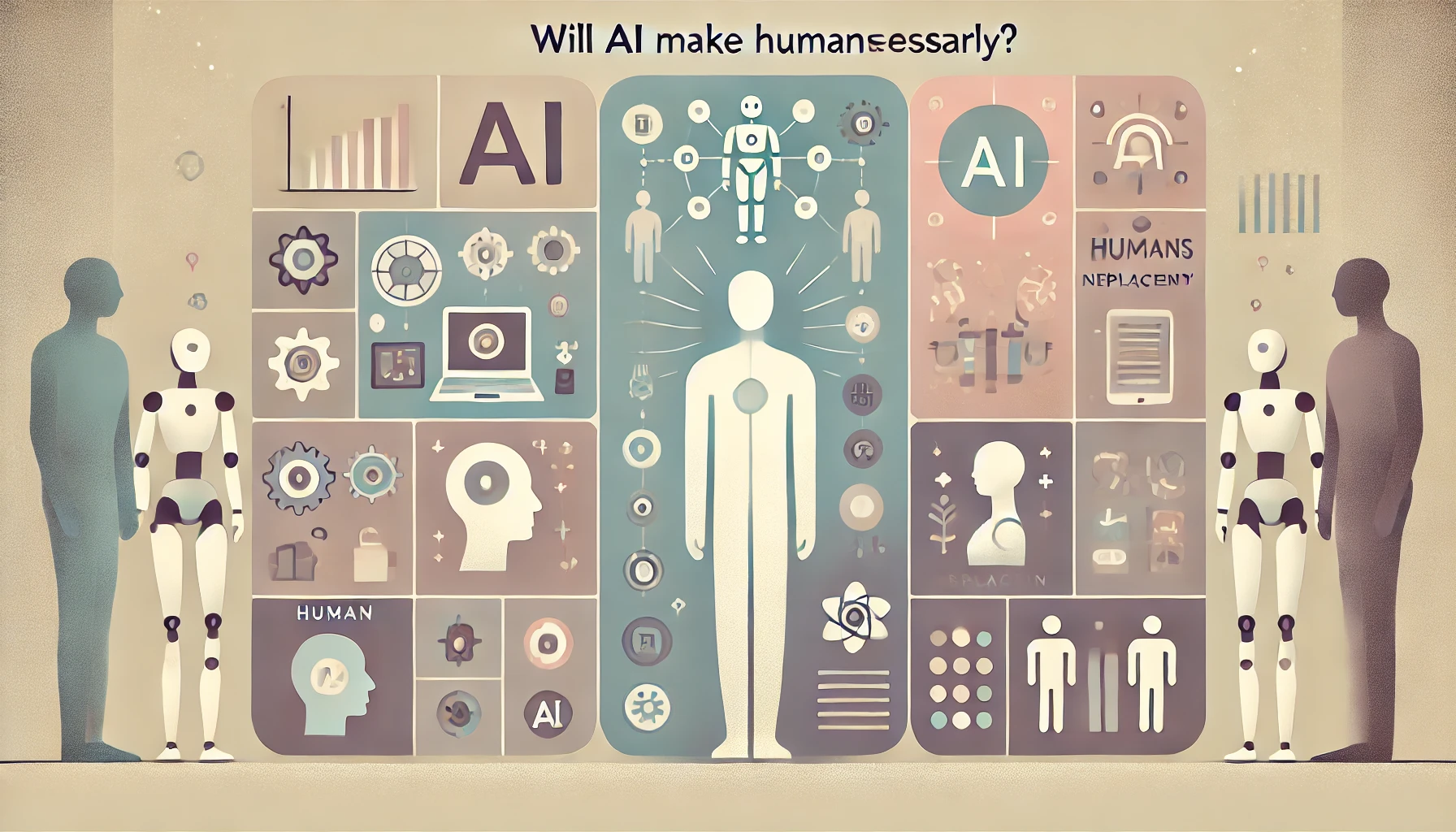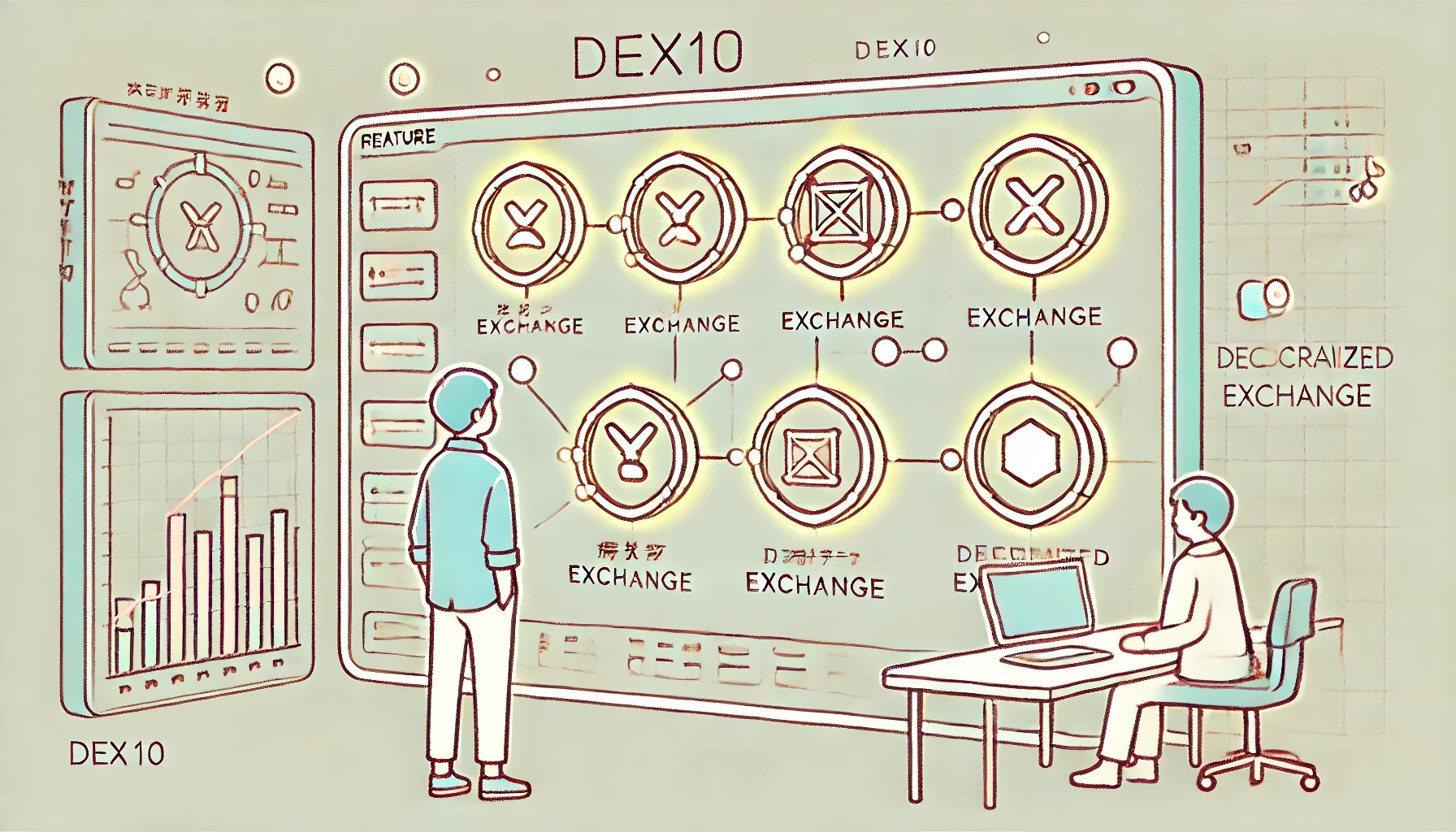この記事では、今注目を集めている「教育×Web3=EduFi(エデュファイ)」の最前線について紹介します。
世界各国でブロックチェーン技術を活用した教育プロジェクトが続々と登場しており、教育のあり方そのものが大きく変わろうとしています。
教師や学習者が主役となり、トークン報酬を通じて経済的価値を得る。あるいは、NFTやDAOといったWeb3的な仕組みによって、学びが「参加型」に変わる。
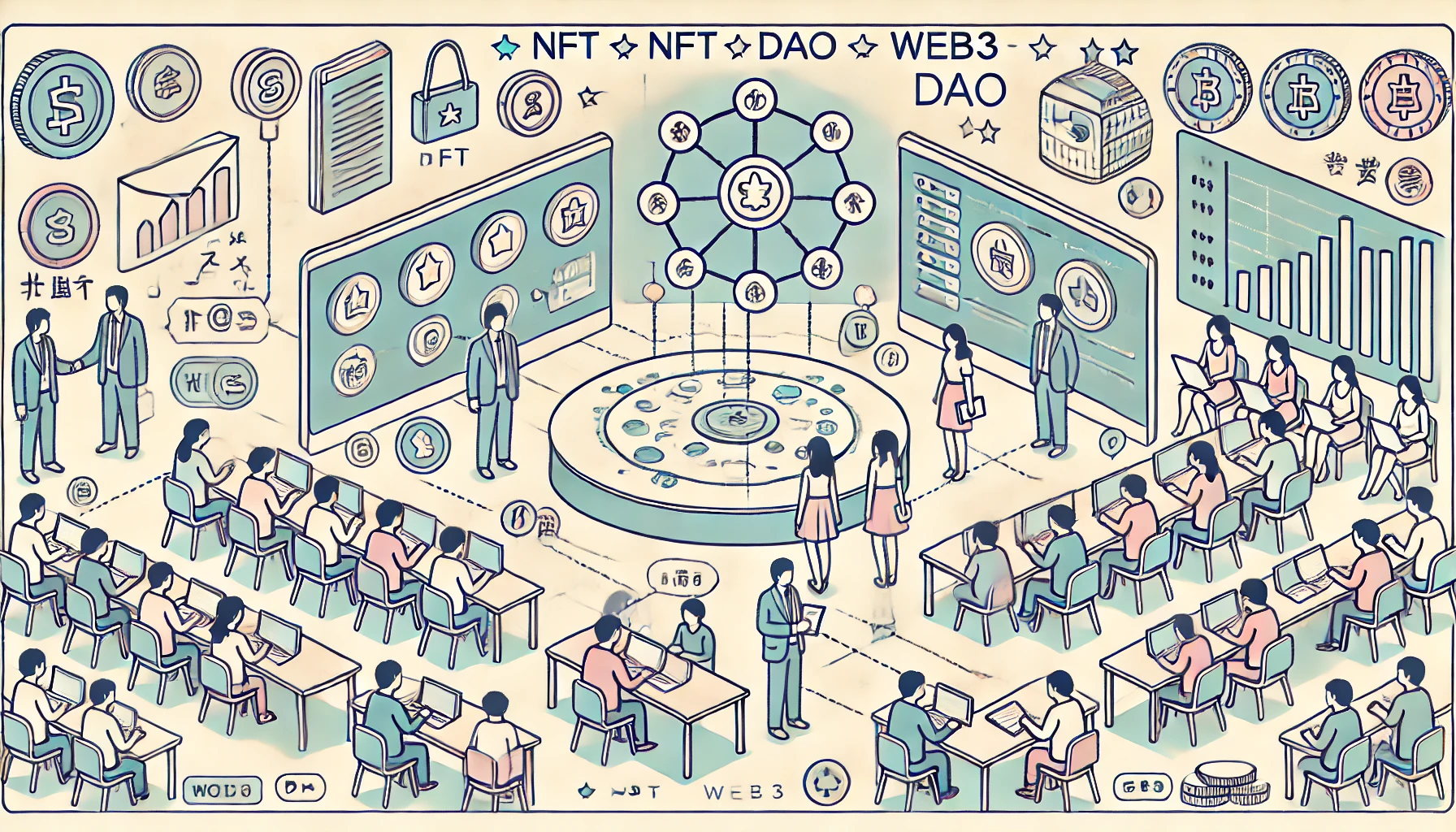
本記事では、そんな新しい教育モデルに挑む先進的なプロジェクトたちをピックアップ。
「Open Campus」「Metacrafters」「BitDegree」など、海外で注目される5つの事例を紹介し、その特徴・意義・今後の課題を整理しました。
教育分野のWeb3化に関心がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
Open Campus(EDU)とは?
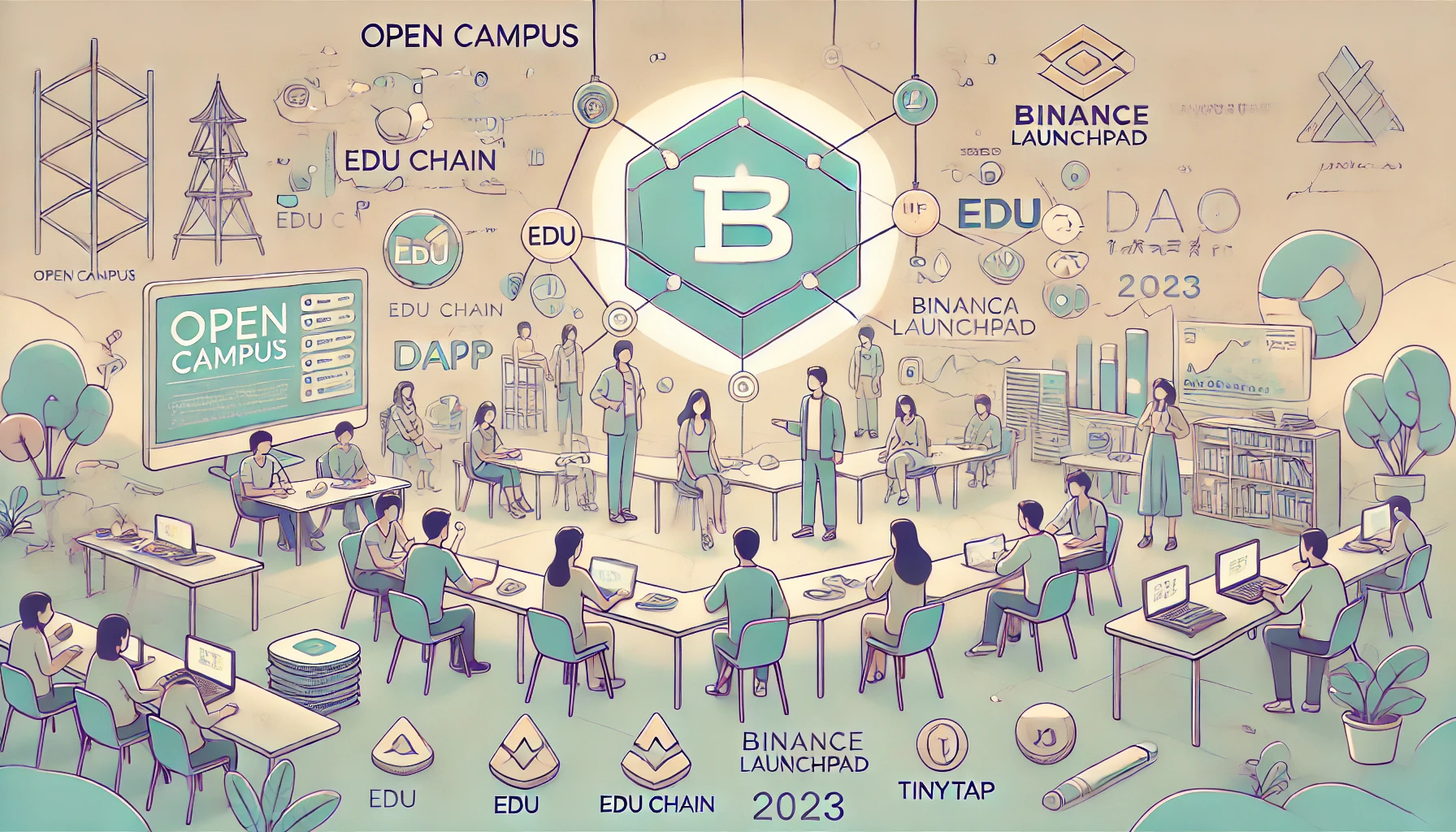
Open Campusは、教育コンテンツの創作者である教師や教育者を経済的に支援することを目的とした分散型プロトコルです。
教育向けのdAppに特化したレイヤー3ブロックチェーン「EDU Chain」をArbitrum上に構築し、ガバナンス兼ユーティリティトークン「EDU」を中心としたトークンエコノミーを展開。
2023年にはBinance Launchpadでも注目を集め、大手のAnimoca BrandsやTinyTapも支援するDAOプロジェクトとして急成長しました。
収益モデルと実例
Open Campusでは、教育コンテンツをNFTやトークンとして資産化し、販売・流通させることで収益化が可能です。
実際に子会社のTinyTapでは、教育ゲームのコースをNFT化して販売。
購入者と教育者が収益を分配する仕組みを導入し、これまでにない「学びのマネタイズ」を実現しています。
社会的意義
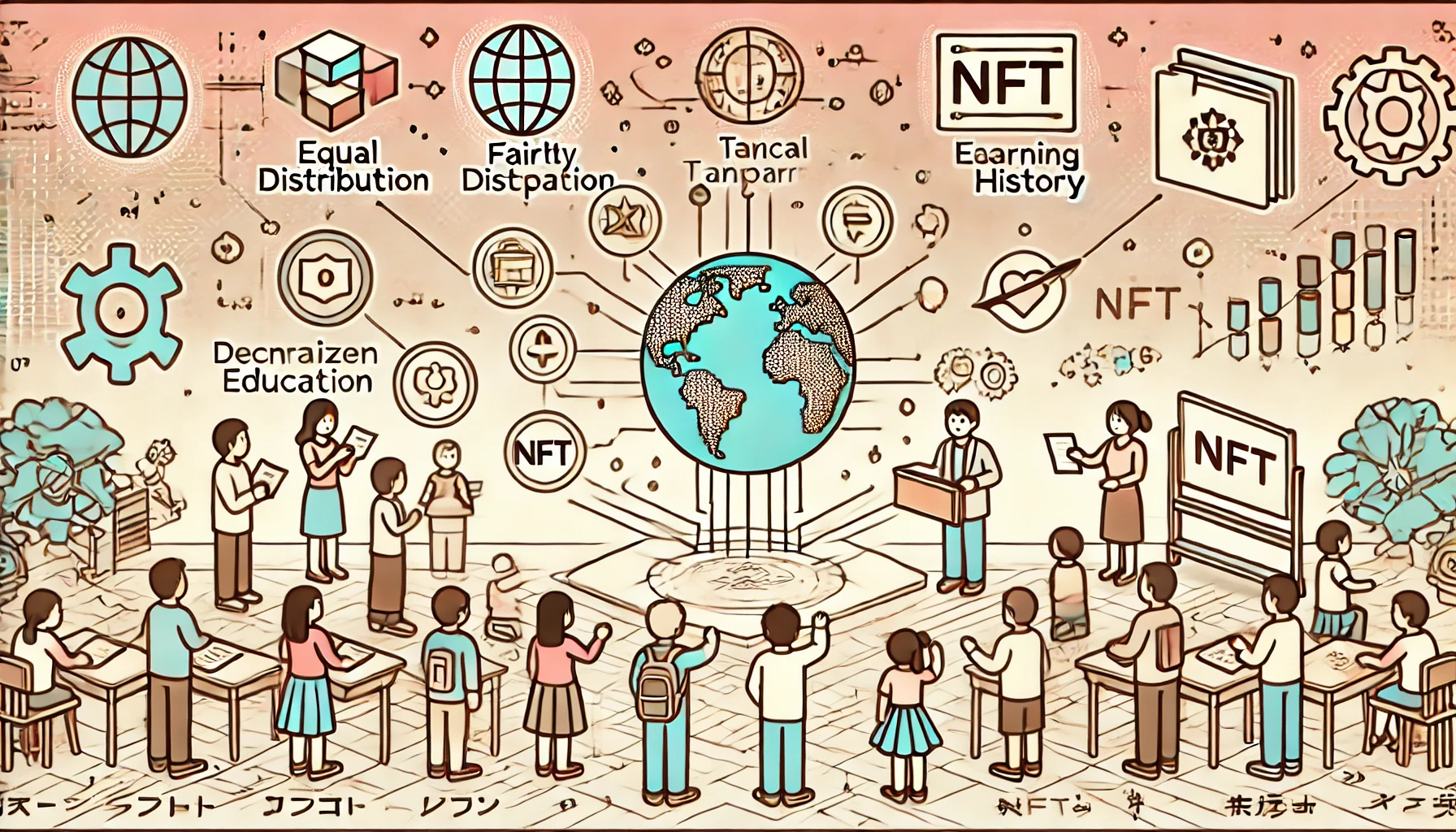
教育格差の解消という観点でも注目されています。
地域や経済力に左右されることなく、教育者が自作の教材をグローバルに販売・評価・報酬化できることは大きな意義があります。
また、コミュニティによる寄付金の透明な分配や、学習履歴のNFT証明など、従来の教育機関に依存しないエコシステムの構築を目指しています。
今後の課題と展望
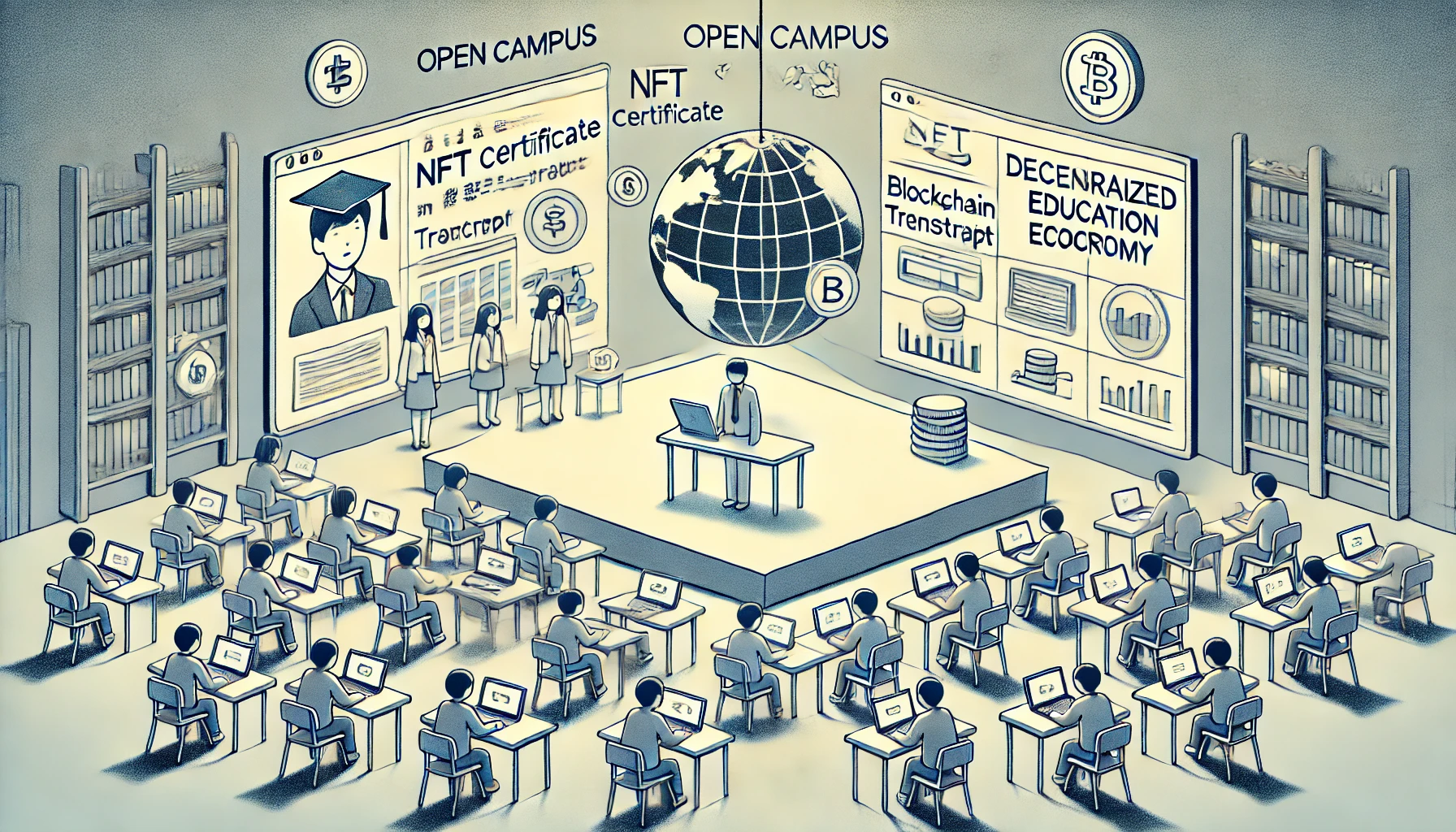
一方で、課題もあります。
ブロックチェーン上の学習履歴やNFT証書を、どこまで従来の学校・企業が認めるのかは未確定。
また、各国の規制によってはトークン導入そのものに制限がかかる可能性もあります。
それでもOpen Campusは、学ぶだけでなく、教育そのものに貢献しながら報酬を得る“分散型教育経済”という新しい未来像を描いており、今後の動向に注目です。
Metacraftersとは?
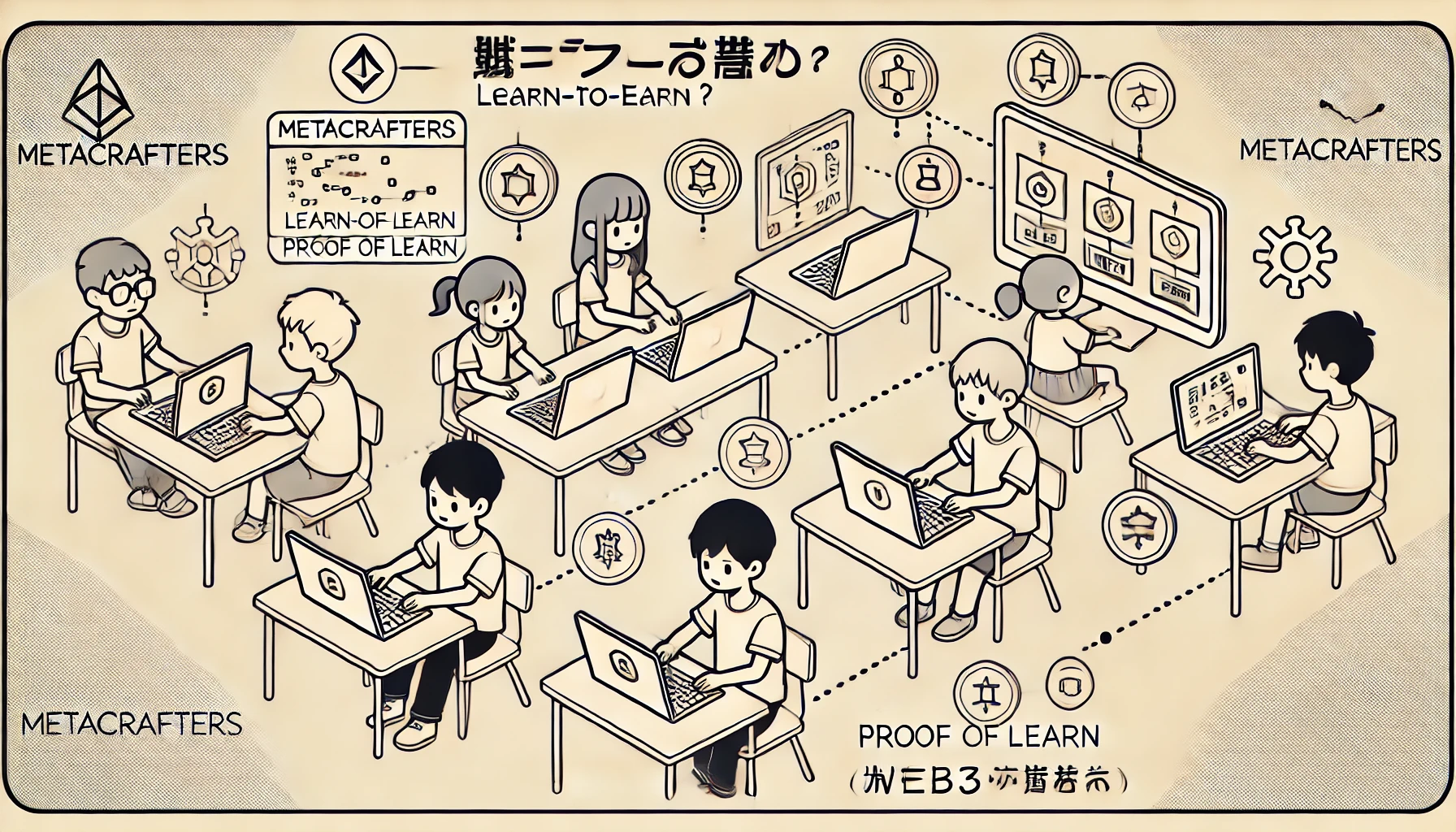
Metacraftersは「学んで稼ぐ」をコンセプトに、ゲーム感覚でブロックチェーン開発スキルを習得できるLearn-to-Earn型の教育プラットフォームです。
運営母体であるProof of Learn社は、特にフィリピンをはじめとした新興国の若者にWeb3エンジニアとしてのキャリア機会を提供することをミッションに掲げています。
奨学金のような報酬モデル
Metacraftersの大きな特徴は、受講料を先払いするにもかかわらず、学習を完了すれば報酬としてそれを取り戻せる点です。
コースを修了することで、スポンサー企業から提供される仮想通貨報酬やNFTバッジが支給され、まるで奨学金付きオンライン大学のような仕組みになっています。
教育から雇用への橋渡し
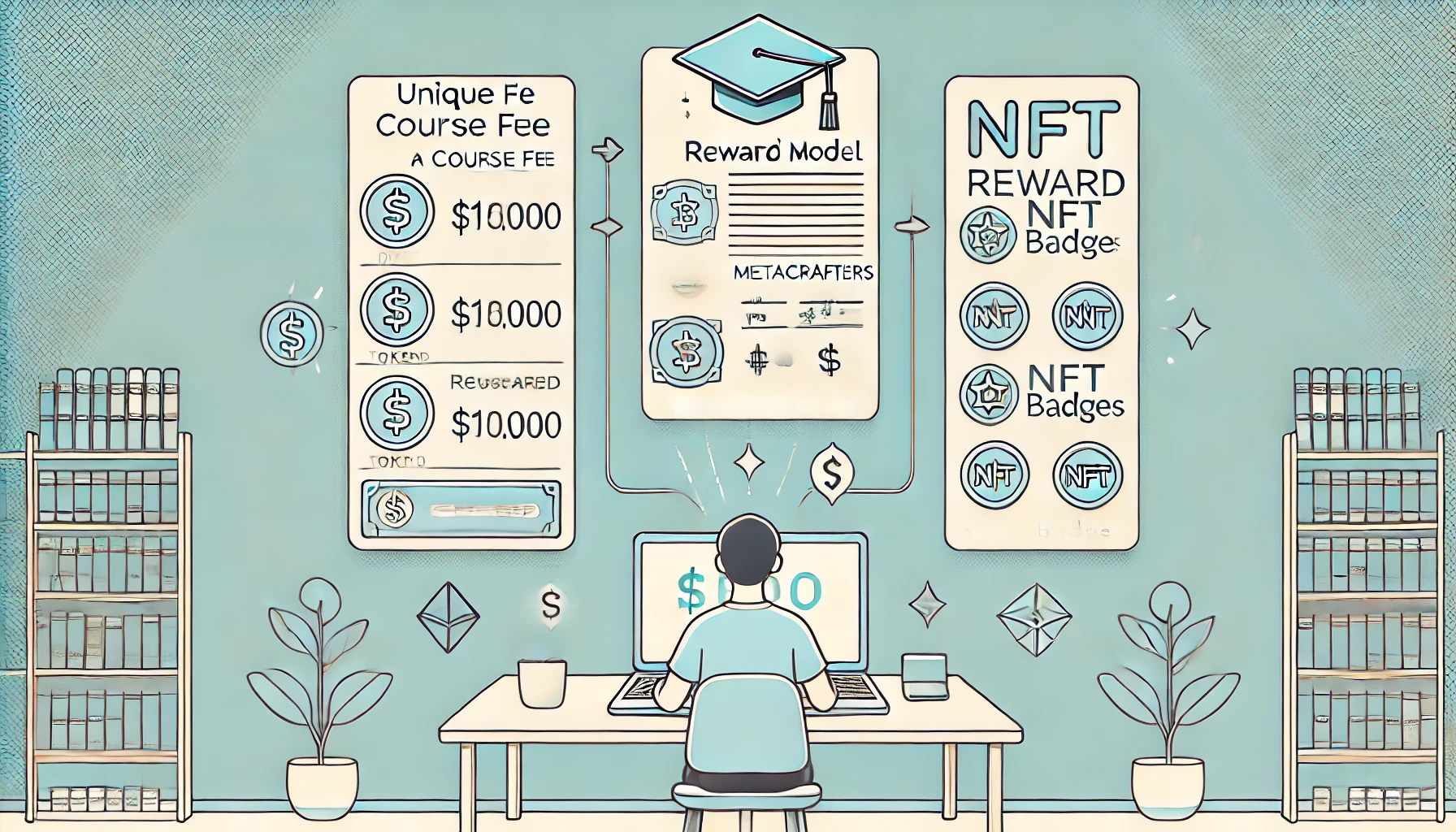
スポンサー企業にとっては、自社技術スタックを学んだ学習者を将来の開発人材として確保できるメリットがあり、Proof of Learn社はそのマッチングと報酬設計を担っています。
Web3企業との連携により、スキル習得後の就職までを一貫して支援する「教育~雇用エコシステム」の構築を進めており、実際に多数のスカラーシップ(奨学生)を輩出しています。
今後の展開と懸念点
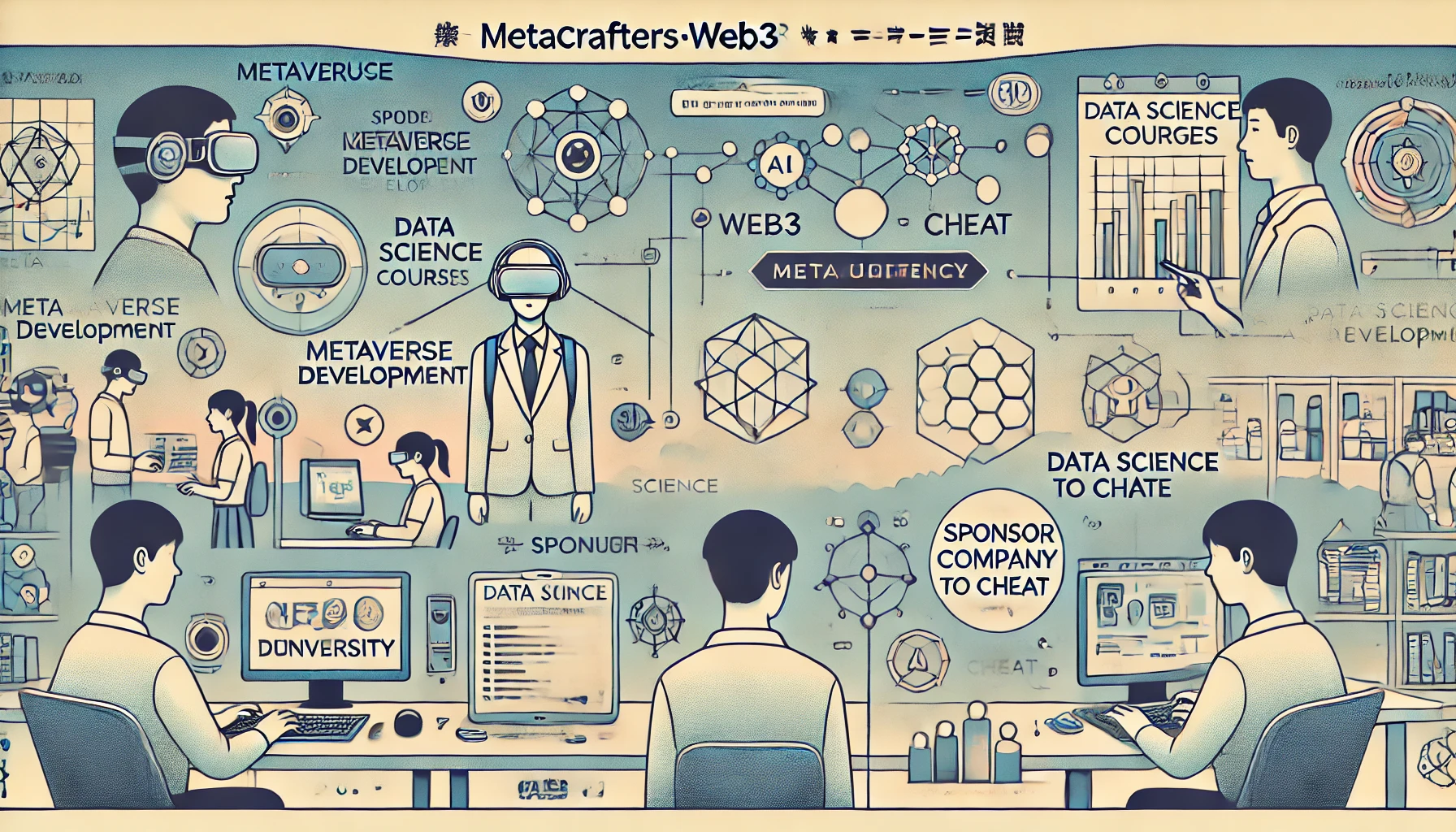
Metacraftersは今後、データサイエンスやメタバース開発などへの講座拡充を予定し、「Web3版オンライン大学」への進化を視野に入れています。
課題は、暗号市場の不況によるスポンサー離れや、チートによる不正報酬獲得リスク。これに対しては、受講選抜や学習支援の強化が必要とされています。
それでも、「学習=報酬」という体験は圧倒的に魅力的であり、次世代の教育モデルとしての注目度は高まるばかりです。
BitDegree(BDG)とは?
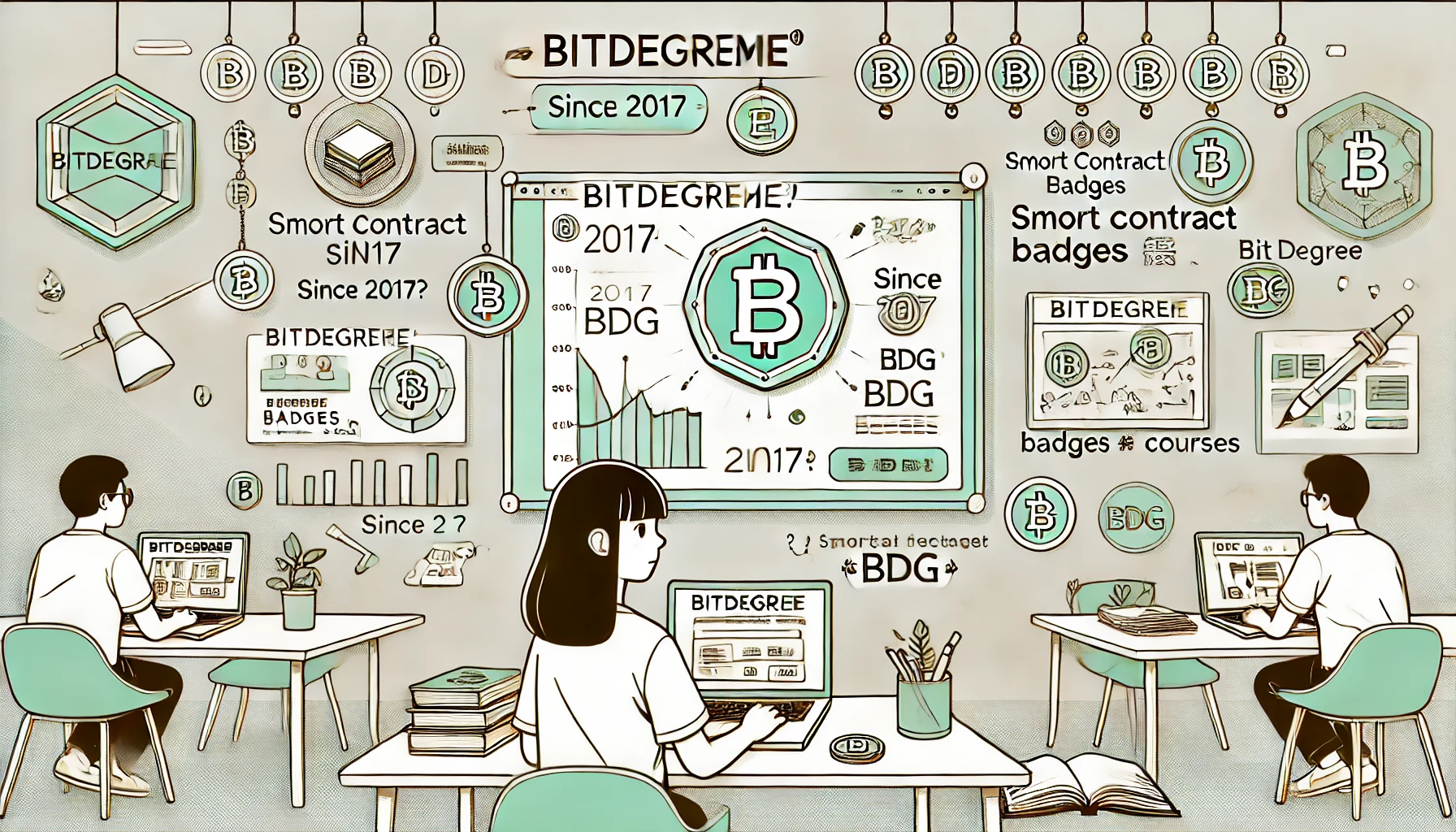
BitDegreeは、2017年からブロックチェーン教育を展開してきた老舗プラットフォームです。
独自トークン「BDG」を使い、ユーザーが学習を通じて報酬を得られる仕組みを世界に先駆けて導入しました。
教育×ブロックチェーン領域における先駆者として、多くの実験的な取り組みを実施してきた点が特徴です。
Learnoverse構想とは

BitDegreeが現在注力しているのが、仮想空間上に構築される教育都市「Learnoverse(ラーノバース)」です。
アバターが街を歩き回り、好きな建物で講座を受けるといった体験を通じて、メタバース上のソーシャルな学びとトークン報酬を融合させる新時代の教育モデルを構想しています。
100万人超の利用者と受賞歴
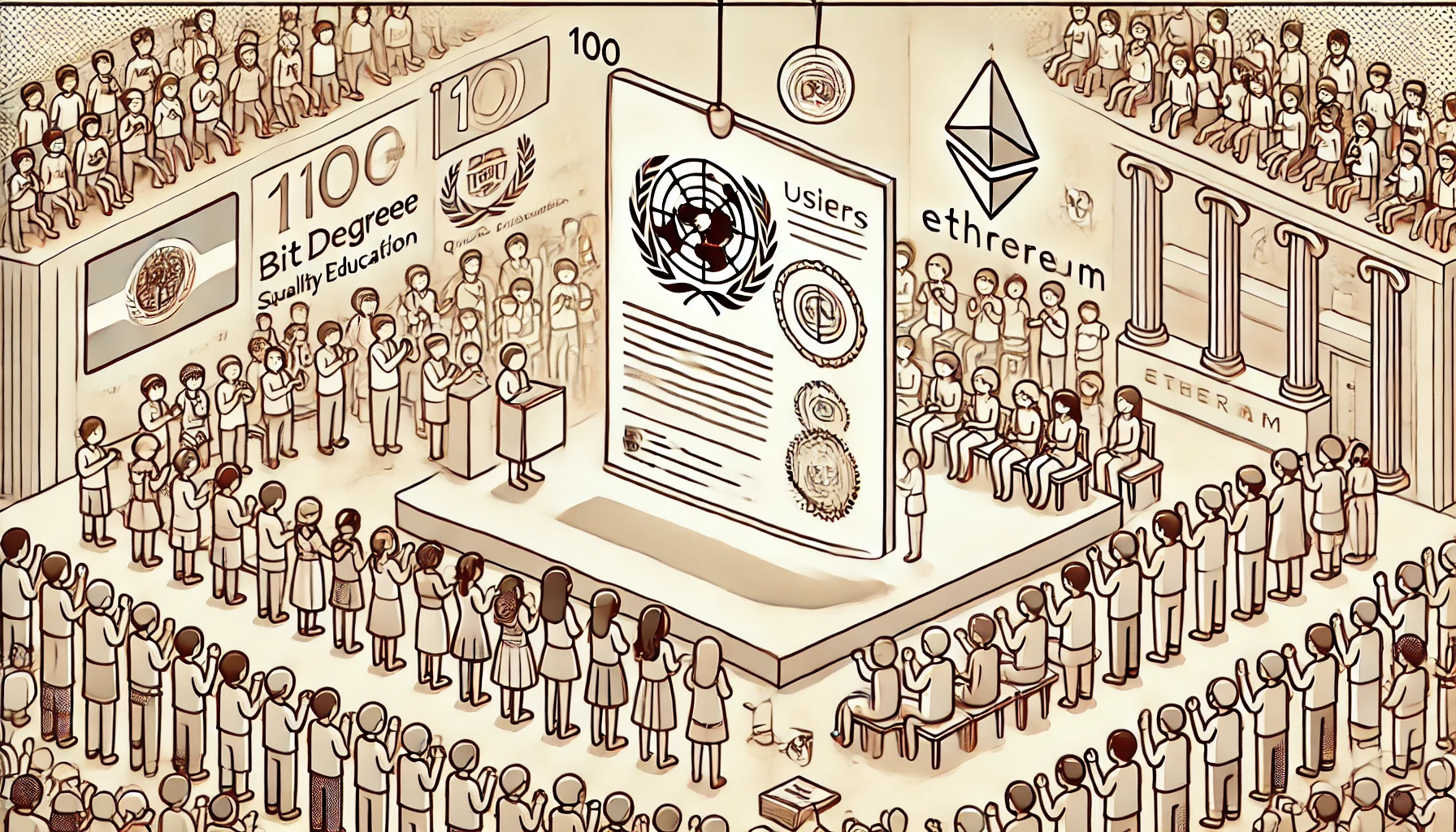
登録者数はすでに100万人を超えており、国連からはSDG4(質の高い教育)に貢献する取り組みとして表彰も受けています。
また、Ethereumチェーン上に履歴を記録する「改ざん不能な修了証明」も早期から導入しており、技術面でも一歩先を行く存在です。
課題と再成長への鍵
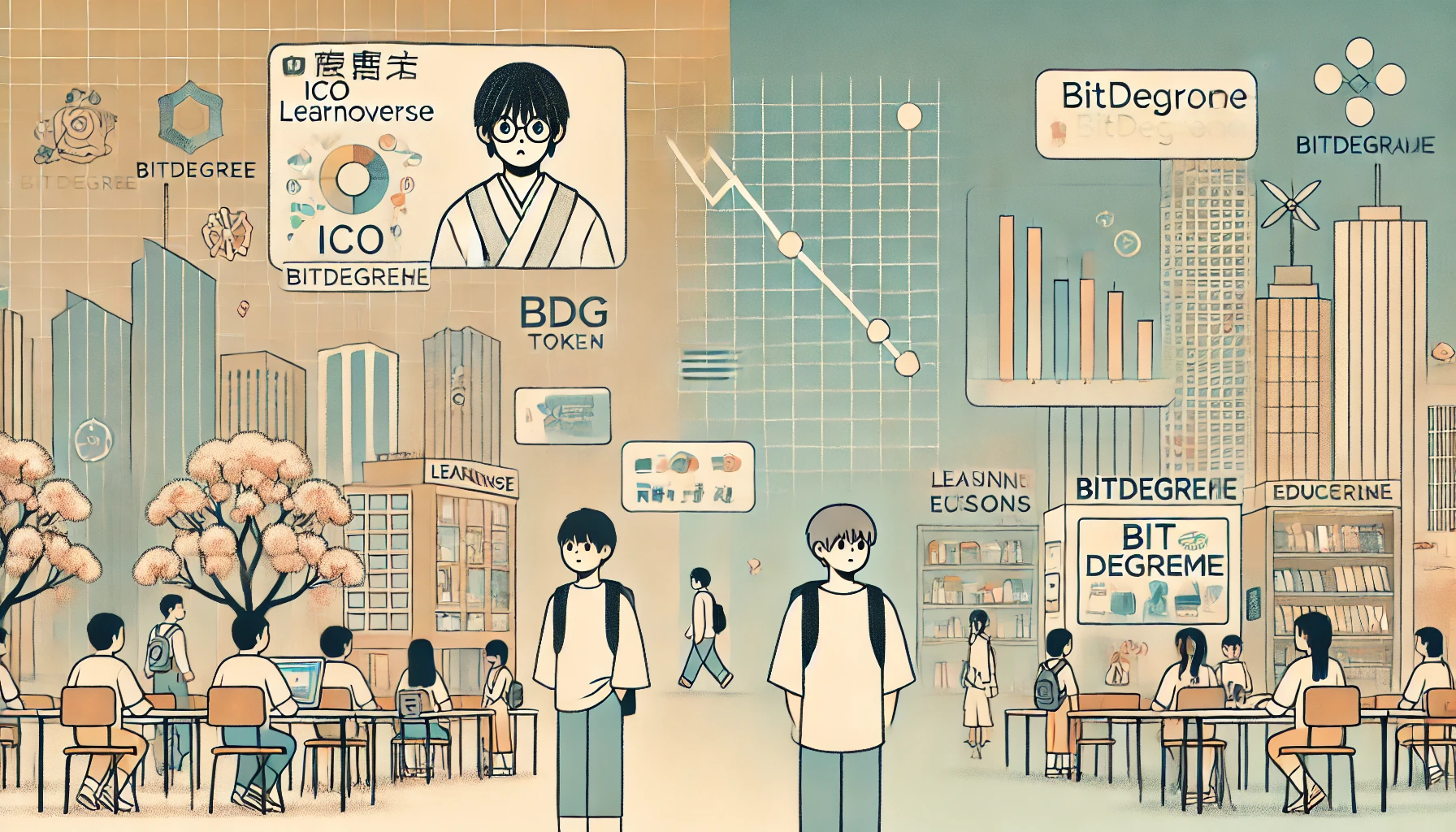
ICOブーム時に高騰したBDGトークンは現在価値が下落し、資金難や一部ユーザー離れの課題も抱えています。
とはいえ、最新トレンドへの柔軟な対応とパートナーシップの広がりにより、メタバース型学習のパイオニアとして再評価されつつあります。
「学習者がアバターで街を歩き、学んで報酬を得る」そんな未来の学習スタイルを提案するBitDegreeの今後に期待が寄せられています。
Education Ecosystem(LEDU)とは?
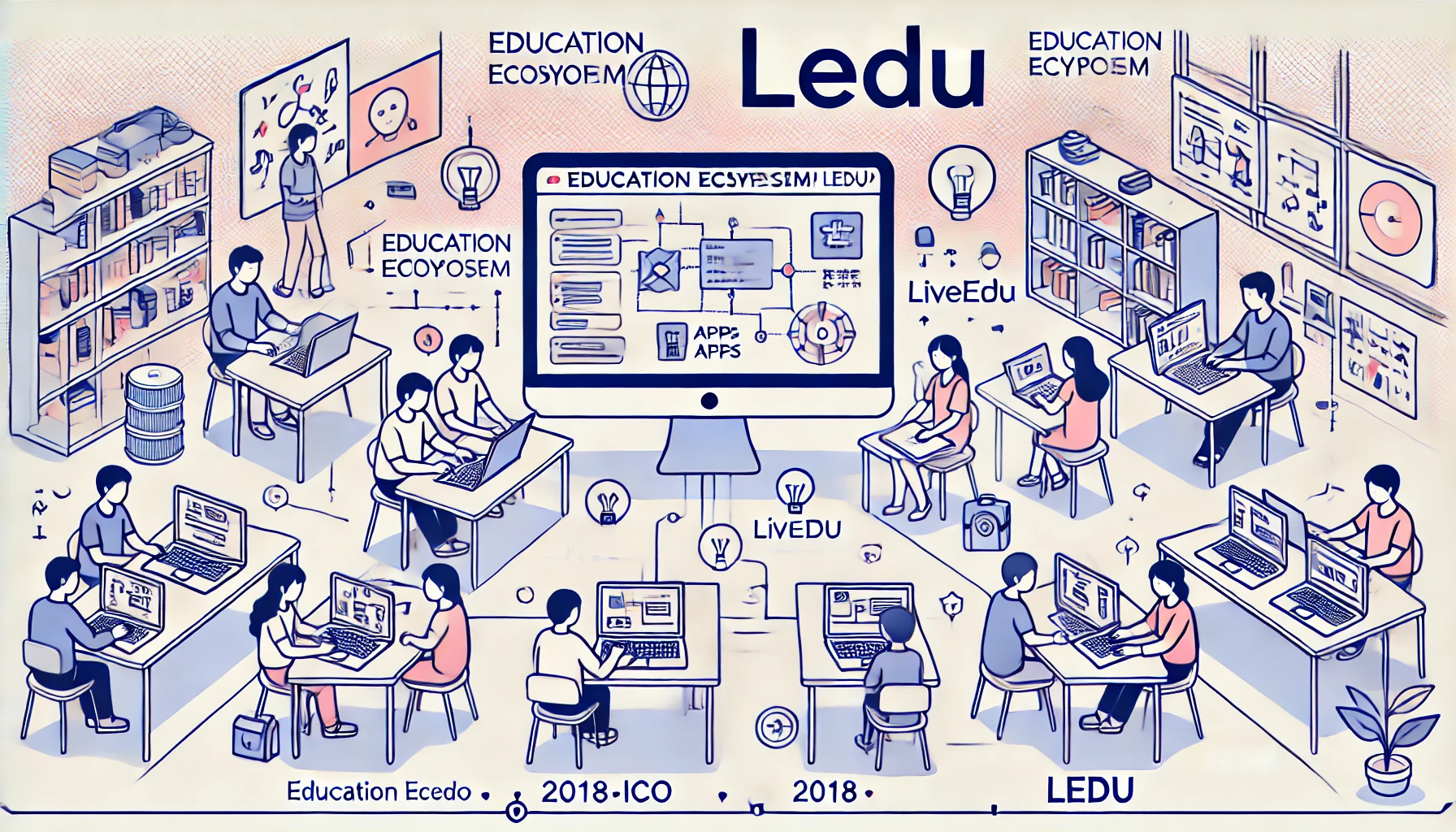
Education Ecosystemは、開発者向けの「実践プロジェクト学習」を分散型で提供するプラットフォームです。
旧称LiveEduとして2018年にICOを実施し、トークン「LEDU」を発行。ハンズオン型の学習とトークン報酬を組み合わせた実験的プロジェクトとしてスタートしました。
学びながら貢献し、稼ぐ

プラットフォームでは、プロのエンジニアが制作した本格的な開発教材を視聴・模倣できます。
学習者が積極的に参加・貢献すると、LEDUトークンが報酬として得られる仕組みが整っており、「学びながら稼ぐ」実践コミュニティが目指されています。
現状と再起の兆し
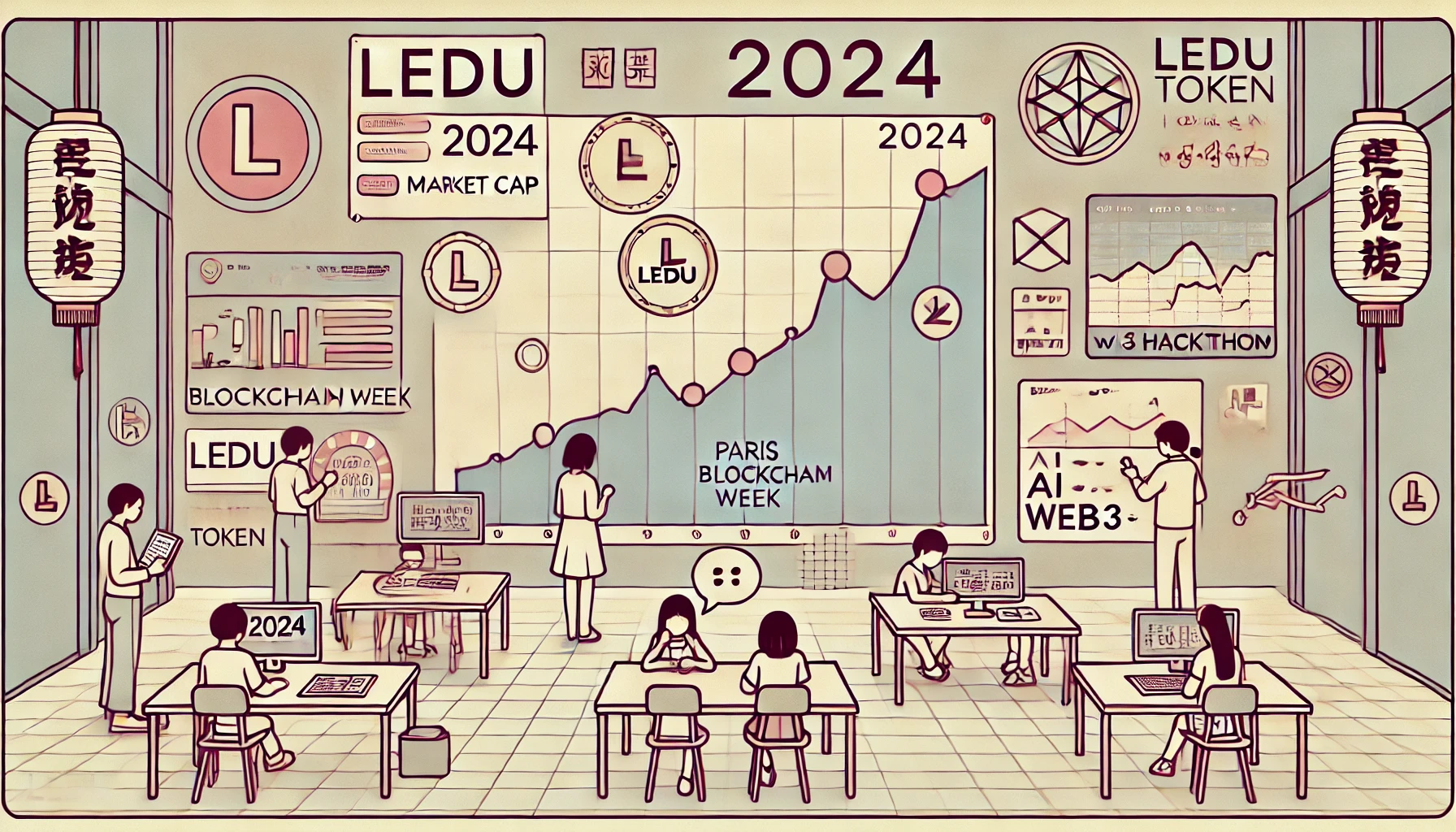
一時は注目を集めましたが、現在LEDUの流動性は低く、時価総額も縮小しています。
しかしながら、2024年にはAI教材やWeb3ハッカソンとの連携が始まり、再評価の動きも。パリのブロックチェーンウィークにも参加し、他プロジェクトとの連携を強化しています。
今後の課題と展望
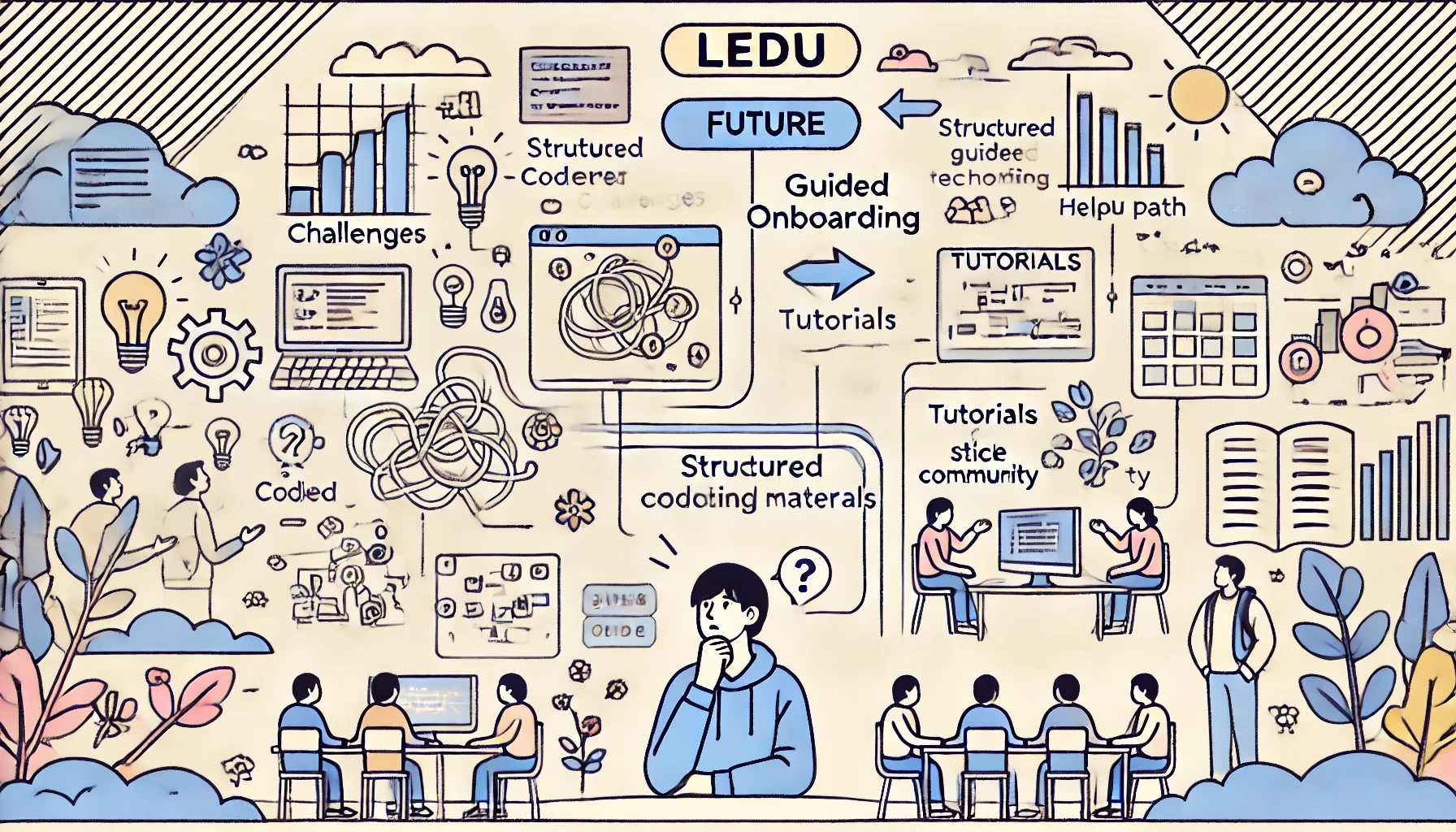
高度な教材は初心者にはハードルが高く、ユーザー拡大のためには体系的な導入設計が必要です。
それでも、ニッチ分野の専門学習をコミュニティベースで共有できるという発想には大きな価値があり、今後のエコシステム活性化に注目が集まります。
Academic Labs(AAX)とは?
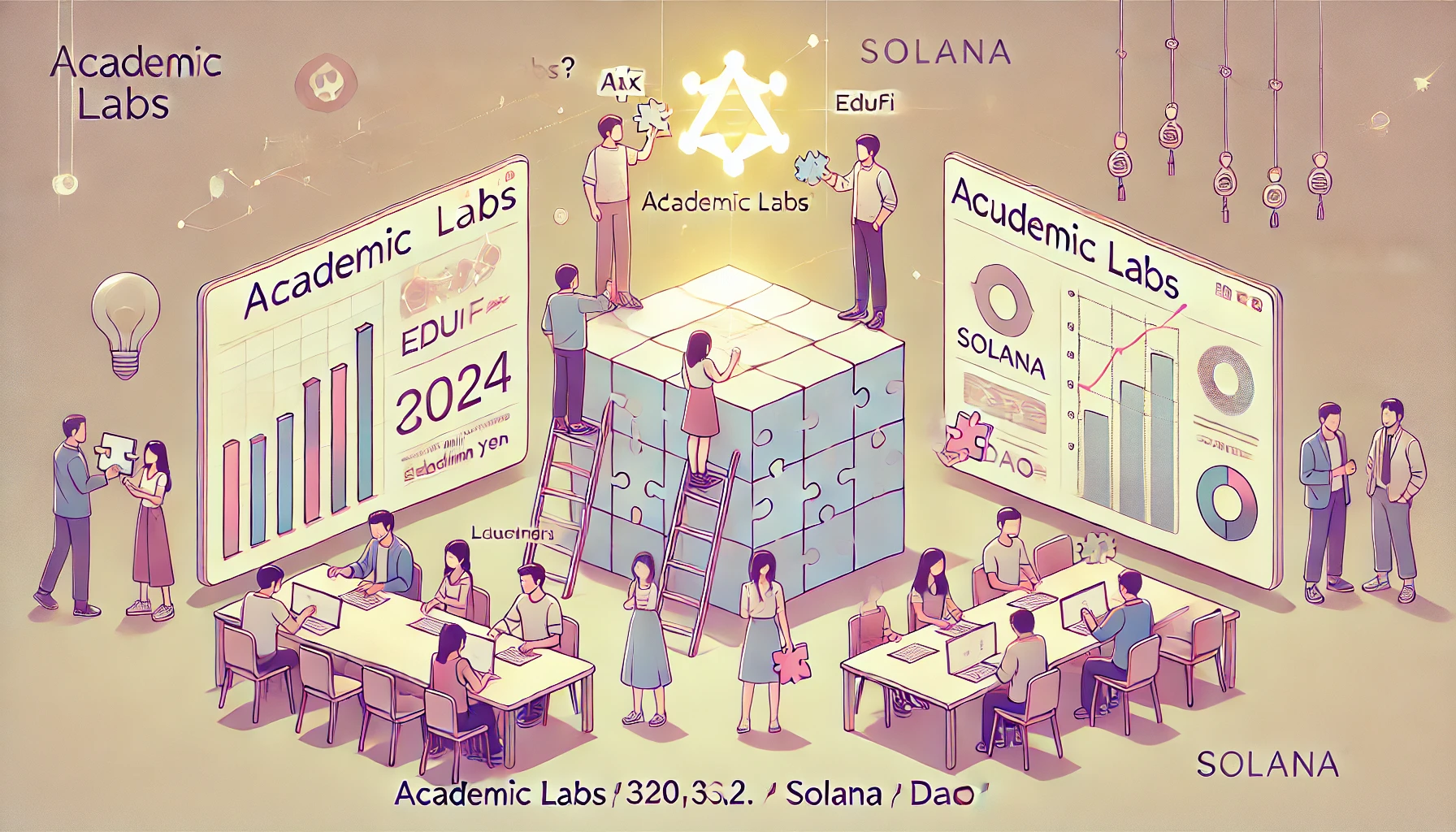
Academic Labsは「学習者と教育者が教育プラットフォームを所有する」という大胆なビジョンを掲げるEduFiプロジェクトです。
東南アジア発で2024年に約3.2億円を資金調達。Solanaチェーン上で展開され、教育DAOとして注目を集めています。
SocialFi要素で拡大中
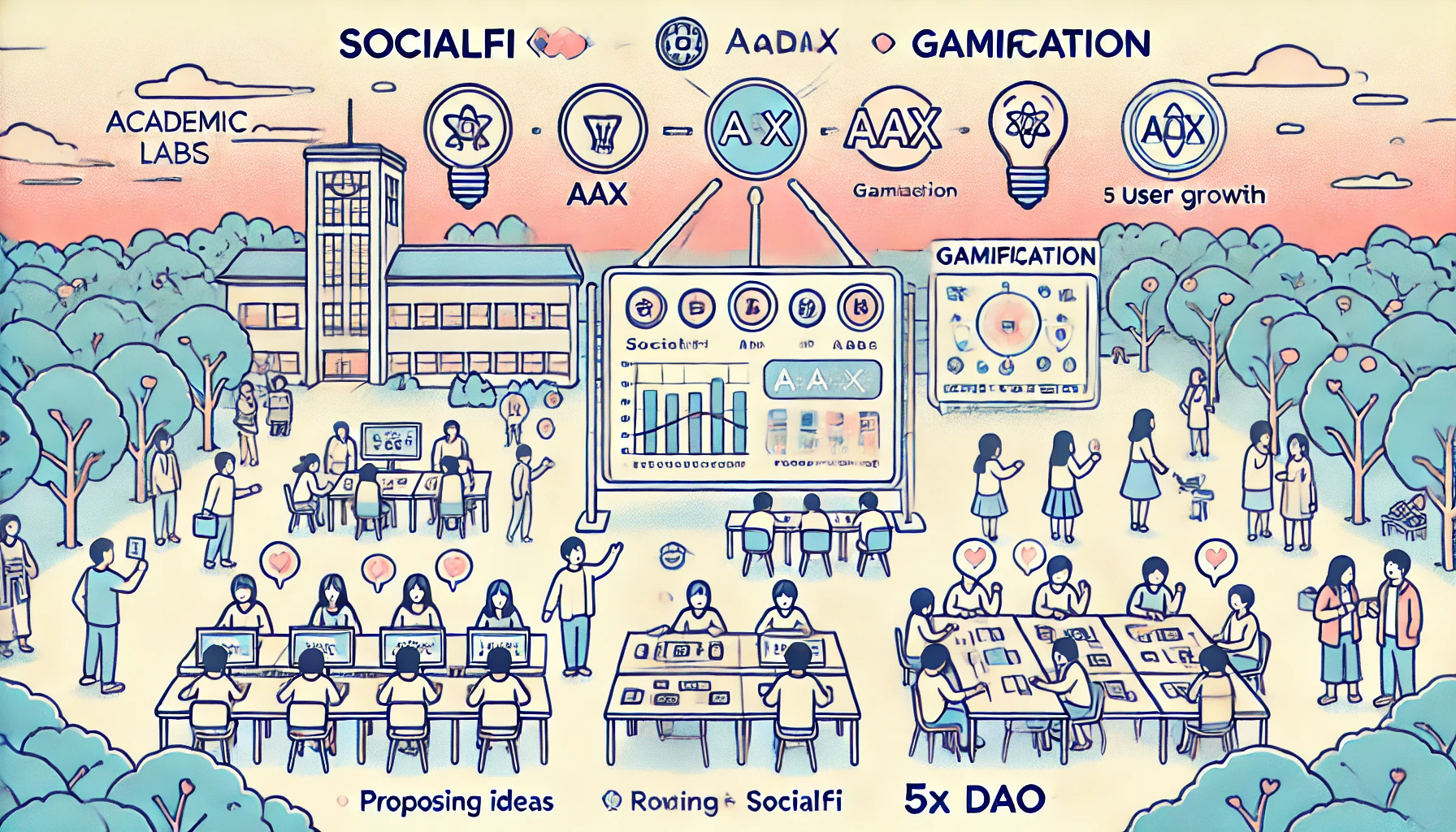
プラットフォームの利用は基本無料で、提案・評価・運営などへの貢献度に応じてAAXトークンが報酬として配布されます。
GamificationやSocialFi設計により、ユーザー数は一気に5倍に拡大。教育DAOの新たなモデルを体現しています。
現実との連携も進行
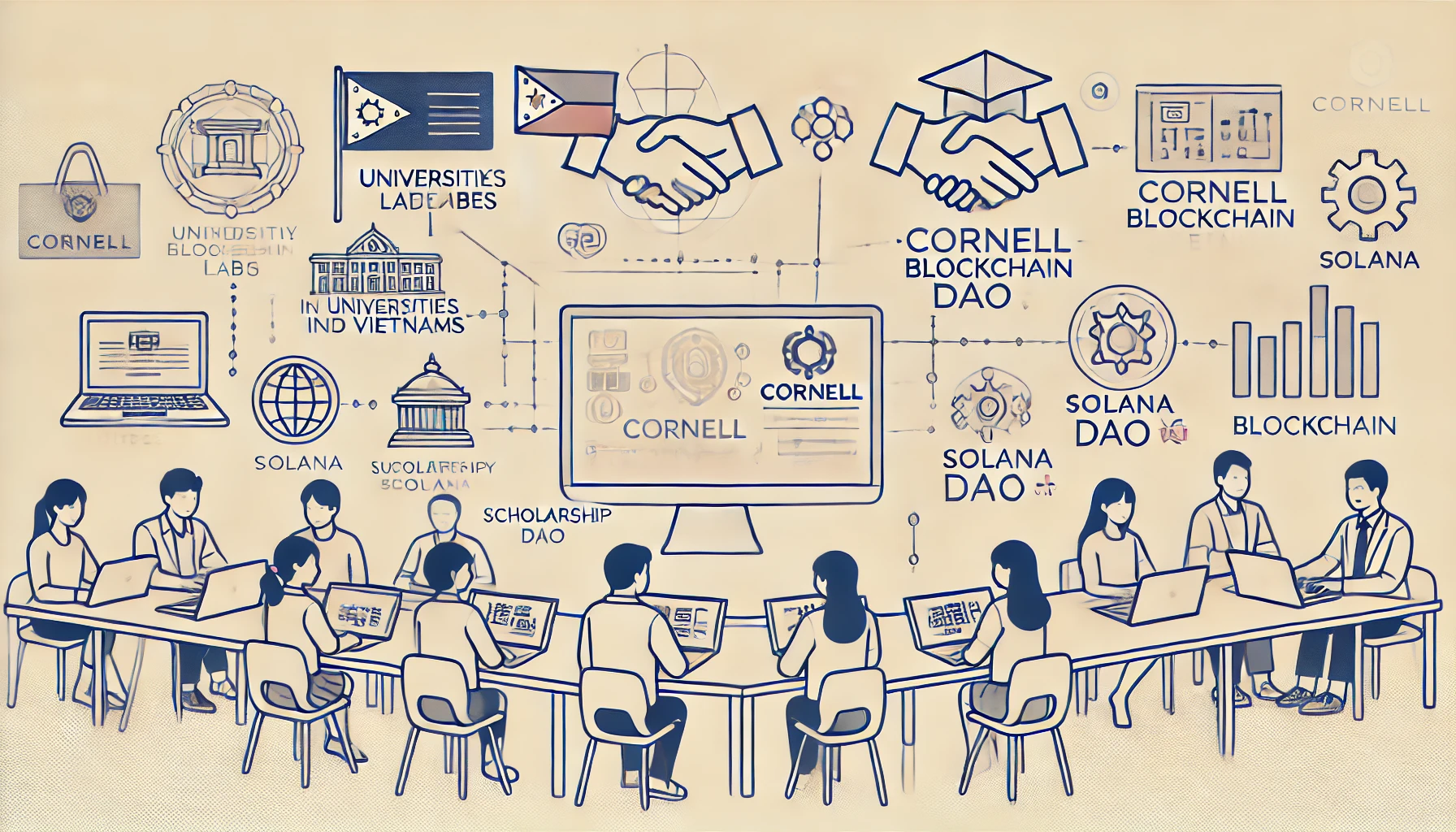
フィリピンやベトナムの大学、さらにはCornell大学のブロックチェーン団体と連携。
Solana系プロジェクトとの協業も活発で、今後はピアラーニングや奨学金DAOの設立も視野に入れています。
価格変動と実需の両立
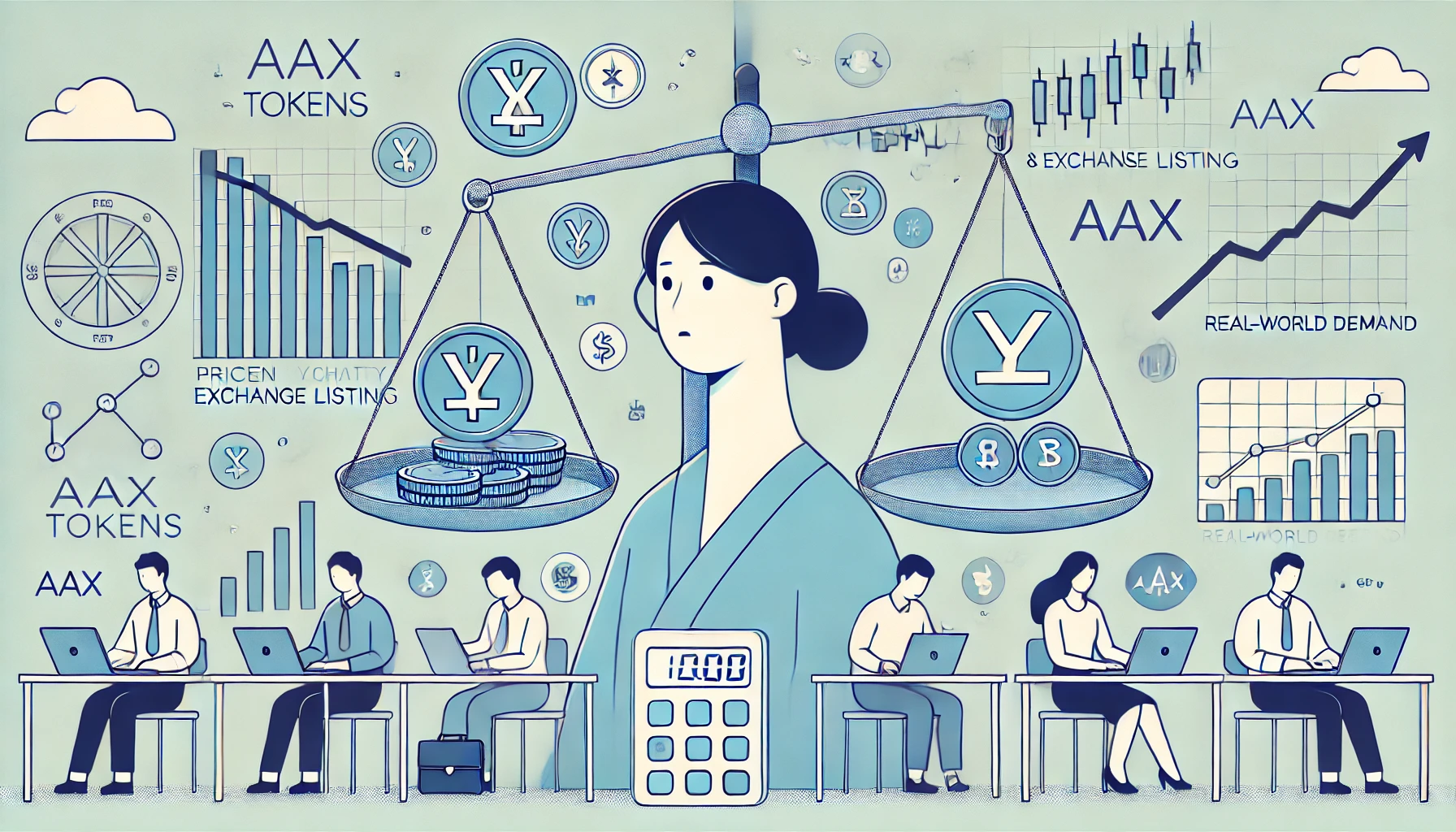
AAXトークンは取引所上場後に価格が急落しており、投機的動向への耐性が課題です。
今後は企業研修など教育サービスそのものでの収益化も必要であり、「実需×分散化」の両立が成功のカギとなりそうです。
RabbitHoleとは?
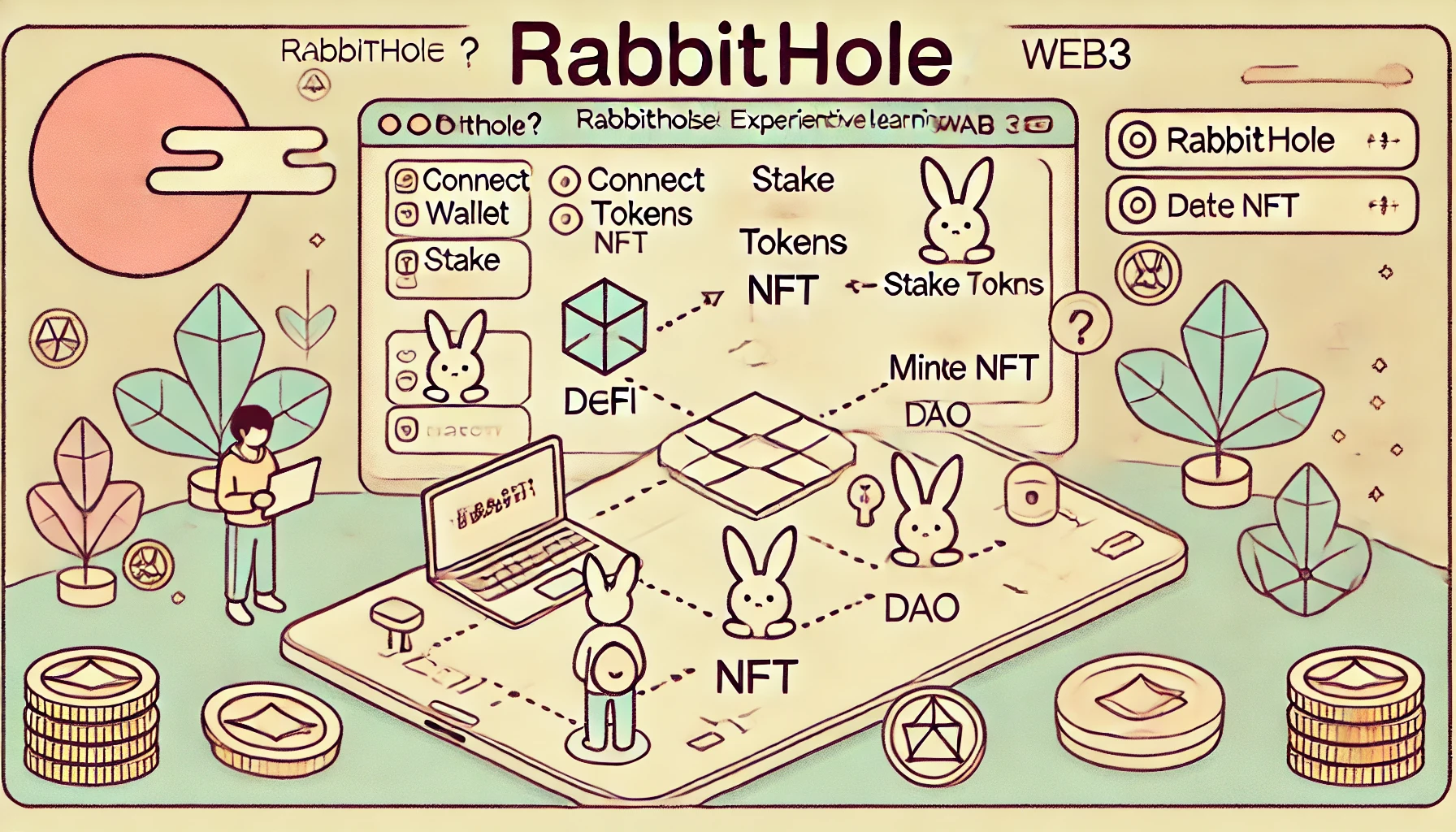
RabbitHoleは、クエスト形式でWeb3サービスを「触って覚える」体験学習プラットフォームです。
DeFiやNFTなど、実際のプロトコルを操作することで理解を深め、完了時に報酬を獲得できます。
クエスト形式で習得
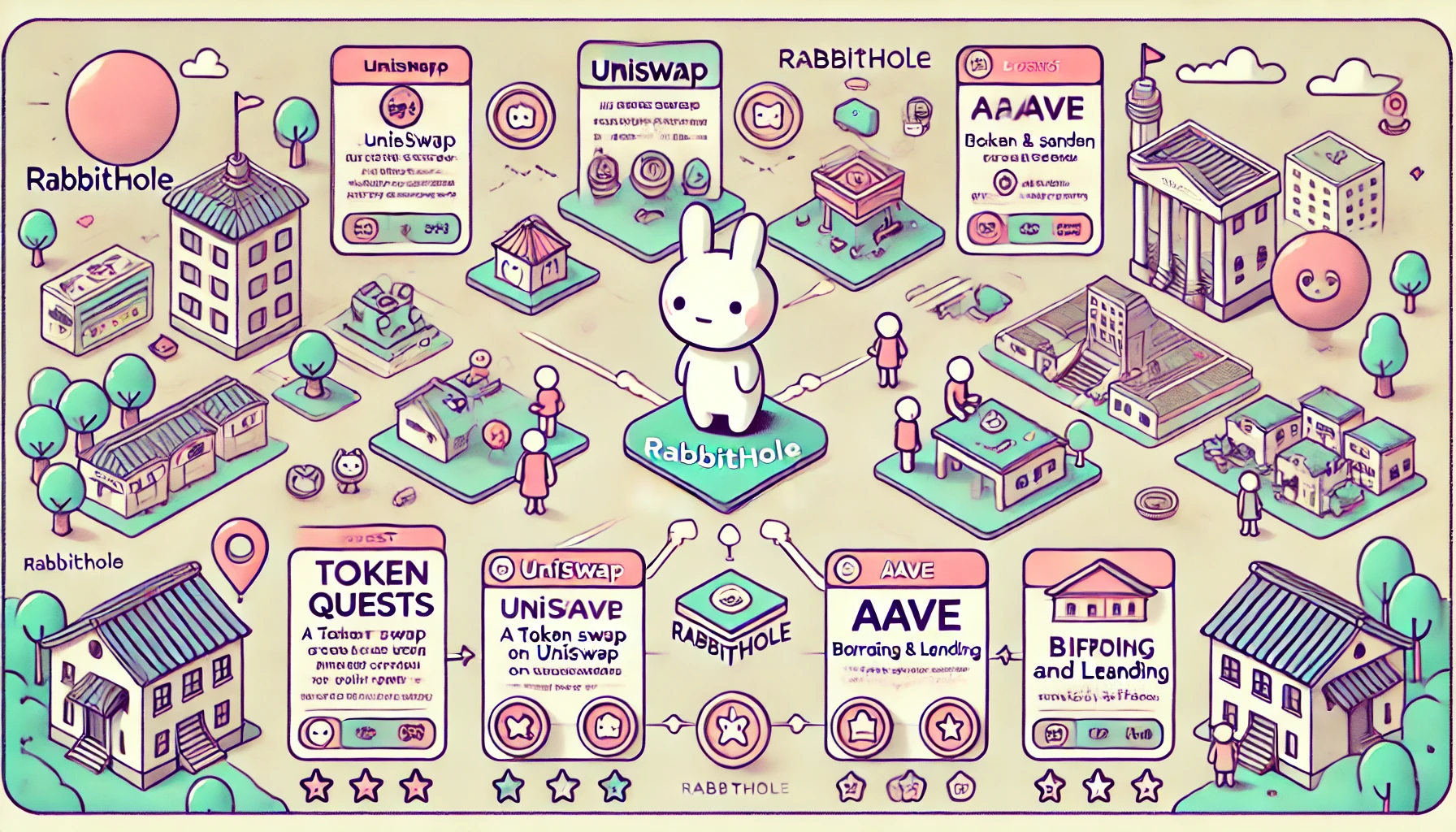
例:Uniswapでのスワップ、Aaveでの貸し借り体験など、実務レベルの学習を報酬付きで提供。
各プロジェクトは新規ユーザー獲得のために報酬を用意し、RabbitHoleが設計・配信を担います。
Web3の入口に
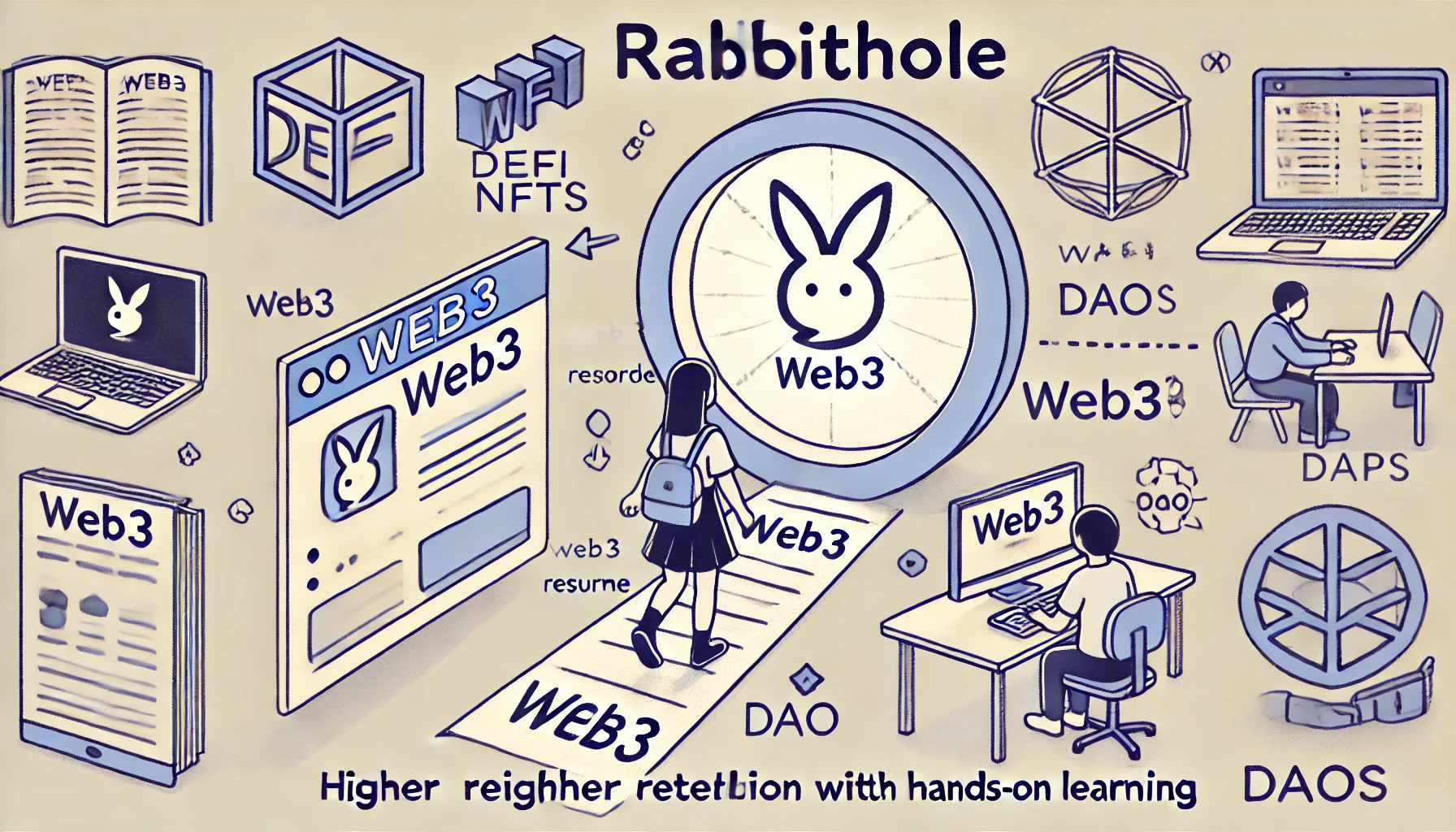
単に読んで学ぶのではなく「実際に使って覚える」ことで、知識の定着率が格段に高くなります。
オンチェーン履歴がWeb3版のスキル証明として活用される可能性もあり、DAOやプロジェクトからのリクルートに直結するケースも。
不正対策と未来像
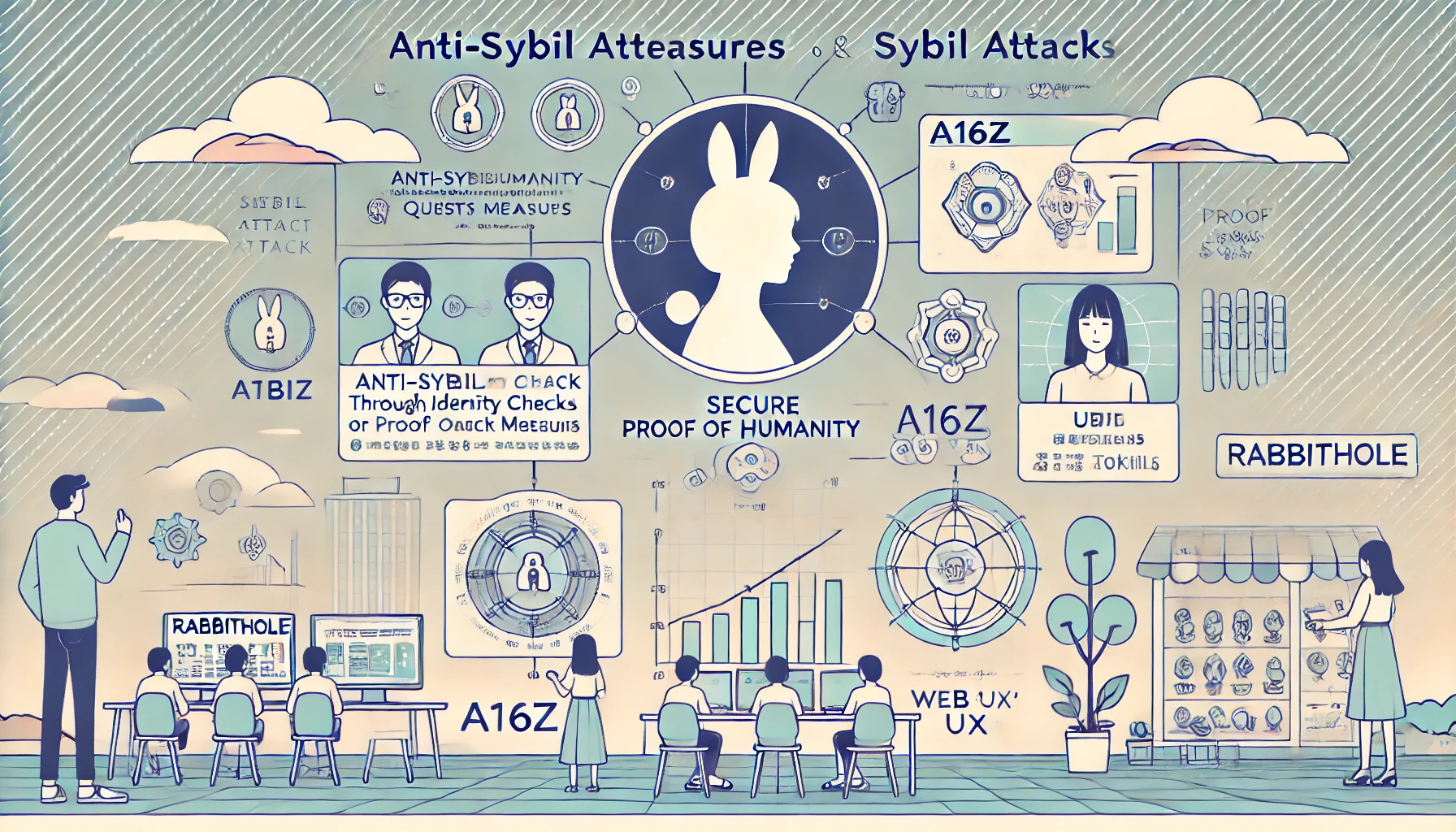
Sybil攻撃(多重参加)を防ぐため、本人確認やクエスト設計での対策が進められています。
a16zなどからの出資もあり、持続可能な運営体制が確立されつつあります。
「スキルを証明し、報酬を得る」Web3時代の教育UXとして注目の存在です。
BCdiploma(EvidenZ)とは?
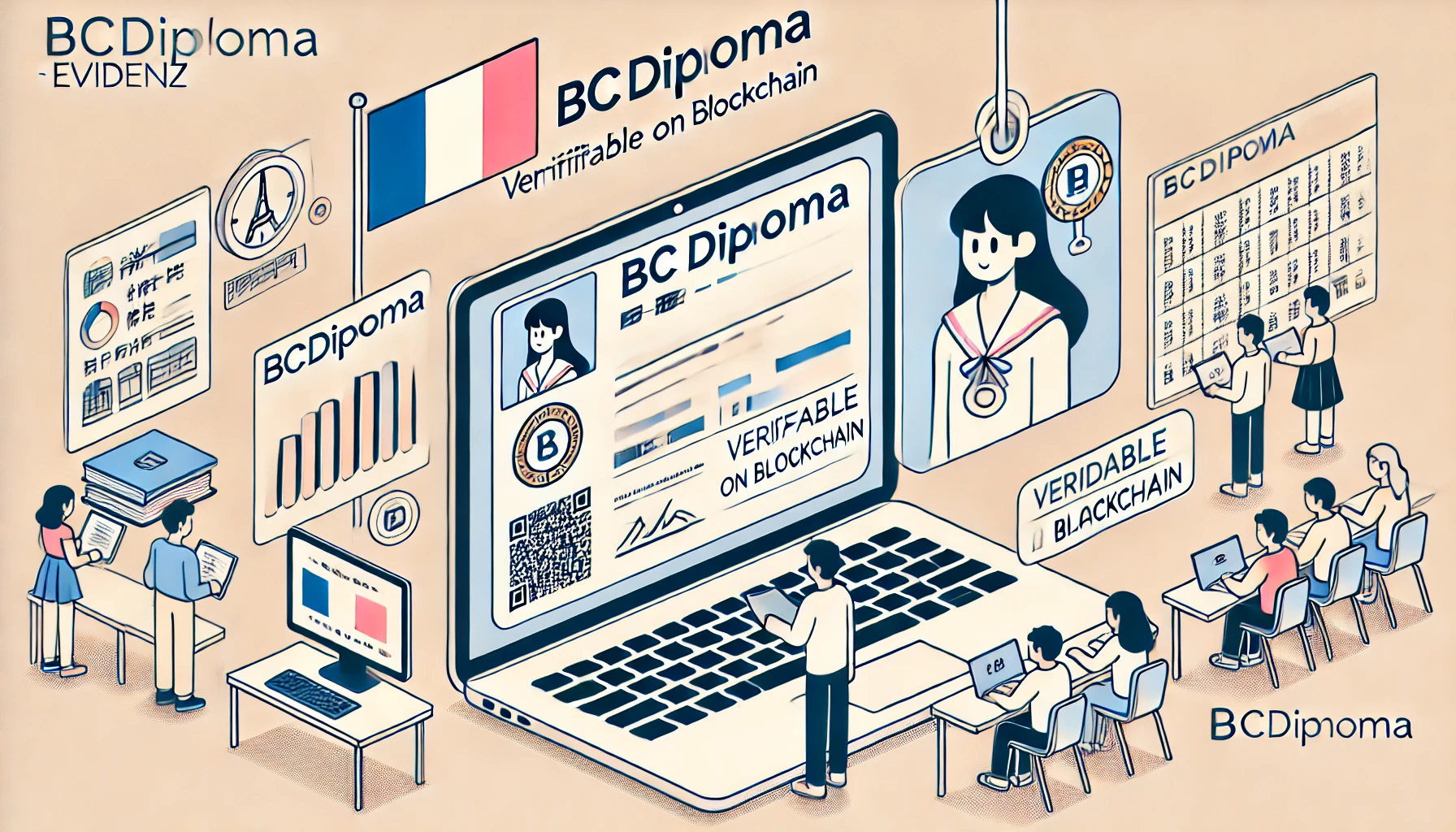
BCdiplomaは、卒業証書や修了証をブロックチェーン上で改ざん不可能な形で発行・検証するインフラです。
フランス発のプロジェクトで、教育機関向けに「EvidenZ」ソリューションを提供しています。
トークンを使った発行システム
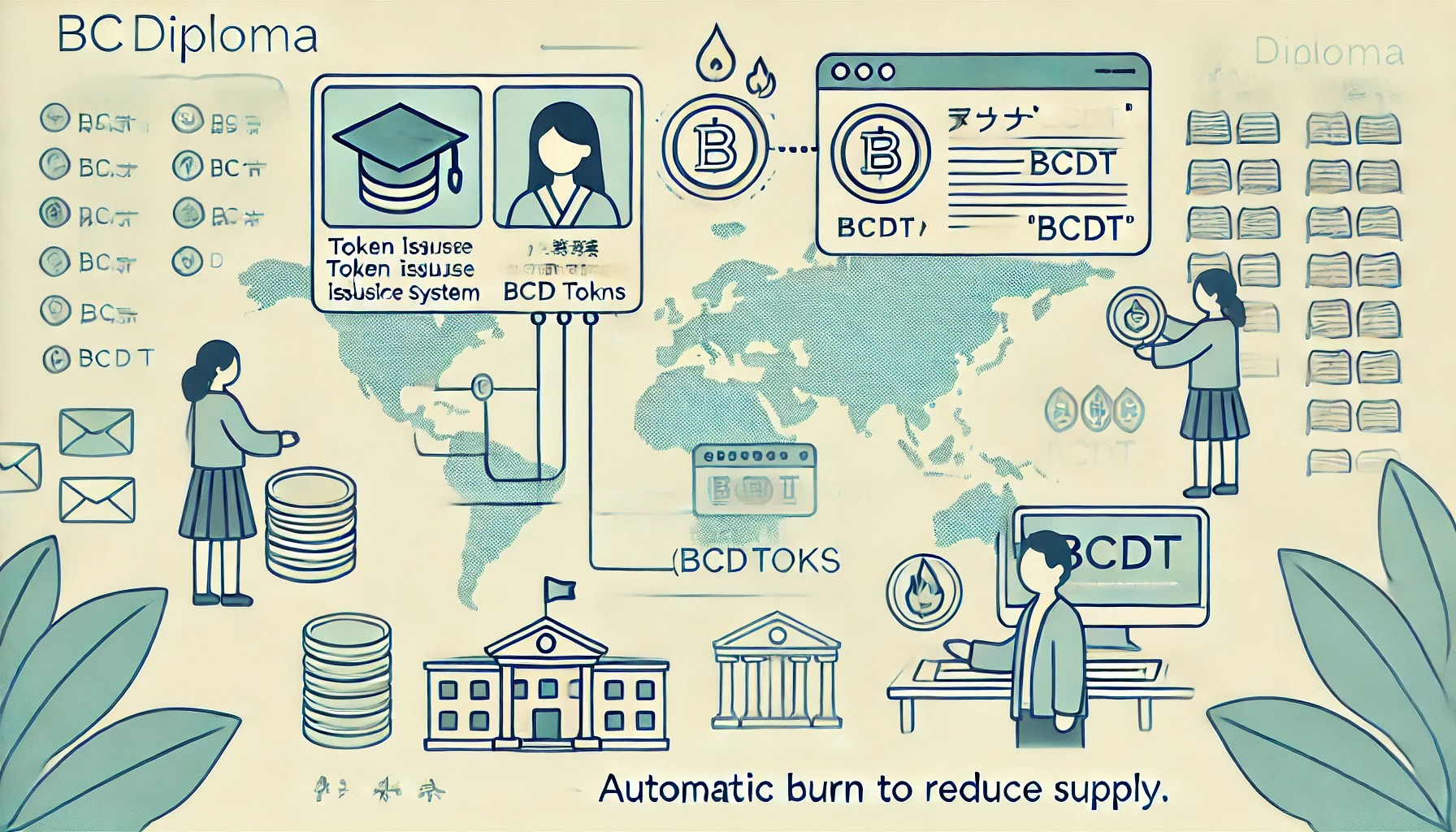
発行には「BCDT」トークンが使用され、一部が自動バーンされることで供給が抑制されます。
すでに数百の大学が導入し、卒業証書や資格証明をブロックチェーン化しています。
本人主権型の学歴管理

学位・資格をオンラインで一元管理し、就職・転職時に簡単に提示できる仕組みが整います。
自己主権型IDとの親和性も高く、将来的には生涯学習の記録管理も視野に入っています。
導入ハードルと将来性
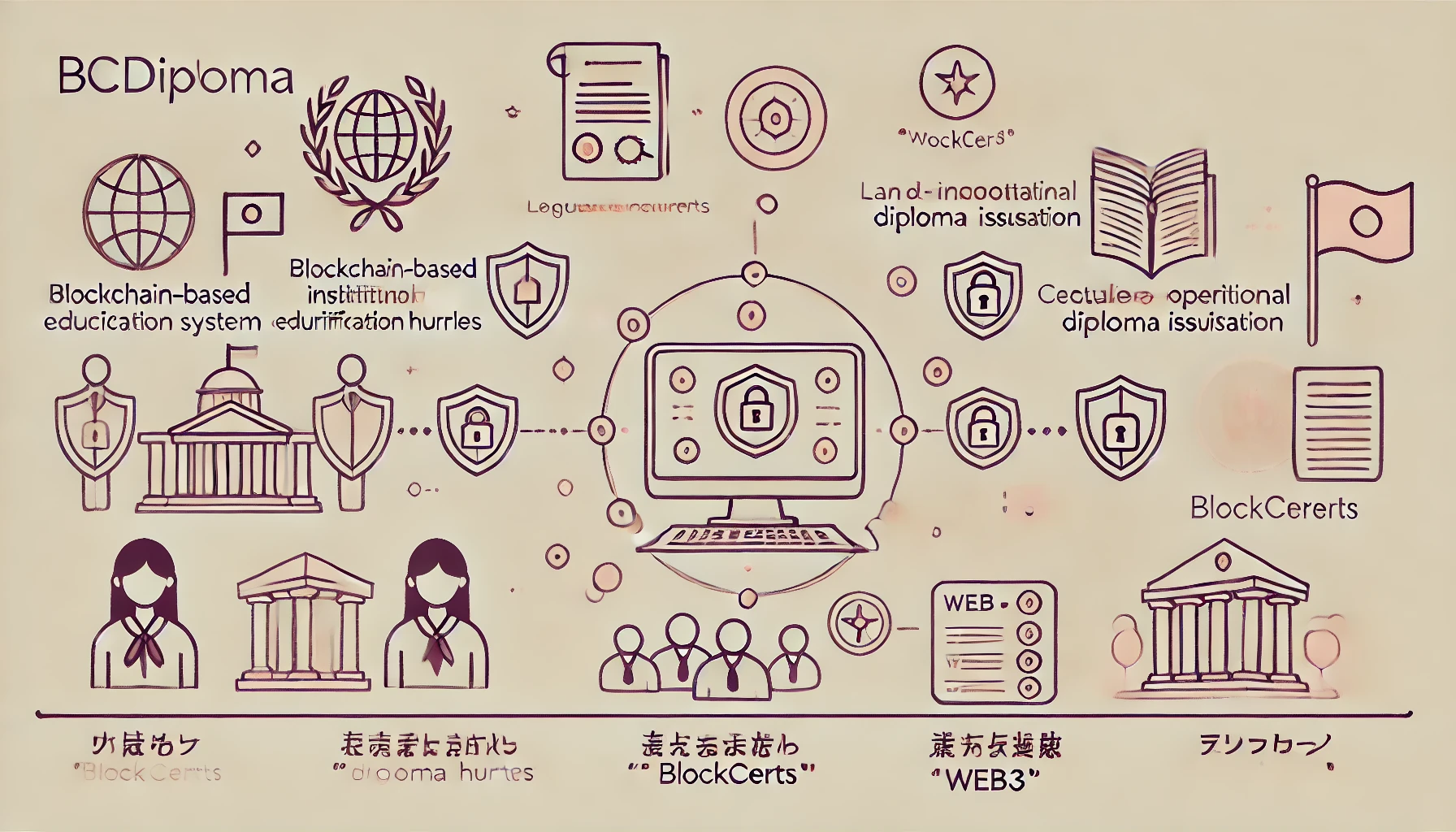
Blockcertsなど競合も存在し、法的証明力を高めるには各国制度との調整も必要です。
それでも、すでに実用化フェーズに入っている点で、堅実かつ信頼性の高いWeb3教育インフラとして注目されています。
まとめ
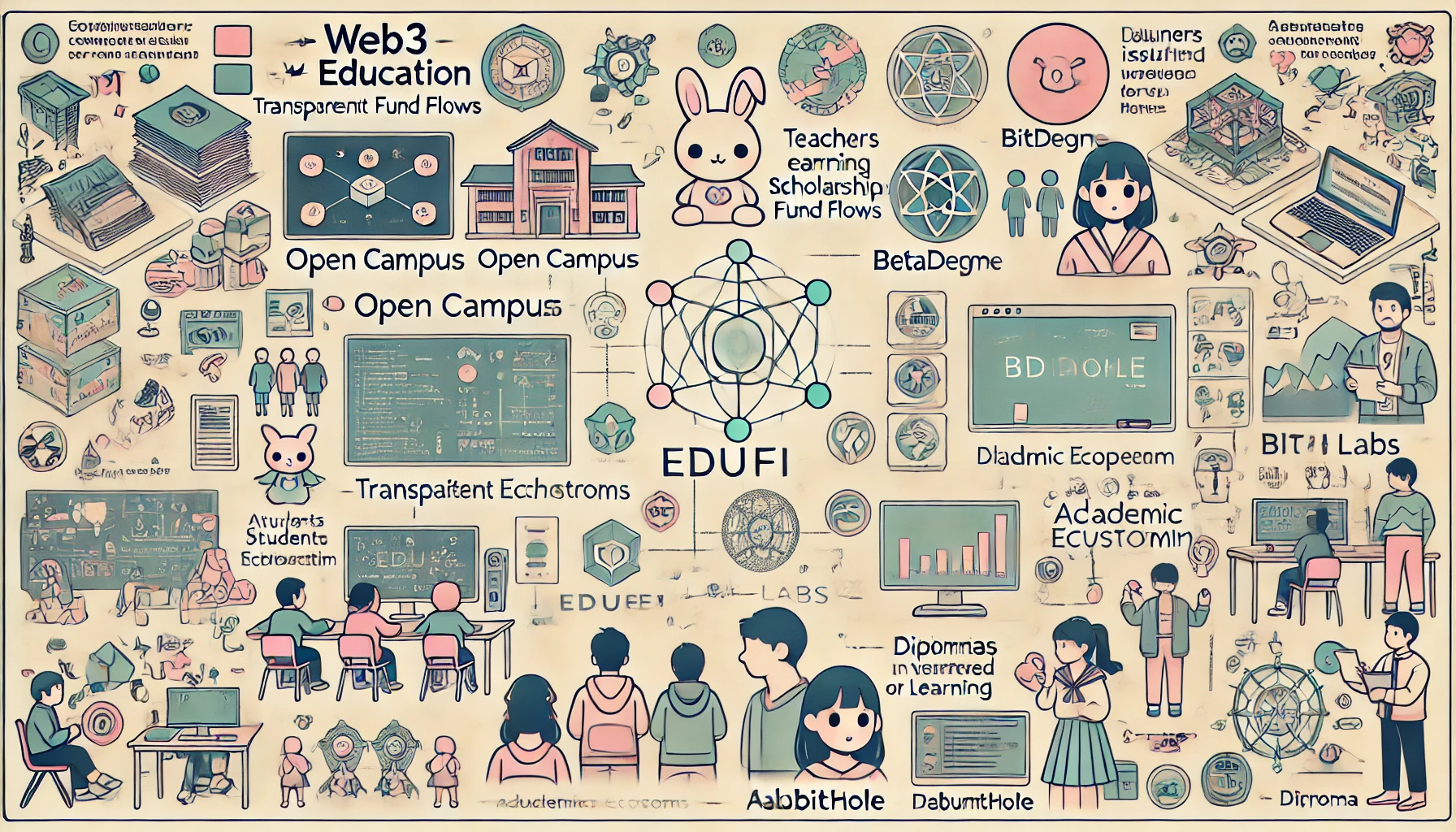
以上、Web3×教育(EduFi)領域における主要プロジェクトの詳細と将来展望をご紹介しました。
それぞれのプロジェクトは「学ぶこと」に対する新しいインセンティブを提示し、従来の教育の枠組みを超えた可能性を示しています。
- Open Campus:教育者に報酬を、学習者に透明な資金循環を
- Metacrafters:ブロックチェーン奨学金でWeb3人材育成を促進
- BitDegree:メタバースとトークンで学びのUXを再定義
- Education Ecosystem:実務教材の共有コミュニティ型ラーニング
- Academic Labs:学習DAOとしての成長を目指す東南アジア発プロジェクト
- RabbitHole:「触って覚える」体験型Web3入門
- BCdiploma:学歴証明をブロックチェーンで世界共通に
どのプロジェクトにも共通しているのは、「教育を通じて経済的・社会的に報われる世界」を目指している点です。
今後は規制や技術の壁を越えつつ、より多くの学習者に届く仕組み作りが求められます。
Web3によって“学ぶことの意味”がどう変わっていくのか、今後も注目していきましょう。