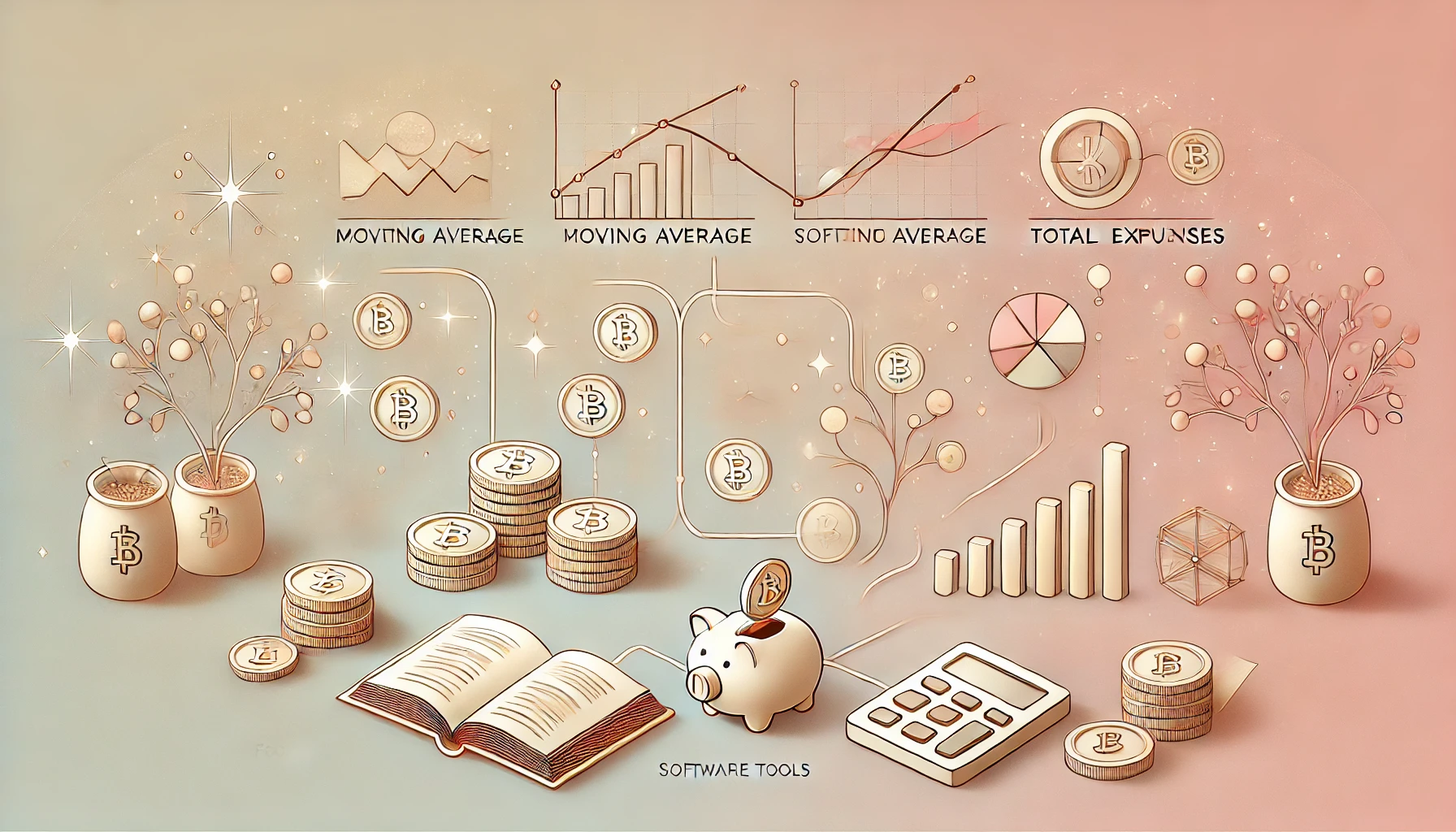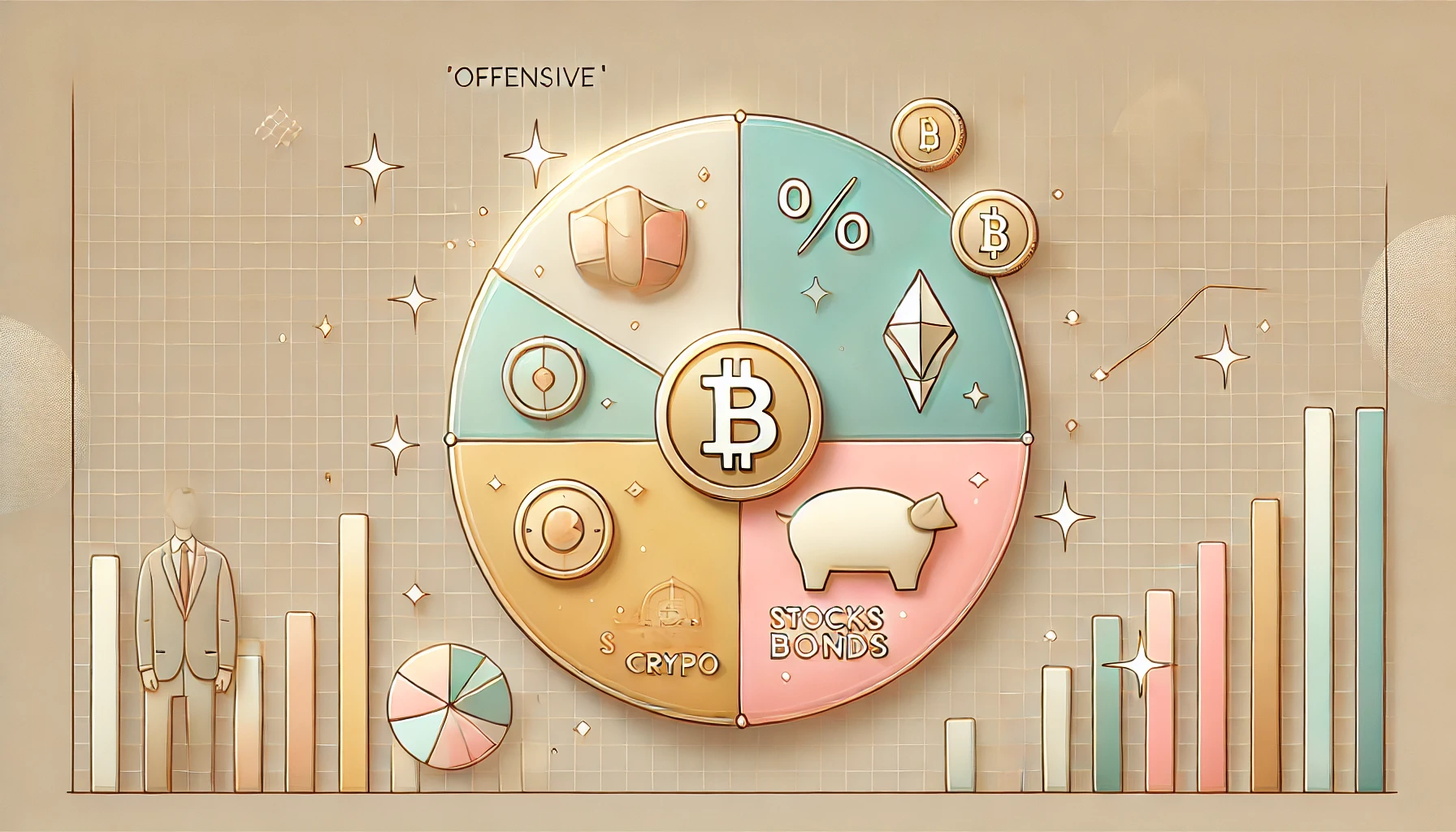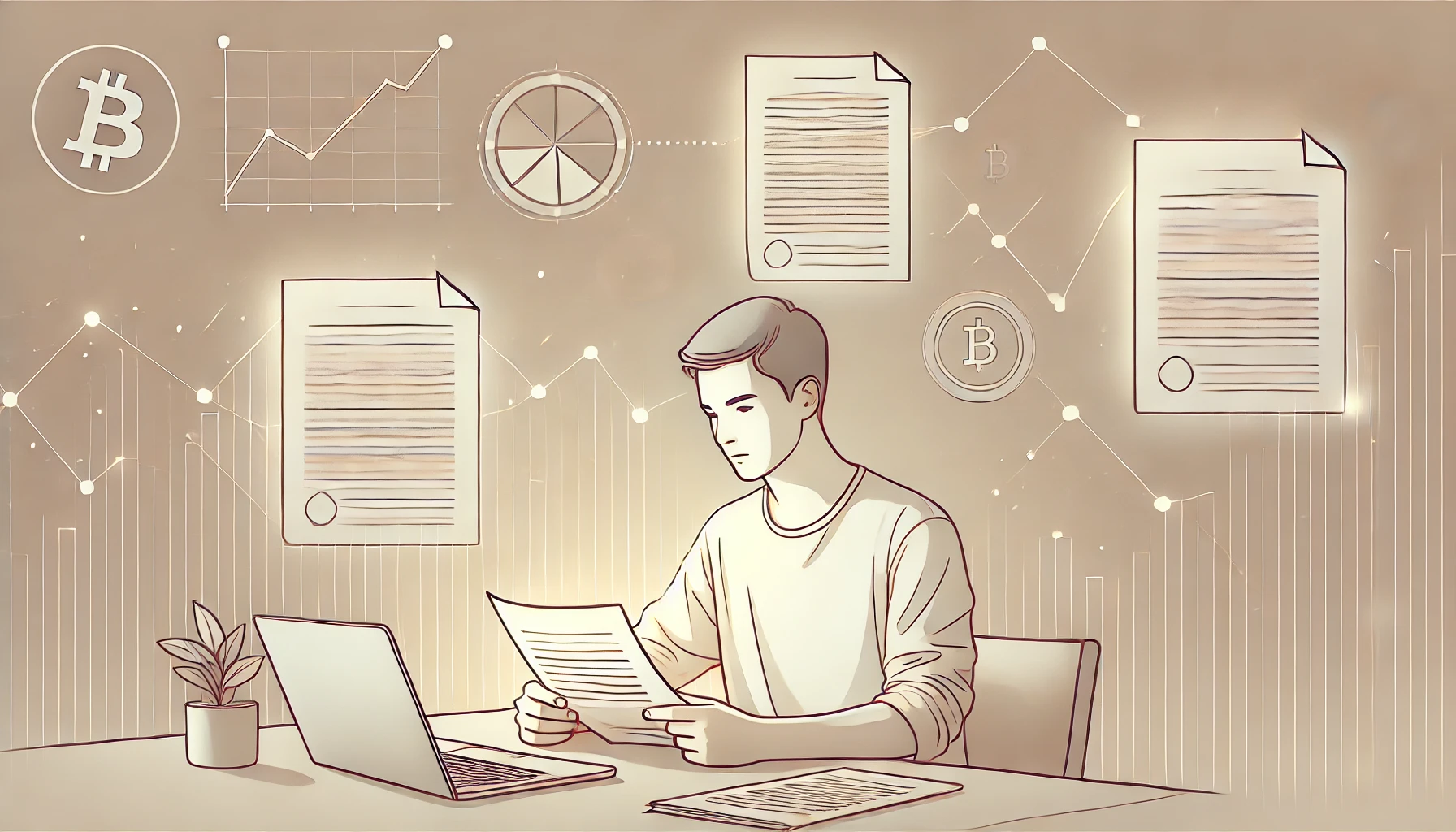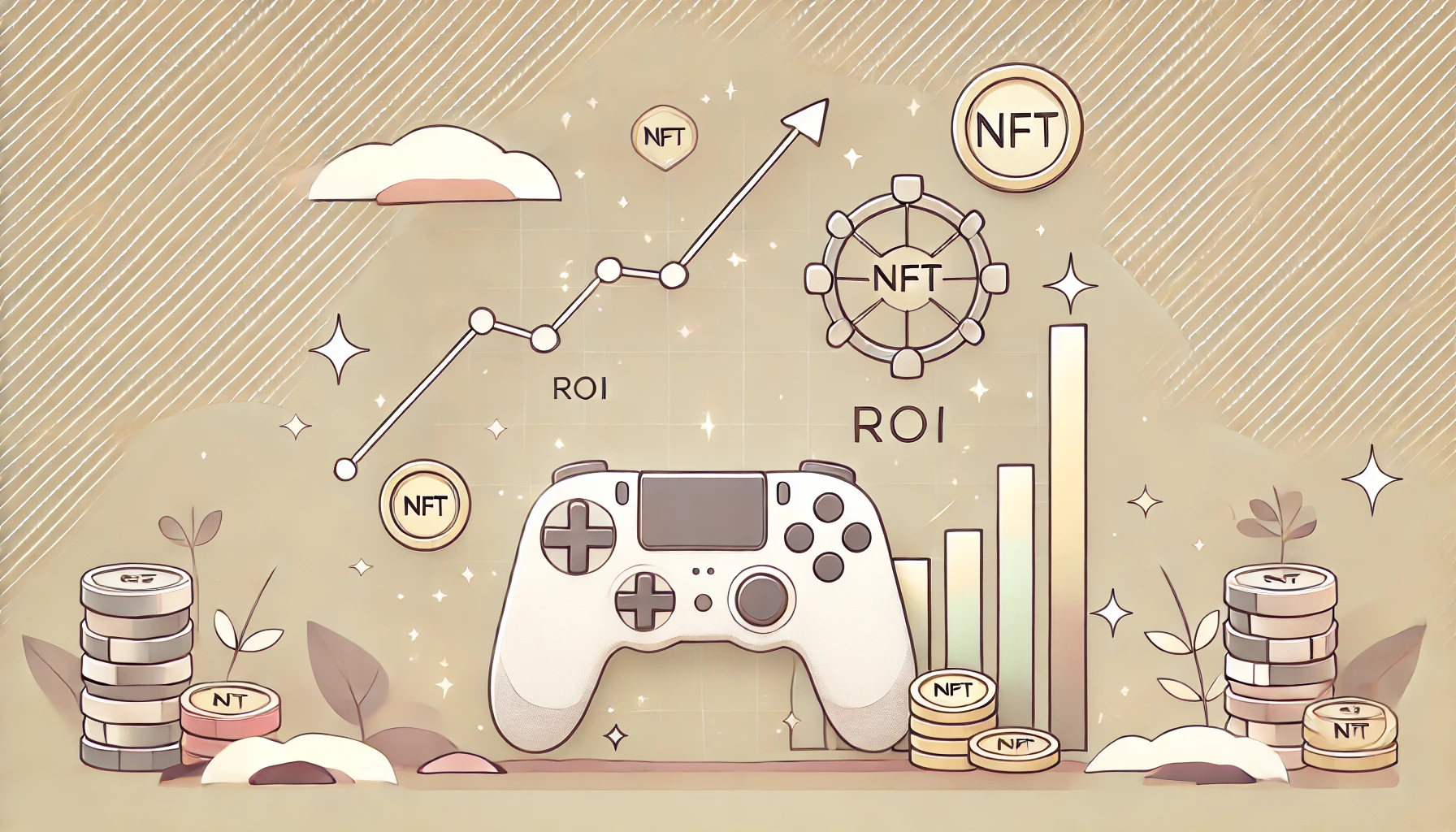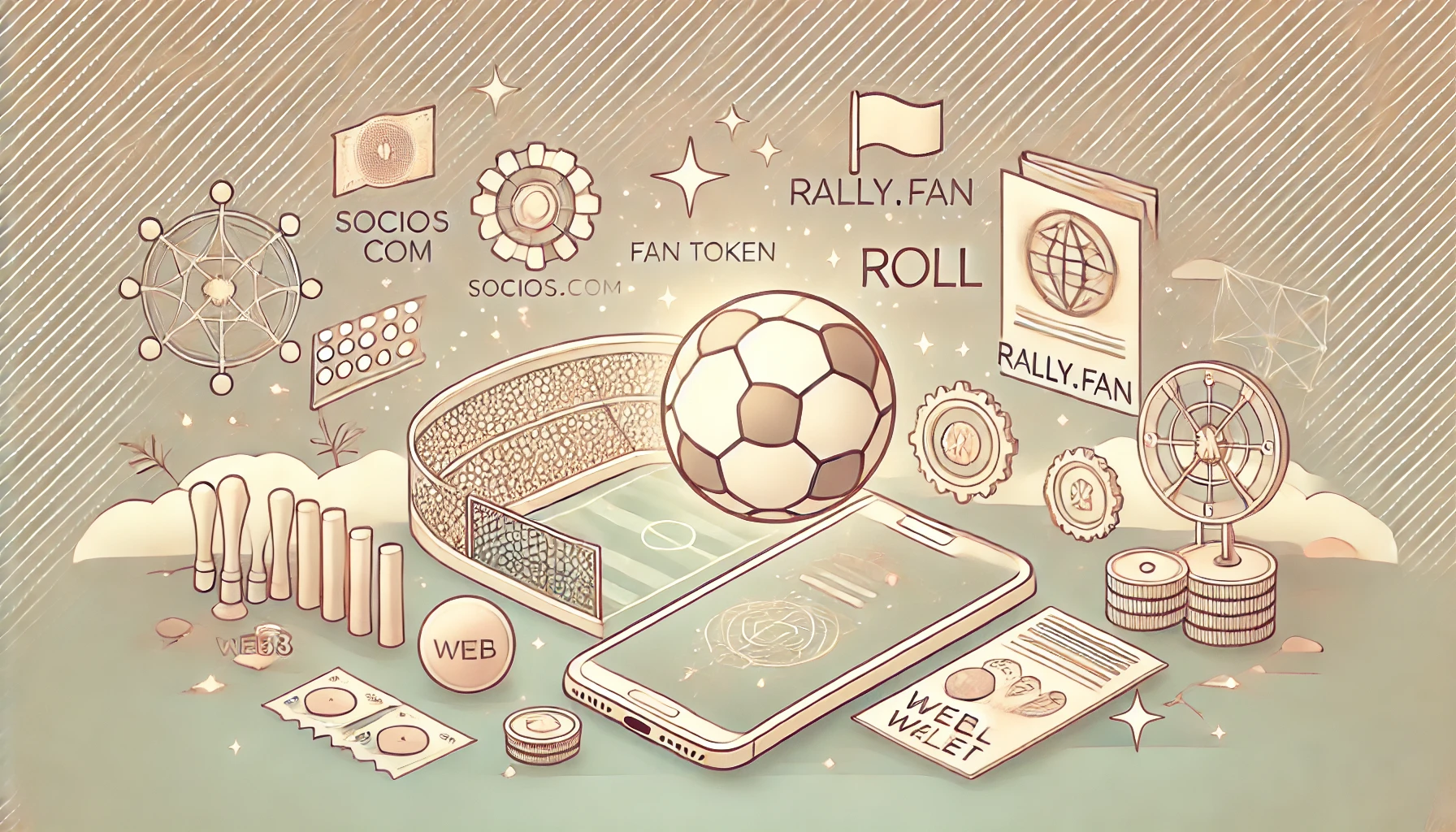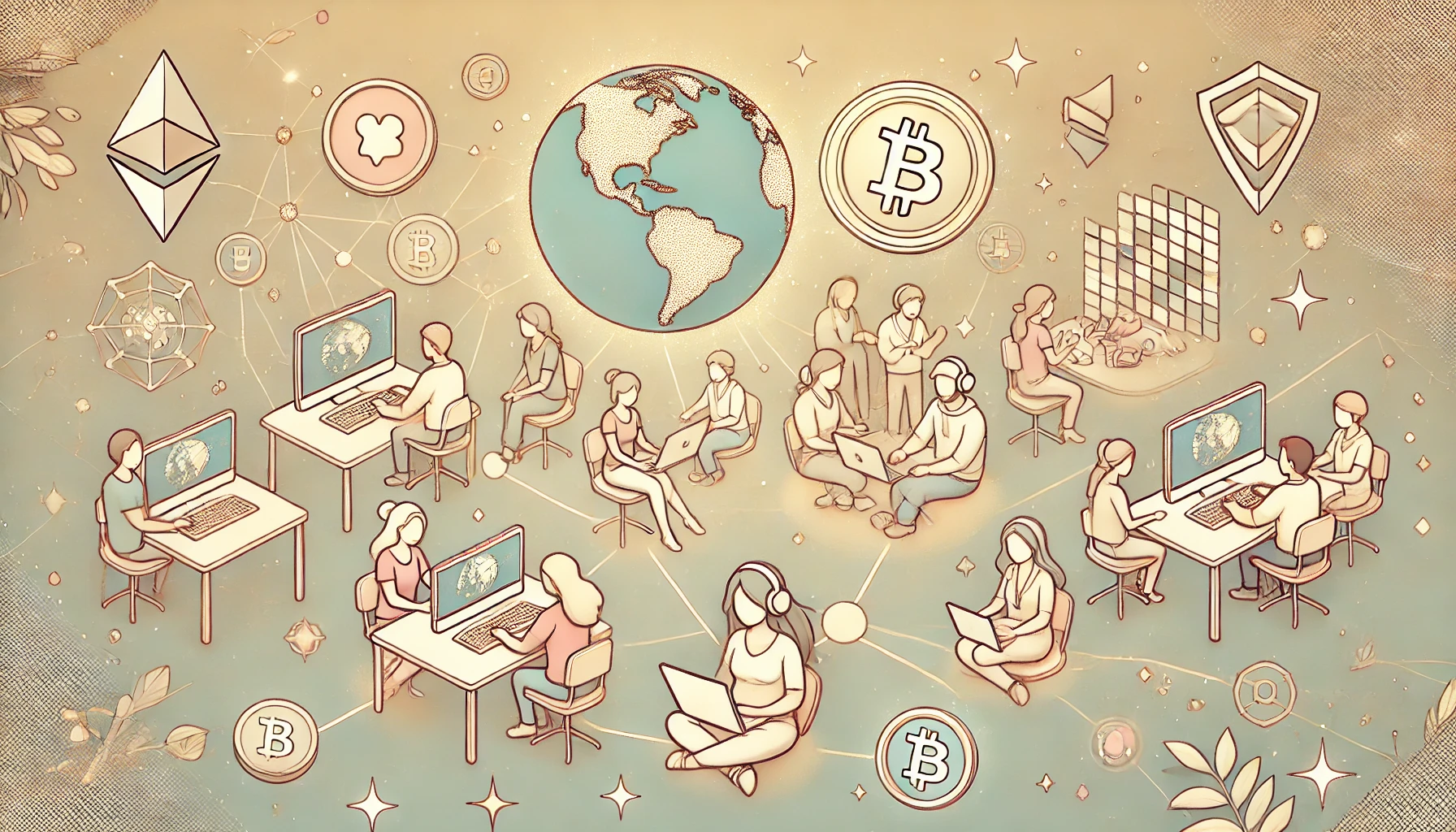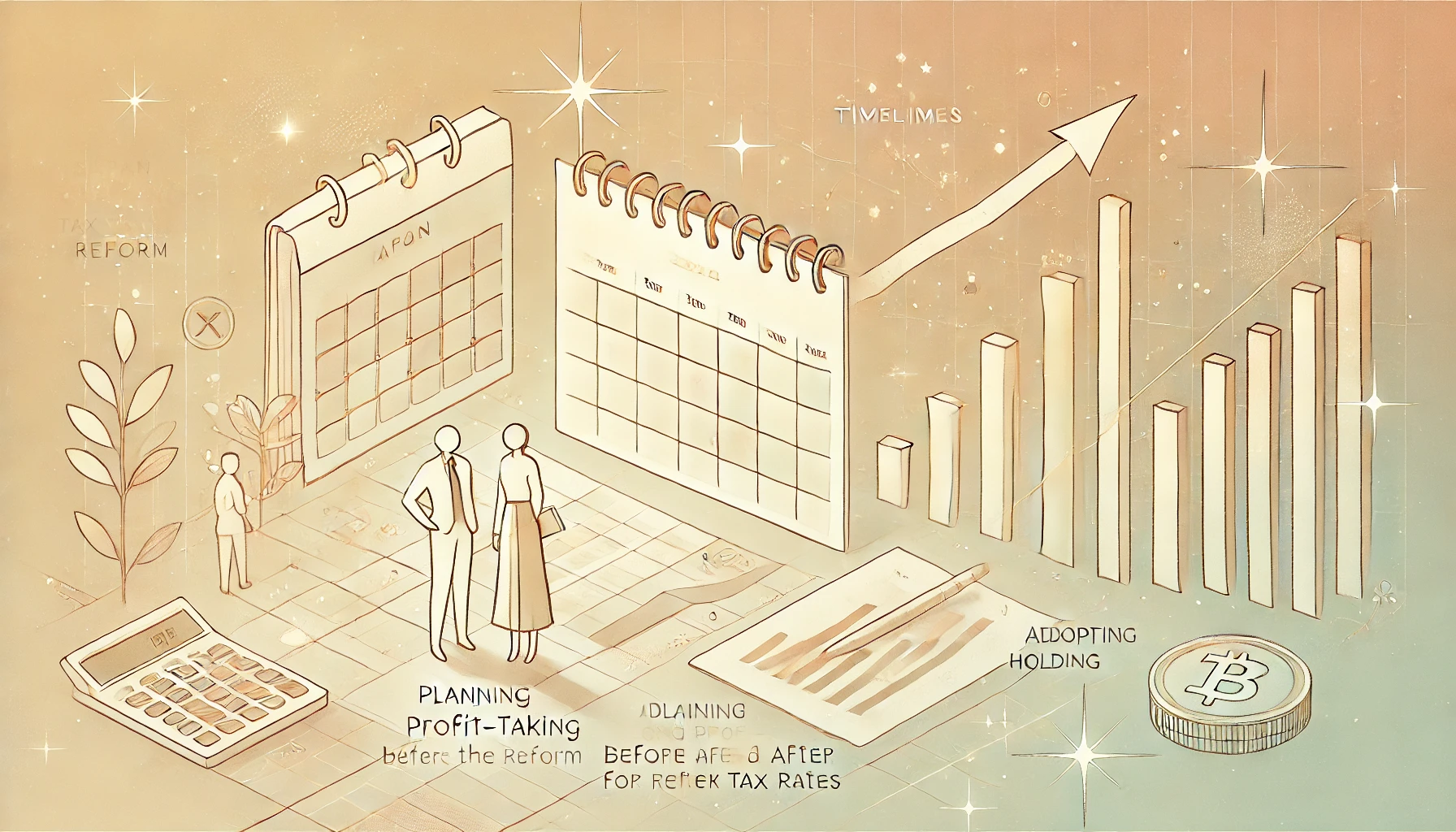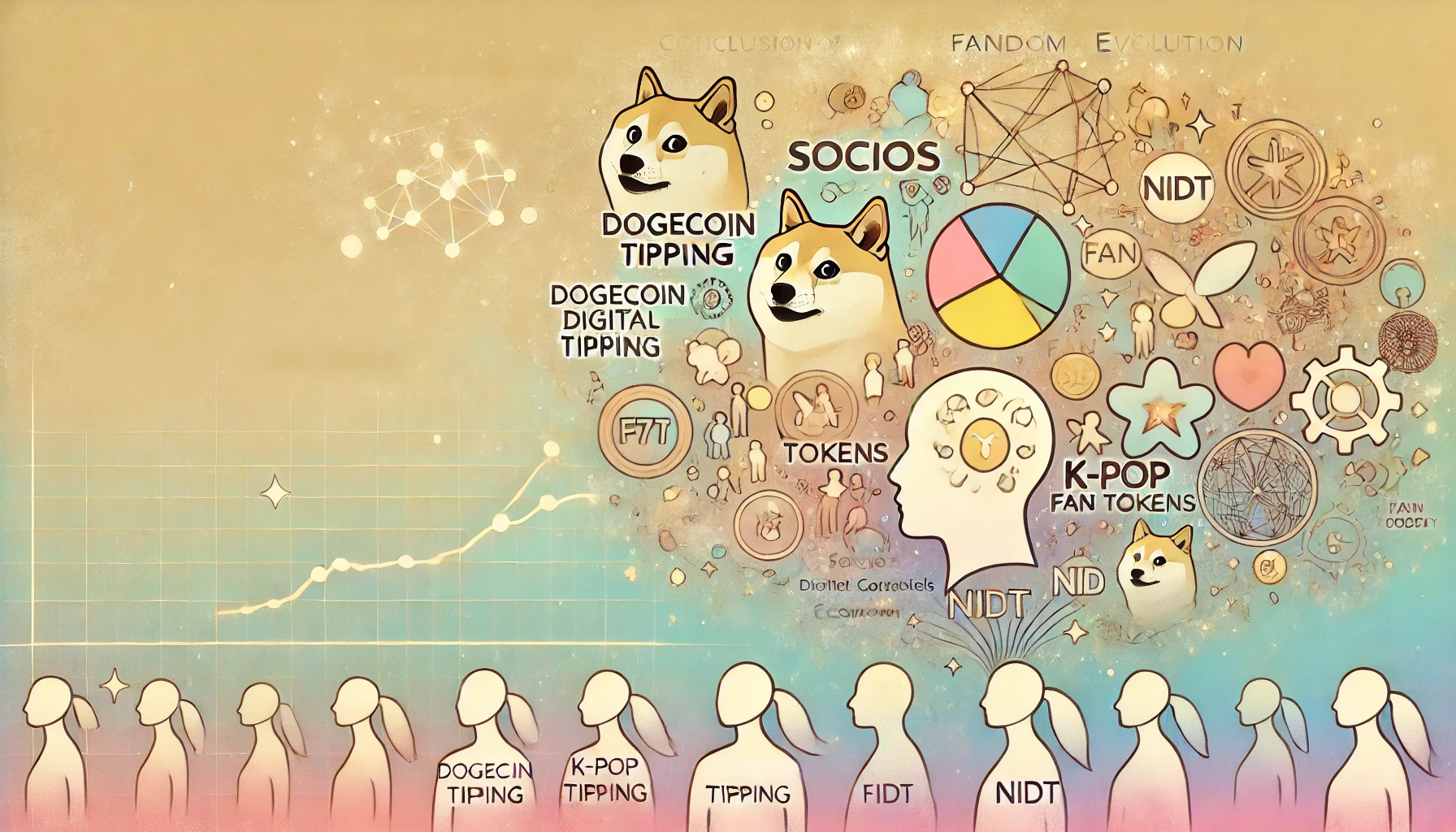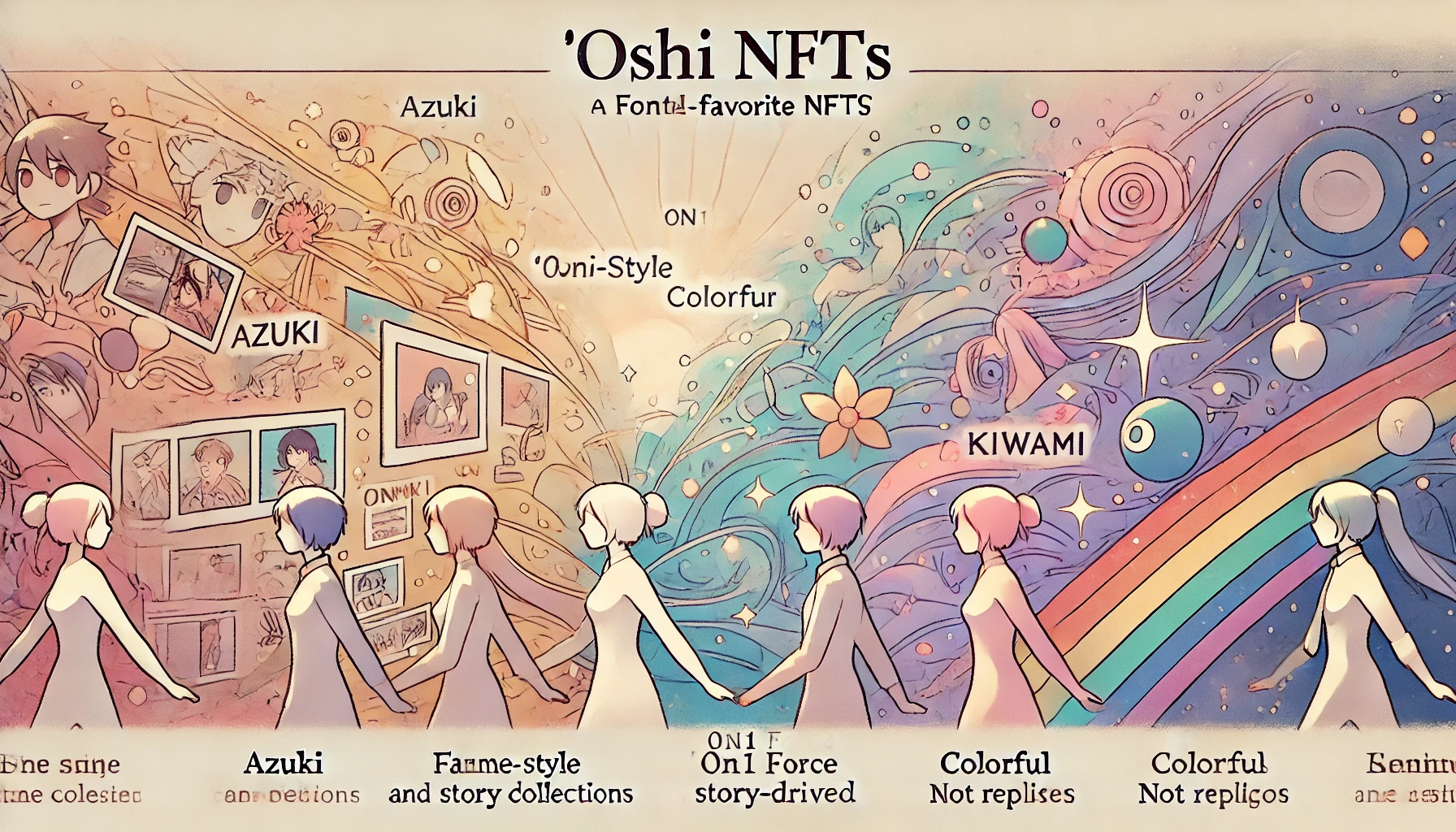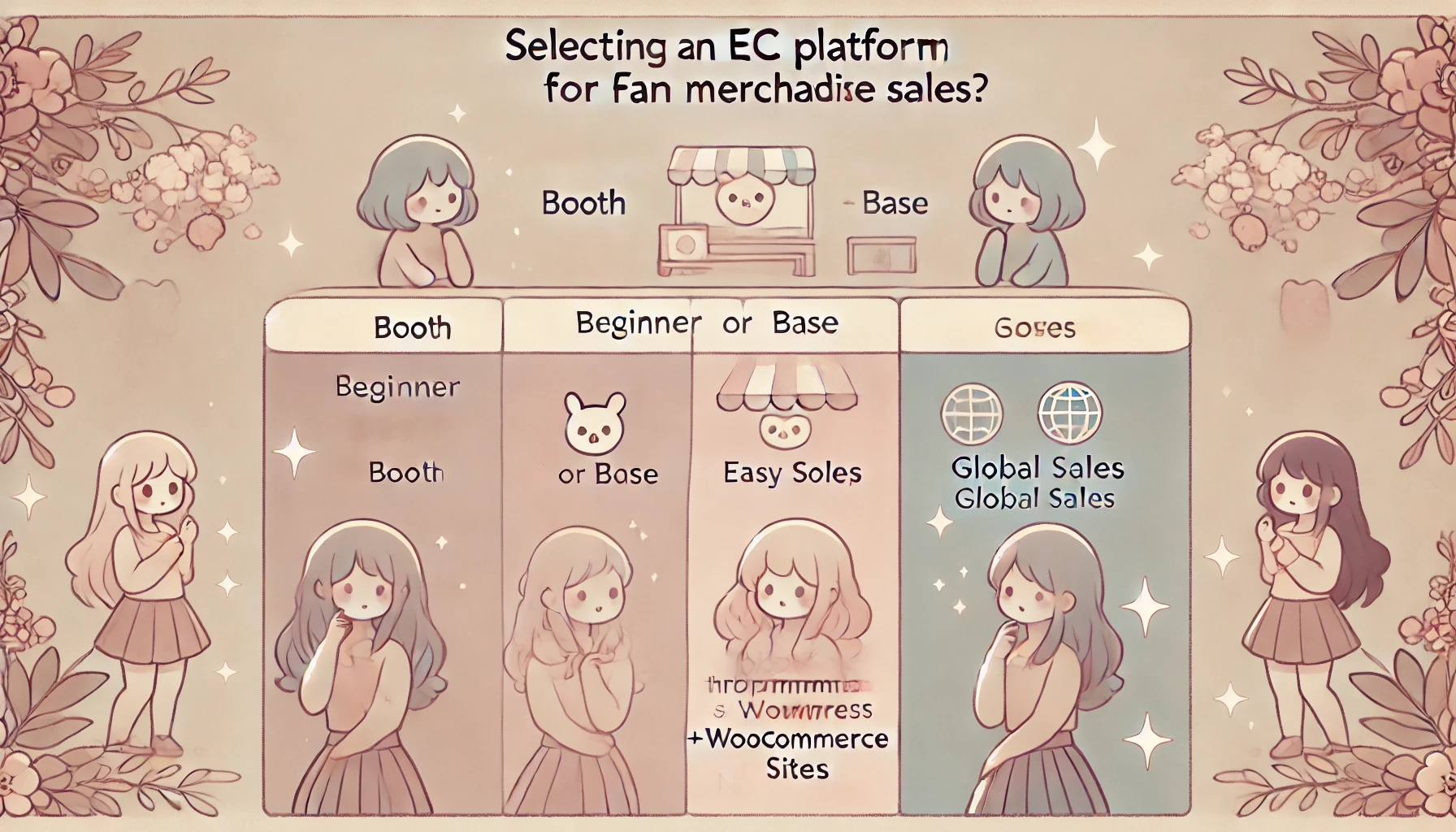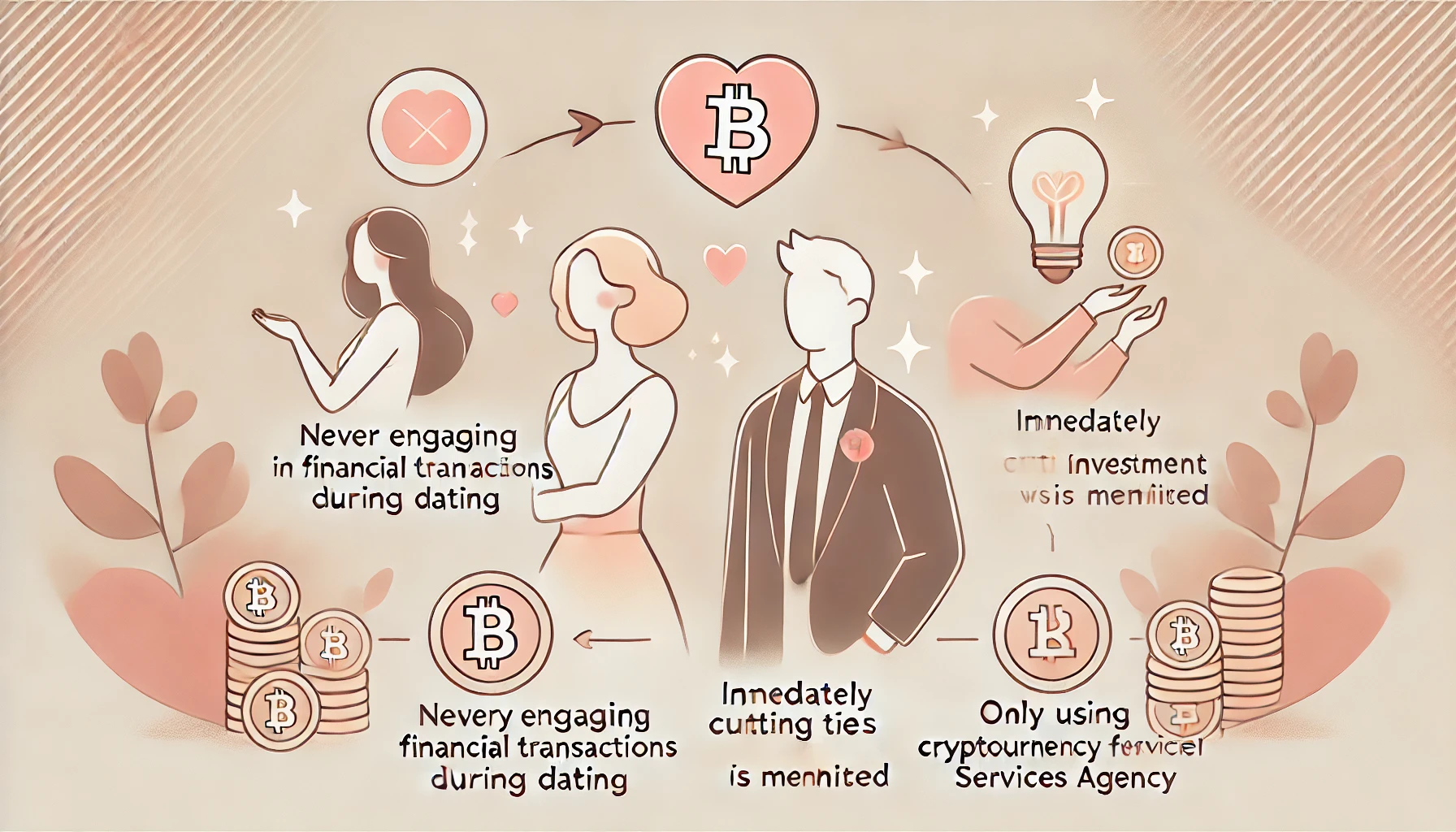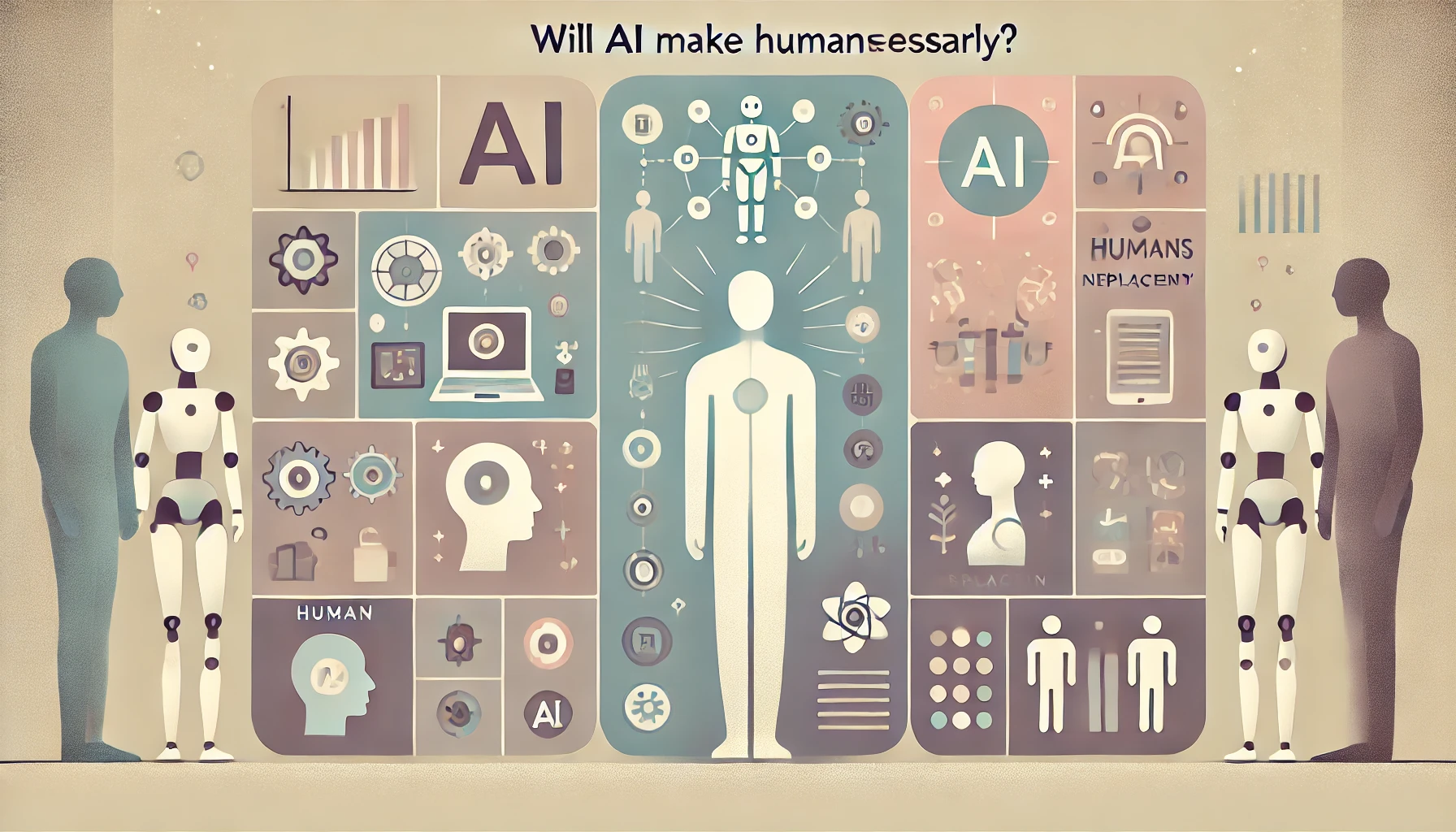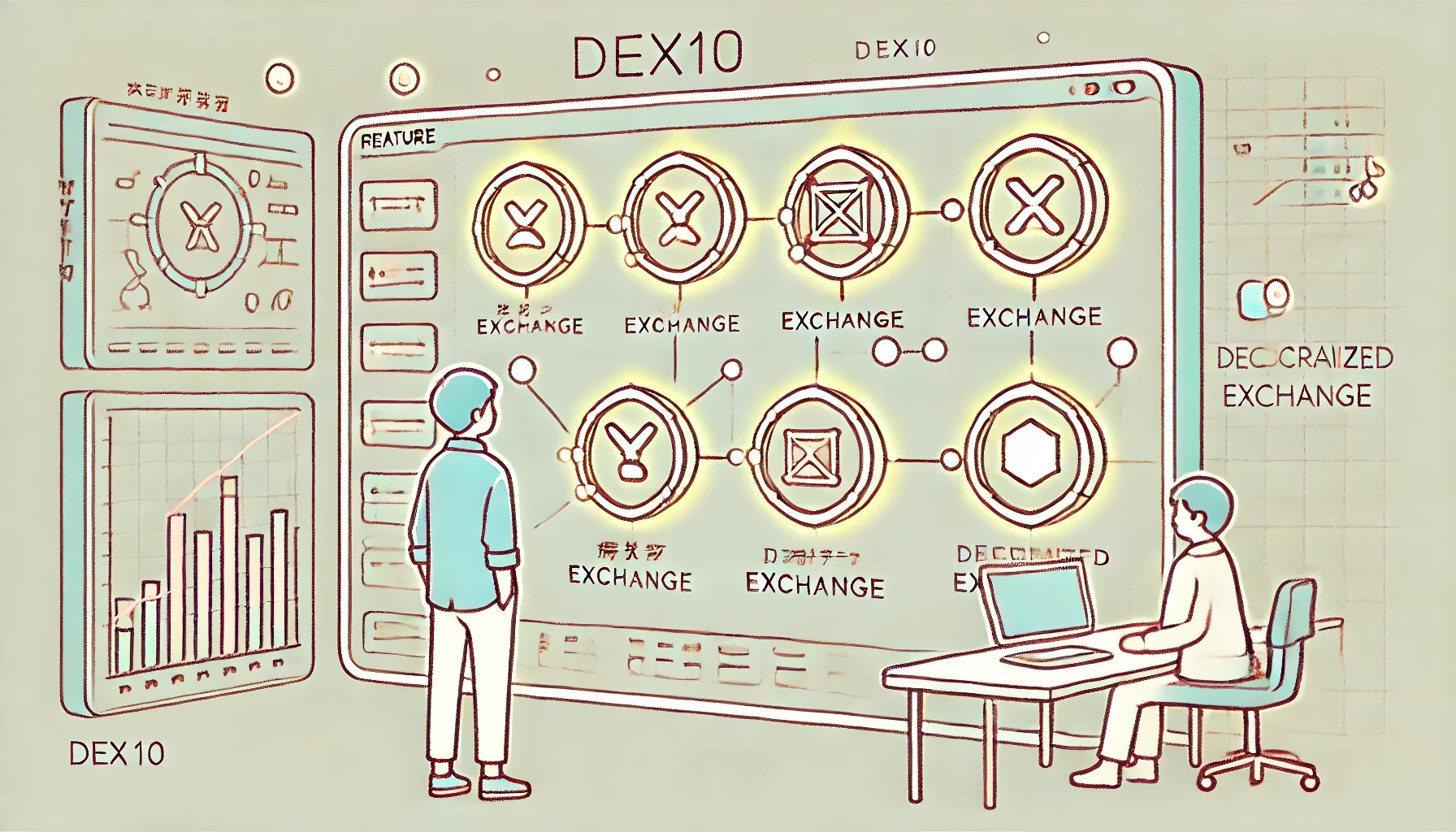仮想通貨アプリを利用する大学生が増えています。しかし、自己管理を誤ると資産が一瞬で失われることも。この記事では、大学生が特に注意すべき仮想通貨アプリ管理の失敗例と、安全に使うための具体策を詳しく解説します。
大学生が陥りやすい仮想通貨アプリ管理の落とし穴
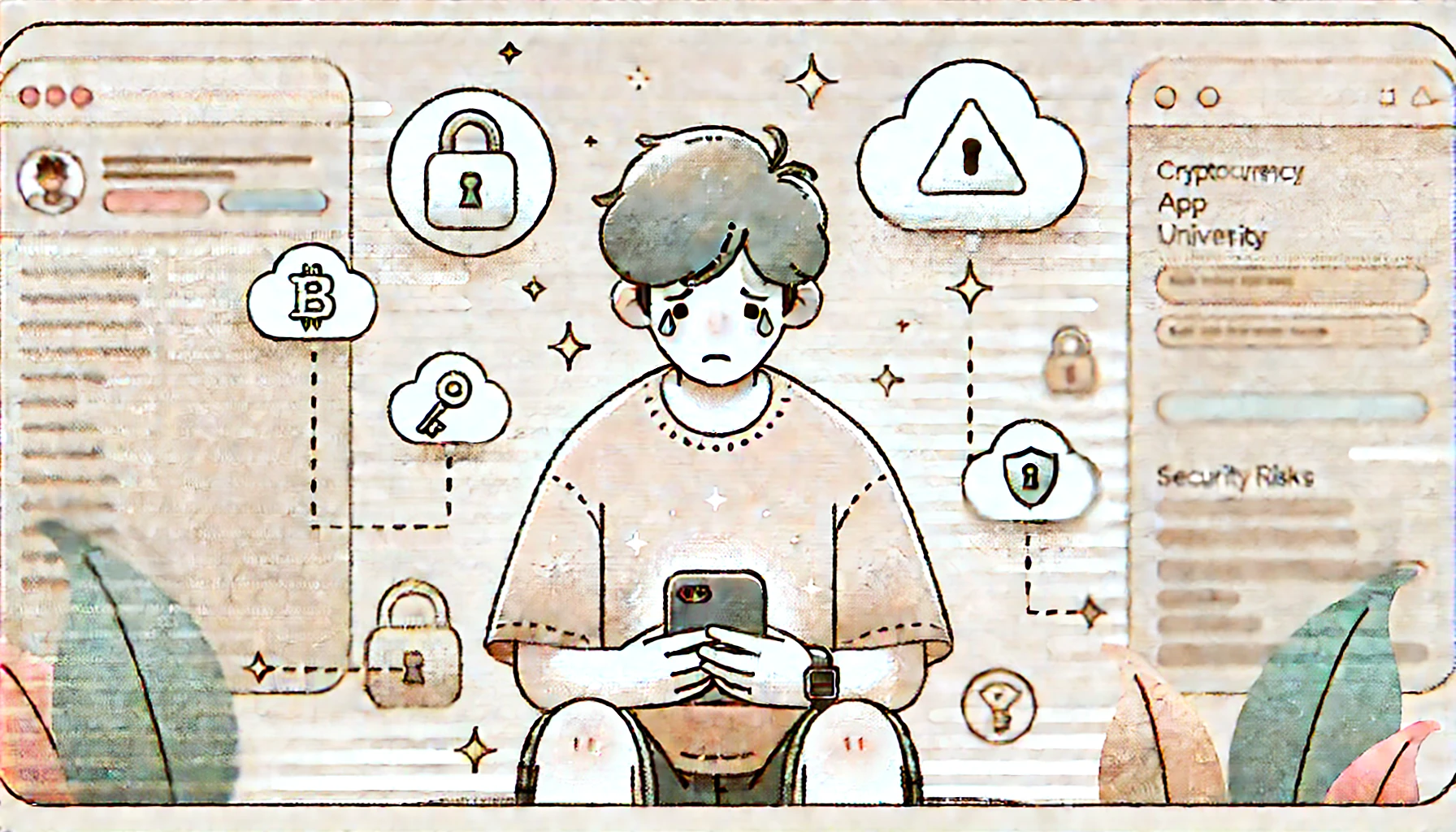
大学生活は自由度が高く、新しい金融サービスにも気軽に触れられる時期です。しかし、仮想通貨は銀行預金のように守られていない資産であり、管理を誤ると即座に失うリスクがあります。
特に以下のようなケースが多く見られます。
- 未登録の海外取引所やアプリを利用し、出金できなくなる
- 二段階認証を設定せず、アカウントを乗っ取られる
- シードフレーズをスマホやクラウドに保存して盗まれる
これらはすべて、正しい知識と習慣で防げるリスクです。次章から具体的な注意点を解説します。
未登録の取引所やアプリを使ってはいけない理由

金融庁登録業者の利用が大前提
金融庁に登録のない取引所やアプリは、システムの安全性や資産管理の基準が不明確です。こうした業者では、入金後に出金できなくなる事例も後を絶ちません。
大学生は特に「手数料が安い」「海外限定のコインが買える」といった宣伝に惹かれがちです。しかし、そうした魅力の裏に高リスクな無登録業者の罠が潜んでいるのです。
公式サイト・アプリストアで確認を
必ず公式サイトのリンクからアプリをインストールし、Google PlayやApp Storeで運営者情報を確認しましょう。金融庁の登録リストも定期的にチェックする習慣が大切です。
二段階認証(2FA)を必ず設定すべき理由

パスワードだけでは不十分
パスワードが流出した場合、第三者による不正アクセスは一瞬です。特にSNSやメールと同じパスワードを使い回している学生は危険です。
二段階認証(2FA)を設定すれば、ログイン時にワンタイムコードが必要となり、乗っ取り被害を大幅に減らせます。
おすすめの認証方法
SMS認証よりも、Google AuthenticatorやAuthyといった認証アプリの利用を推奨します。これらはSIMカードを抜き取る攻撃(SIMスワップ)にも強い防御になります。
シードフレーズの保管は“紙と金庫”が鉄則

デジタル保存は盗難リスクが高い
シードフレーズや秘密鍵をスマホやクラウドに保存するのは危険です。ハッキングやマルウェアに感染すれば、全資産が一瞬で奪われます。
オフラインで複数保管を
紙に書き出し、耐火金庫や貸金庫で保管しましょう。オンライン環境には絶対に置かないことが鉄則です。可能であればハードウェアウォレットの導入も検討しましょう。
パスワードの使い回しが招く重大リスク

1つ突破されると全アカウントが危険に
多くの大学生がやりがちなのが、複数のサービスで同じパスワードを使い回すことです。もし1つのサイトから情報が流出すると、取引所やウォレットのアカウントまで一気に突破される危険性があります。
安全なパスワード管理の方法
パスワードマネージャーの利用が最も効果的です。1PasswordやBitwardenなどのツールを使えば、各サービスごとに複雑で異なるパスワードを生成・保存できます。さらに二段階認証と組み合わせることで堅牢なセキュリティが実現します。
確定申告を怠るリスクと対策
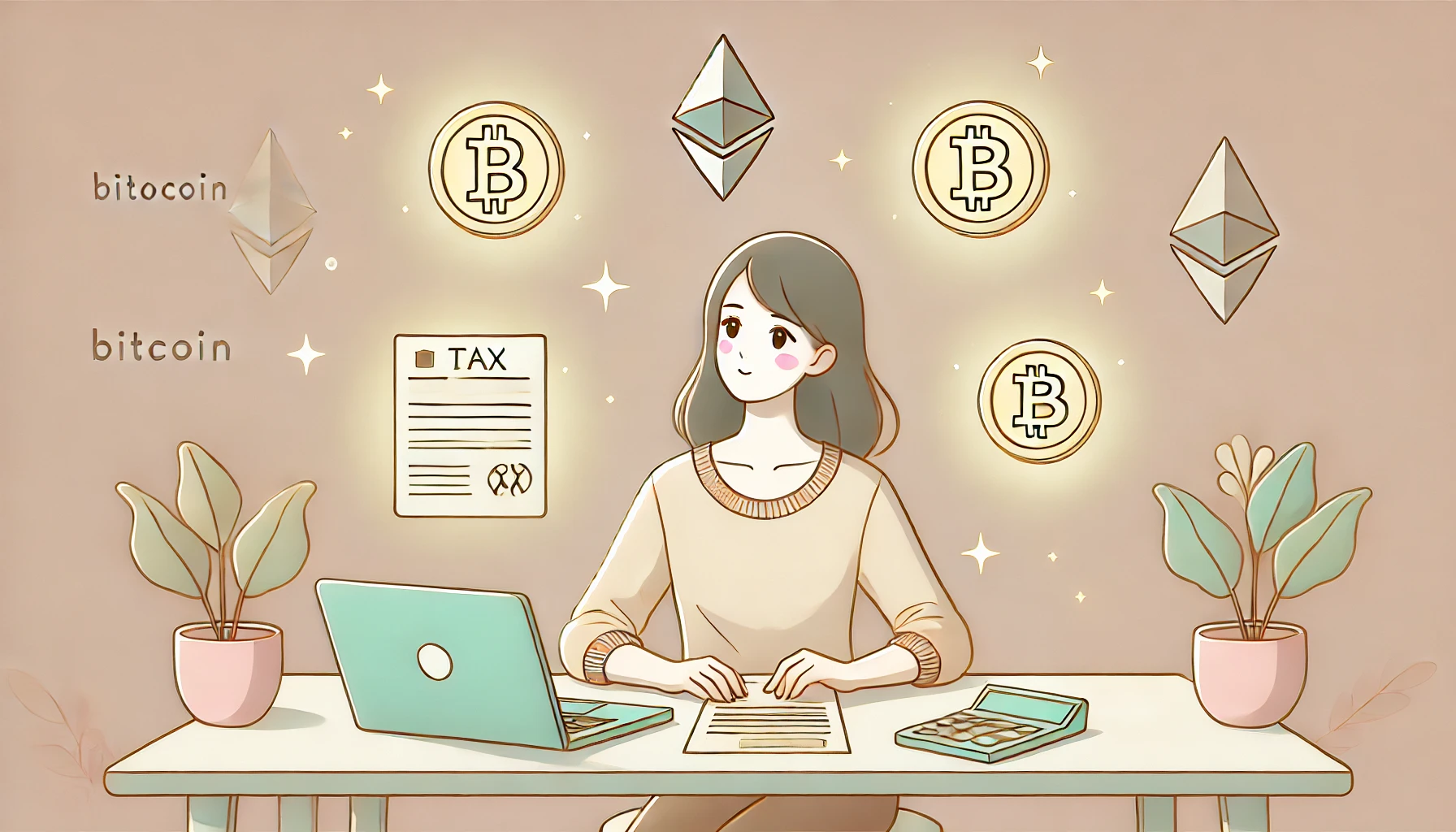
「バレない」は大きな誤解
仮想通貨の売却益やステーキング報酬は、雑所得として課税対象です。年間20万円を超える利益がある場合は確定申告が必要となります。
「少額だから」「学生だからバレない」というのは誤りで、取引所は国税庁に取引記録を報告するため、無申告は追徴課税のリスクを伴います。
申告をスムーズに行うための工夫
取引履歴はこまめにCSVで保存し、会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を活用するとスムーズです。早めの準備が結果的に節税にもつながるでしょう。
アプリのアップデートを怠る危険性

脆弱性は放置すると攻撃の標的に
取引所やウォレットのアプリには、日々セキュリティ改善のアップデートが提供されています。古いバージョンを使い続けると、既知の脆弱性を狙った攻撃の標的になりかねません。
自動更新の活用でリスクを軽減
スマホやPCでは、自動アップデート機能をオンにして常に最新状態を維持することが重要です。特に取引アプリやウォレットは、更新内容にセキュリティ修正が含まれることが多いため、放置せず即時更新を徹底しましょう。
画面共有が招く情報流出リスク

友人との共有が思わぬトラブルに
「取引のやり方を教えるため」「残高を見せるため」といった理由で、画面共有を行う大学生も少なくありません。しかし、QRコードやシードフレーズが映り込むと、一瞬で資産を抜き取られる恐れがあります。
絶対に見せてはいけない情報
シードフレーズ・秘密鍵・ウォレットアドレスの管理画面は、いかなる場合も第三者に見せない運用を徹底しましょう。もし画面共有が必要な場合は、該当部分を非表示にするか、共有専用のデモアカウントを用意するのが安全です。
仮想通貨アプリ管理のチェックリスト
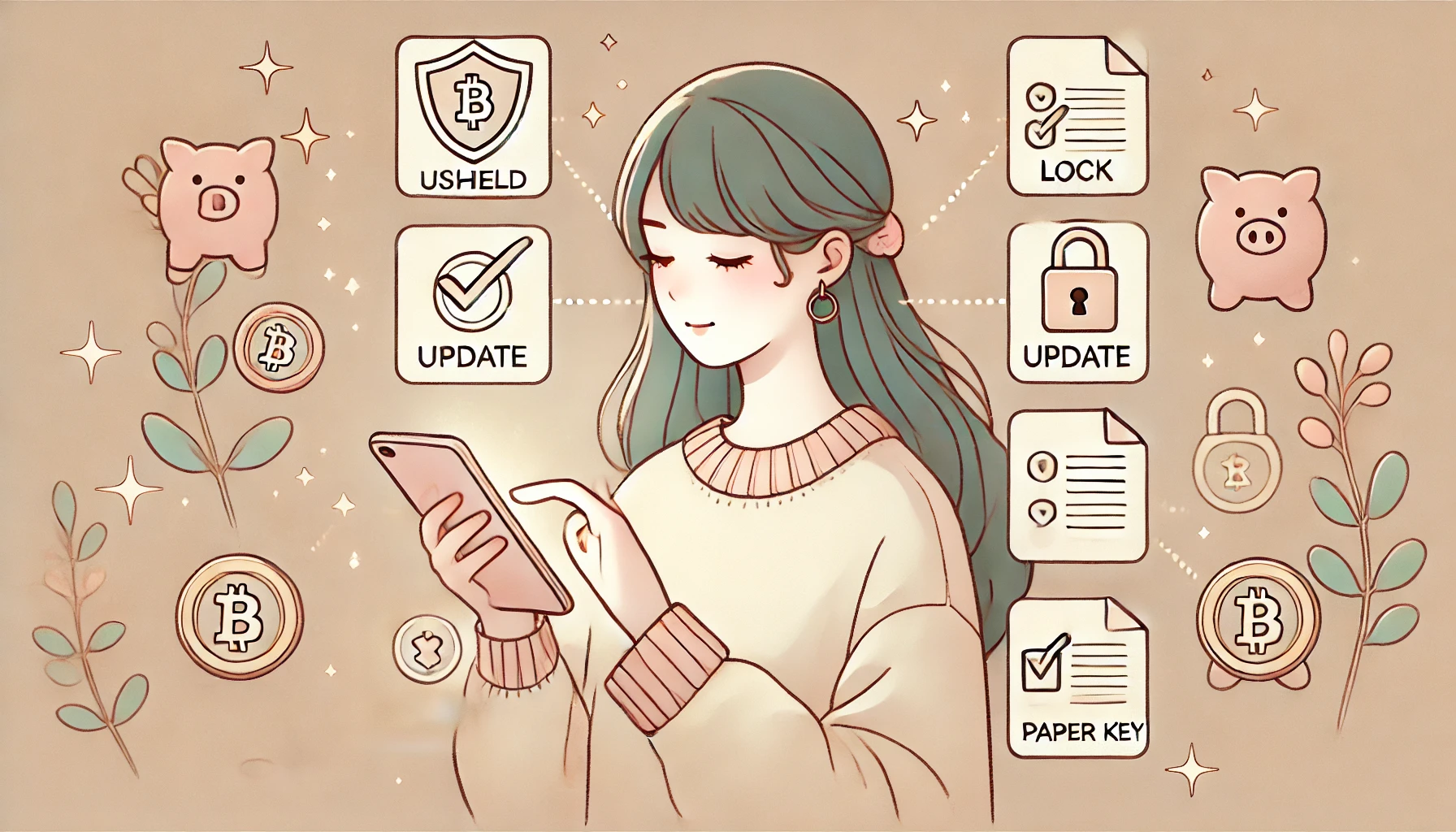
今日から実践できる10の安全対策
ここまで紹介した内容を踏まえ、大学生がすぐに取り組めるチェックリストをまとめます。これらを日常的に確認するだけでも、大きなトラブルを避けられるでしょう。
- 金融庁登録の取引所・アプリのみを利用する
- 二段階認証(認証アプリ)を必ず設定する
- シードフレーズは紙+金庫でオフライン保管
- URLは自分で入力・ブックマークした公式のみ使用
- 不要なDApp承認はこまめに解除
- 公共Wi-Fiでは取引せずVPNやモバイル回線を利用
- パスワードは使い回さず、パスワードマネージャーを導入
- 仮想通貨の利益は必ず確定申告
- アプリは常に最新バージョンに更新
- 画面共有では秘密情報を絶対に映さない
これらは特別な技術や高額なツールを必要としません。意識と習慣の徹底こそが最大の防御になります。
まとめ:自己管理が未来の資産を守る

仮想通貨は銀行のような補償がなく、すべてが自己責任の世界です。だからこそ、大学生のうちから正しい管理習慣を身につけることが、将来の大きな資産形成につながります。
今回紹介した10のチェックポイントを日常的に意識し、「安全に資産を育てる」という考え方を常に持っておきましょう。小さな習慣の積み重ねが、未来の安心と成功への第一歩になります。