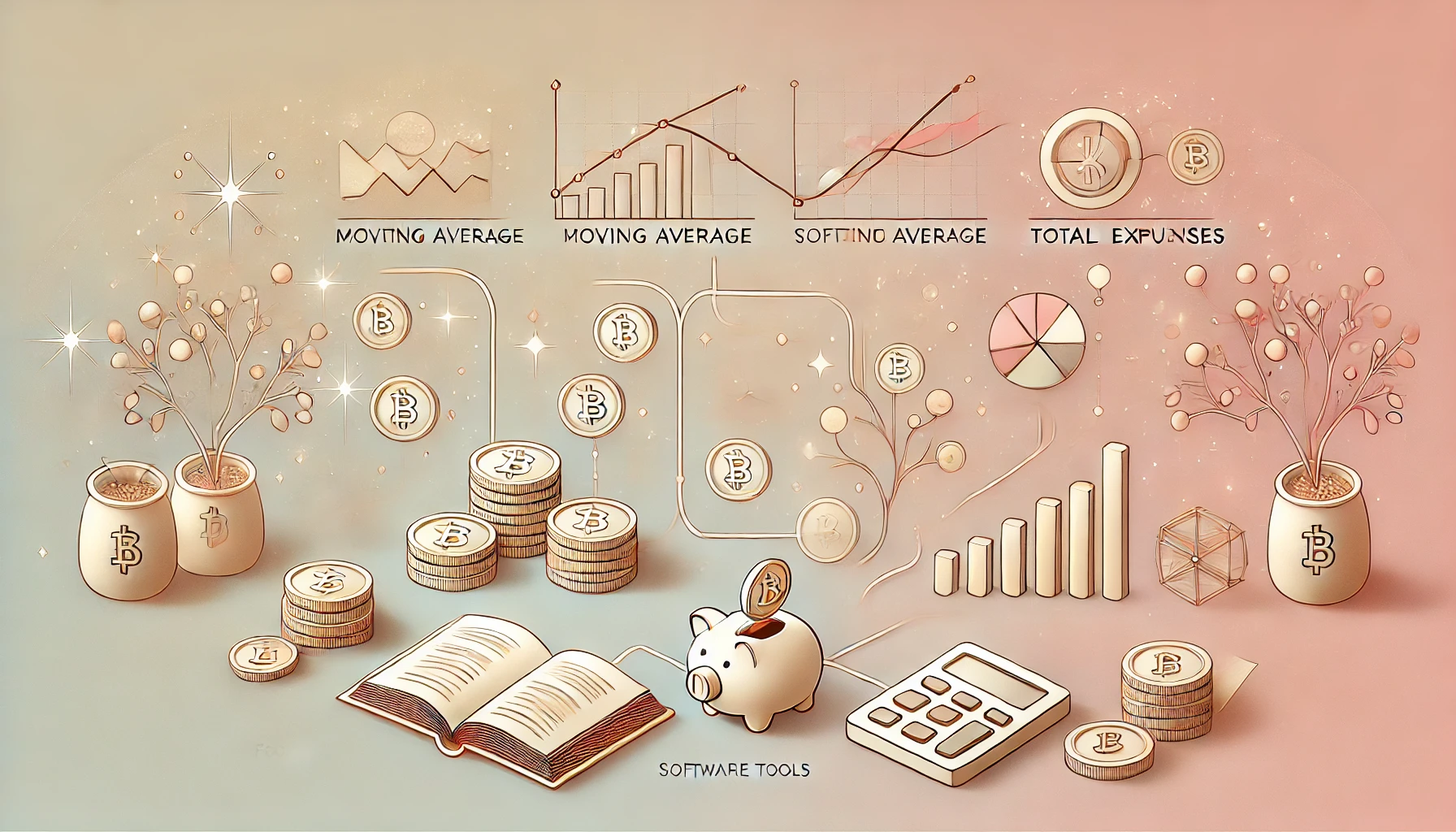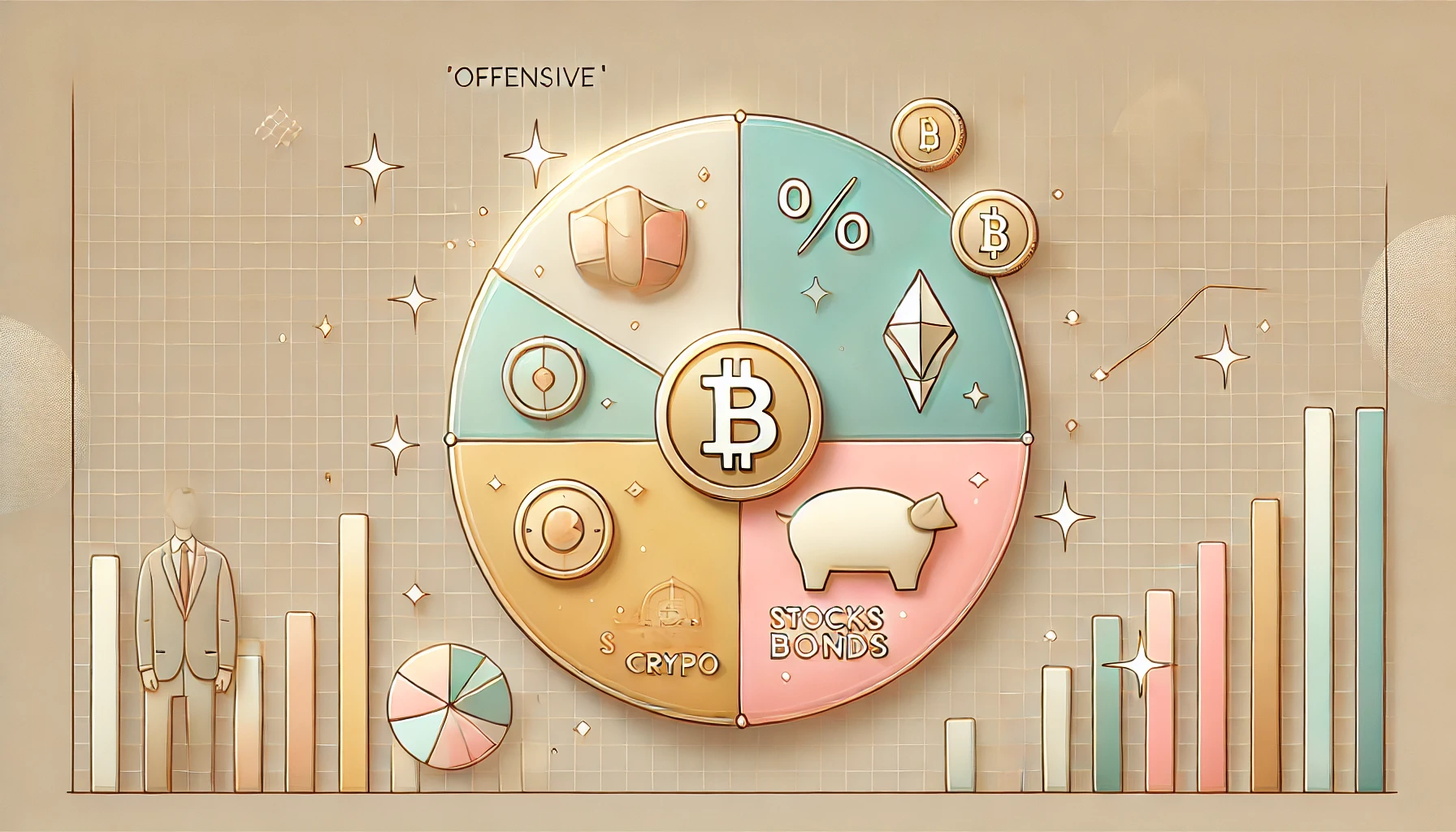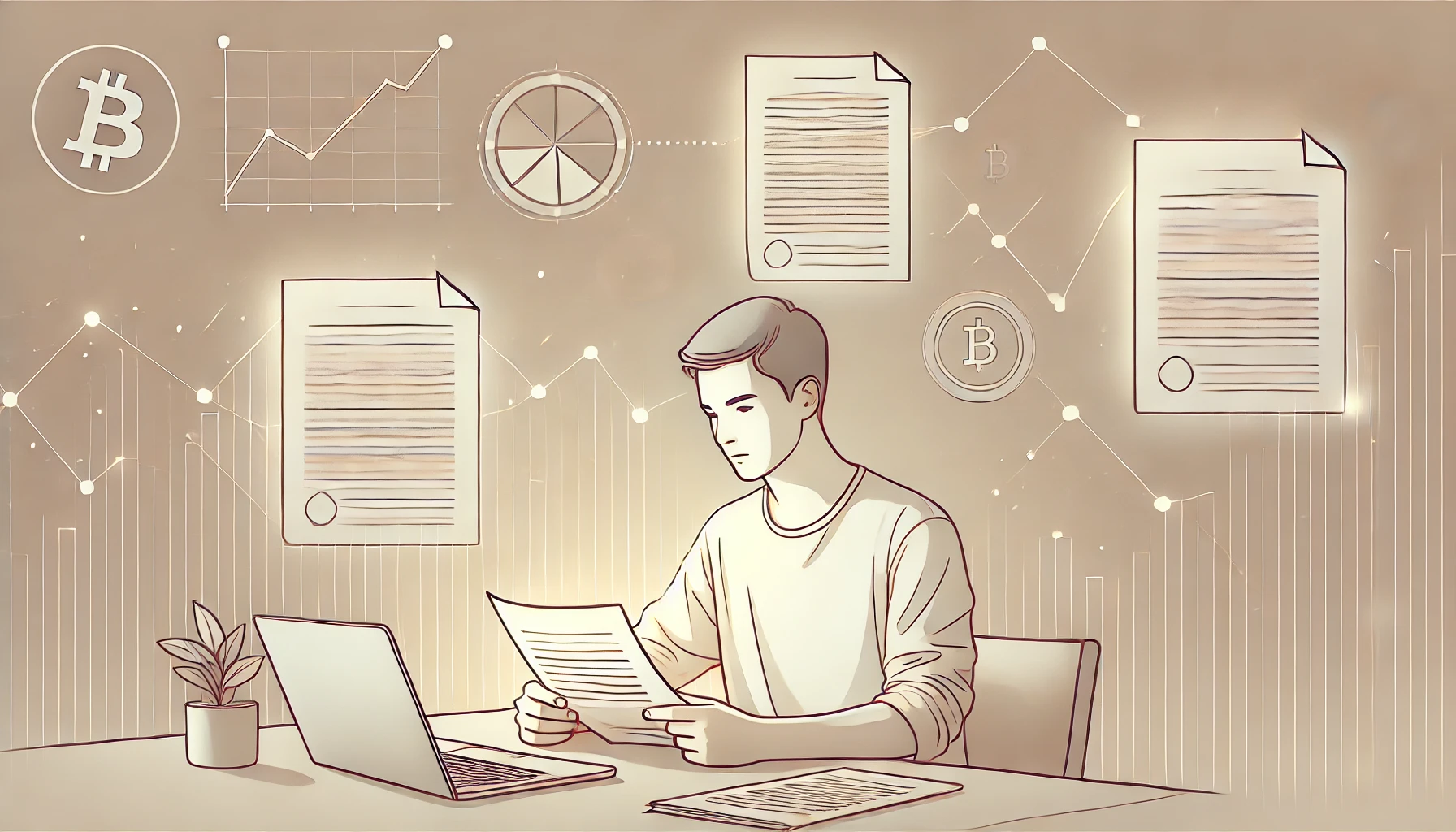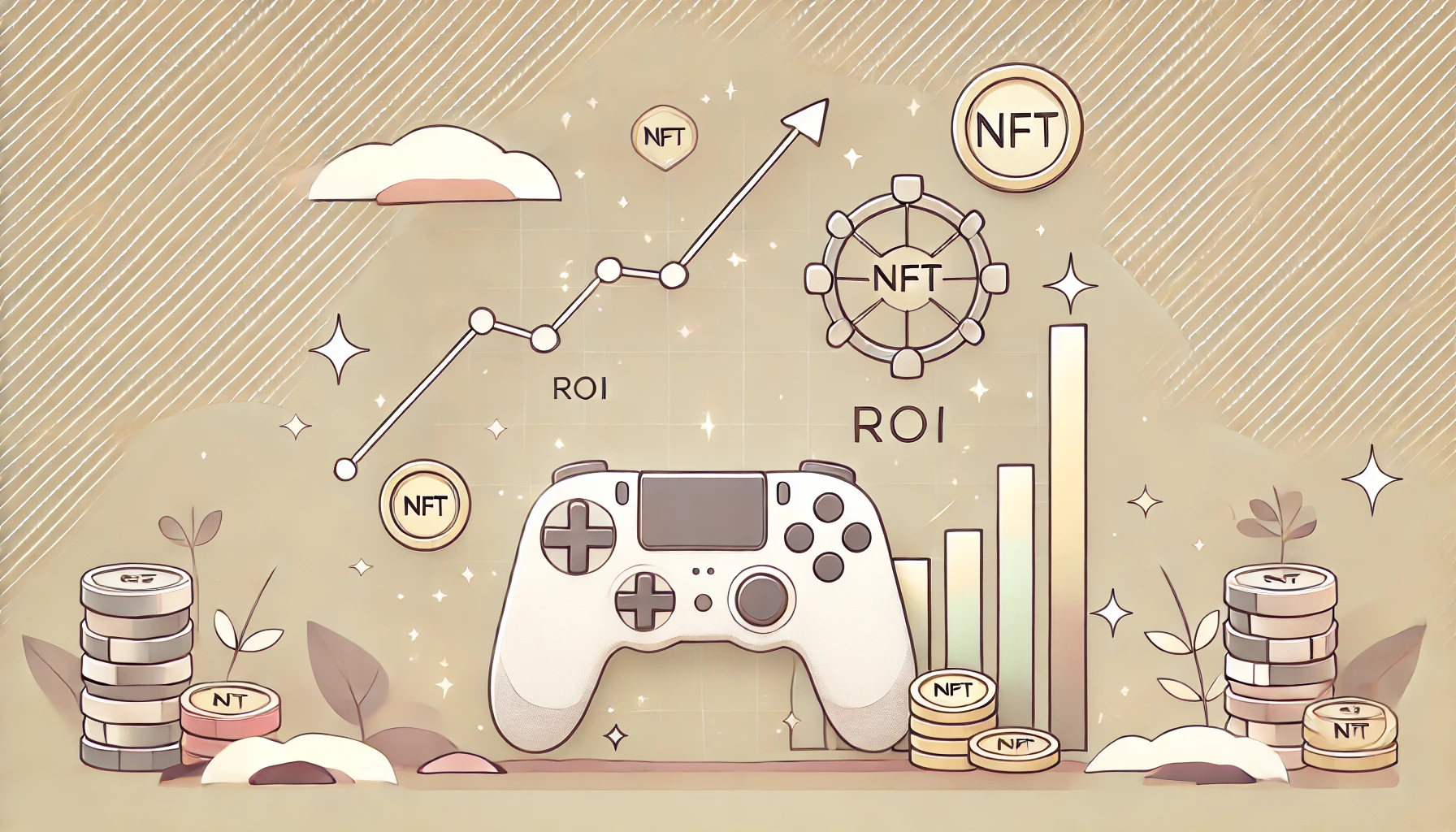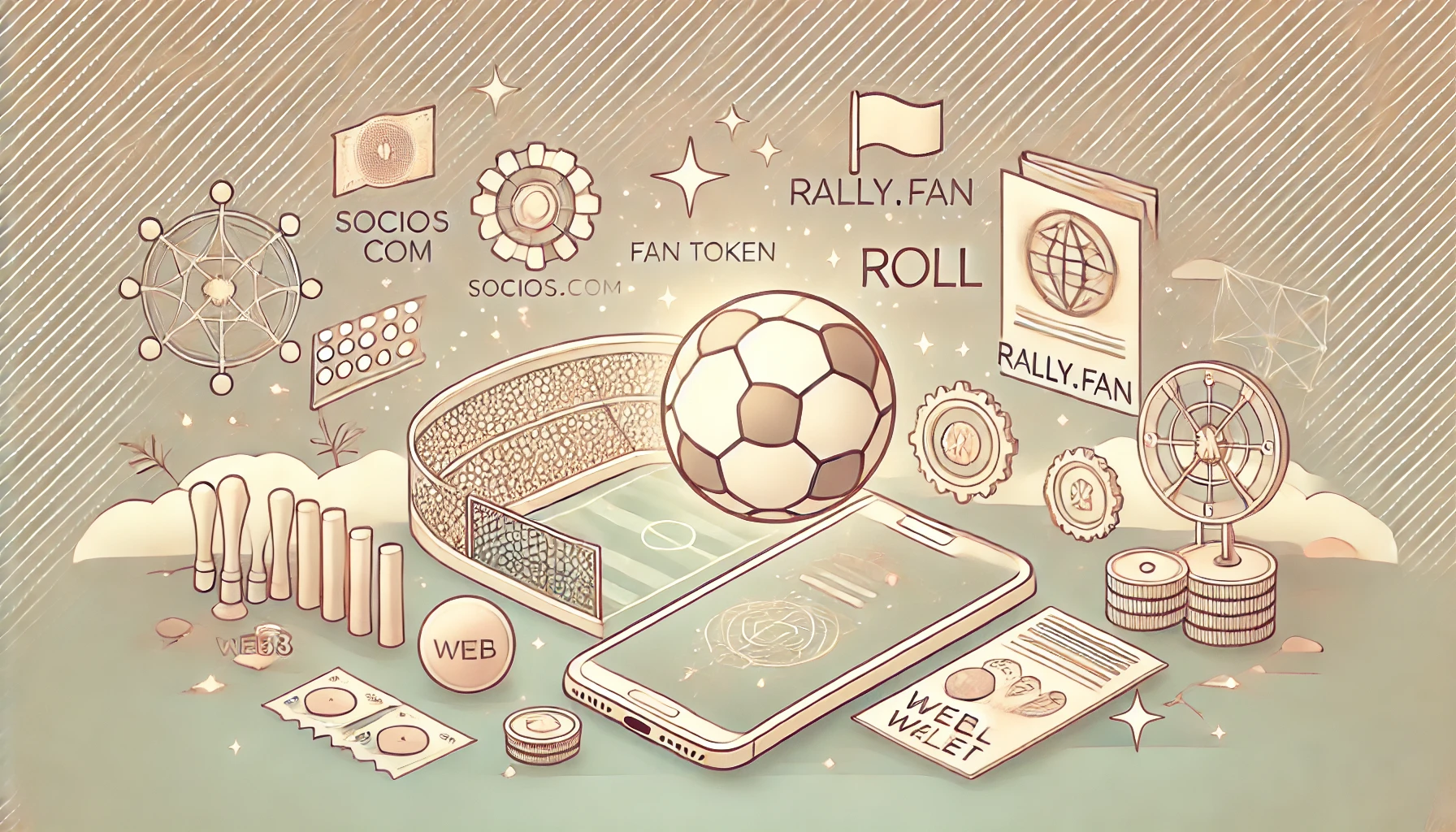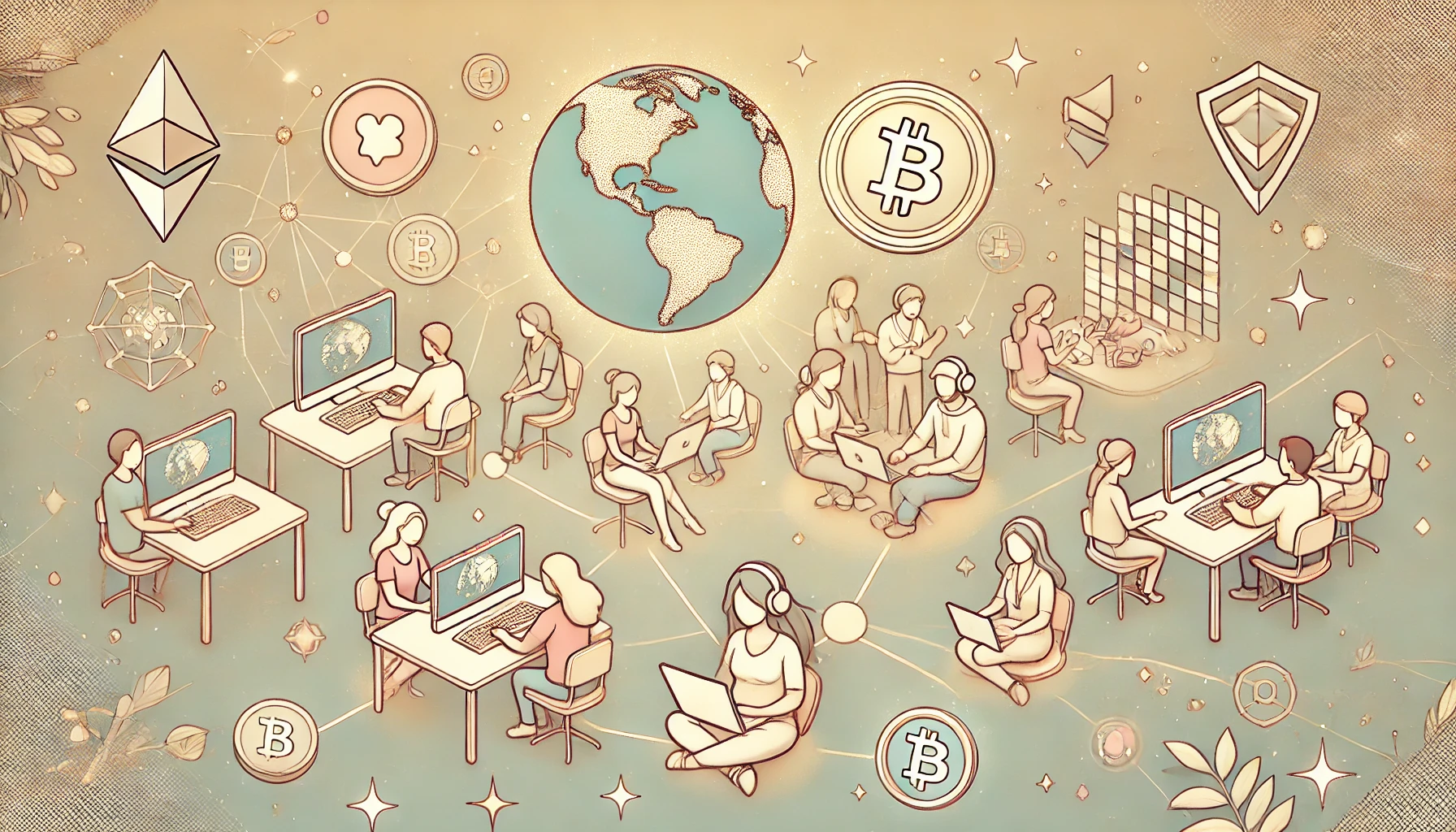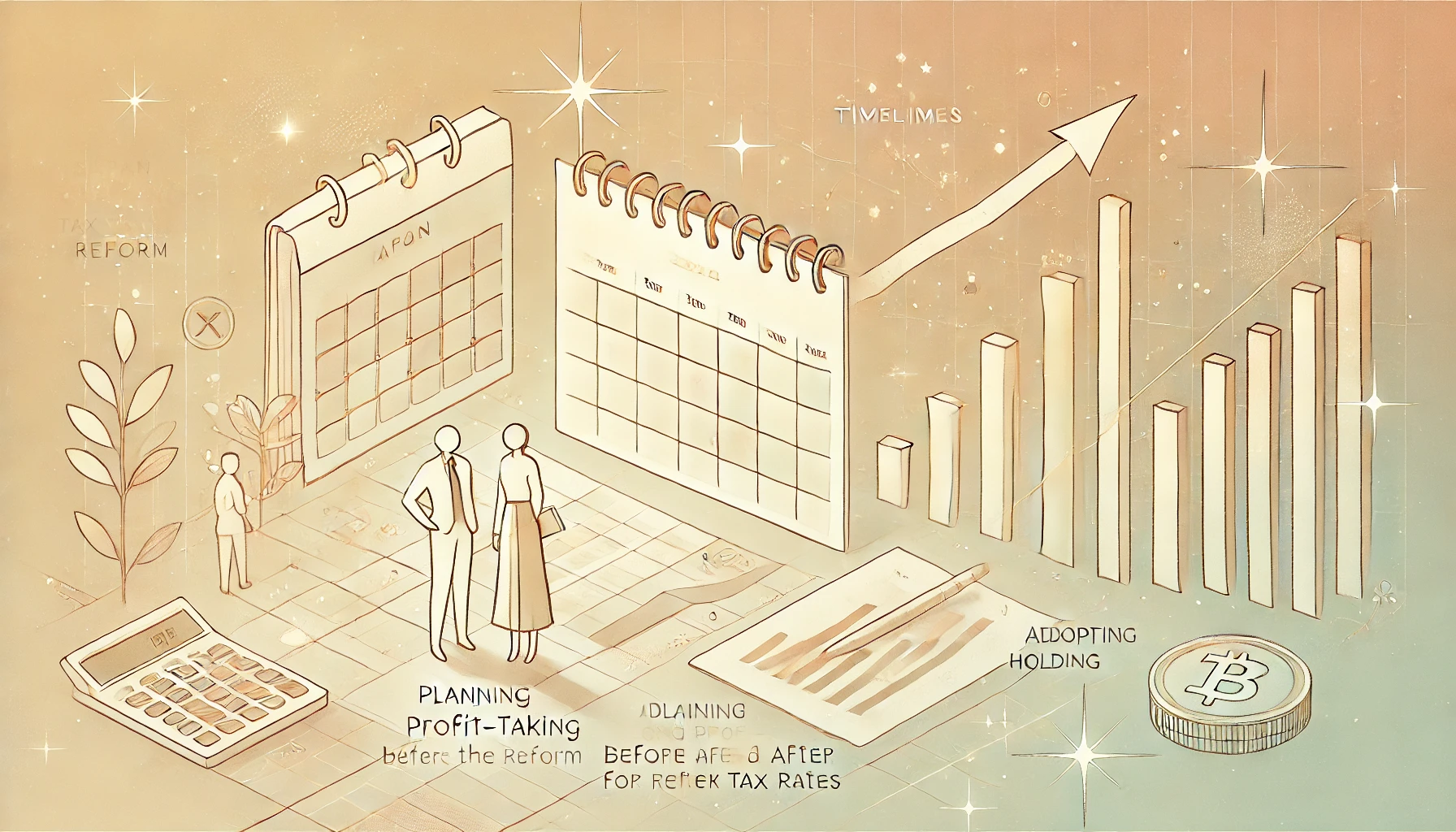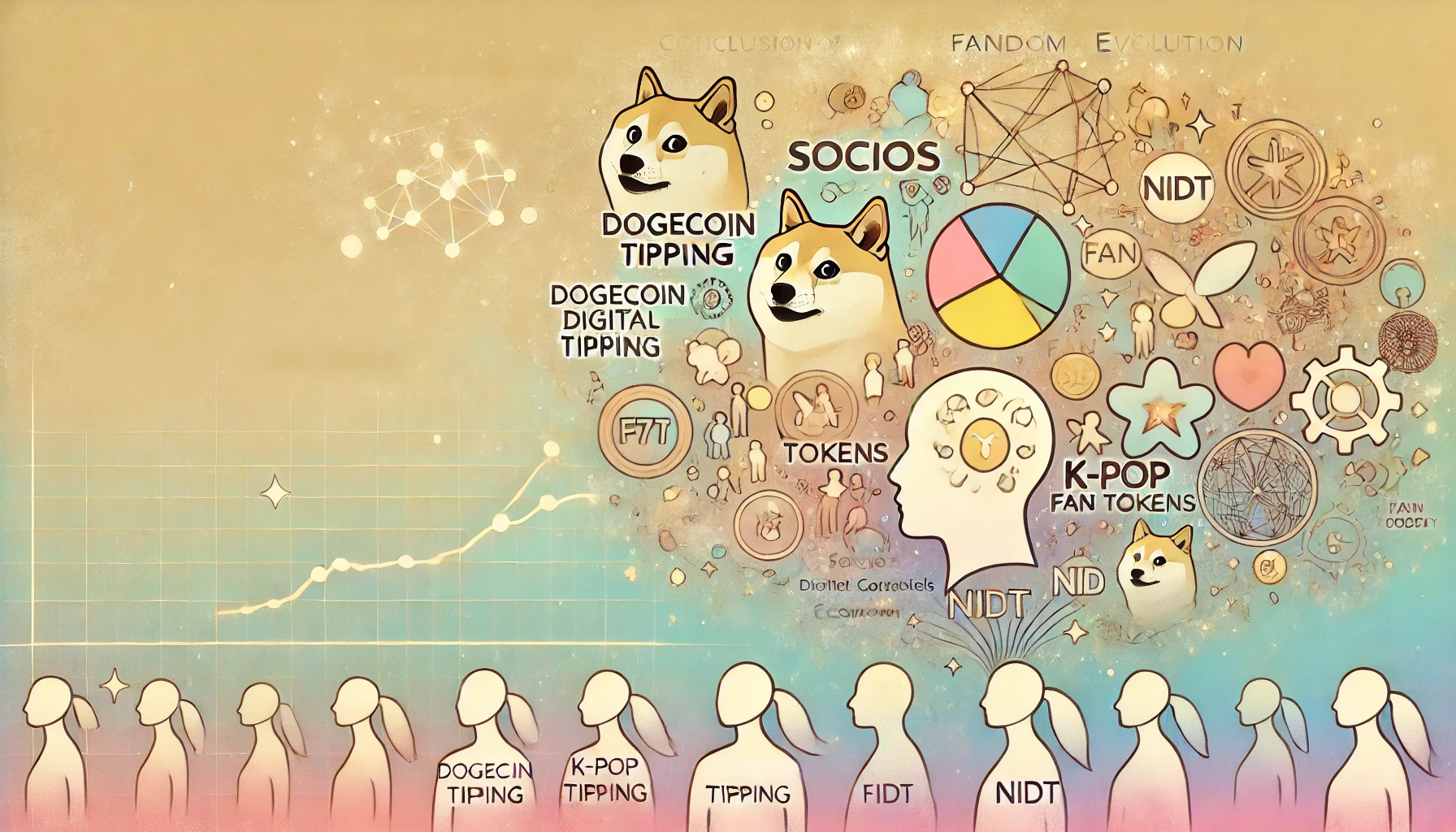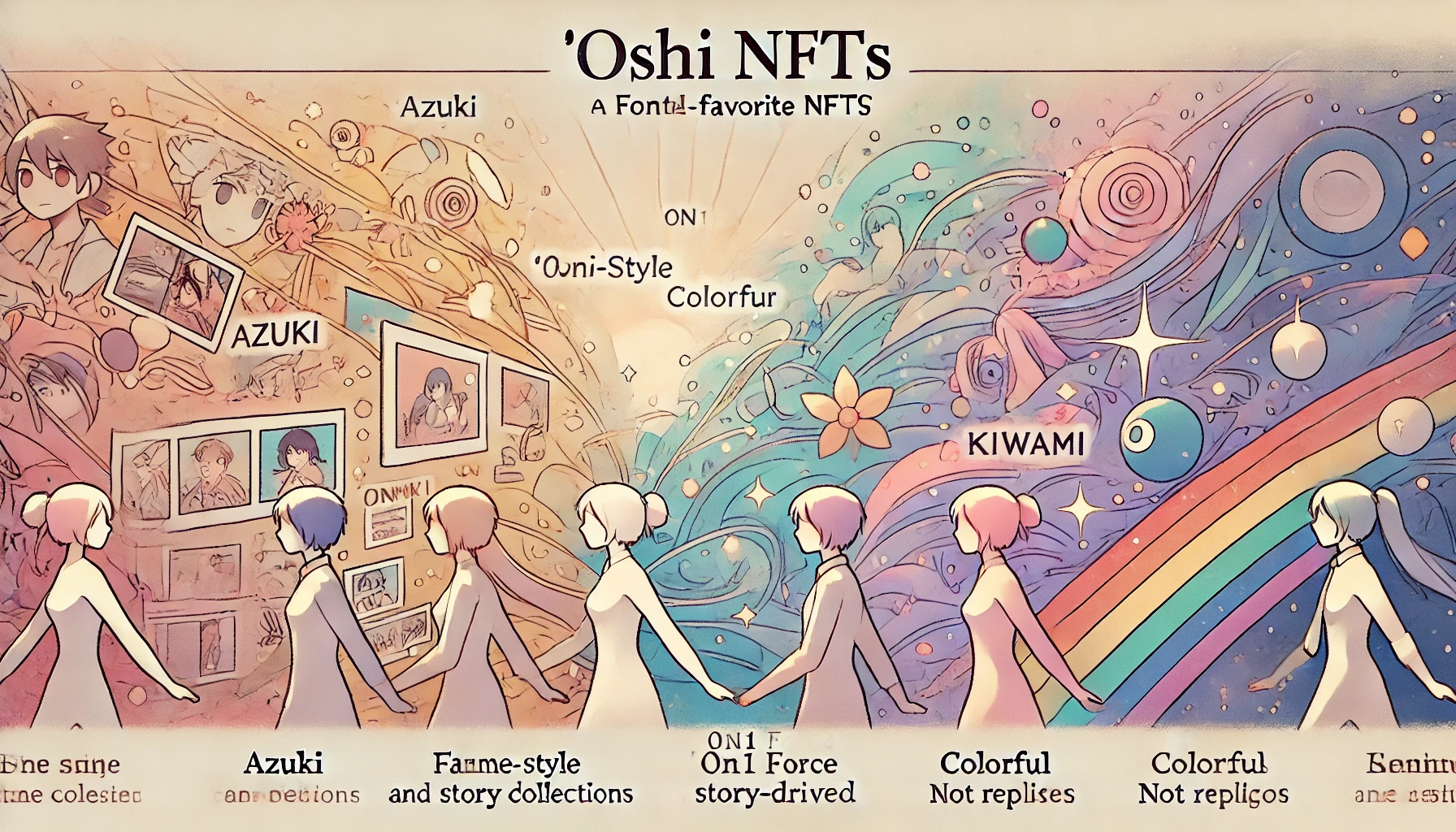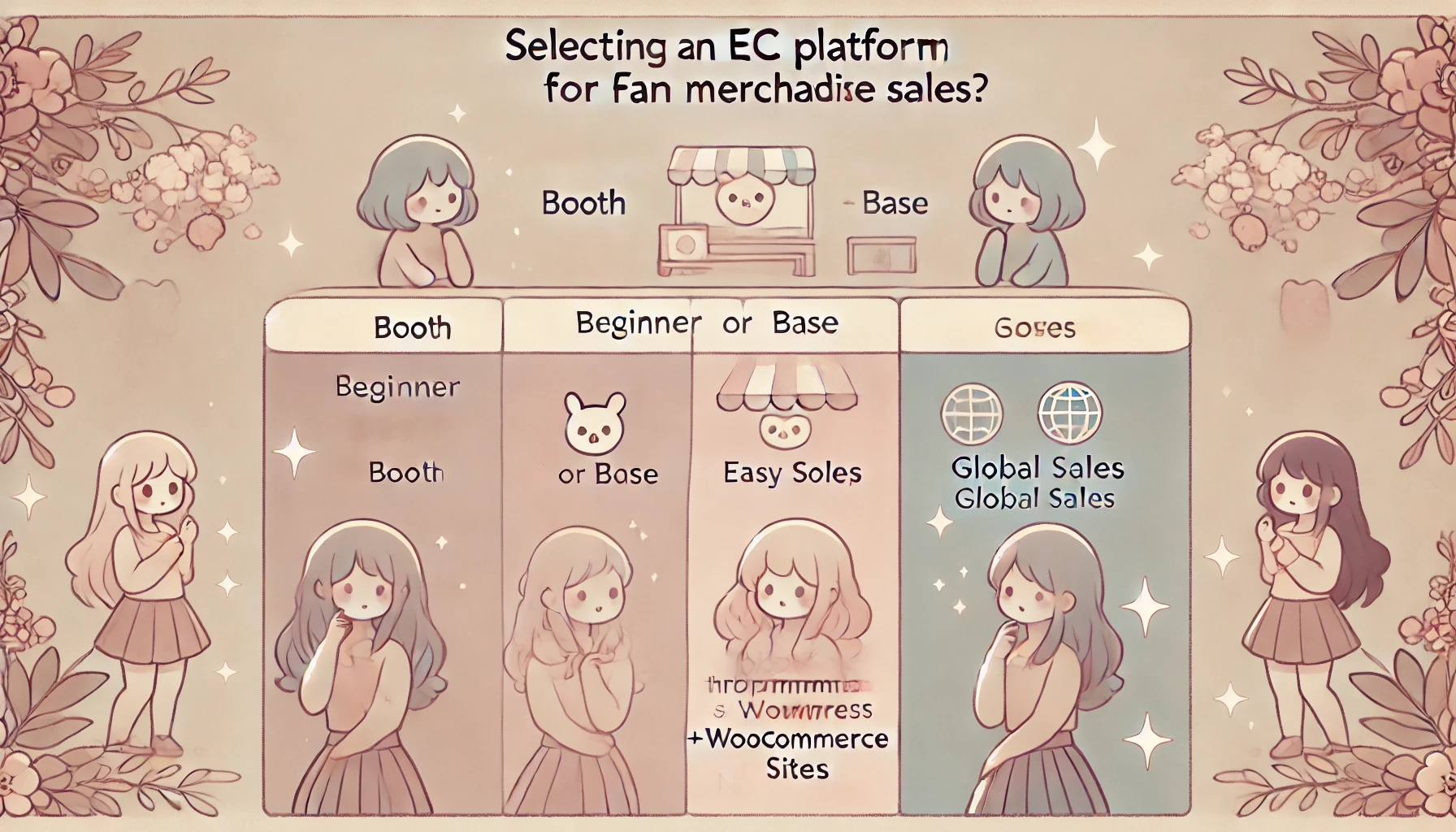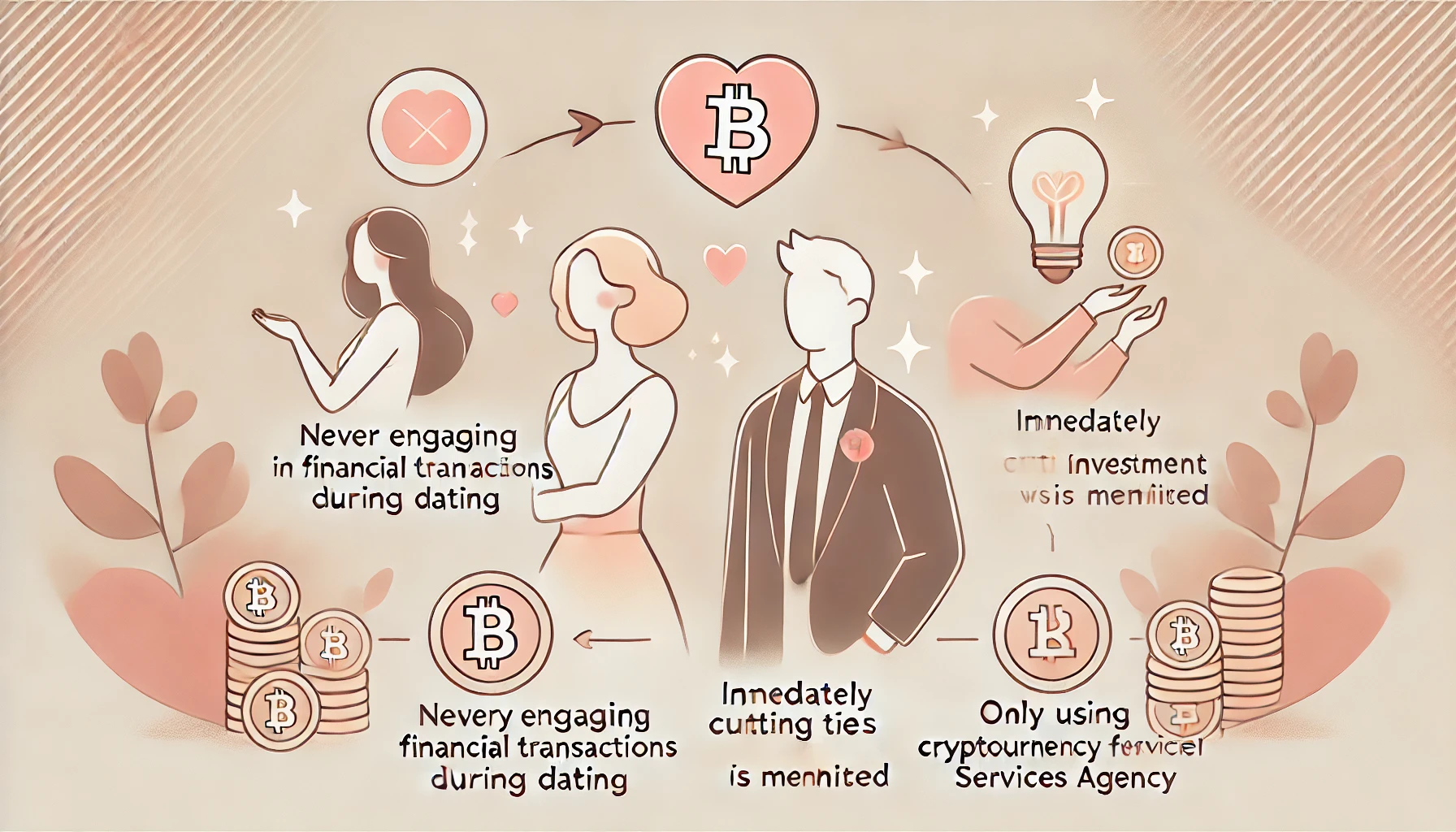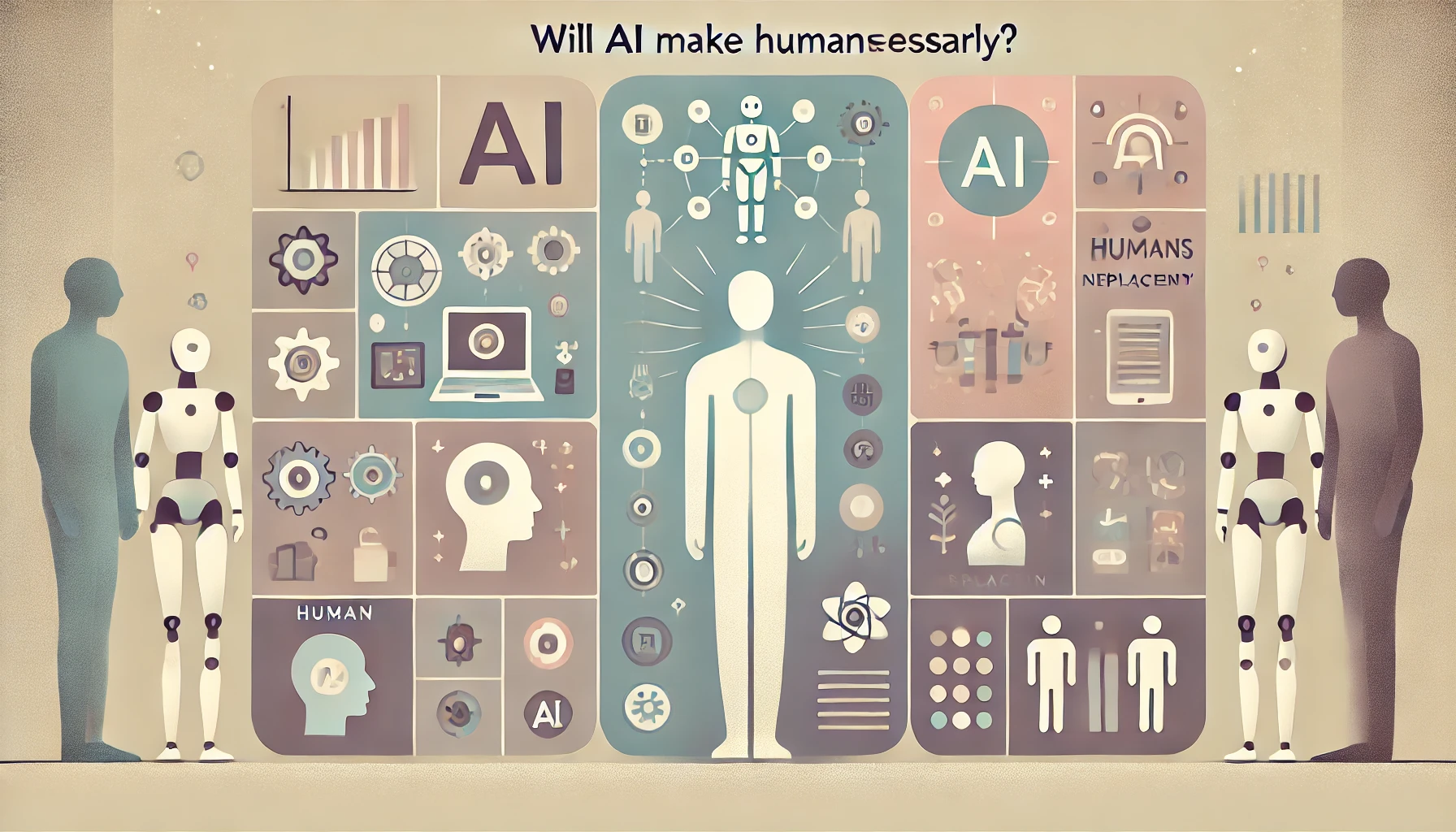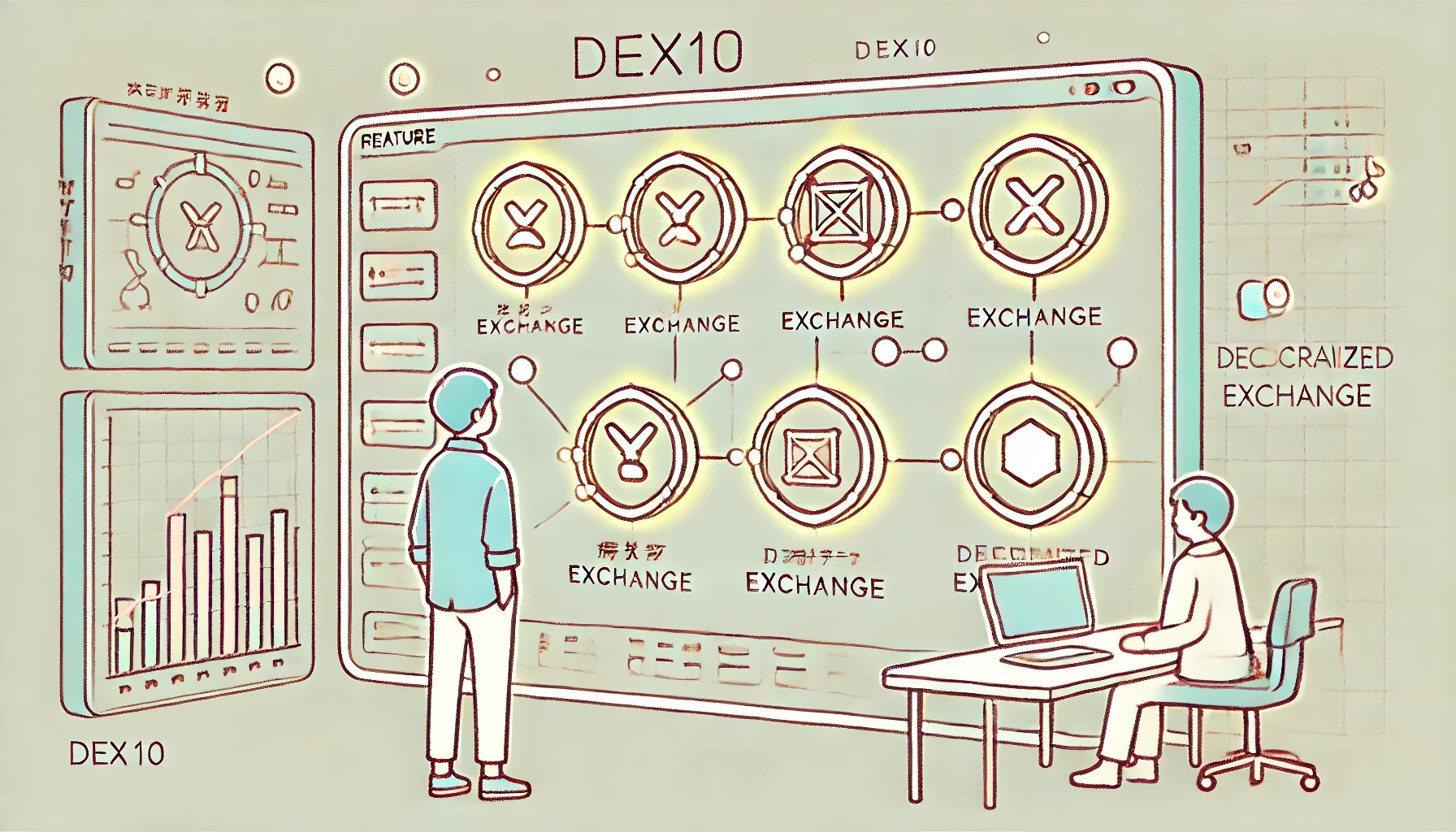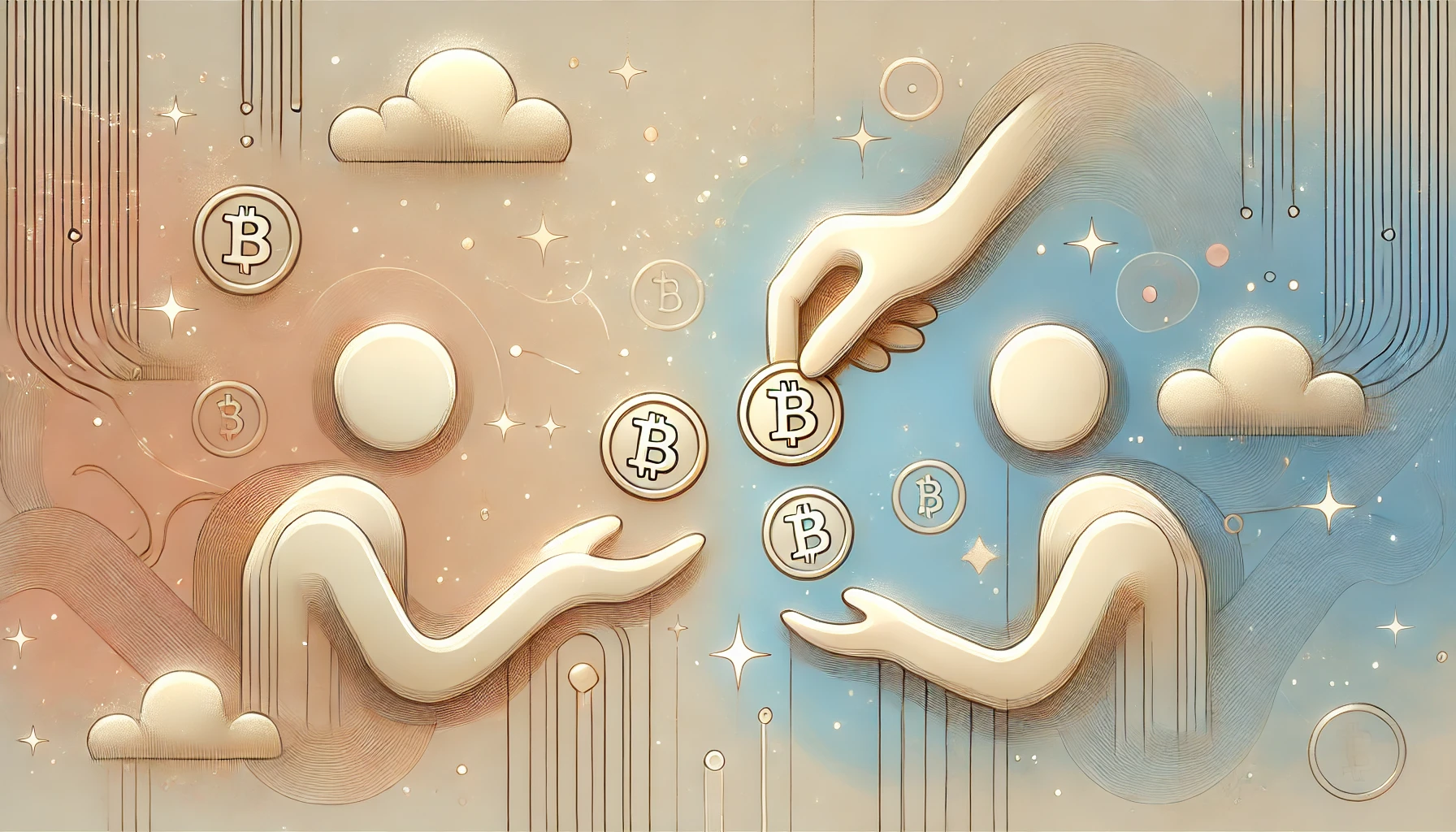
仮想通貨による「投げ銭」は、クリエイターや配信者、イベント参加者が新しいかたちで支援を受けられる手段として注目を集めています。本記事では、日本と海外の主要プラットフォームを比較し、選び方や法規制の注意点を解説します。
日本発の仮想通貨投げ銭プラットフォーム比較
まずは国内のサービスから見ていきましょう。日本では、MonaCoinや独自トークンを活用したプラットフォームが多く、クリエイター支援やコミュニティ形成に特化しています。
ALIS API:SNS連携を想定した新世代サービス
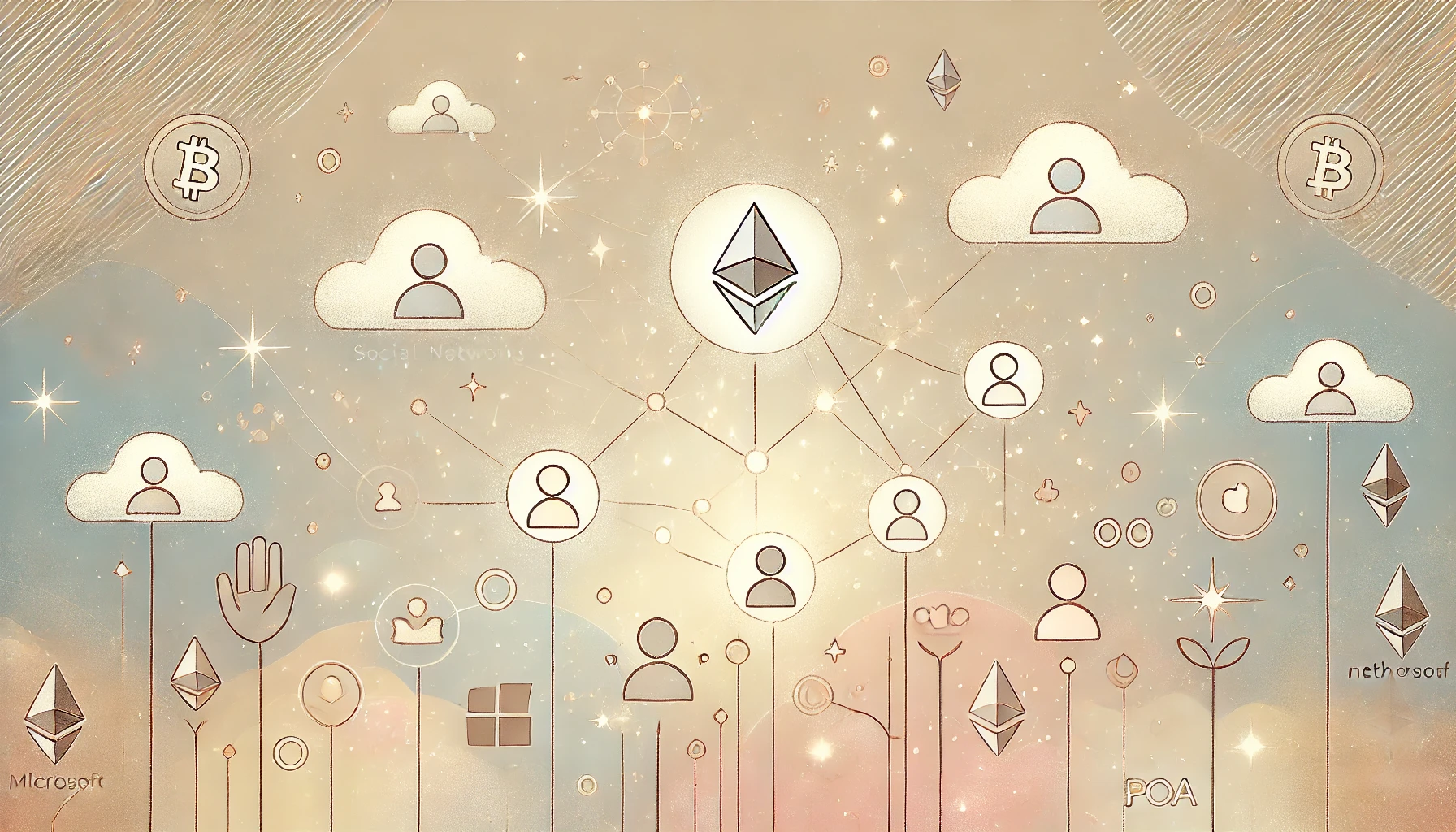
ALISが提供するAPIは、EthereumのPoAネットワーク上で動作し、SNSや企業サービスへのシームレスな投げ銭機能の組み込みを可能にします。Microsoftと共同で検証が進められ、将来的には企業や店舗連携が想定されています。
KanadeTip:誰でも使える簡易ウィジェット
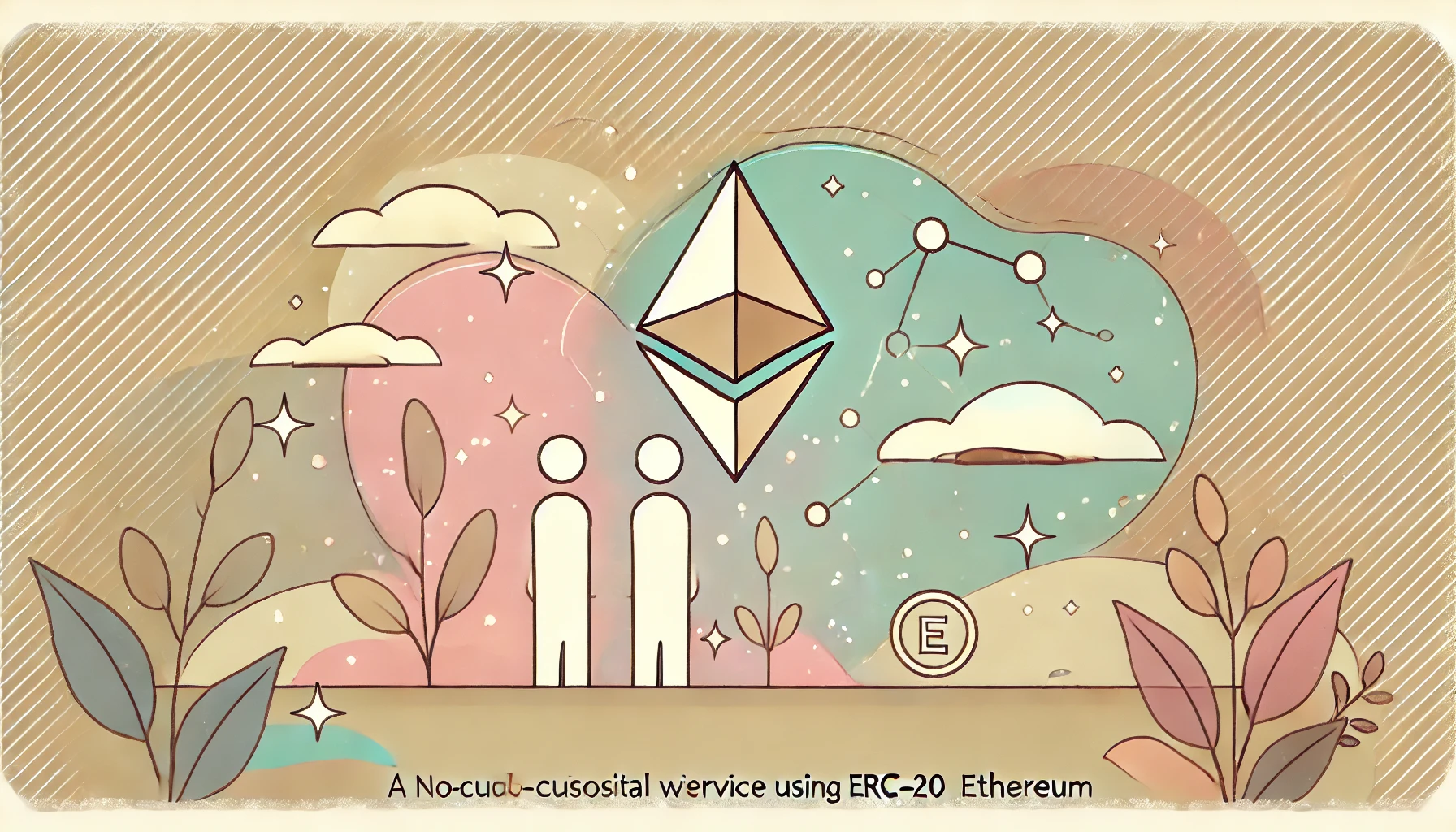
KanadeTipは、Ethereum上のERC-20トークンを利用する非カストディアル型のウィジェットサービスです。β版の提供段階で無料利用が可能で、HTMLに簡単なコードを貼り付けるだけで利用できるため、初心者にも扱いやすいのが特徴です。
MonappyとAskMona:MonaCoin文化を支える老舗

Monappy(サービス終了)やAskMonaは、日本初の暗号資産MonaCoinを利用した掲示板&ウォレット機能付きプラットフォームです。特にAskMona 3.0は掲示板文化と連動し、ユーザー間で自然なやり取りの中で投げ銭が行われています。
Fantasfic:クリエイター向けオールインワン支援
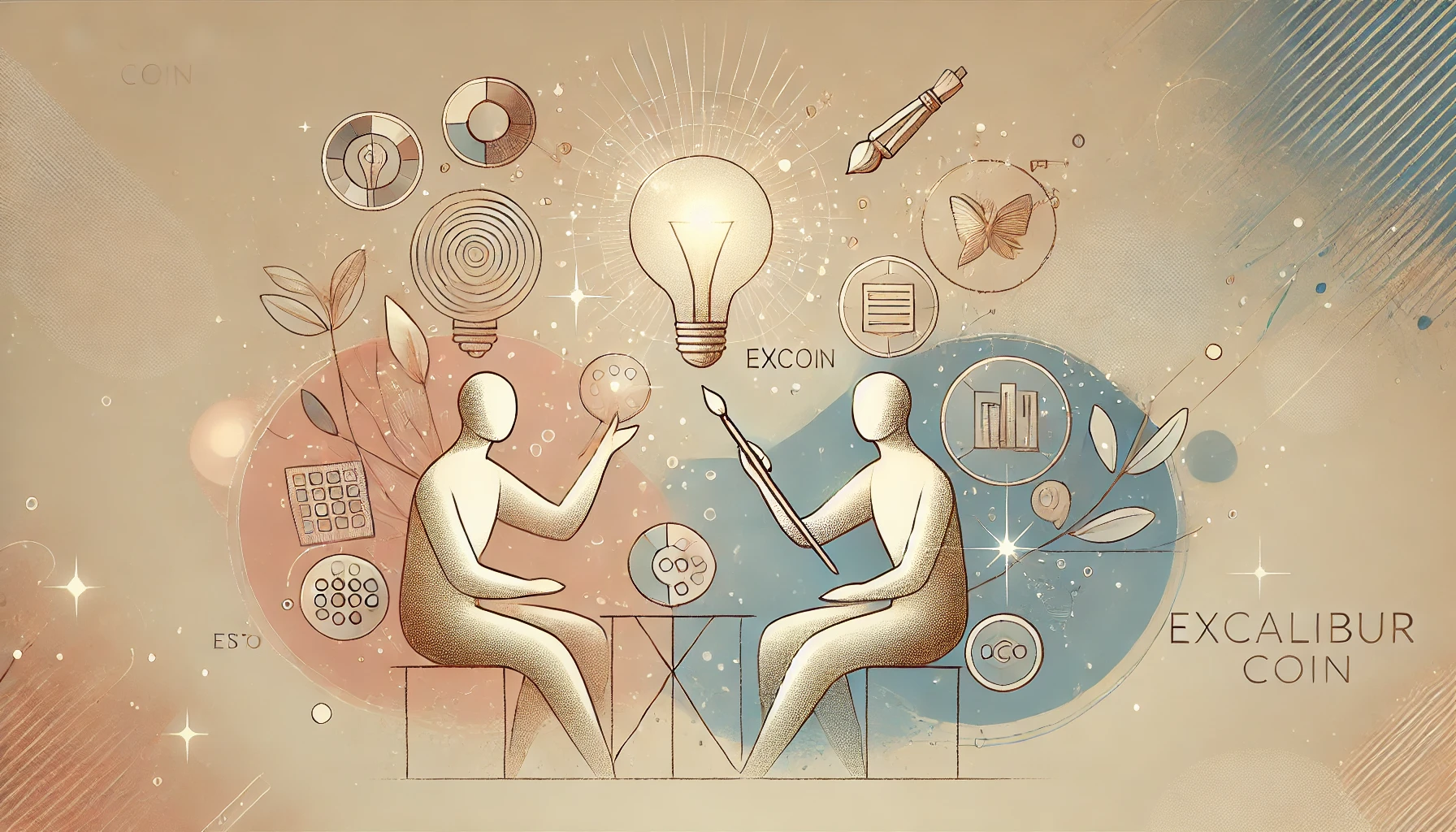
Fantasficは独自通貨ExcaliburCoin(EXCo)を使い、クリエイターが作品を公開しつつ収益を得られる場を提供します。二次創作の収益還元や自動翻訳機能が搭載され、多国籍なファン層を巻き込める点も魅力です。
海外発の仮想通貨投げ銭プラットフォーム比較
次に海外の事例です。グローバル展開を前提にしたサービスが多く、複数通貨やSNS連携、手数料設計の柔軟性が特徴です。
Twitter Tips:Strike経由でのBitcoin送金
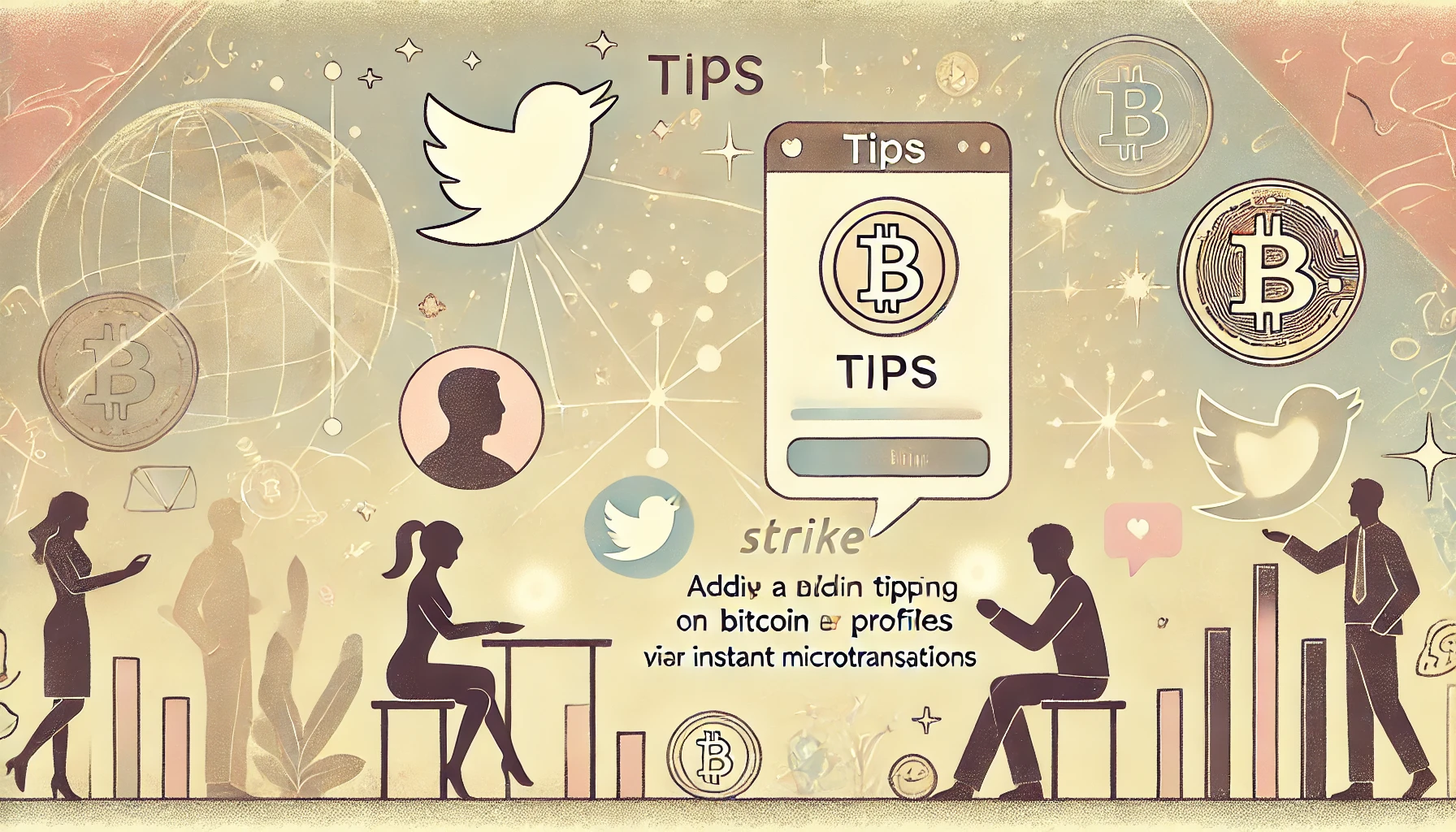
Twitterの「Tips」機能は、プロフィールにビットコイン送金ボタンを設置できる仕組みです。Strike経由で即時の少額送金が可能で、グローバルなクリエイター支援に活用されています。
CryptoTipX:マルチコイン&ウェアラブル連携

CryptoTipXは、複数の仮想通貨と法定通貨に対応し、スマートコントラクトによる即時決済が可能です。ウェアラブルデバイスとの連携機能もあり、実店舗やイベント現場での利用シーンが広がっています。
Shang:ガス代負担ゼロの完全オンチェーン型
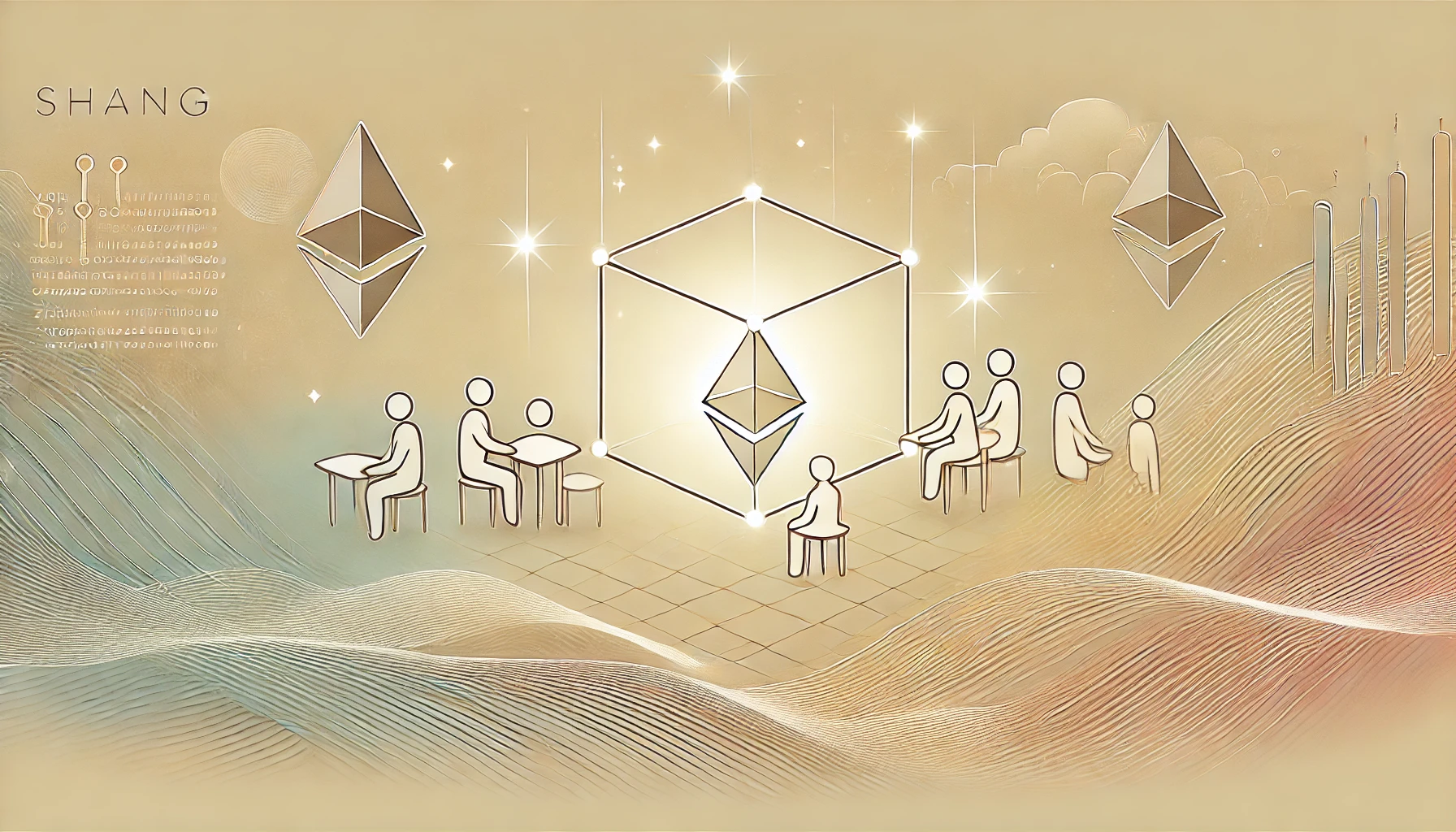
ShangはEthereumベースで構築された新興プラットフォームで、ガス代を運営が負担するという特徴があります。Testnetでの運用を経て、2025年5月にMainnetでの本格サービス提供が予定されており、全トランザクションがオンチェーンで記録される透明性の高さが強みです。
Cwallet Tip Box:800種類以上のトークンに対応

CwalletのTip Boxは、800種類以上の暗号資産に対応しており、QRコード・リンク・埋め込みボタンといった多様な形で投げ銭を受け取ることができます。オフライン決済にも対応しており、リアルイベントでの利用もしやすい設計です。
その他の海外投げ銭Bot・サービス
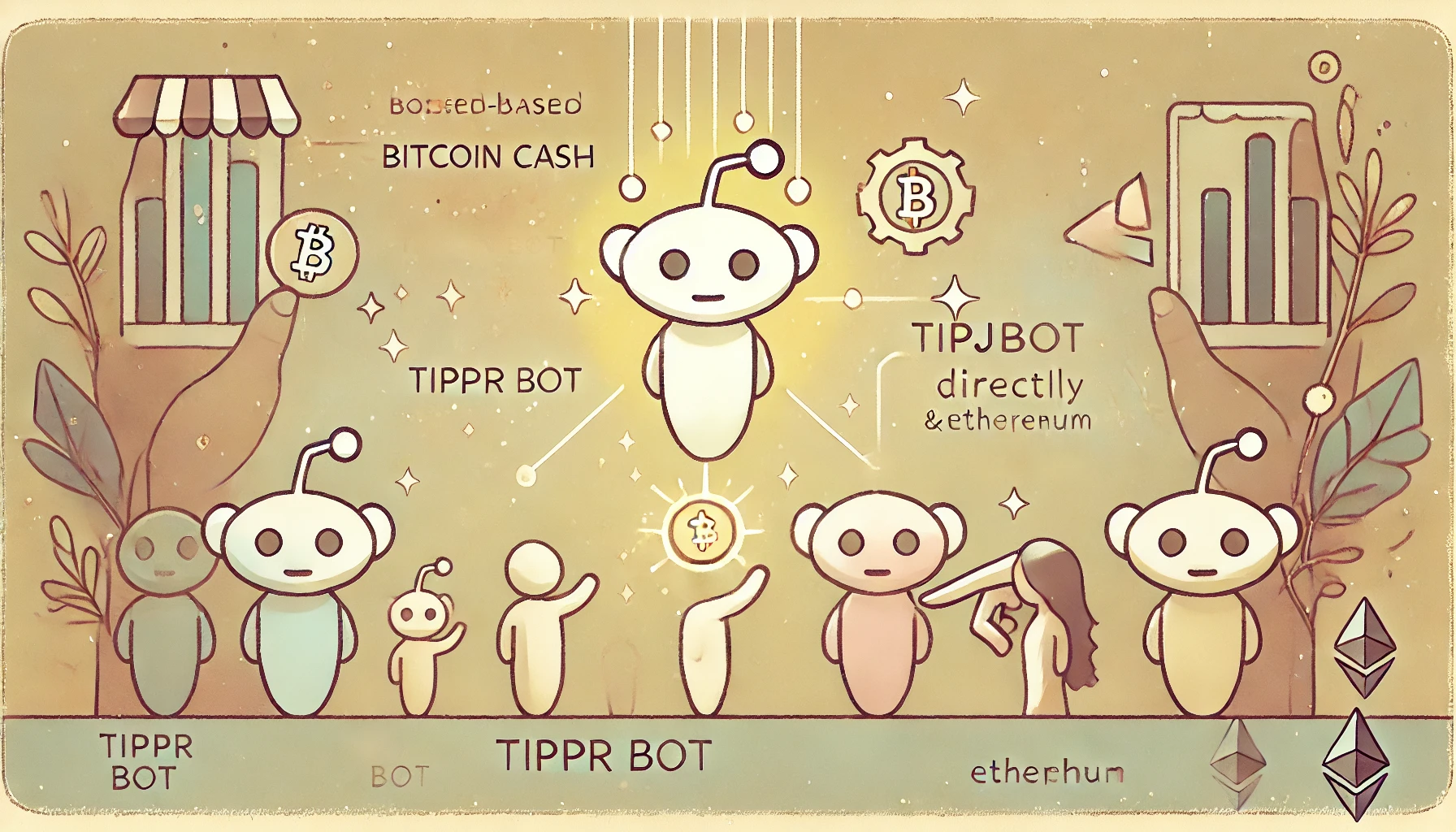
RedditやGitHubで利用できるTippr Bot(Bitcoin Cash)、TipJar Bot(Ethereum)などのBot型投げ銭も注目されています。SNSや開発者コミュニティと連携した少額送金が主な利用シーンであり、Gitcashのようにコメント欄で直接投げ銭できる仕組みも登場しています。
プラットフォーム選定の視点
数多くの投げ銭サービスが存在するなかで、どのような基準で選べばよいのでしょうか。ここでは主な比較軸を整理します。
非カストディアル型か、カストディアル型か
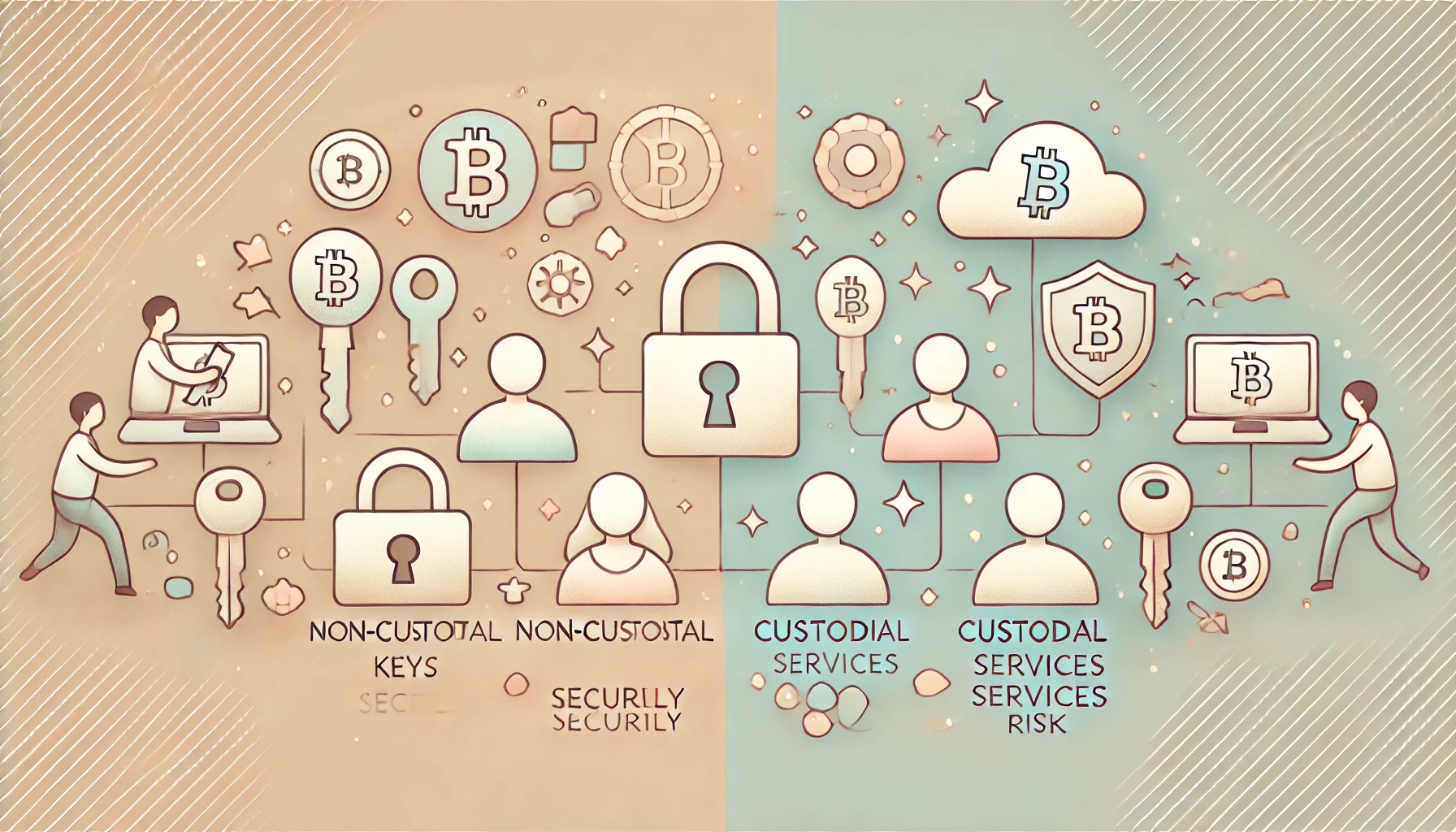
非カストディアル型はユーザー自身が秘密鍵を管理し、プラットフォームが資産に介入しません。これに対してカストディアル型は運営が資産を預かる形で、利便性は高いものの、ハッキングリスクや運営破綻時のリスクがあります。日本の改正資金決済法の観点では、非カストディアル型が有利とされるケースも多いです。
手数料とコスト構造
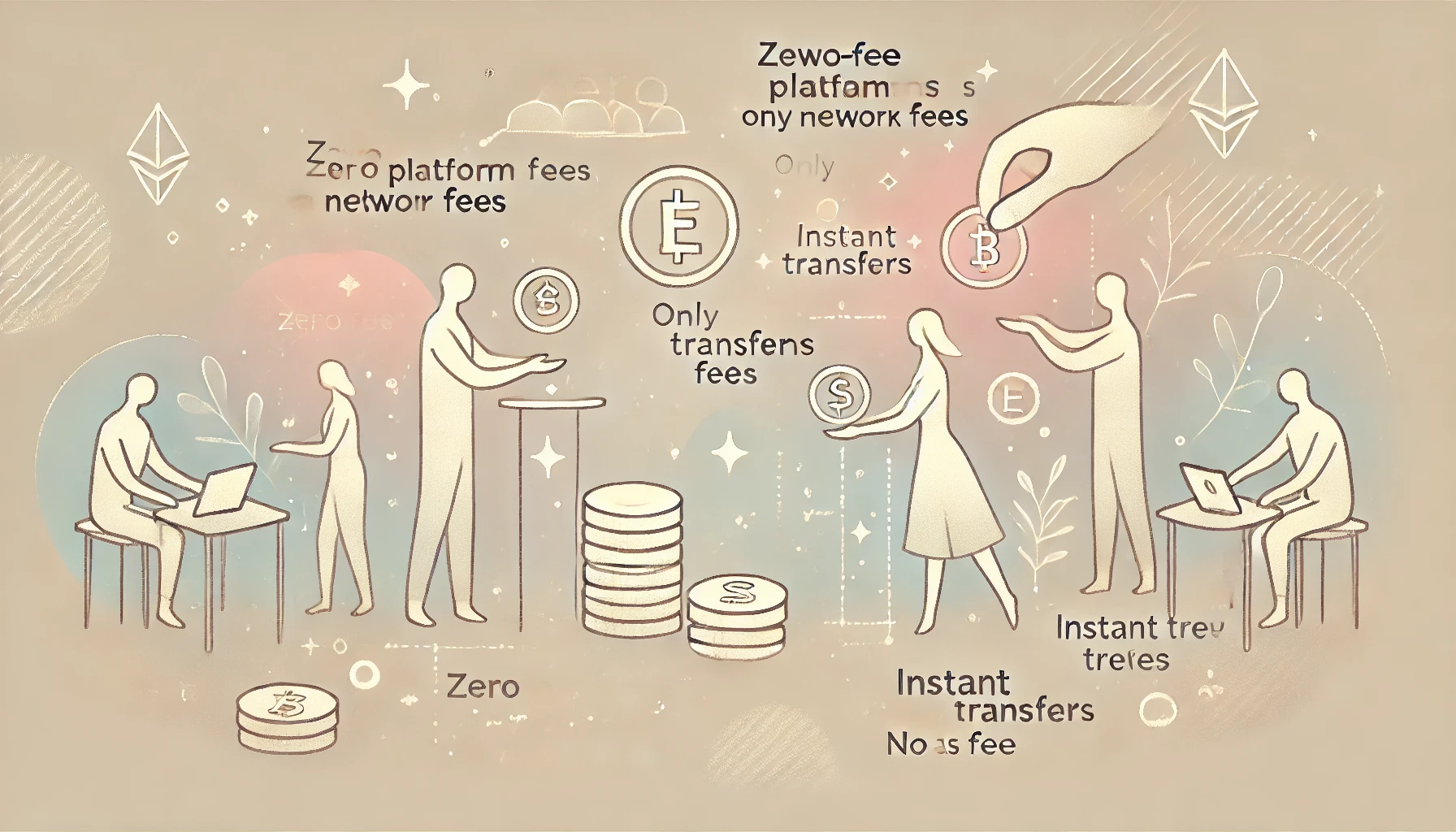
投げ銭額が小口になりやすいことから、プラットフォーム手数料ゼロか、ネットワーク手数料のみで済む設計が好まれます。即時送金やガス代負担の有無も重要なチェックポイントです。
対応通貨とユーザビリティ
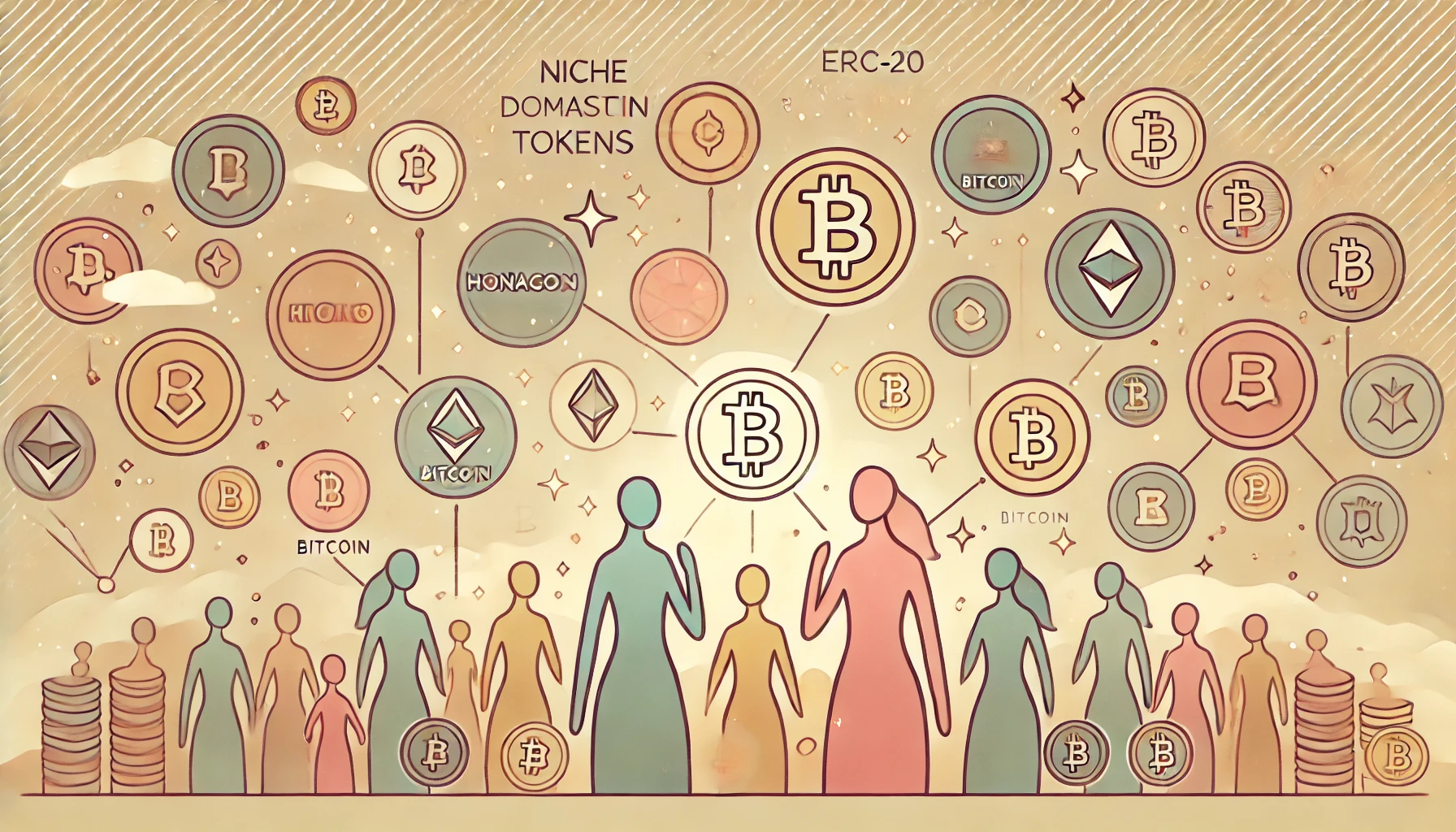
MonaCoinのようなニッチな国産通貨から、BitcoinやERC-20トークン、さらには数百種類以上のマルチコイン対応サービスまでさまざまです。推しとファン双方の利用環境に合わせて選ぶのが現実的でしょう。
SNS・Webサービスとの統合性
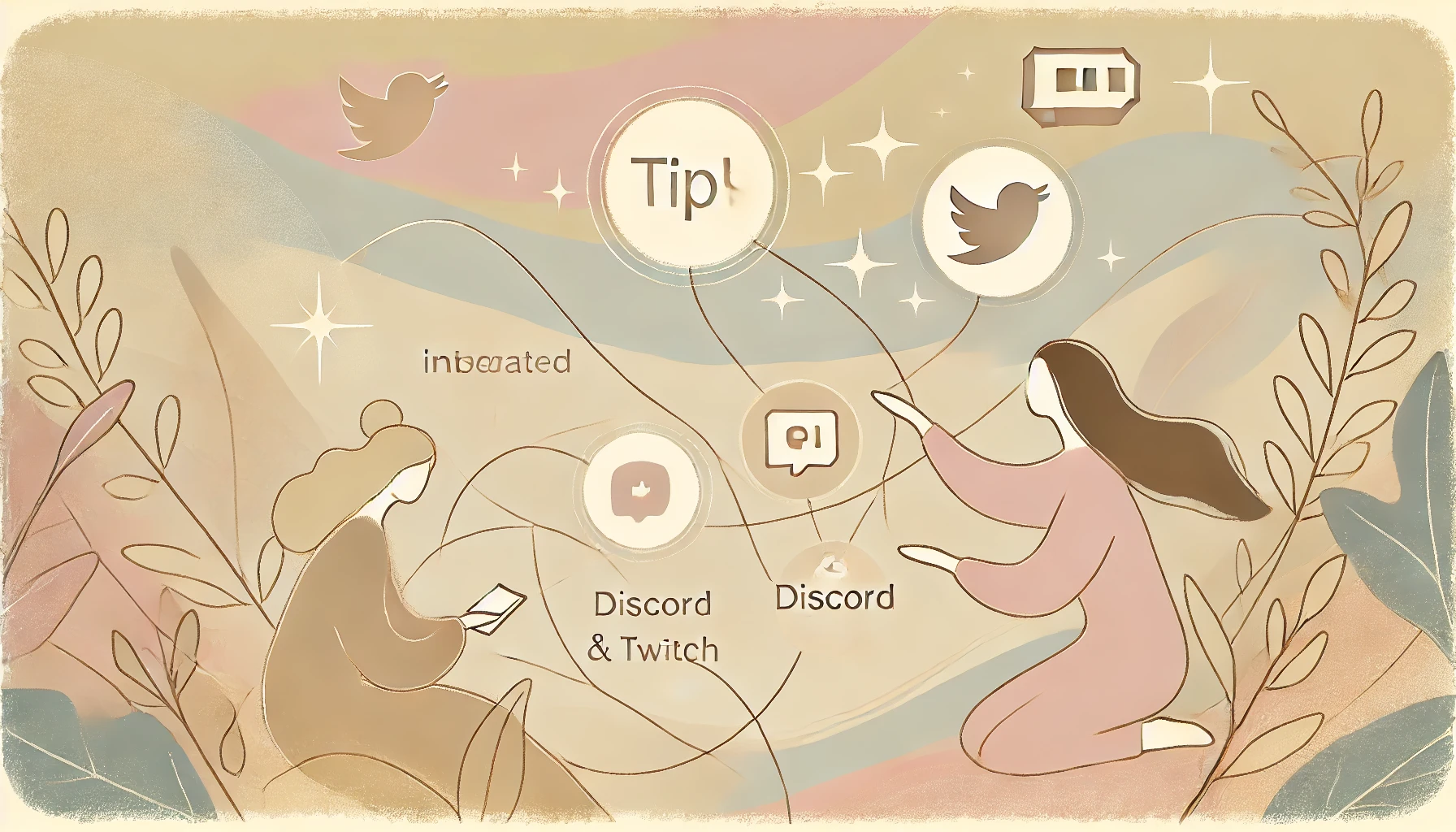
投げ銭は「使われて初めて意味がある」機能です。TwitterやDiscord、Twitchなどの既存SNSとの連携や、Webサイト・ブログへのウィジェット設置が容易かどうかは重要な選定基準になります。とくにクリエイターの場合、導線が複雑だとファンの利用が進まず、投げ銭が機能しなくなることも少なくありません。
コミュニティ文化との親和性

プラットフォームごとに形成されるコミュニティ文化も見逃せません。MonaCoinの掲示板文化のように、ファンとクリエイターの自然な交流を促進する環境があるかどうかは、長期的な支援の定着に大きく影響します。
法規制と税務の留意点
仮想通貨による投げ銭は、資金決済法や所得税法、消費税法といった複数の法規制が関わる領域です。サービスの運営形態によっては暗号資産交換業者としての登録が必要になるケースもあります。
資金決済法上の取り扱い
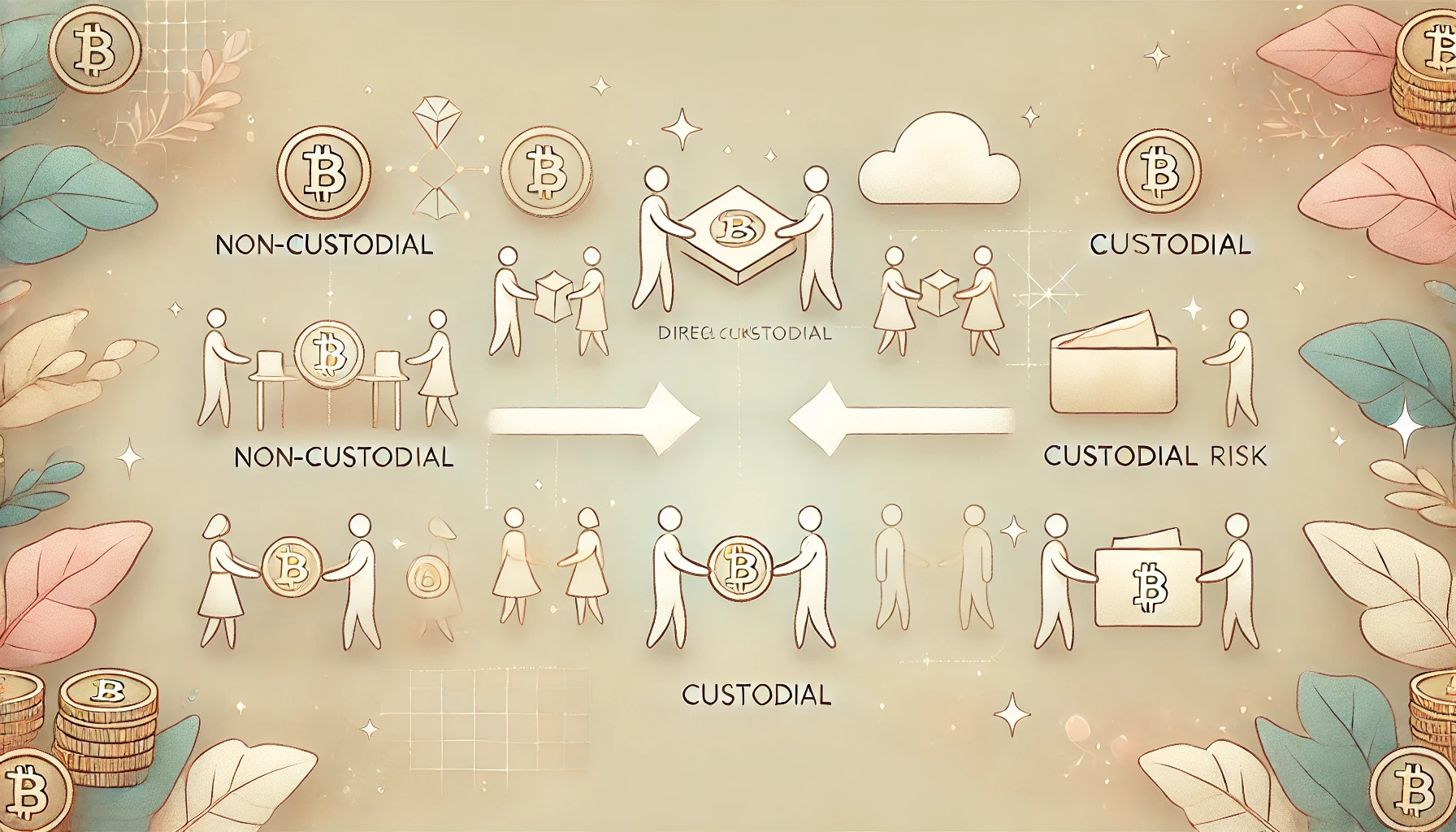
非カストディアル型はユーザー同士の直接送金に近く、比較的規制リスクが低いとされます。一方でカストディアル型は、運営が顧客資産を預かるため、交換業登録の対象になる可能性があります。利用前にプラットフォームの運営形態を確認することが大切です。
税務上の課題
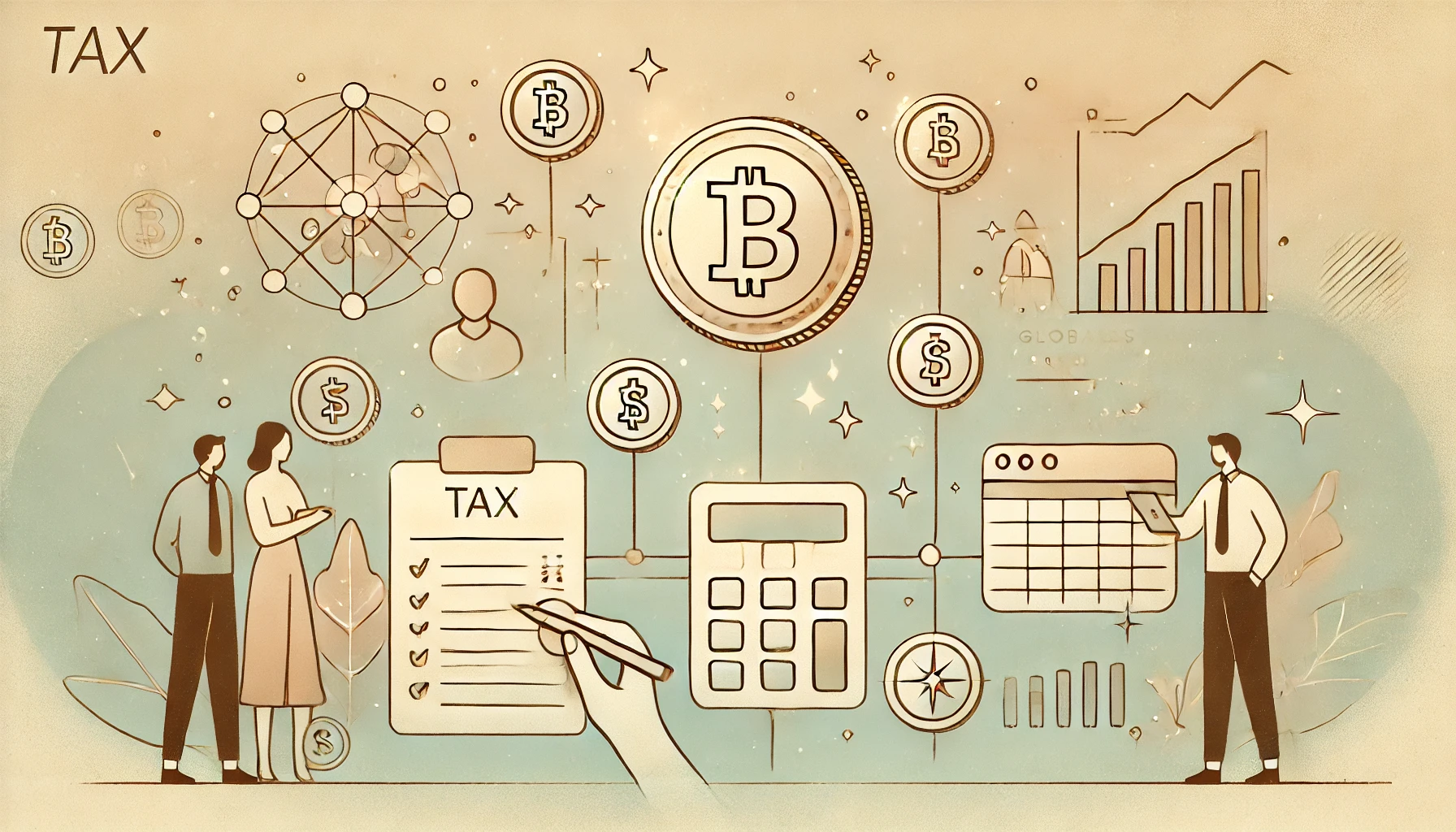
仮想通貨による投げ銭は、受け取った側に所得税が発生する場合があります。クリエイターの場合、雑所得や事業所得として申告が必要になり、海外からの送金であっても課税対象になることがあります。さらに、換金タイミングによって評価額が変わるため、受領日ベースでの記録管理も欠かせません。
消費税や源泉徴収の可能性
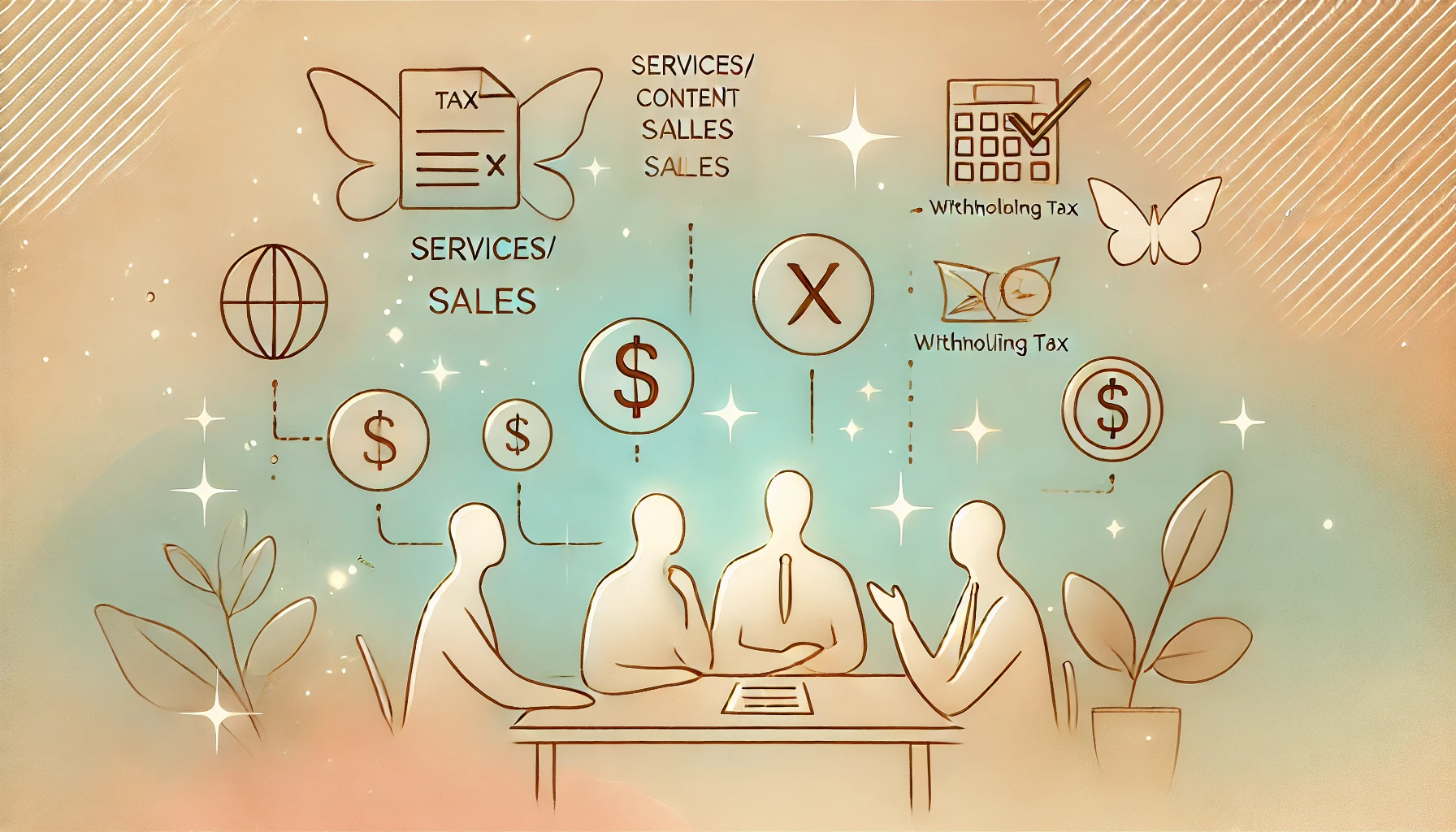
サービス提供やコンテンツ販売と投げ銭の境界が曖昧なケースでは、消費税や源泉徴収の対象になる場合もあります。事前に税理士や専門家への相談を行い、適切な処理をすることがリスク回避につながります。
導入・活用事例
ここからは、実際に仮想通貨投げ銭がどのように活用されているかを見ていきましょう。国内外の事例から、現場での使われ方や成果が見えてきます。
日本コミックマーケットでのMonaCoin投げ銭
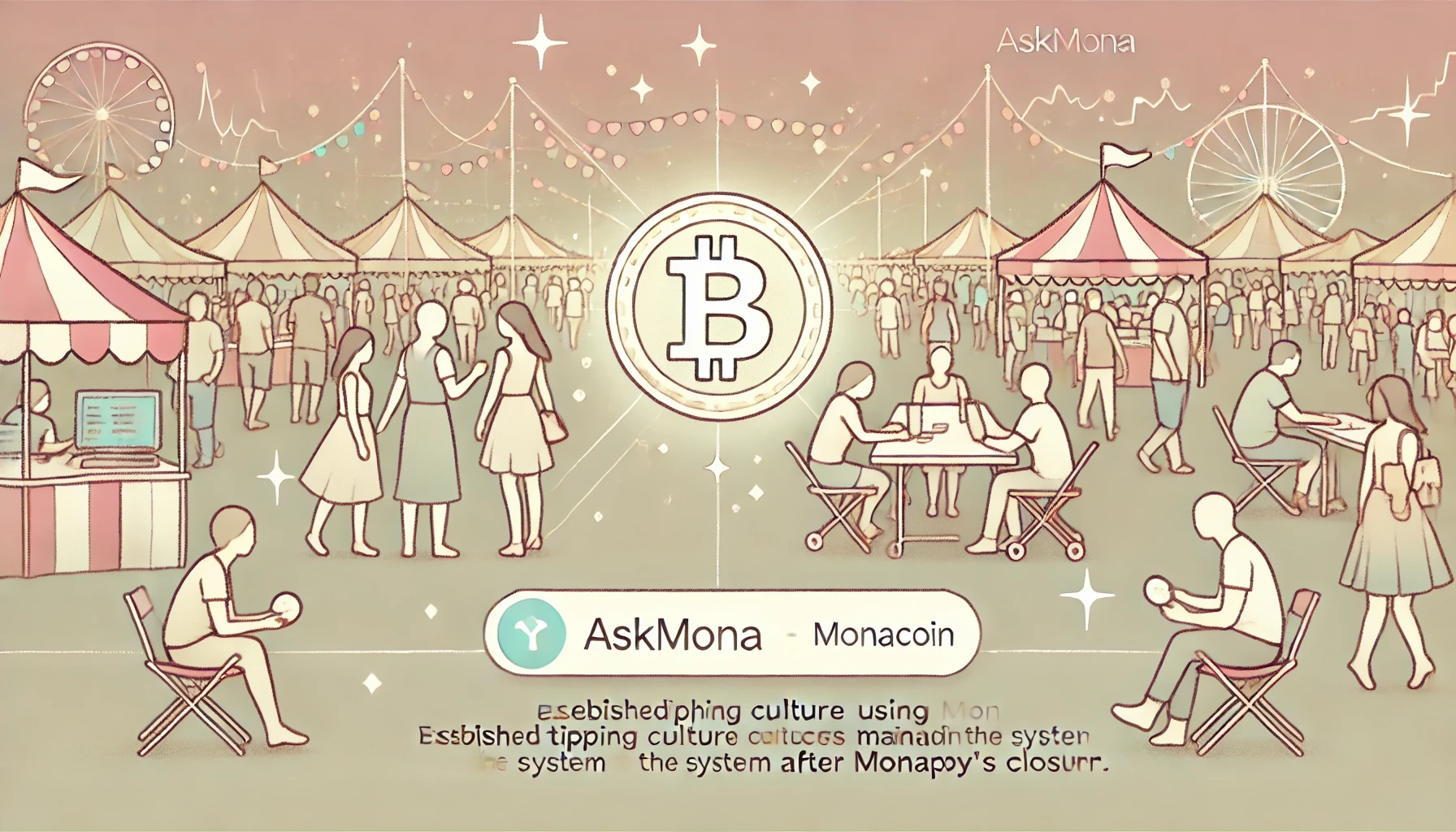
日本では、コミックマーケットでMonaCoinを使った投げ銭文化が定着しています。AskMona掲示板を中心に、クリエイター同士やファンとのやりとりが生まれ、即座に応援の気持ちを形にできる仕組みとして活用されてきました。Monappy撤退後も有志がシステムを維持し、文化として残し続けています。
海外ライブ配信でのCryptoTipX活用
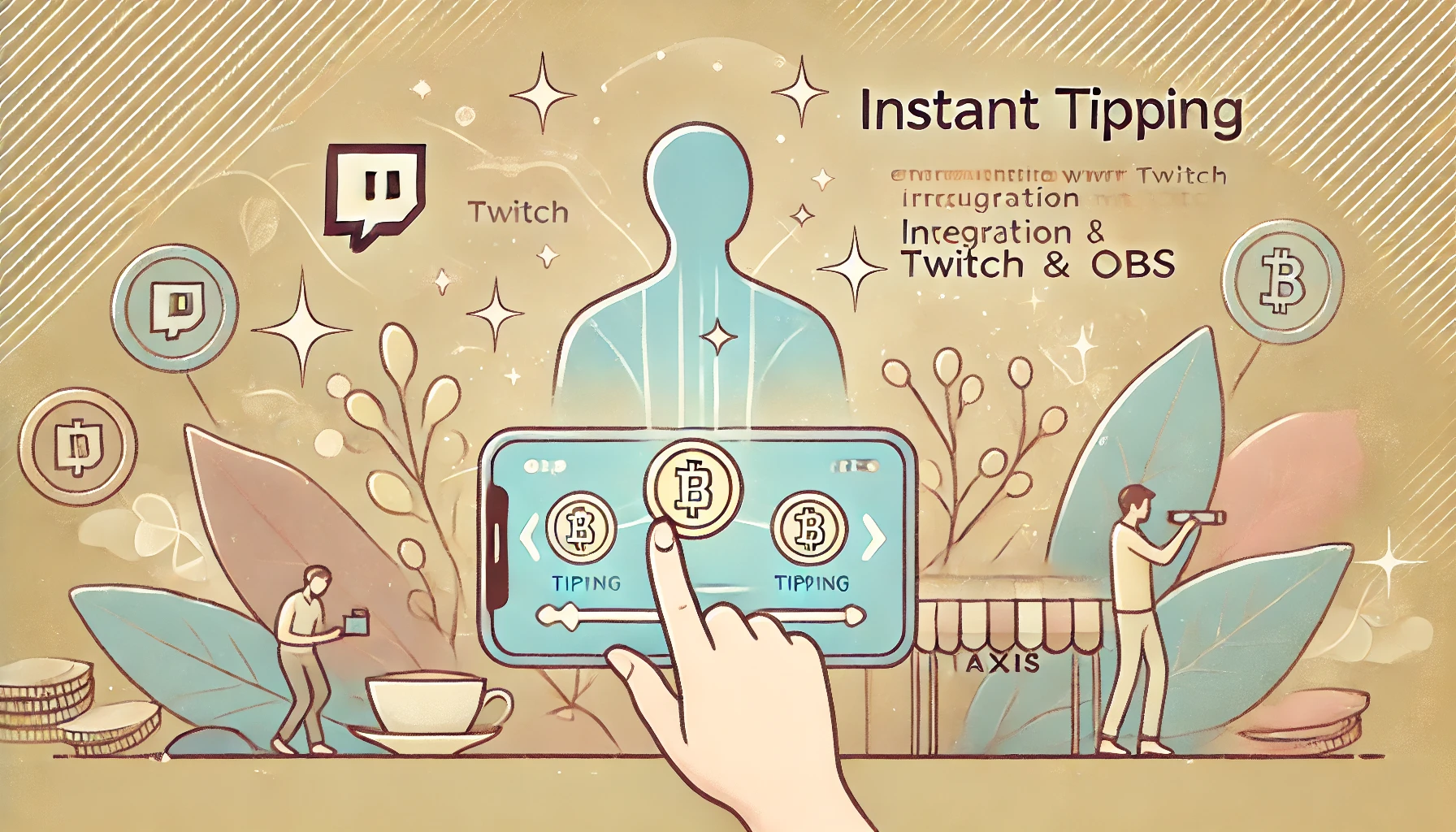
海外では、CryptoTipXがTwitchやOBSと連携し、配信者への即時投げ銭を可能にしています。ウェアラブルデバイスを通じてリアルイベントでも投げ銭が受け取れるため、カフェやタクシーなど多様な現場での支援にも広がっています。
Twitter Tipsによるグローバルクリエイター支援
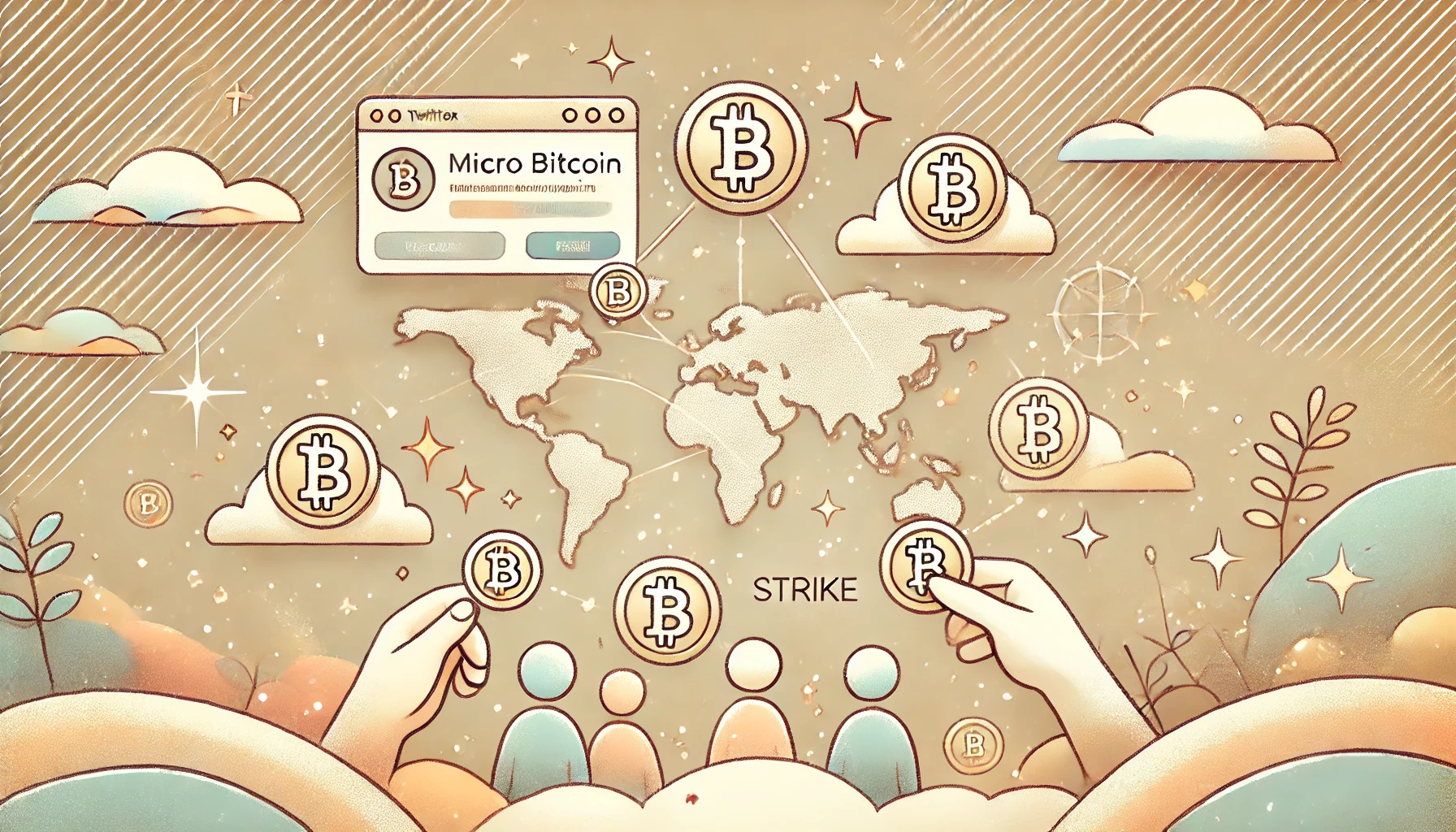
Twitter(現X)の「Tips」機能は、世界中のクリエイターが手軽にBitcoinを受け取れる仕組みとして注目されています。Strike経由での少額送金は手数料が低く、寄付文化のハードルを下げる結果につながっています。
GitHubでの投げ銭:Gitcash

開発者コミュニティでは、GitHub上でコメント内に投げ銭を埋め込める「Gitcash」が利用されています。オープンソース開発者への直接支援が可能になり、金銭的なモチベーションを高めるツールとして評価されています。
仮想通貨投げ銭を成功させるための工夫
投げ銭プラットフォームを導入しても、使われなければ意味がありません。ここでは、より効果的に運用するための工夫をまとめます。
ファンにとってのわかりやすさを優先する
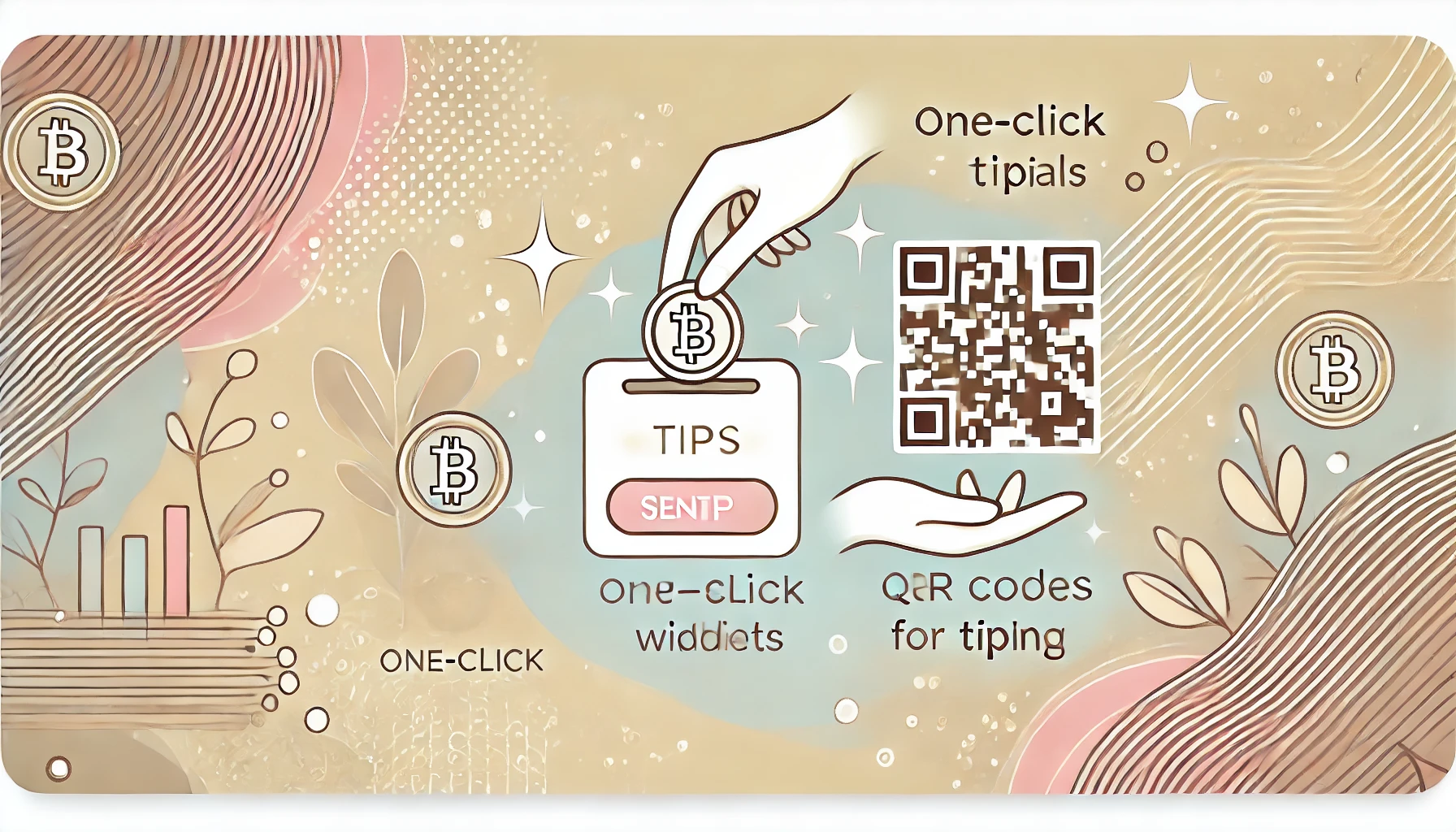
仮想通貨に詳しくないファン層も多いため、送金方法やウォレットの使い方を簡単に説明したガイドやチュートリアルを用意するとよいでしょう。ワンクリックで送金できるウィジェットやQRコードの活用も効果的です。
特典や感謝のフィードバックを用意する
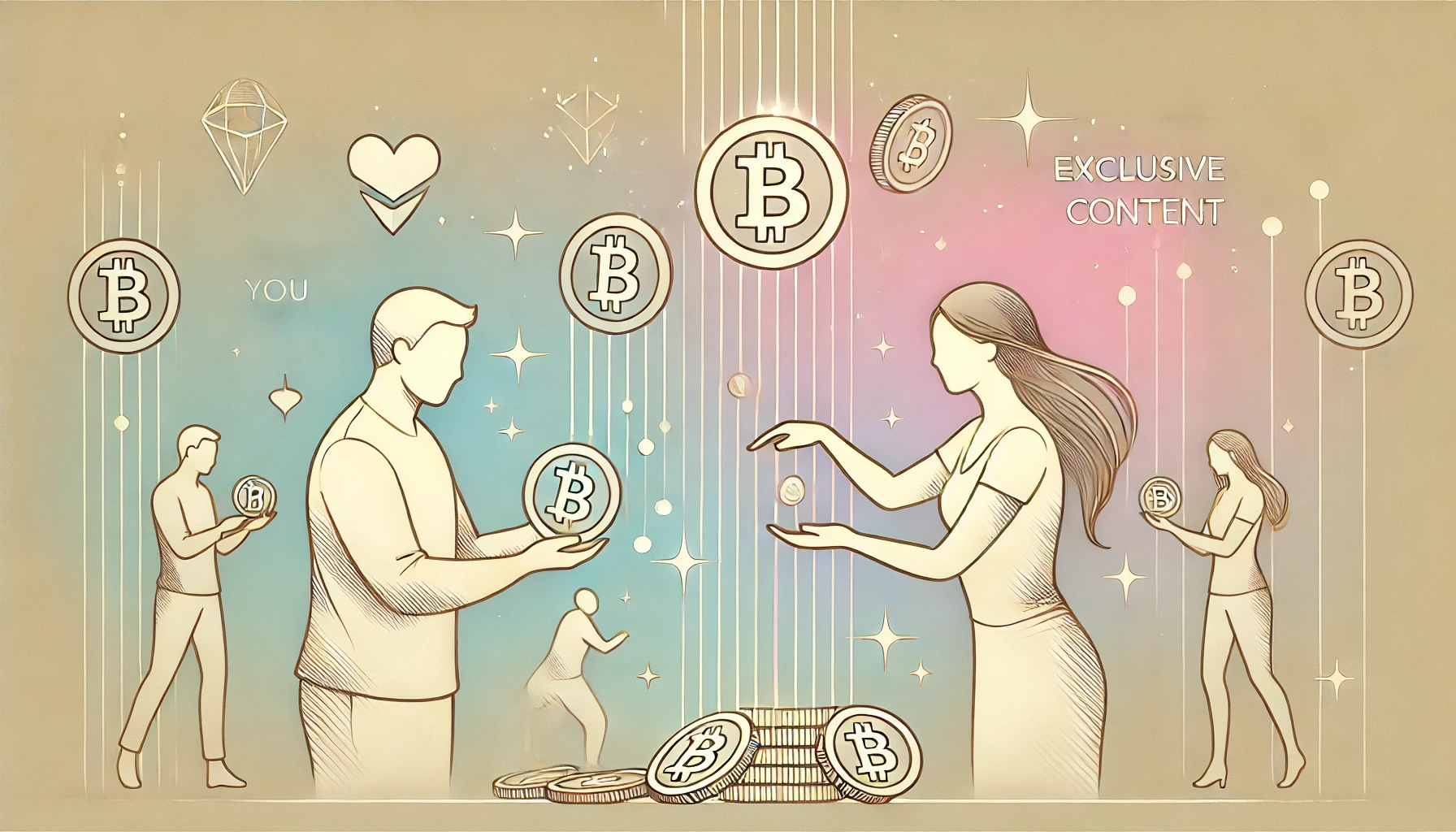
投げ銭は「応援したい」という気持ちの可視化です。お礼のメッセージや限定コンテンツなど、投げ銭に対するフィードバックを用意することでリピート率が高まります。
コミュニティとの関係構築
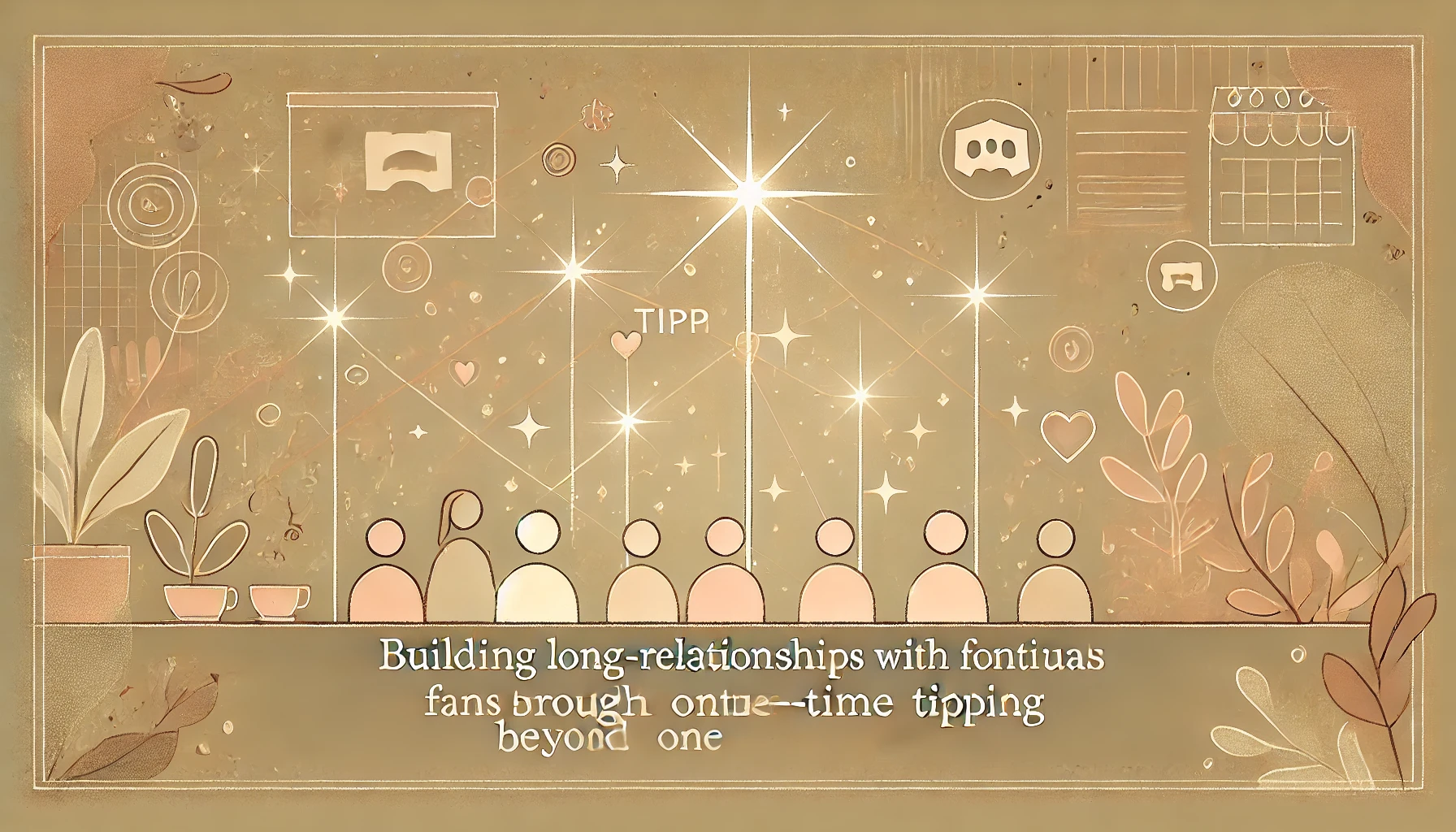
単発の投げ銭ではなく、ファンとの継続的な関係構築を意識しましょう。Discordや掲示板などで交流の場を持つことで、投げ銭が文化として定着しやすくなります。
まとめ:投げ銭文化を自分のコミュニティに取り入れる

仮想通貨による投げ銭は、匿名性・少額送金・低手数料といった利点を持ち、クリエイターや配信者の新しい収益手段として広がりを見せています。
非カストディアル型の安全性や手数料の低さを意識して選び、推しやコミュニティの文化に合ったプラットフォームを導入することが成功の鍵です。
あなたの活動に最適な投げ銭サービスを取り入れ、ファンとともに新しい応援の形を作っていきましょう。