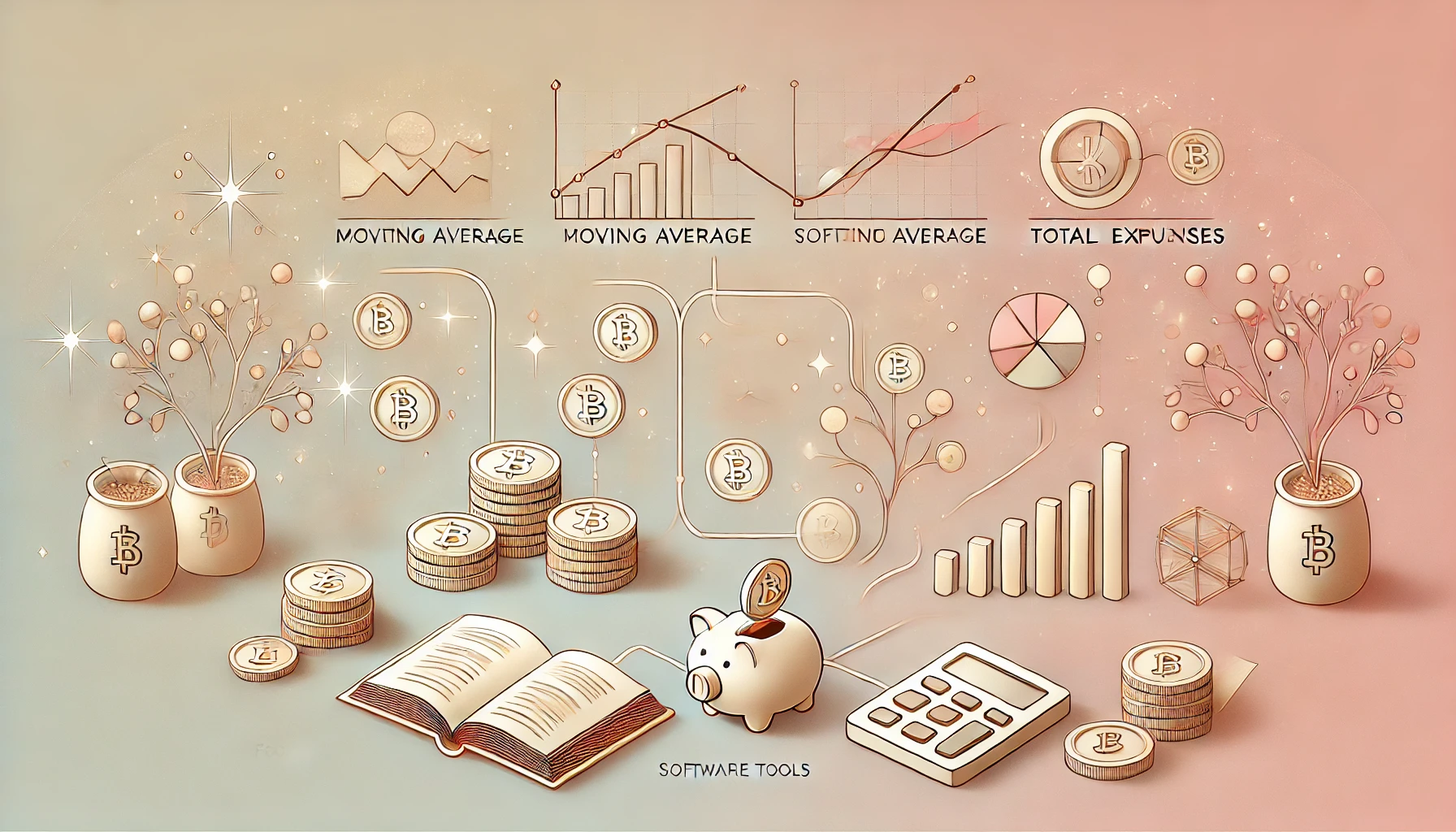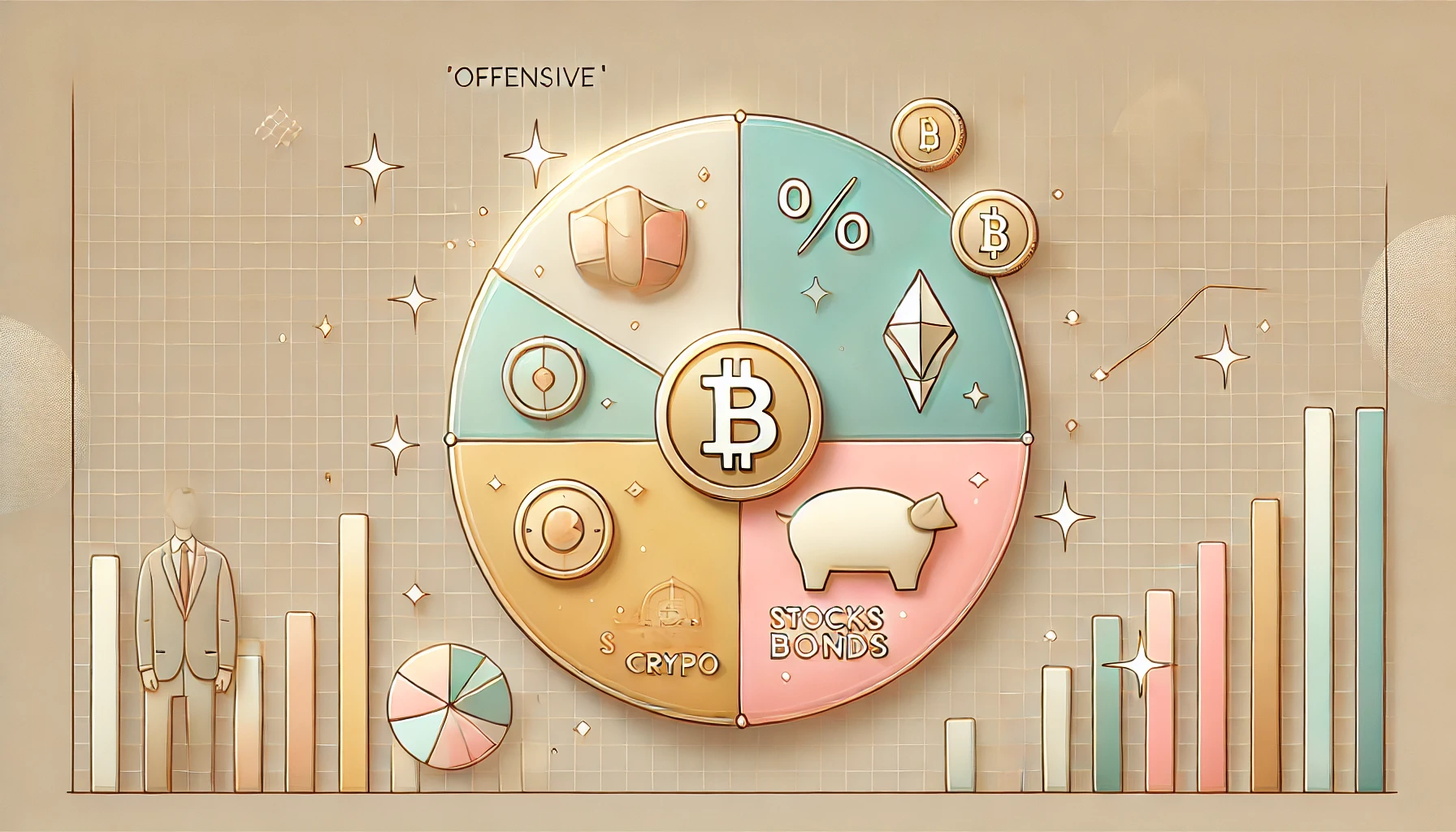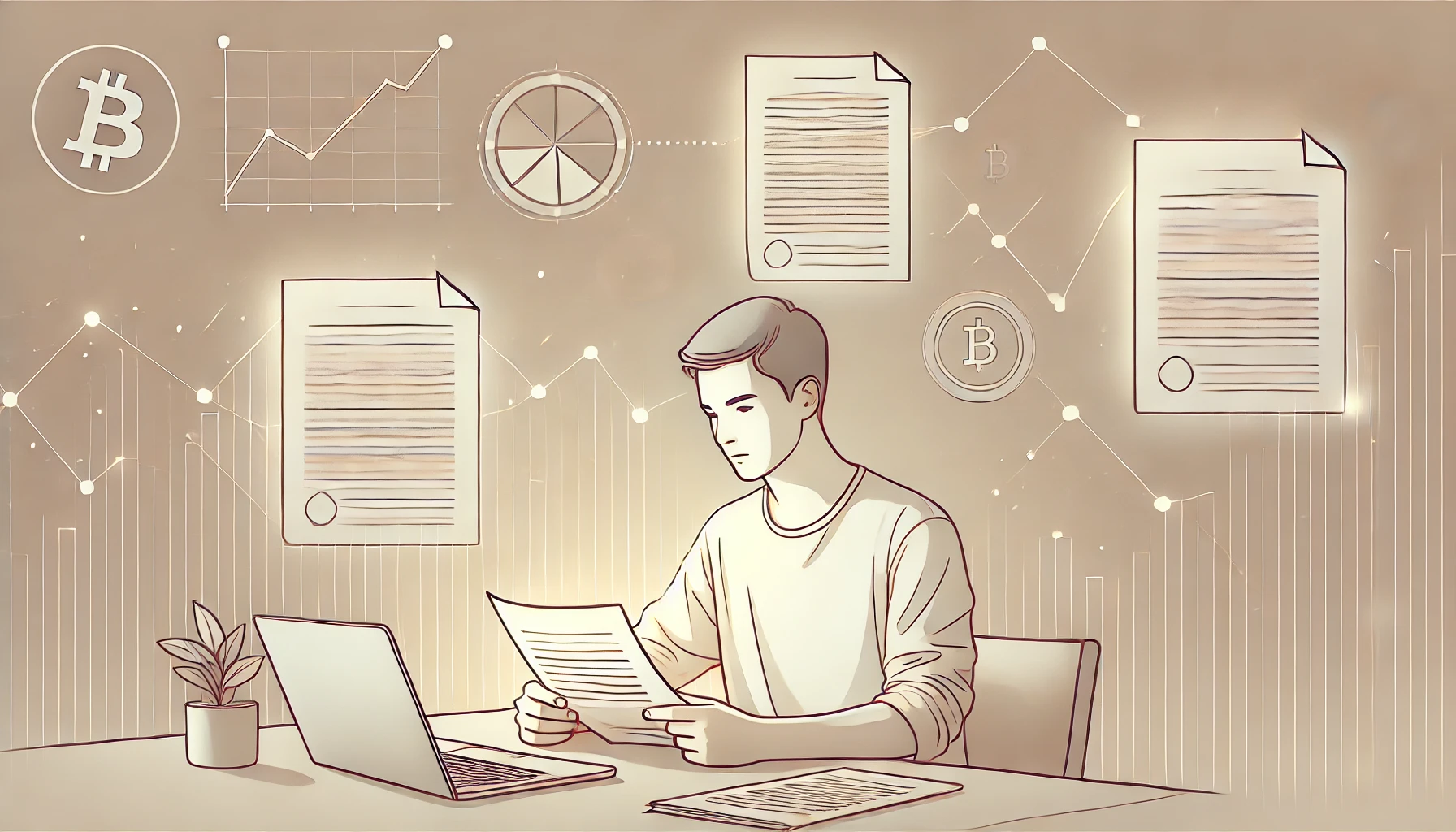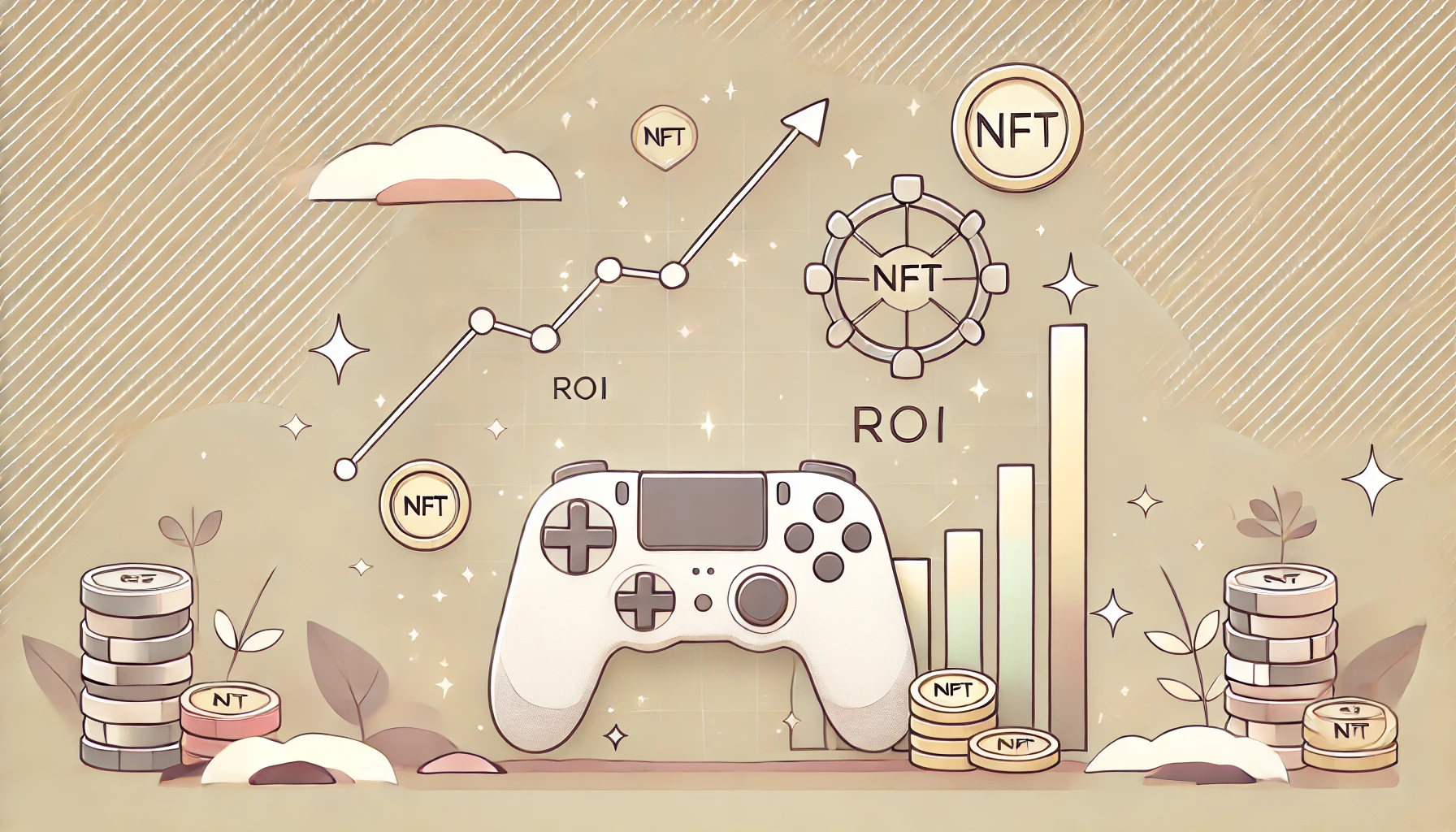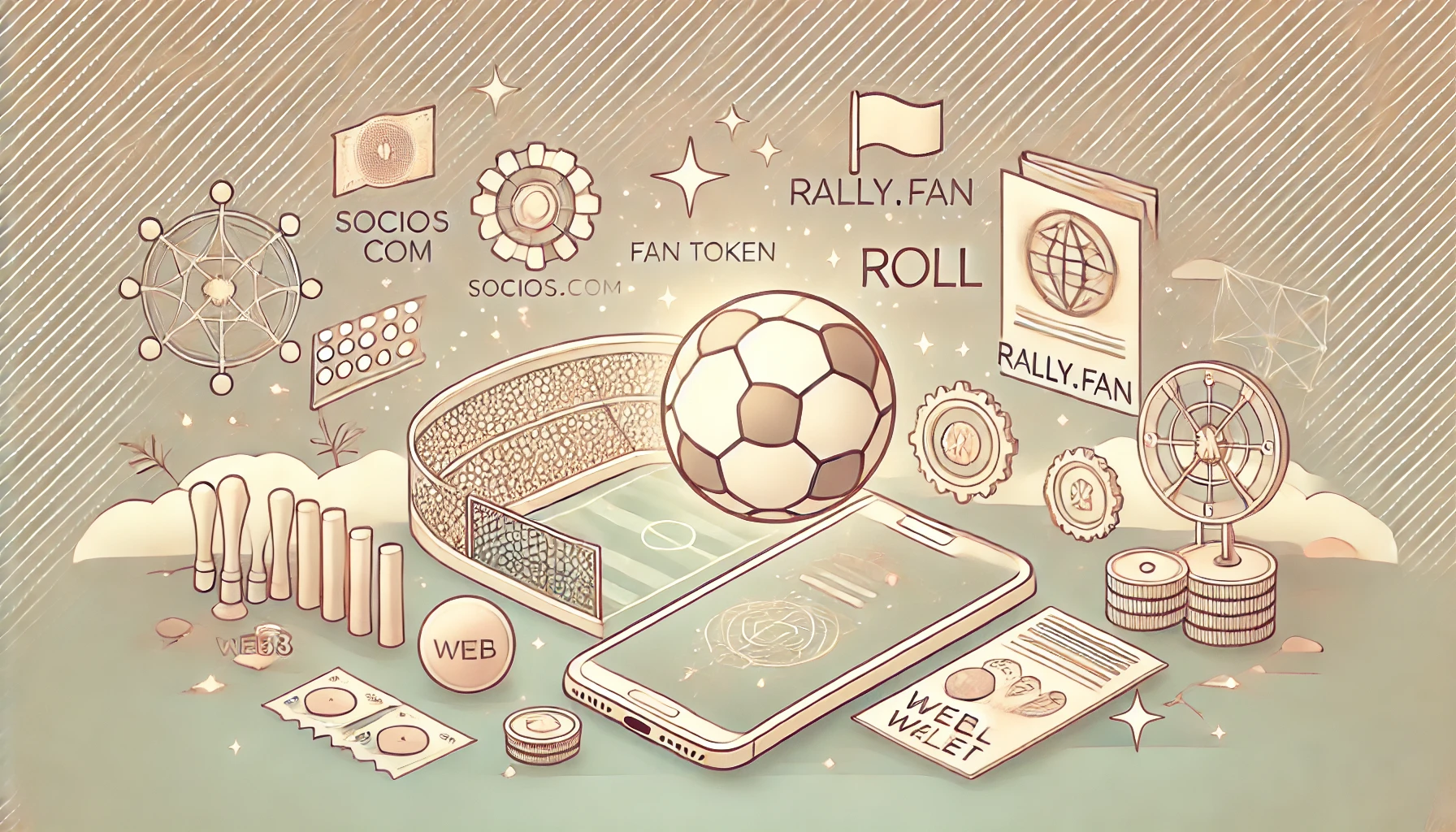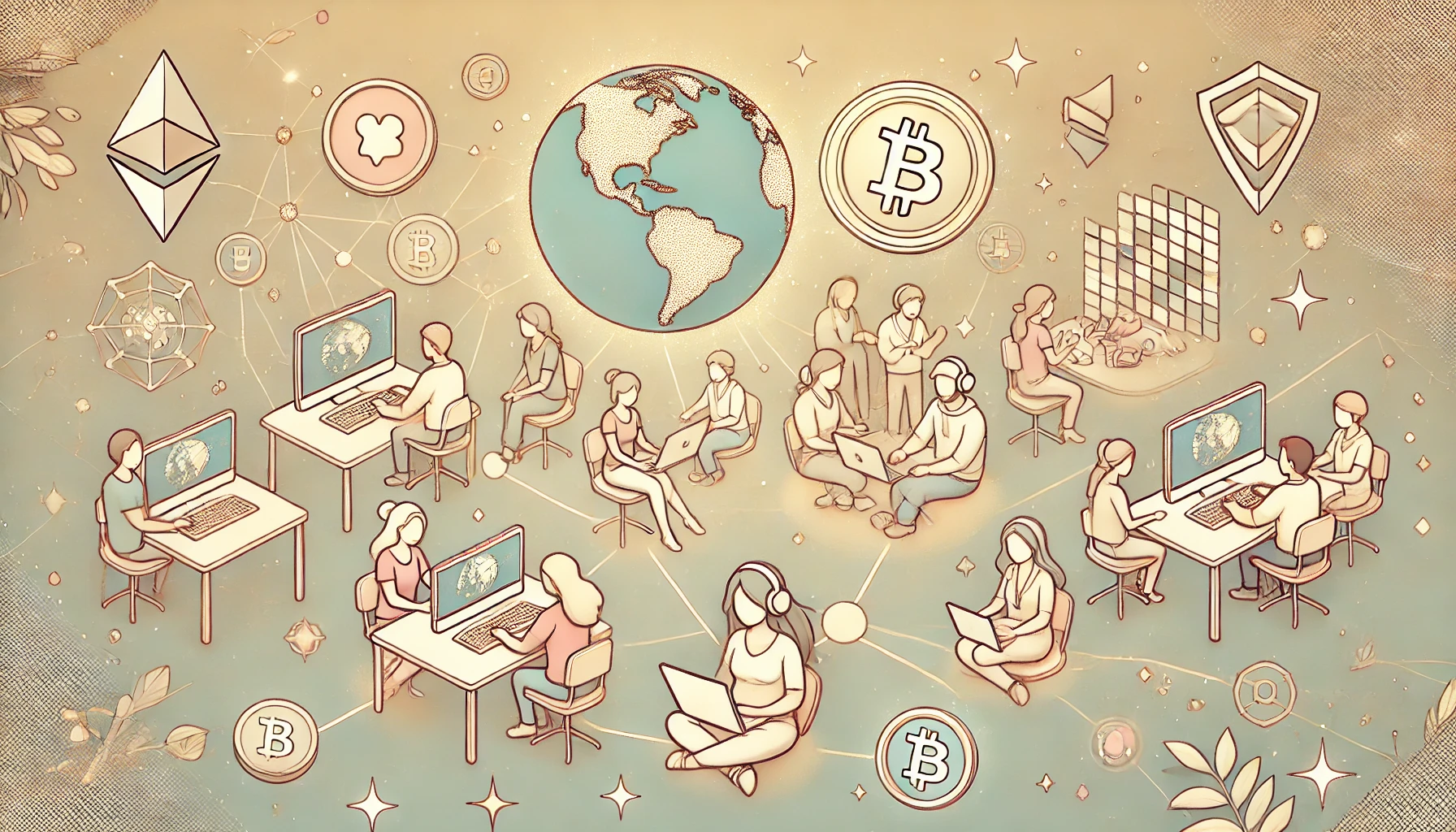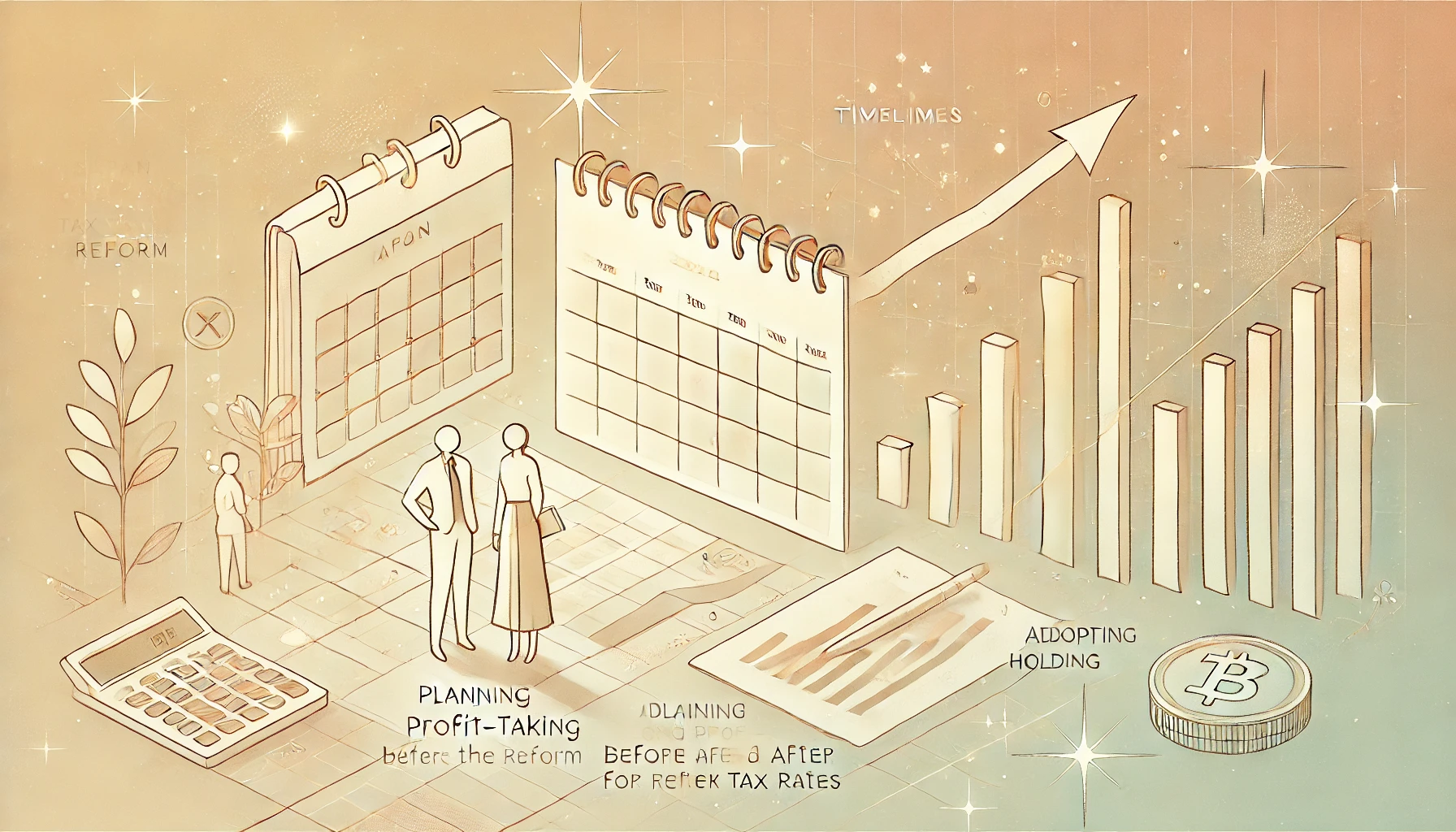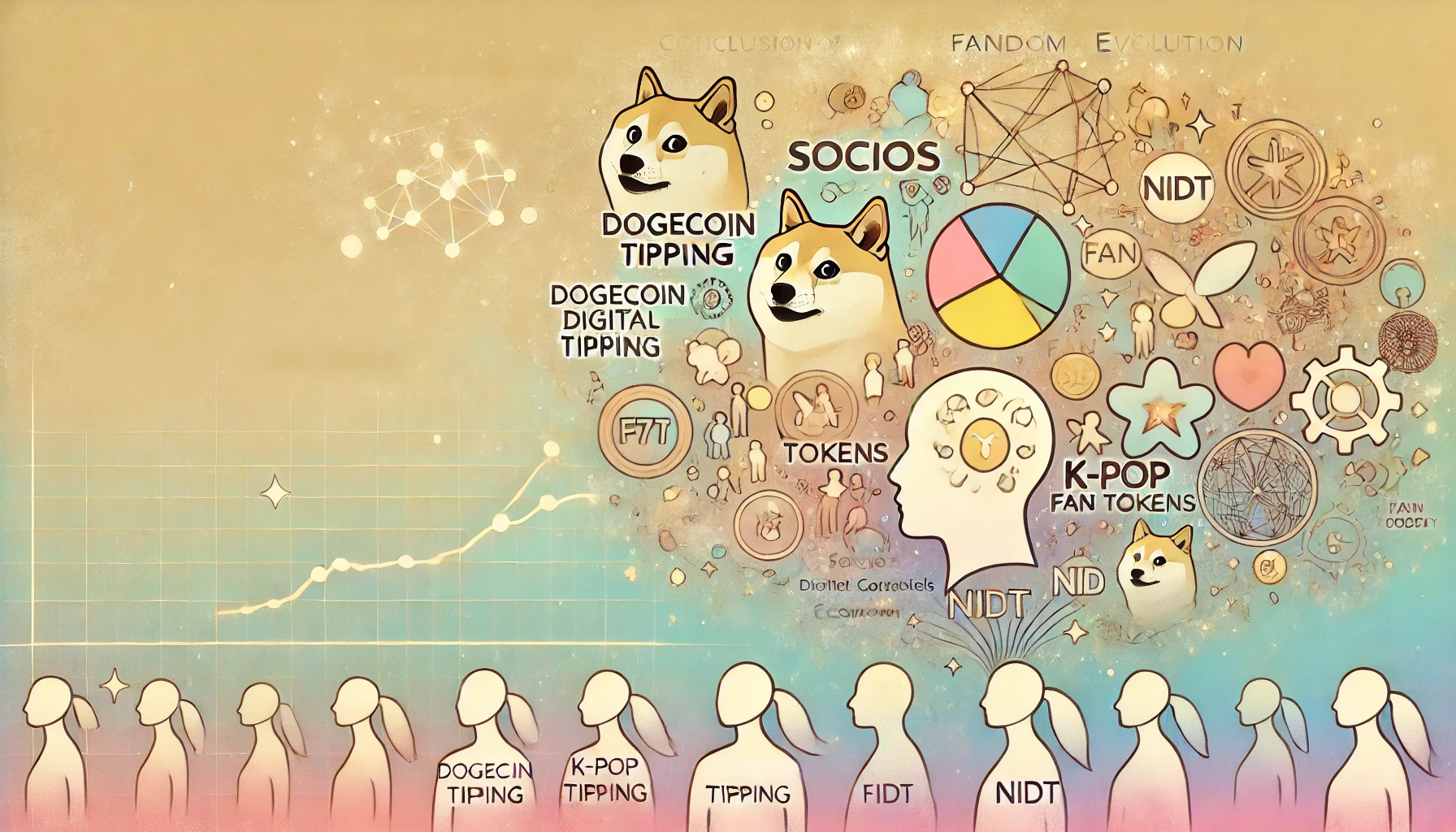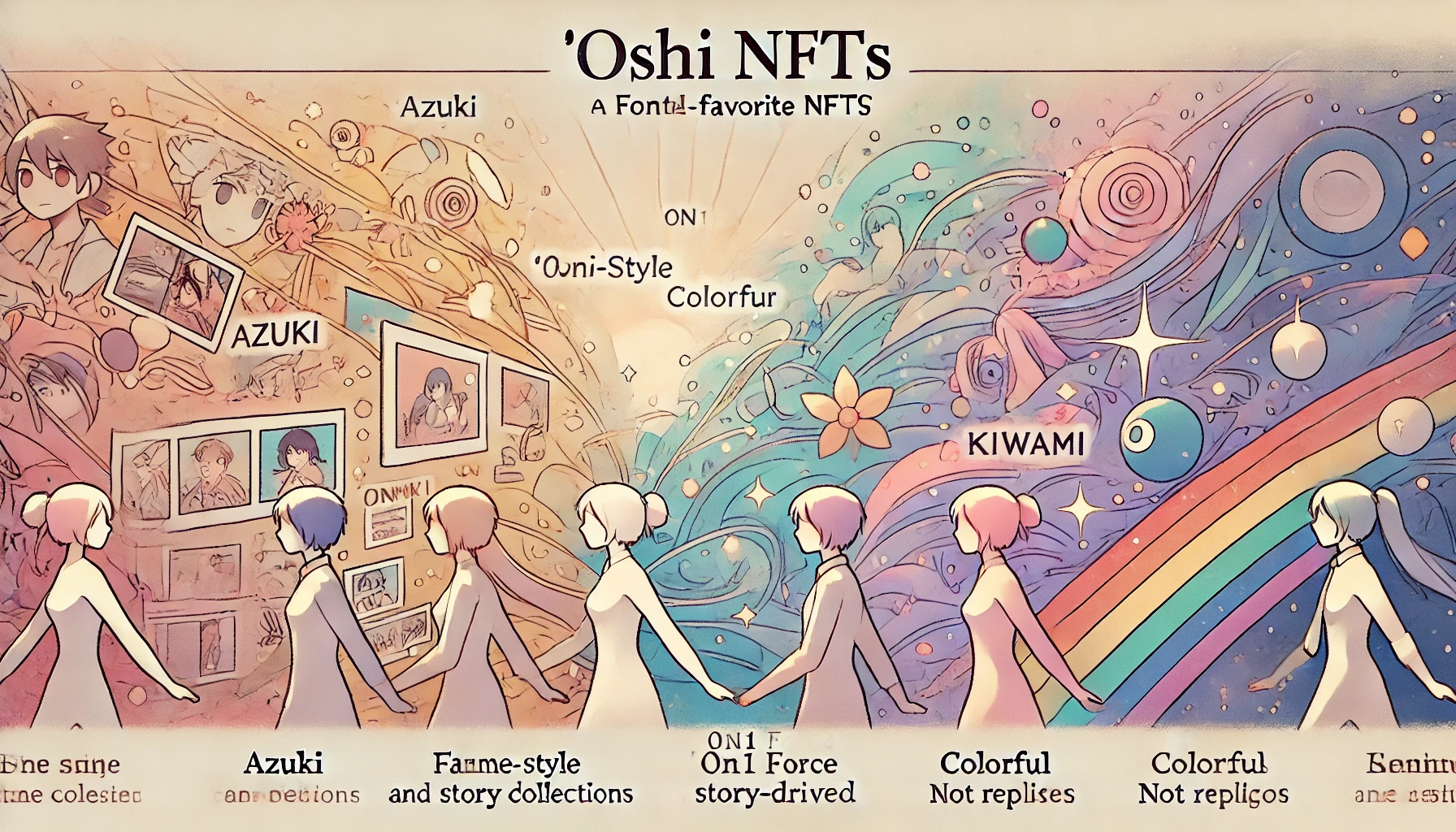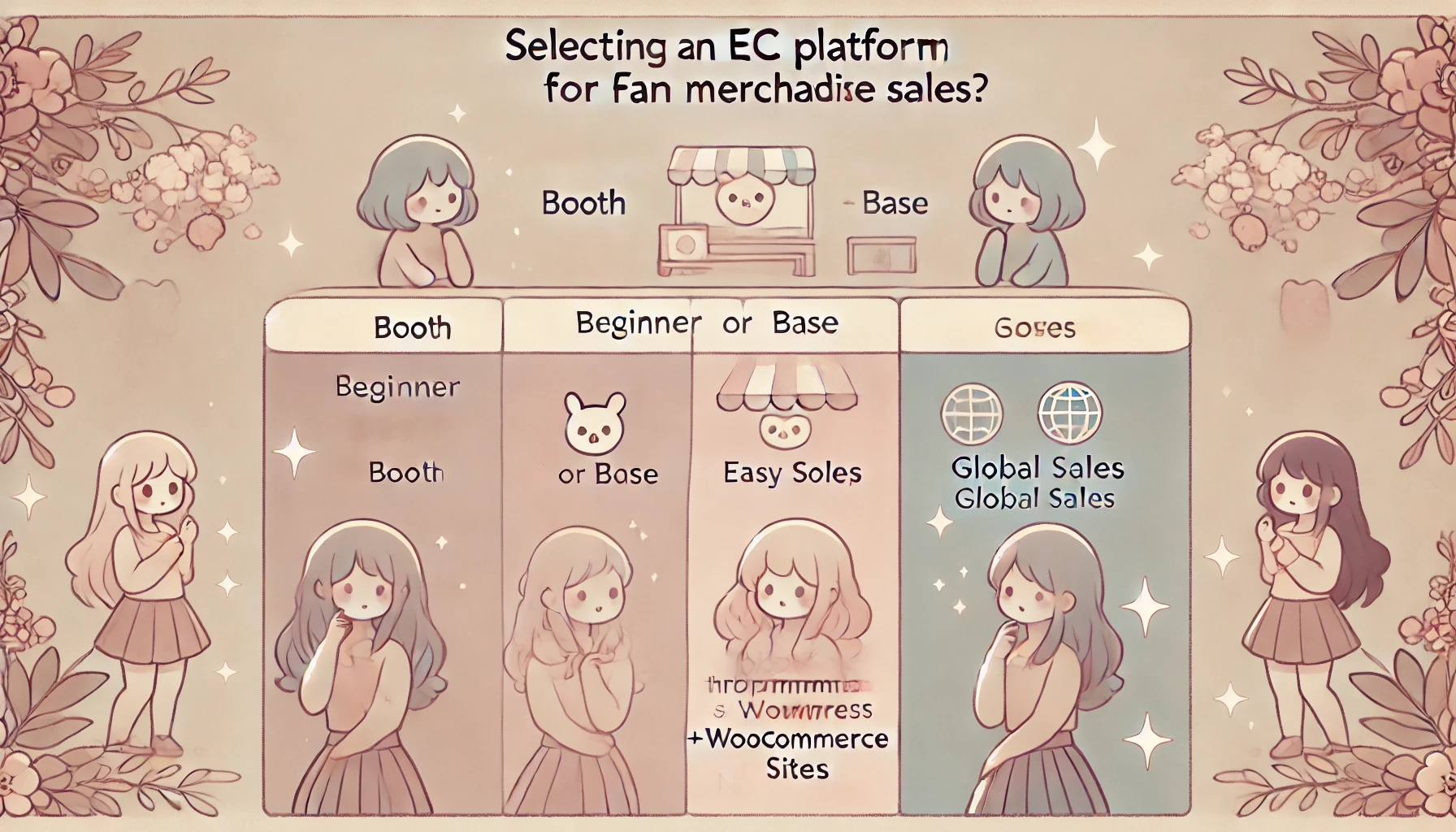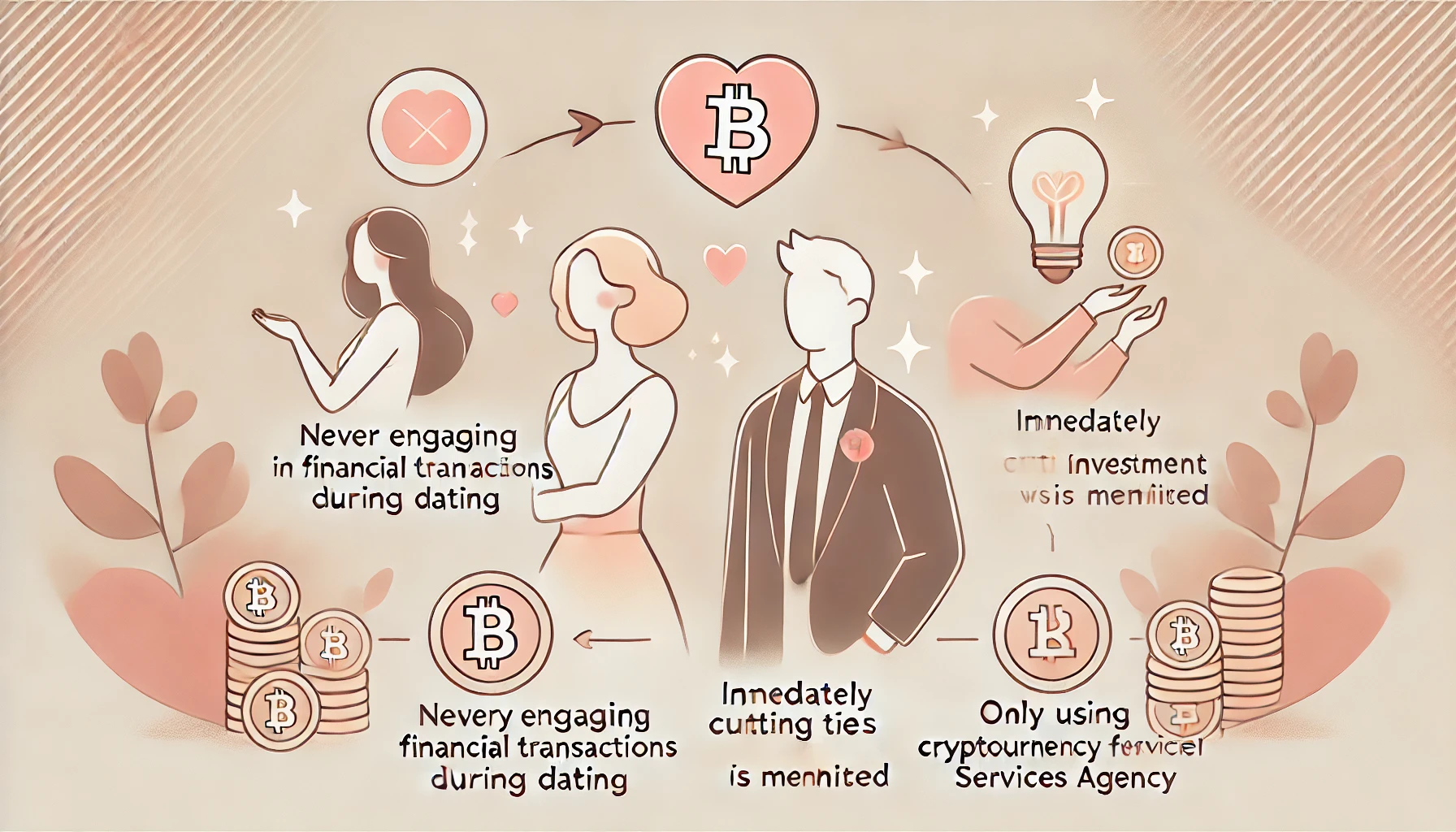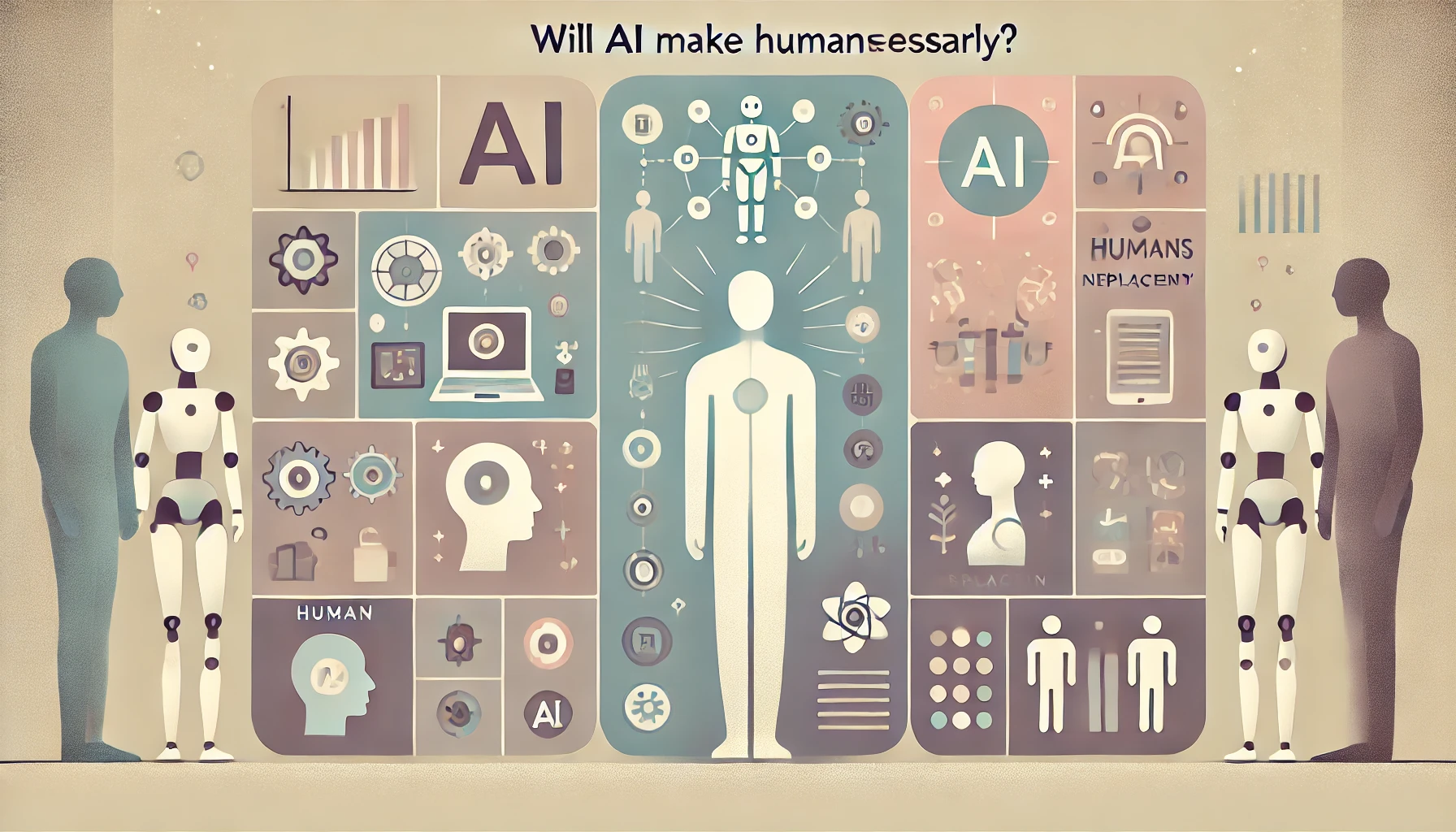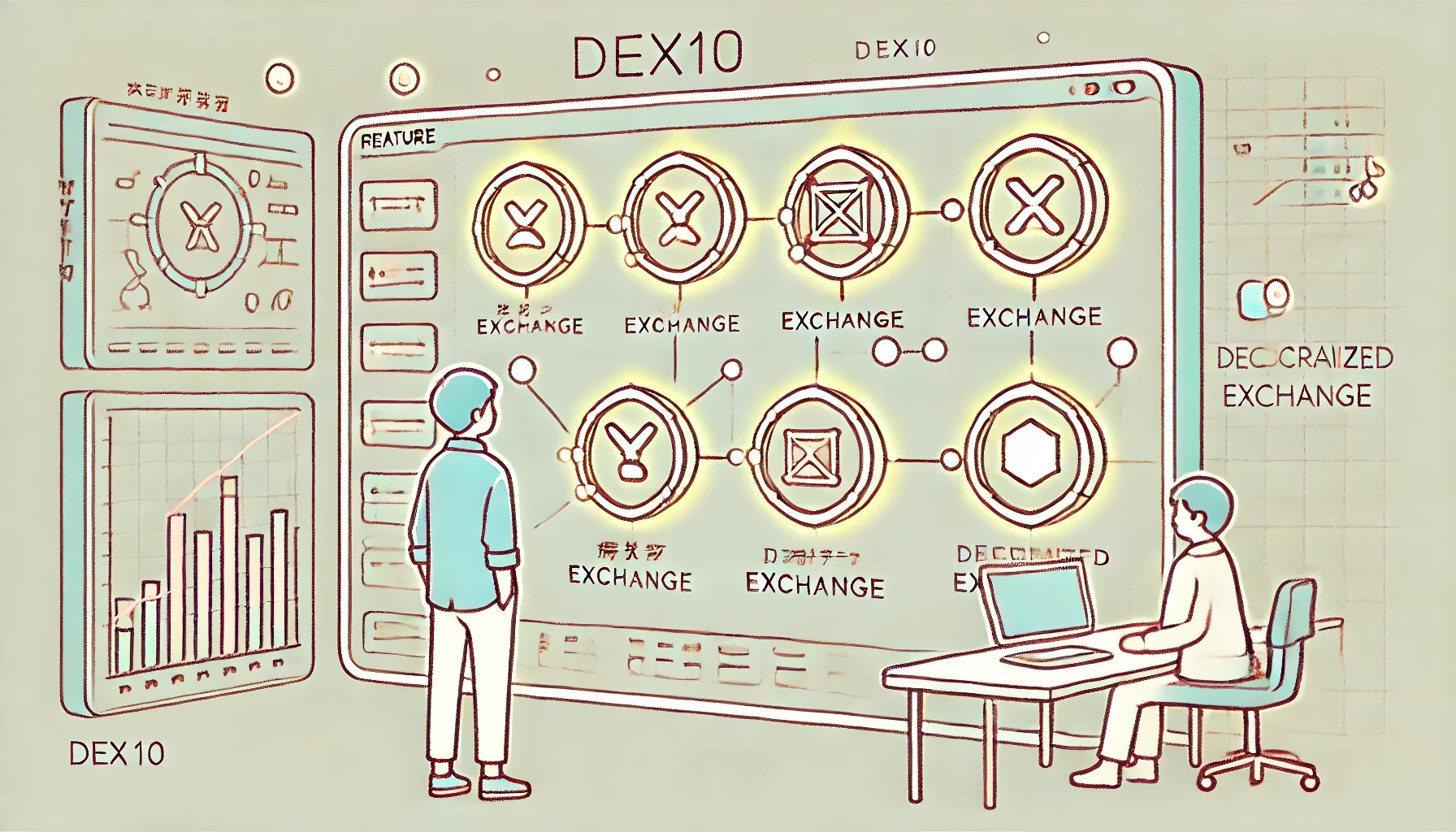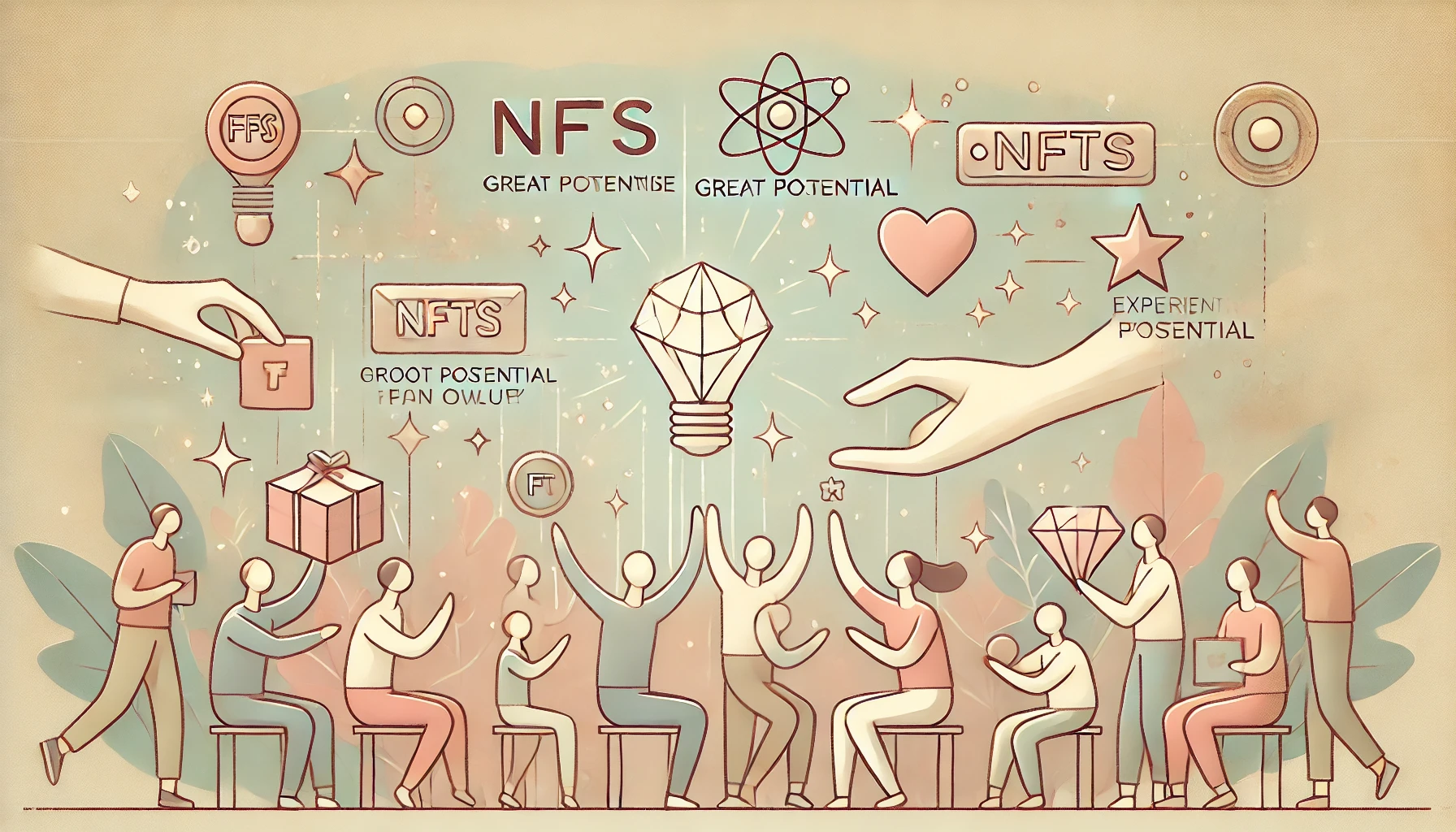
推しグッズのNFT化は、ファンにとって「所有証明」と「体験価値」の両方をもたらす新しい潮流です。しかし、その市場には大きな可能性とともに、高いリスクも潜んでいます。本記事では、最新事例をもとに成功・失敗の分岐点を深掘りします。
推しグッズNFT化の背景と広がり
NFTがもたらすデジタル所有権の革新
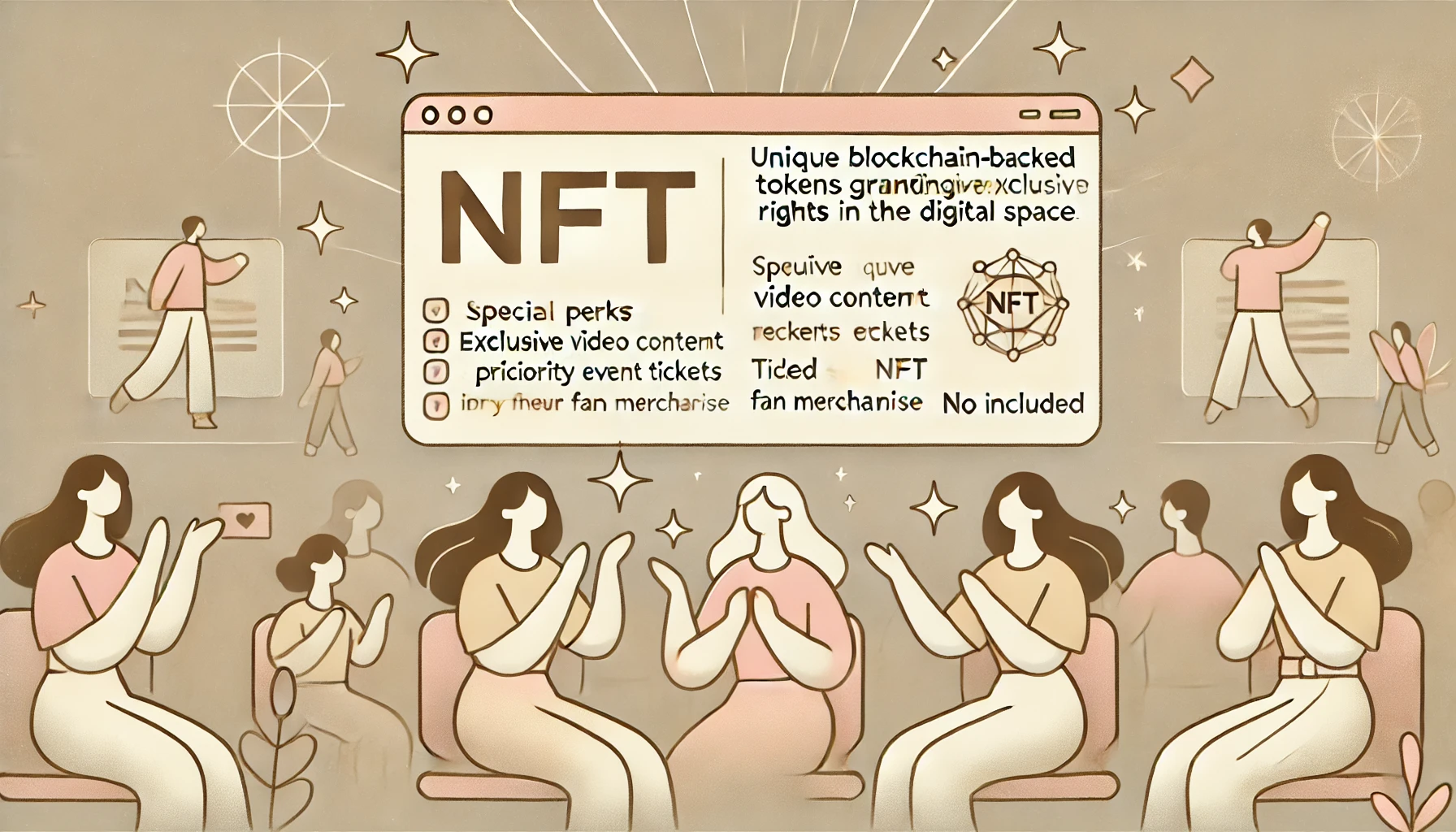
NFT(非代替性トークン)は、ブロックチェーンによって唯一性と所有権を保証します。
これにより、ファンは「自分だけの特別な権利」をデジタル空間で保有できるようになりました。
推し活においては、限定動画視聴権や優先チケットなどの特典が付与されるケースも増えています。
メタバースやリアルイベントと融合する推し活

メタバース空間でのバーチャル握手会、アバター限定ライブ、さらにはシリアル番号付きデジタルチェキなど、体験型のコンテンツが次々と登場しています。
NFTは単なる所有証明にとどまらず、ファンが参加型で楽しめるコンテンツの入口になりつつあります。
成功事例から見るNFT推しグッズのポテンシャル
PerfumeのNFTアート

Perfumeが2021年に発行したNFTアートは約300万円で落札され、話題を集めました。
この事例は、デジタルアートとアイドル文化の融合が新たな収益源となる可能性を示しました。
ももクロの10周年記念NFT
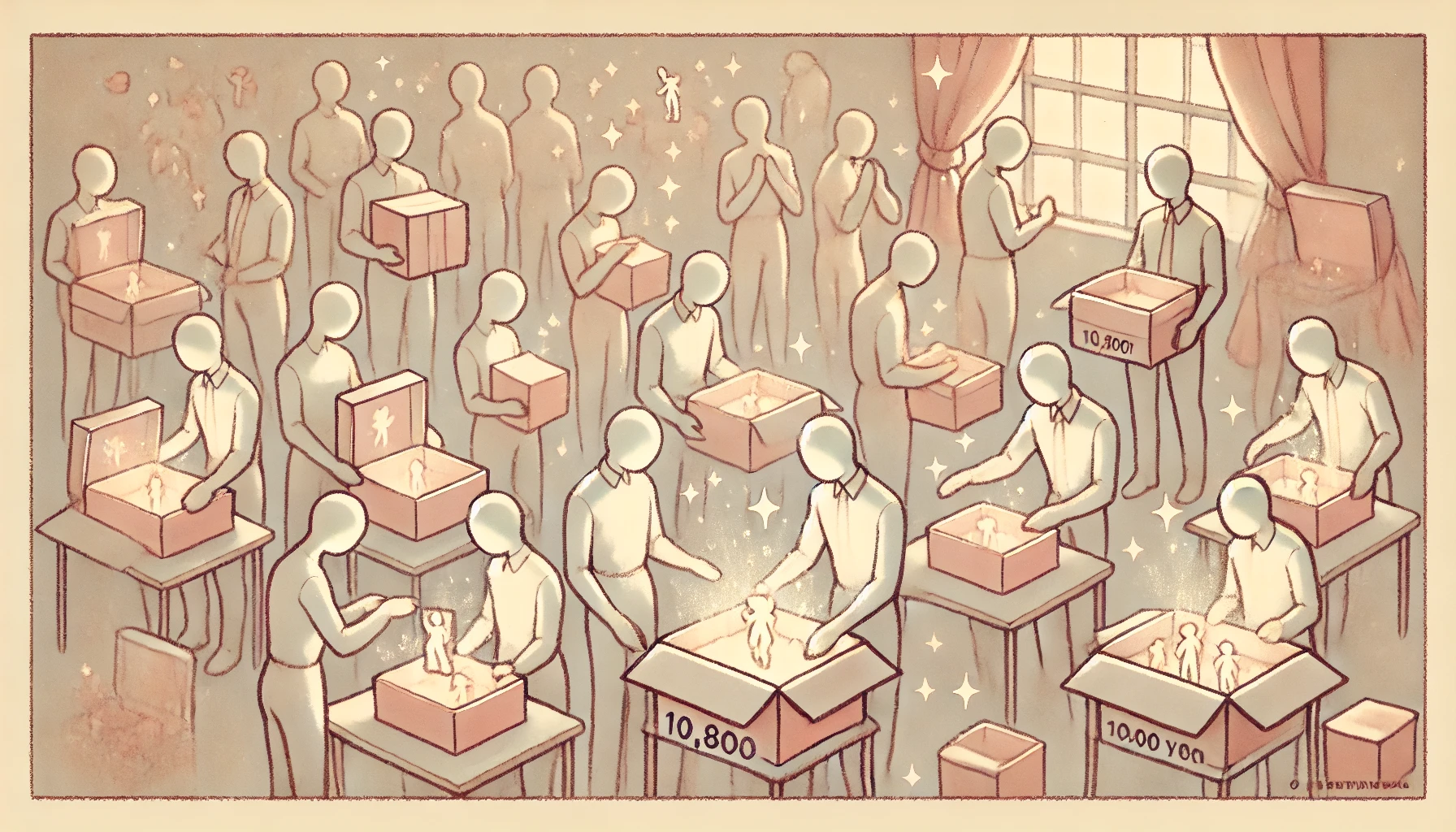
ももいろクローバーZは10周年記念NFTを1パック10,800円で販売し、コレクター需要を見事に喚起しました。
希少性とファン心理を突いた設計が成功の要因といえるでしょう。
海外事例:PixarPalsとAzuki

ピクサーがVeVeで展開した「PixarPals」は、54,995個が即完売し約330万ドルの売上を記録。
さらにNFTコレクション「Azuki」では、投資額が2.3倍に上昇するなど、グローバル市場でも高い収益性を示しています。
大損事例から学ぶNFT推しグッズのリスク
Pudgy Penguinsと価格暴落

NFTコレクション「Pudgy Penguins」では、発行当初の人気に反して二次流通価格が97%減少する事態となりました。
購入者の多くが高値掴みとなり、NFT市場のボラティリティの高さを象徴する事例となっています。
市場全体の課題:95%が無価値化
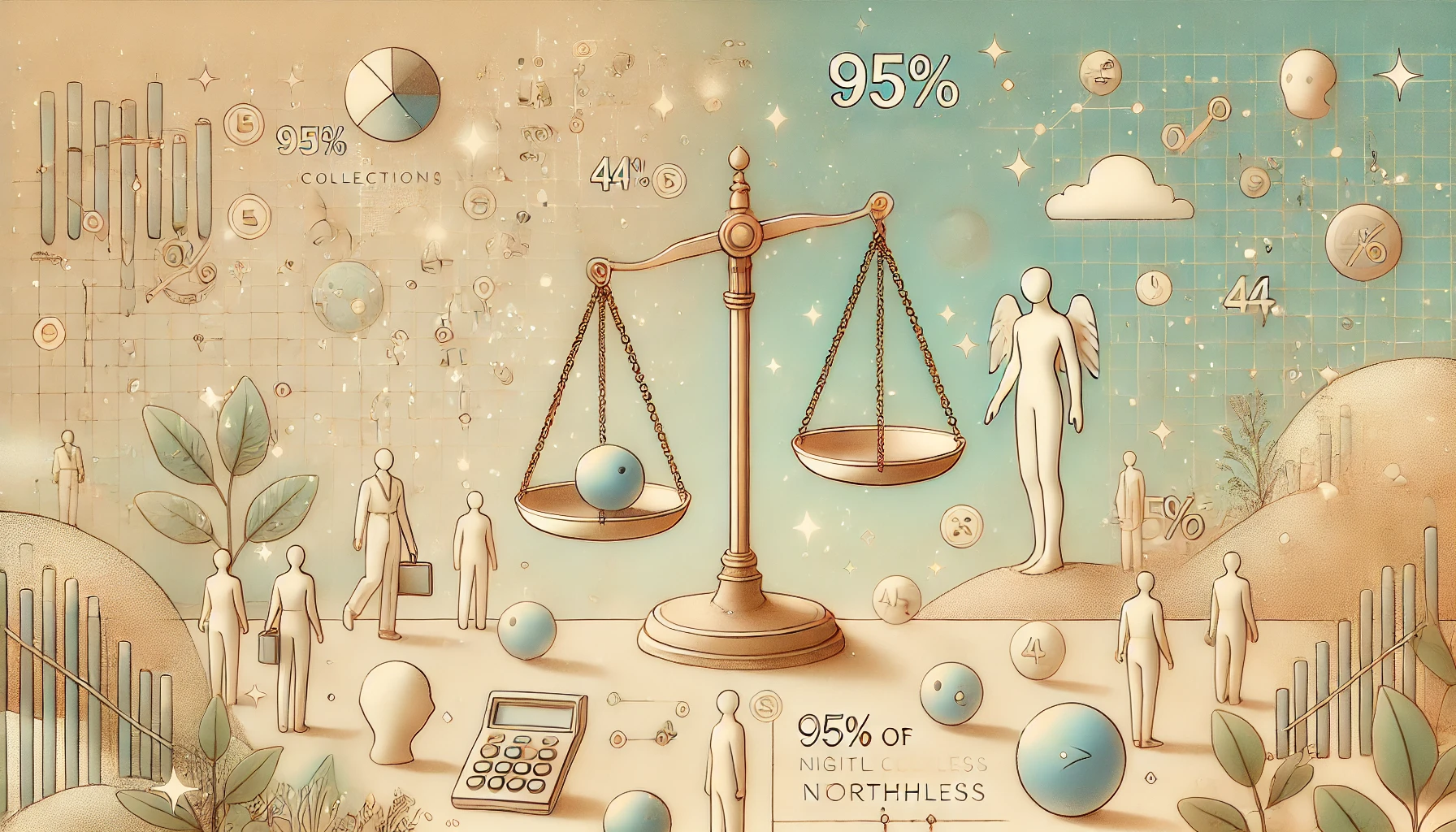
NFTScanの調査によると、NFTコレクション全体の95%が「ほぼ無価値」と化し、平均損失率は44.5%に及んでいます。
推しグッズNFTも例外ではなく、需要と供給のバランス崩壊が大損の背景にあります。
税務リスクによる損失

クリエイターのJonathan Mann氏は、NFT売却益にかかる課税評価額を納税後にETH価格が大幅下落し、約130万ドルの純損失を被りました。
暗号資産は受領時点の評価額で課税されるため、換金タイミングを誤ると巨額の税務リスクを背負うことになります。
失敗例:ポルシェ「PORSCHΞ 911」
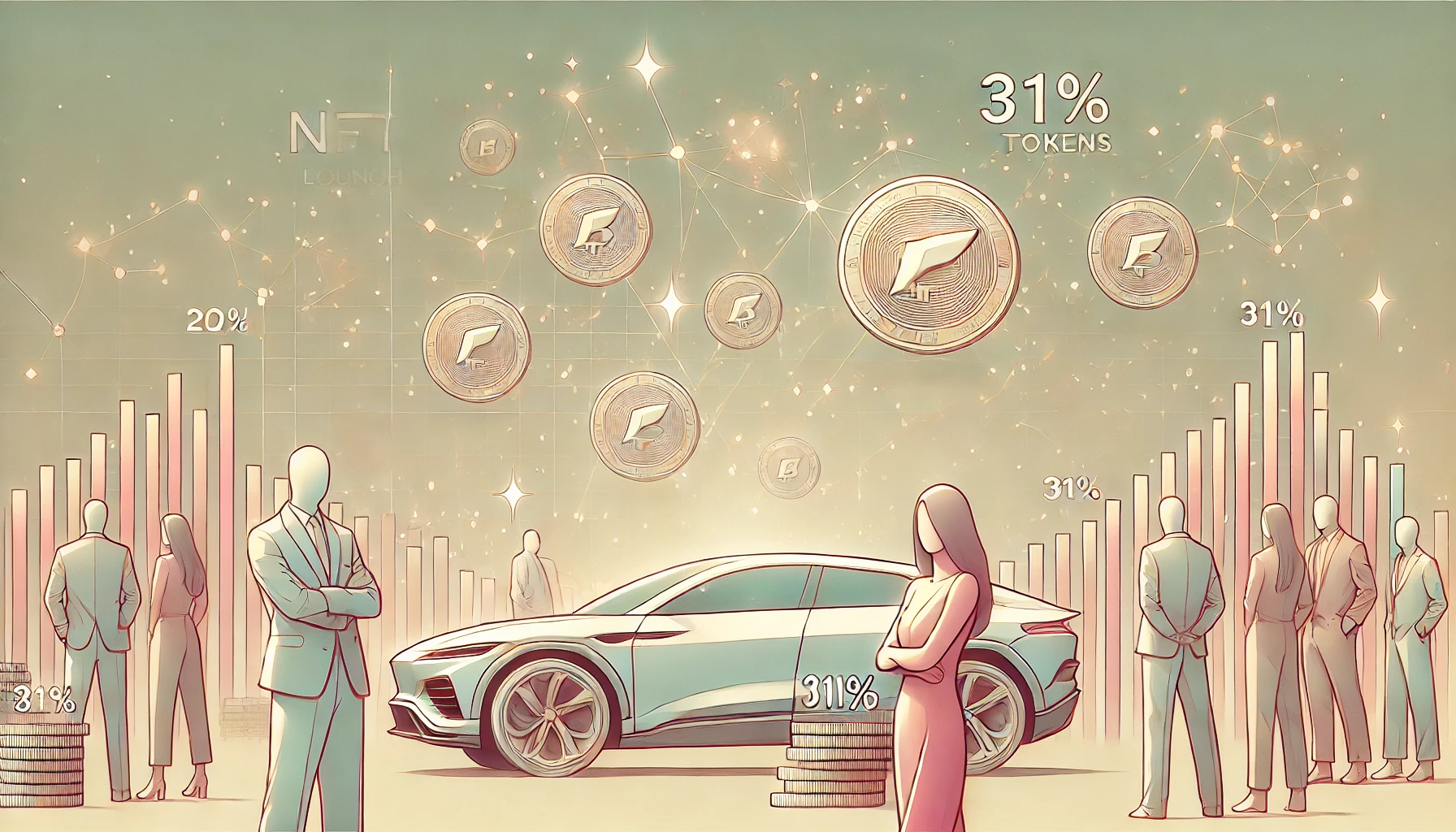
ポルシェが2023年に発行したNFTは価格設定の不適切さから販売が低迷し、ミント率は31%にとどまりました。
ブランド力があっても、価格と需要の乖離が失敗を招くことが明らかになりました。
なぜ成功と失敗が分かれるのか
価格設定と希少性のバランス
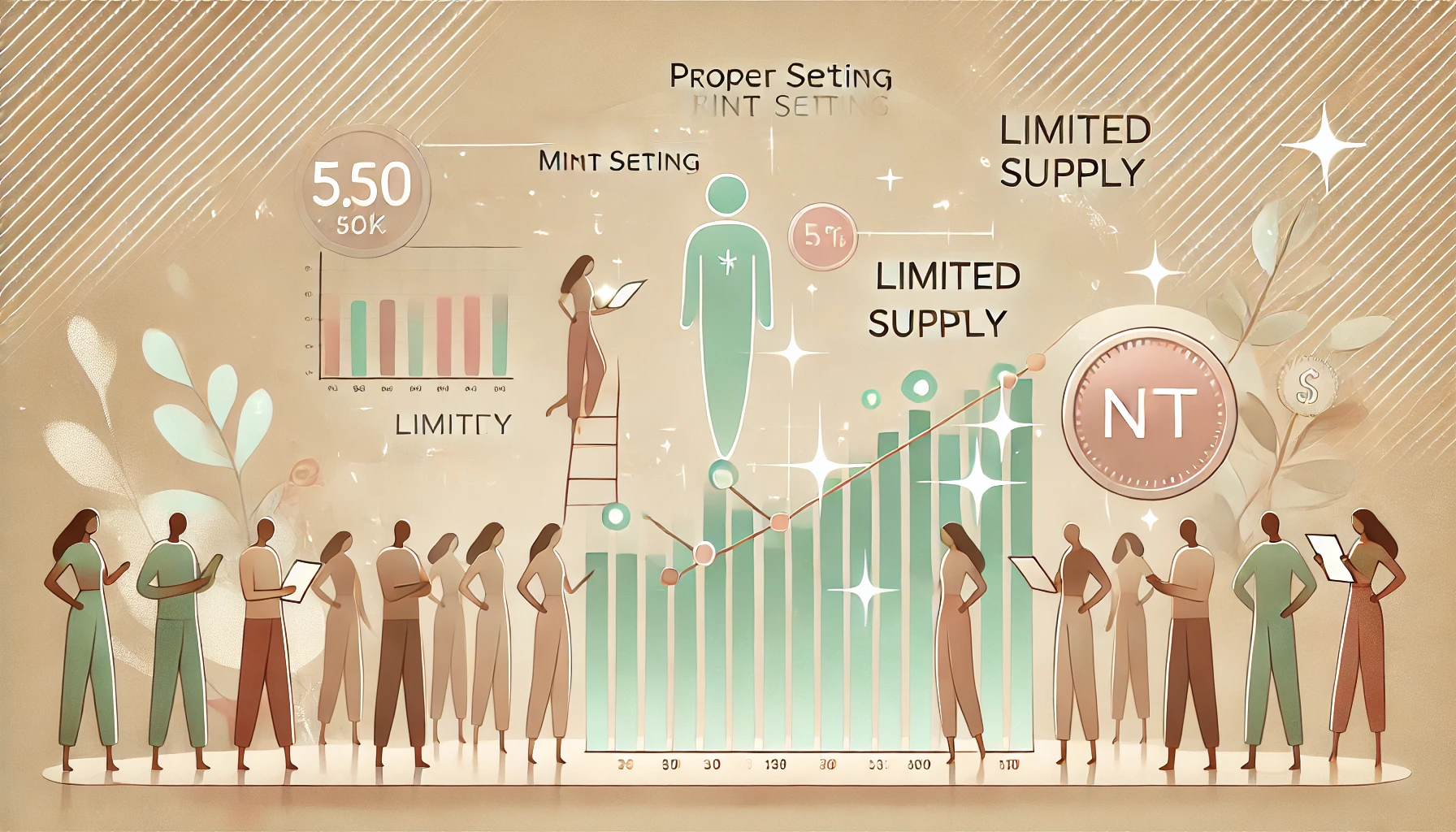
ミント価格が高すぎたり、発行枚数が多すぎたりすると、ファンや投資家がついてこられません。
成功している事例では、適切な価格設定と希少性の演出が徹底されています。
ユーティリティ(特典)の重要性
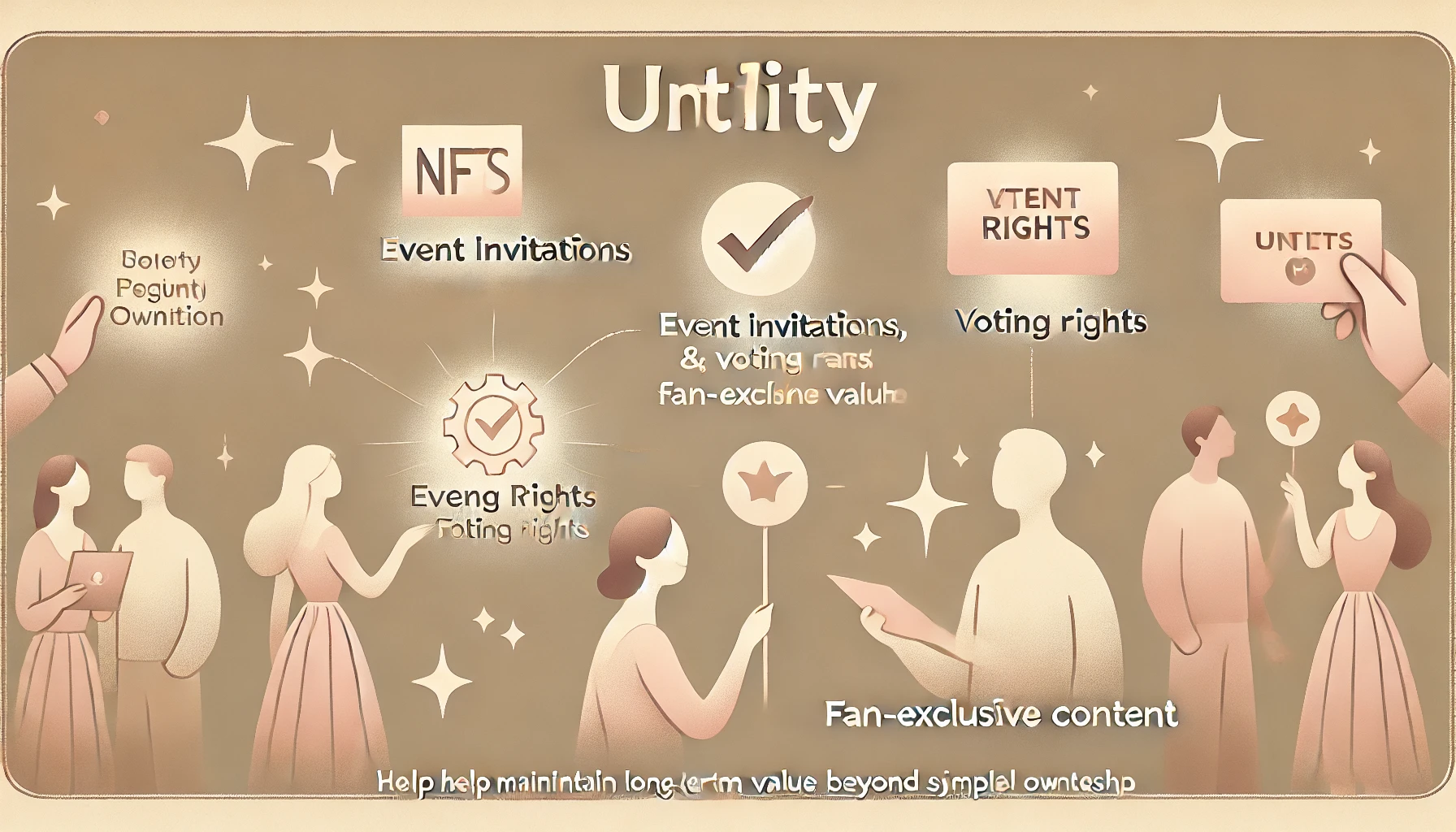
NFTが単なるデジタル所有証明にとどまると二次市場での価値が下がりやすいです。
一方、イベント招待や投票権、ファン限定コンテンツなどの実用的なユーティリティを付与することで、価値が持続しやすくなります。
マーケティングとコミュニティ戦略
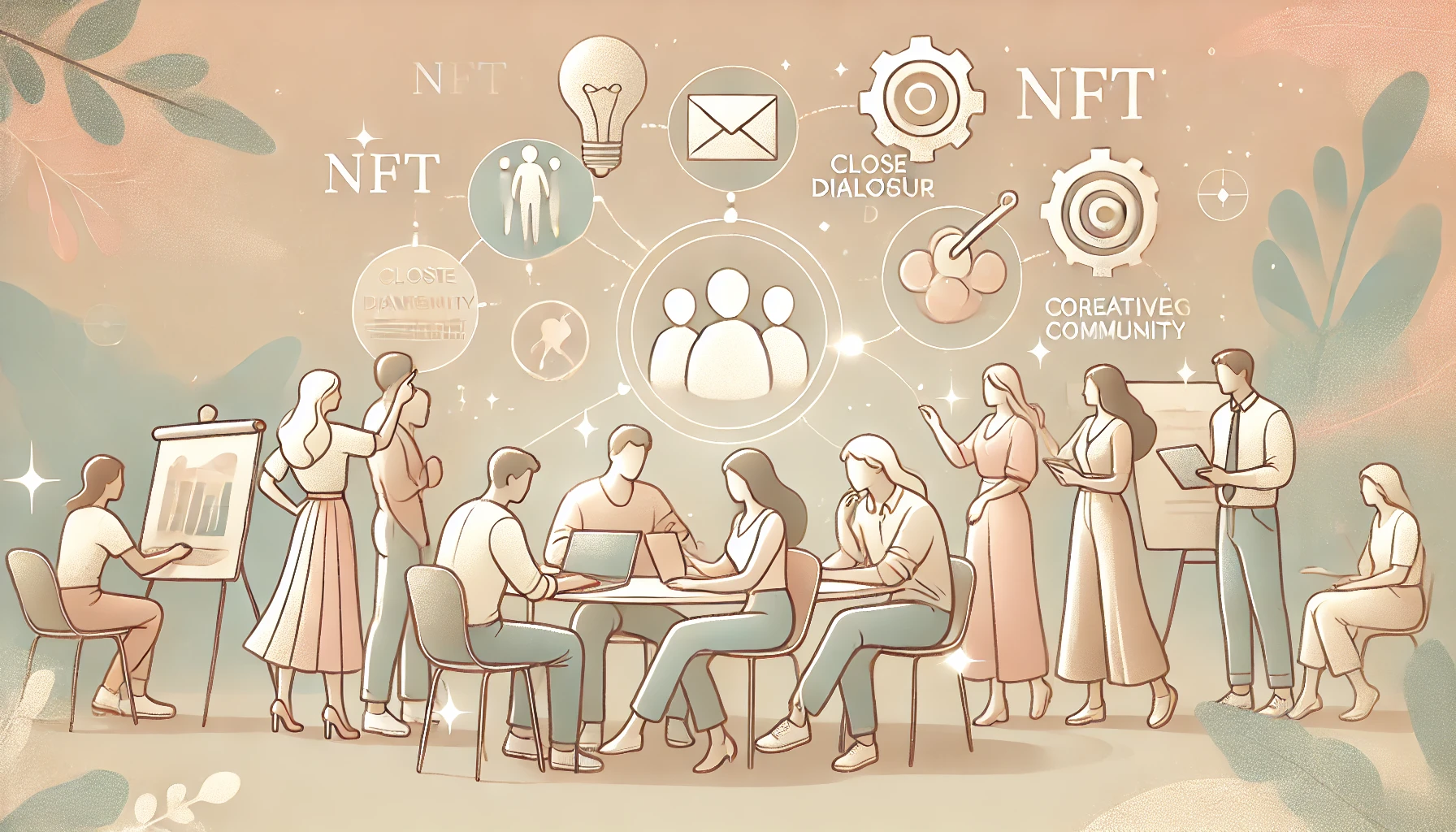
成功事例の多くはコミュニティとの密な対話を重視しています。
発行前にファン意見を反映させ、「共創型コンテンツ」として市場に送り出すことが、長期的な支持につながります。
推しグッズNFTで得られる新しいファン体験
デジタルとリアルの融合

推しグッズNFTの魅力は、デジタルとリアルがつながる体験にあります。
NFTを保有することで、リアルイベントの優先入場権や限定グッズ購入権を得られるケースが増えています。
これにより、ファンは所有する喜びと特別な体験を同時に享受できます。
メタバースでの推し活

メタバース内でのライブやバーチャル握手会など、物理的な制約を超えた新しい推し活の形が広がっています。
デジタル空間での交流は、距離や時間に縛られないファンコミュニティを育みます。
コレクションとしての価値
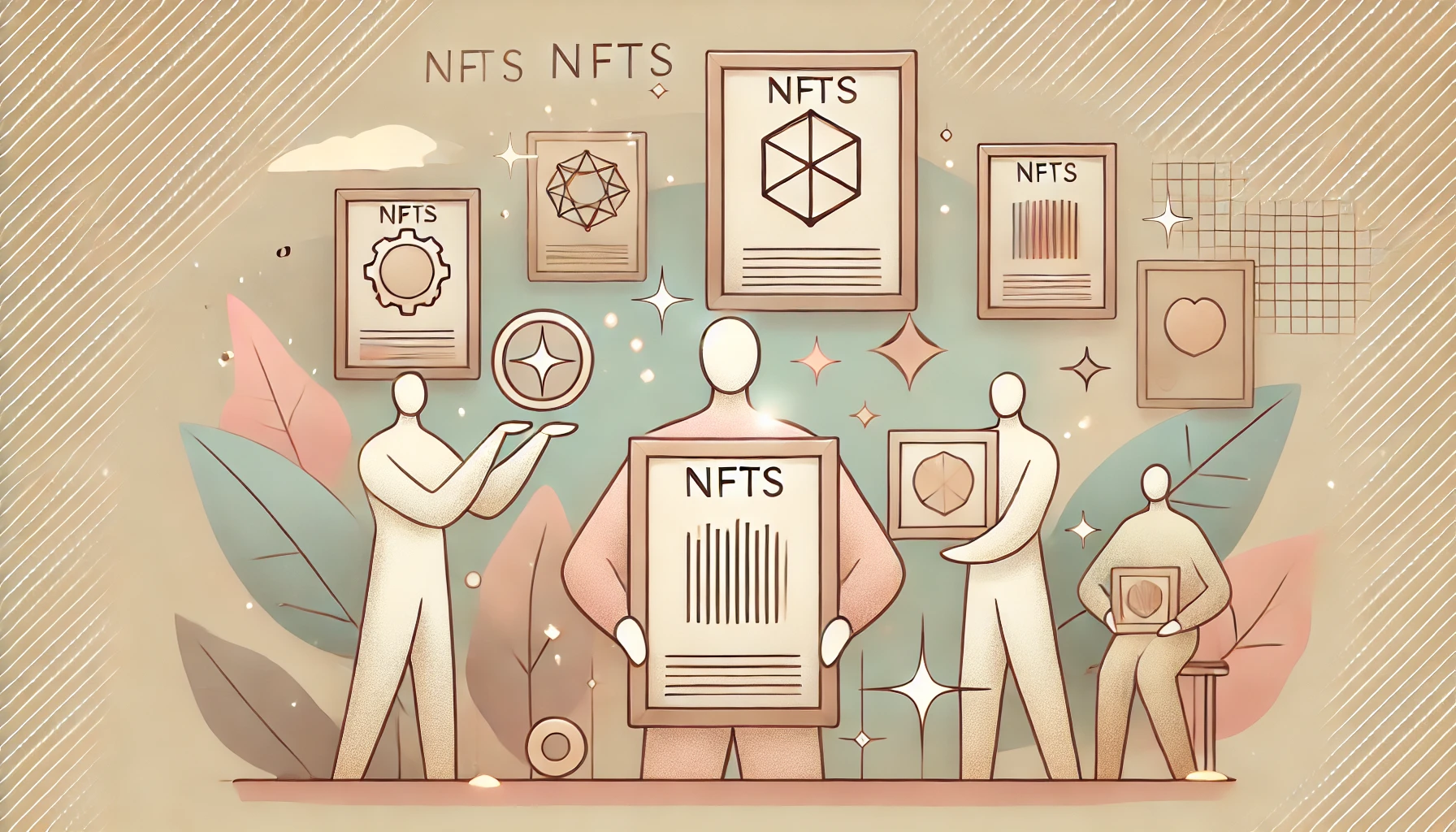
シリアル番号付きデジタルチェキや限定アートワークなど、NFTはコレクター心をくすぐる要素を多く備えています。
「唯一無二の証明」としてブロックチェーンに記録されることで、ファンは長期的な価値保持を期待できます。
税務・法務の落とし穴と回避策
課税のタイミングと評価額のズレ
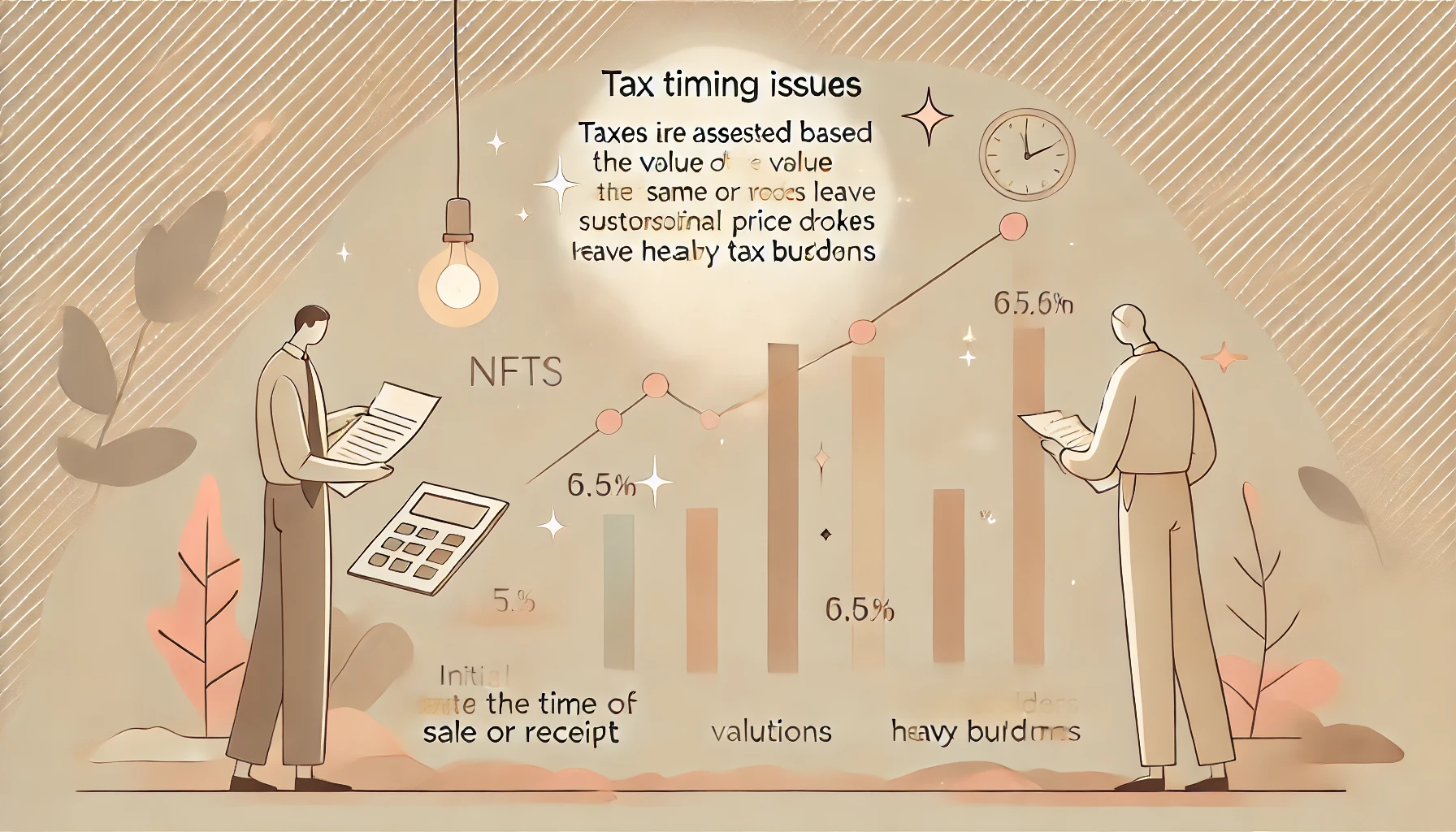
NFT売却や受領時には、その時点の評価額で課税が発生します。
しかし、その後価格が下落した場合でも税額は減額されず、納税負担だけが重く残るケースが頻発しています。
ギャンブル性と規制リスク

ランダム型販売(ガチャ形式)では賭博罪や資金決済法の適用が議論されることがあります。
特にファン向けNFTでは、法務チェックの徹底が欠かせません。
専門家との連携
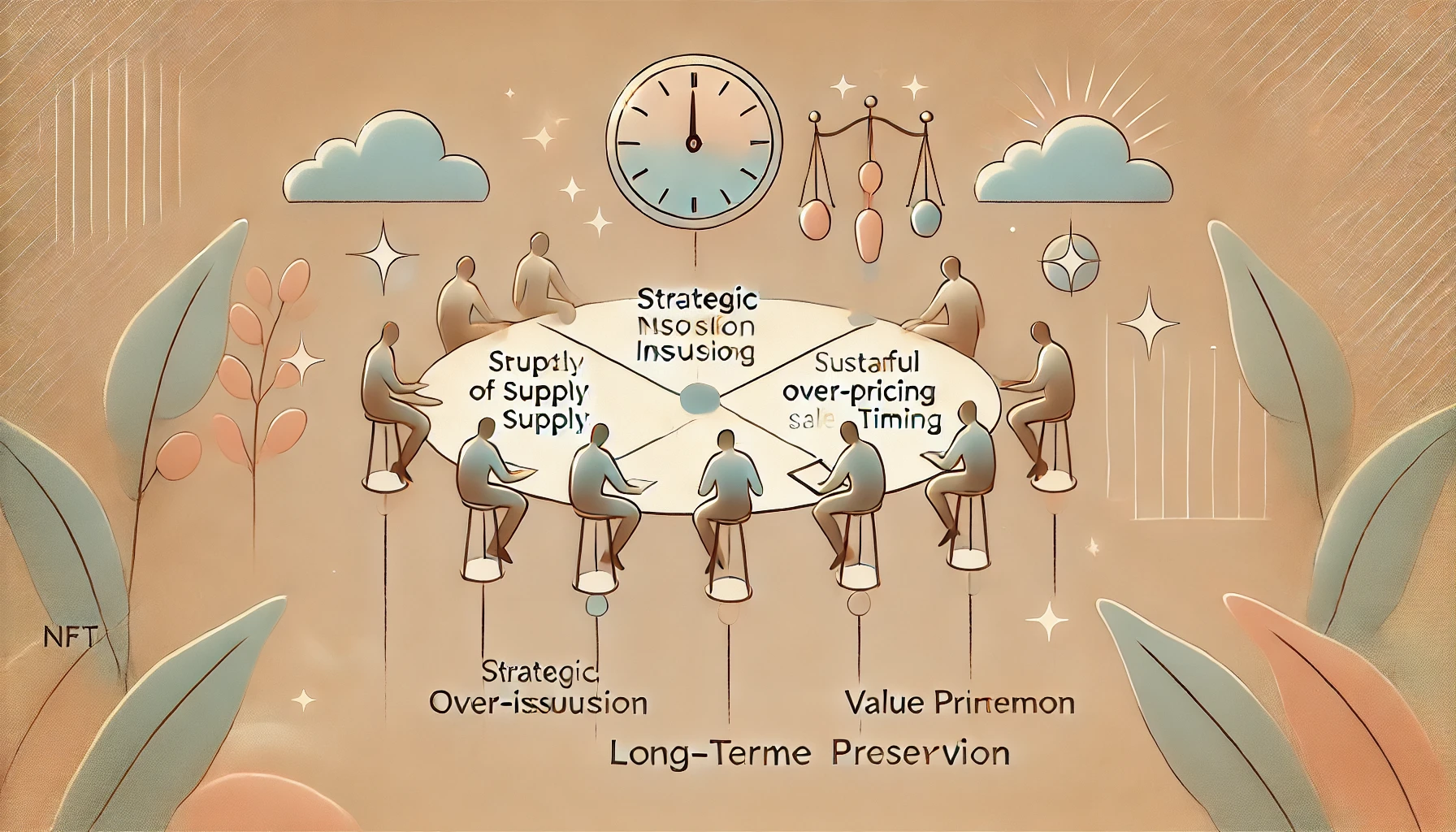
税務・法務リスクを最小限に抑えるためには、発行前から専門家と連携することが重要です。
これにより、法的トラブルや不意の納税負担を回避できます。
成功するNFT推しグッズの条件
戦略的な発行計画
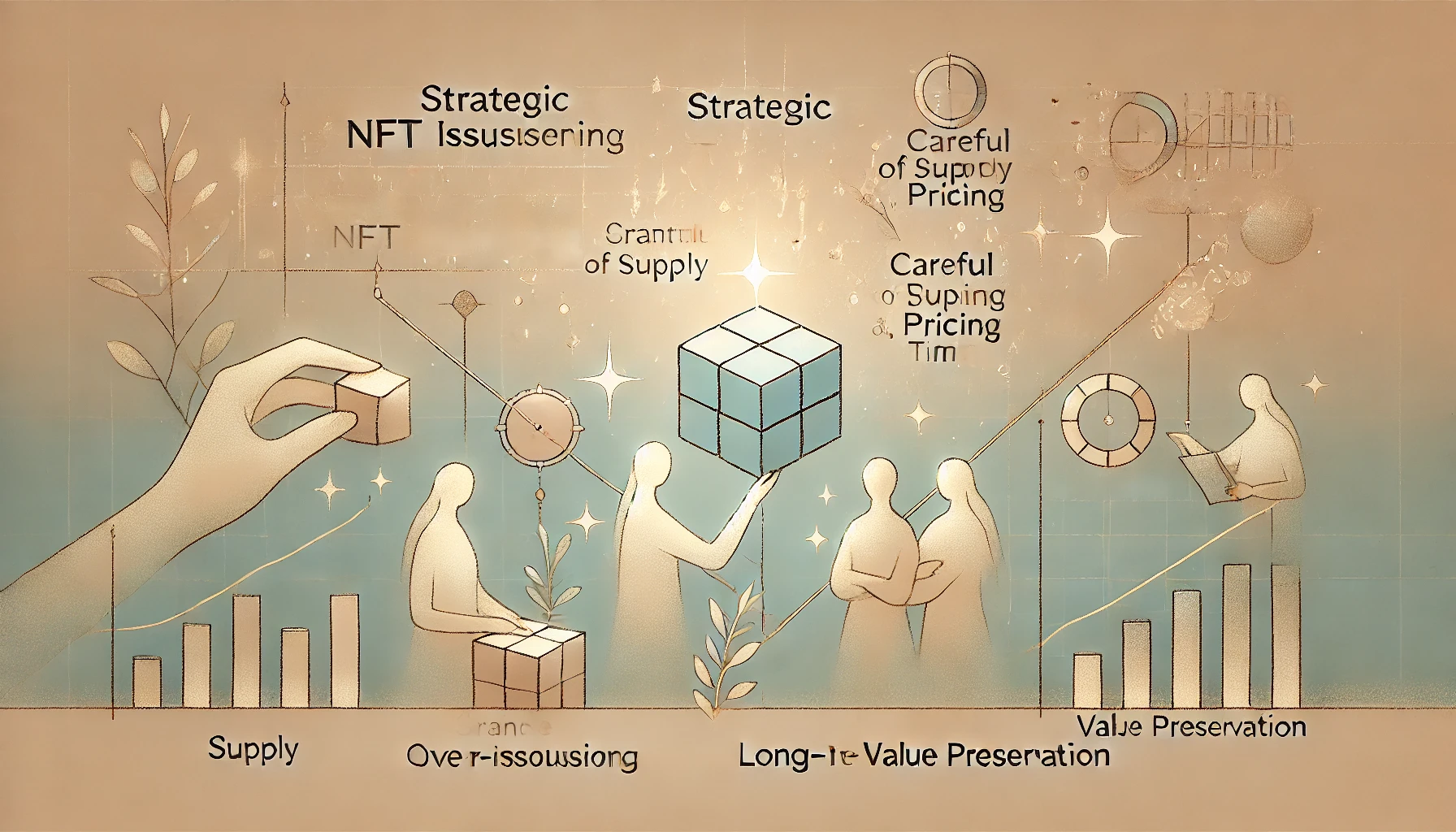
成功しているプロジェクトは、発行枚数・価格・販売タイミングを綿密に設計しています。
特にファンコミュニティの声を反映し、過剰発行を避けることが長期的な価値維持につながります。
継続的なユーティリティ提供

初回販売だけで終わらず、保有者限定の追加特典やイベント招待など、継続的なインセンティブを設けることが大切です。
これにより、NFTが「一度買って終わり」のものではなく、コミュニティ参加の鍵として機能します。
二次流通でのロイヤリティ収益
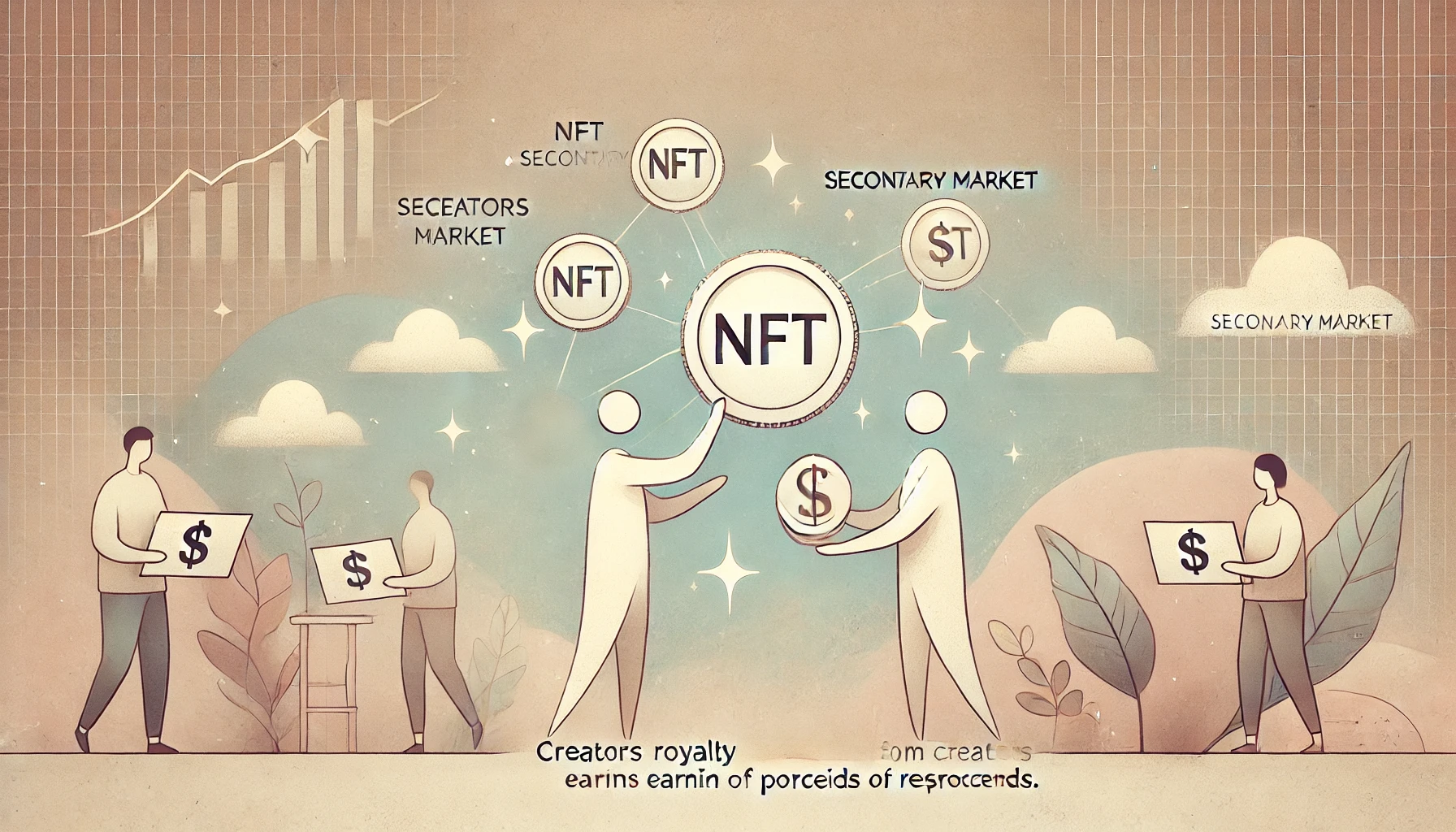
NFTには転売時に制作者へ一定の収益が入るロイヤリティ機能を付与できます。
これにより、一次販売だけでなく二次流通でも収益を確保でき、プロジェクトの持続性が高まります。
ファンと共創するコミュニティ作り
ファン参加型の企画

ファン投票で楽曲制作やグッズデザインを決定するなど、共創型の仕組みを導入することで熱量が高まります。
NFTはそのための投票権や参加権としても活用可能です。
情報発信と透明性

発行意図や運用方針を定期的に発信し、コミュニティに透明性を持たせることが信頼につながります。
特に運営チームの顔が見える発信は、ファン心理の安定に効果的です。
失敗例からの学び

過去の失敗事例は、過剰な価格設定や情報不足が原因であることが多いです。
これらを分析し、改善策を先回りして講じることが必要です。
今後の展望と提言
デジタル×リアルの連携強化
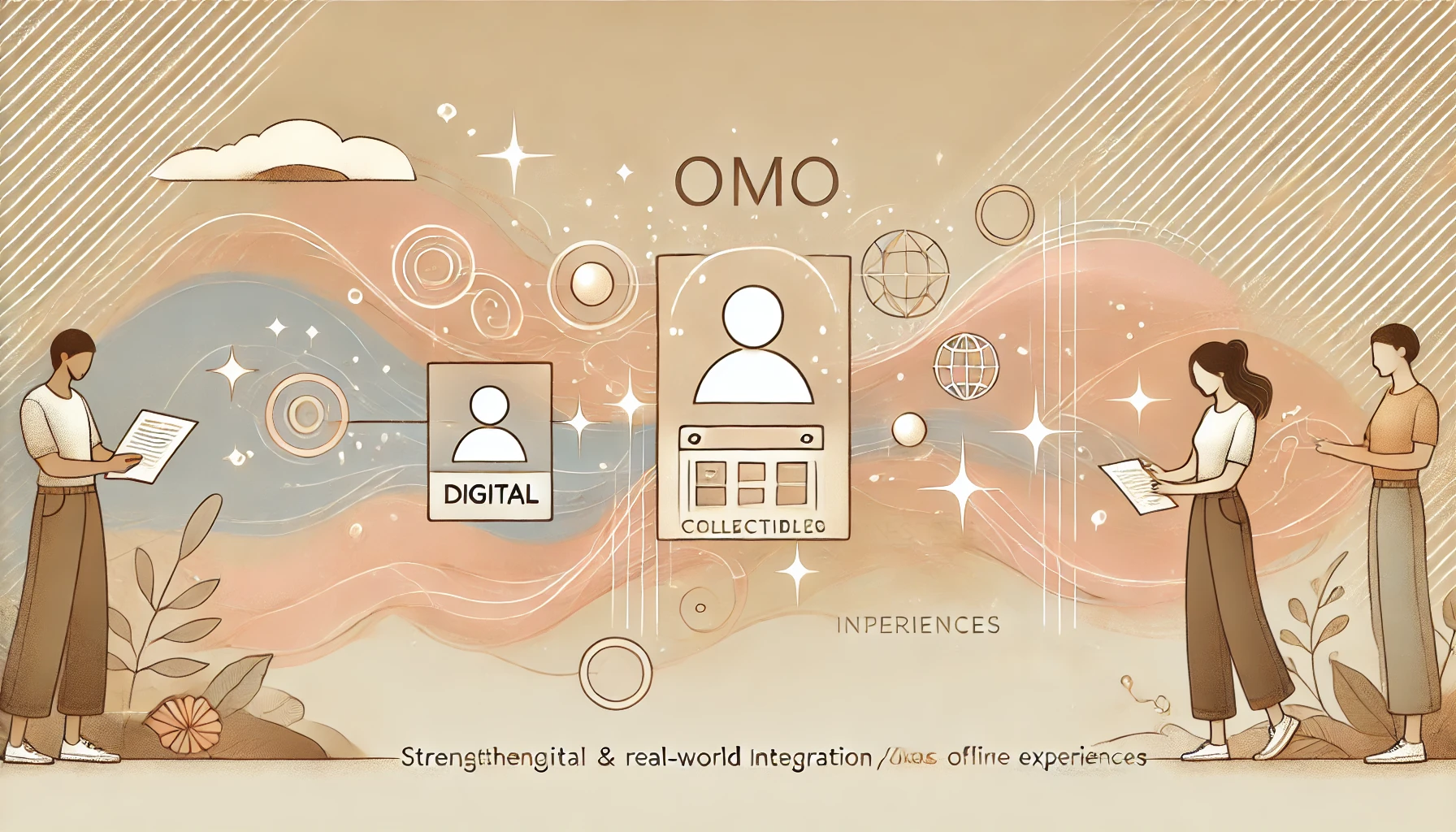
今後は店舗来店特典やイベント連動など、OMO(Online Merges with Offline)体験の拡充が重要です。
デジタル上の権利とリアルの体験を組み合わせることで、ファンはより深い満足感を得られるでしょう。
リスクマネジメントの徹底

法務・税務リスクへの対策は不可欠です。
発行前から専門家を交えたリスクチェックを行い、トラブルを未然に防ぐ体制を整えましょう。
中長期的な価値設計

一過性の販売ではなく、中長期的に価値を高める仕組みが求められます。
NFTは「推しとの関係を深め続けるためのツール」として進化していくべきです。
まとめ:推しグッズNFTは“所有”と“体験”を変える
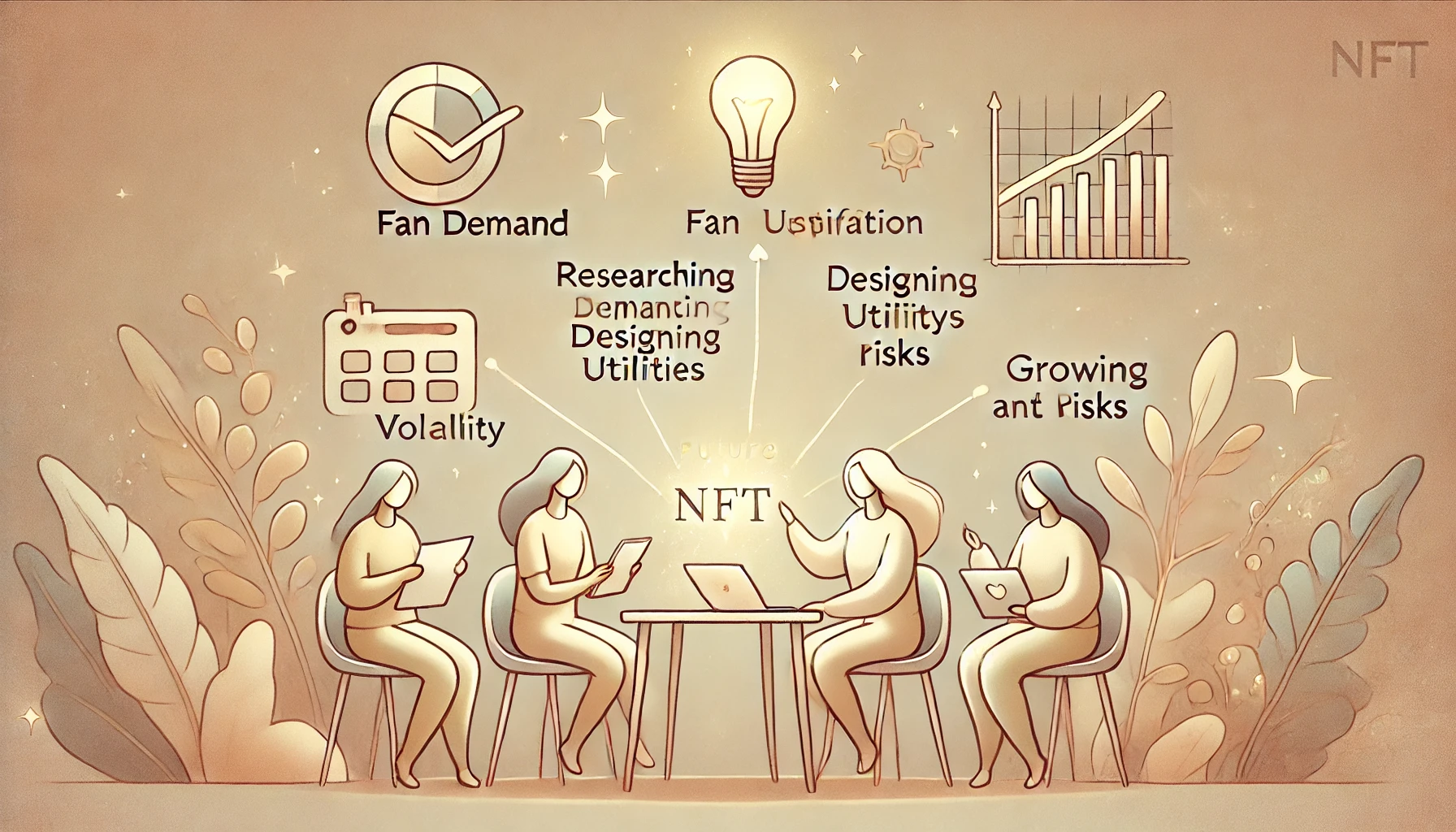
推しグッズのNFT化は、ファンにとって新しい形の満足をもたらす一方、ボラティリティや税務といった大きなリスクも伴います。
だからこそ、需要リサーチ・ユーティリティ設計・リスク管理の三位一体が欠かせません。
NFT推しグッズはまだ発展途上の分野です。
成功事例と失敗事例から学び、ファンと運営が共に育てることで、この市場はさらに豊かに成長していくでしょう。